結論を先に要約します。銘柄(またはETF)100株 × 1コールの基本単位を守り、デルタ基準のストライク選定とIVコンタイル(IVP)で建玉タイミングを最適化、さらに配当月の早期行使(アーリーアサイン)回避と定型ロール基準を組み合わせると、裁量に依存しない運用が実現します。
1. カバードコールの構造と損益の直感
構造はシンプルです。現物株を保有し(ロング)、同じ銘柄のコールを売ります(ショート)。受け取るプレミアムは即時のクレジット(収入)で、満期まで時間経過(シータ)とともに価値が減少しやすいのが特徴です。株価が大きく上昇した場合はストライクで上値を“譲る”代わりに、横ばい〜ゆるやかな上昇ではプレミアムが効いてトータル収益が安定します。
損益直感は以下の通りです。現物の損益に、受取プレミアム(最大利益の一部)を上乗せしますが、ストライク以上のキャピタルゲインは放棄します。ゆえに「天井を売って床を固める」発想です。ボラティリティが高いとプレミアムが厚くなり有利ですが、その分、価格変動も大きくなります。
数式的には、総損益 ≒ 現物損益 + 受取プレミアム −(株価がストライク超過時の上値放棄分)。この“上値放棄”を小さくする鍵が、ストライクの選び方と建玉タイミングです。
2. ベースライン設計:銘柄、サイズ、期限
2-1. 銘柄選定
初心者はまず、流動性が高く、オプション板が厚い大型銘柄や指数連動ETFから始めるのが無難です。板が薄いとスプレッドが広がり、理論値から乖離しやすく、約定コストが増えます。配当の有無・権利月、決算スケジュールにも注意が必要です。
2-2. サイズ(単位)
米国株を前提とすると、100株につきコール1枚が基本単位です。ETFでも同様です。これを超過した売り枚数は「ネイキッド」に近づき、下落時のヘッジが弱くなるため避けます。
2-3. 満期(期限)
初心者はまず残存日数(DTE)30〜45日をベースにします。理由は、受取プレミアムと時間価値減少のバランスが取りやすく、ロールもしやすいからです。慣れたら週次(7〜14日)も検討可ですが、管理頻度が上がります。
3. ストライク設計:デルタ法とプレミアム比率法
ストライクは最重要パラメータです。以下のいずれかで整然と決めます。
3-1. デルタ法(推奨)
コールのデルタが+0.25(±0.05)になる価格帯を基準にします。デルタは満期までの上場確率の粗い近似としても使え、「程よくプレミアムを得つつ上値の余地を温存」するバランスが取りやすいからです。相場が強い時はΔ0.20へ、弱い時はΔ0.30へシフトする裁量を許容します。
3-2. プレミアム比率法
受取プレミアム ÷ 現物時価の月率換算が目標閾値(例:月0.8〜1.2%)を満たすストライクを選びます。利回り志向に直結し直感的です。ただし、過度に利回りを追うと上値放棄が大きくなります。
実務では、「基本はデルタ法、比率法はフィルタ」という使い分けが扱いやすいでしょう。
4. 建玉タイミング:IVコンタイル(IVP)の活用
同じストライクでも、インプライド・ボラティリティ(IV)が高い時ほどプレミアムは肥大化します。よって、IVの水準に応じて建玉濃度をコントロールします。実務では「IVパーセンタイル(IVP)」——直近1年などの分布に対して、現在のIVが上位何%か——を用います。
- IVPが70%以上:建玉を積極化(フルサイズ)。
- IVPが40〜70%:標準サイズ。
- IVPが40%未満:様子見、またはDTEを短くして回転数で稼ぐ。
こうすると、ボラが高い局面で厚いプレミアムを取り、低ボラ局面では無理をしない運用が自動化されます。
5. 配当月の早期行使(アーリーアサイン)回避
米国株の配当権利落ち前は、深く実現化した(ITM)のコールが早期行使されやすいため注意が必要です。原則は以下。
- 配当落ちの2〜3営業日前に、ITM幅が広いコールを一旦買い戻す(またはストライク引き上げのロールアップ)。
- 配当後にIVが上がったら、改めて売り直す。
プレミアムの時間価値がゼロ近辺の場合、行使のインセンティブが強く、現物を売られやすくなります。配当近辺は「時間価値の残り」を必ず確認しましょう。
6. ロール基準:いつ・どこへ・どれだけ
裁量の不一致を避けるために、ロール(買い戻して別満期・別ストライクで売り直し)の基準を明文化します。
- 含み益の90%を確保:オプション価格が建値の10%未満になったら買い戻し。残り価値の時間効率が悪いため。
- DTEが15日を切ったら:決済して30〜45日にロール。管理しやすく、ガンマリスクを抑制。
- 株価がストライクの1%以内に接近:相場が強ければ、ストライクを上にズラしつつ同クレジット以上を目安にロールアップ。
ロール時は「クレジットを維持または増やす」を原則とし、プレミアムの“取り直し”で年率を積む設計にします。
7. 具体例:SPYを用いた数値シミュレーション
仮にSPYを100株保有(価格500)、DTE 35日、Δ0.25付近(ストライク520)のコールを5.50で1枚売ったとします。受取は550ドル。満期時の概算は次の通りです。
- 株価が520以下:現物は520以下の価格で評価されるが、受取550が丸々利益。株価横ばいならインカムが光る。
- 株価が520超:520で売渡し(アサイン)となり、(520−500)×100=2000のキャピタルゲインに加え、受取550。ただし520超過分の上値は放棄。
この例では「横ばい〜緩やかな上昇」に強いプロファイルです。強烈な上昇局面では上値放棄が効きますが、その代償としてプレミアム積み上げで年率を整えるのが本戦略の思想です。
8. ミニ検証:IVPで建玉を間引く意義(ロジック思考)
データへの直接アクセスがない環境でも、ロジック上の意義は明確です。IVPが高い時にのみ売ると、同じΔでも受取プレミアムが厚くなり、(受取/拘束資本)の効率が向上します。また、IVは平均回帰しやすいため、売った後の低下(ボラクラッシュ)で早期利確しやすいという副次効果もあります。逆にIVが極端に低いと、わずかな上昇でITM化→上値放棄となりやすく、リスク・リワードが悪化しがちです。
9. リスクと対策:初心者がやりがちな落とし穴
9-1. 上値取り逃しのストレス
強い上昇相場では「売らなければよかった」という後悔が生まれます。これを避けるには、ポートフォリオの一部のみをカバード化し、残りは素の現物で上値を追う配分にするのが有効です(例:保有株の50〜70%に限定)。
9-2. 配当前の早期行使
前述の通り、配当落ち直前+時間価値が薄いITMは要注意。2〜3営業日前の点検と必要なら買い戻しをルーティン化します。
9-3. 決算・イベントのボラ急騰
決算前はIVが上がり、プレミアムは魅力的になりますが、ギャップでの大幅ITM化も増えます。決算回避またはストライク遠目+短DTEで素早く回転など、事前ルールを用意します。
9-4. ロールでのデビット化
ロール時に焦ってデビット(支払い)でリセットすると、収益が薄くなります。基本はクレジットでのロールを守り、建玉急がず「待てばIVが戻る」局面まで粘るのも手です。
10. 実務フロー:チェックリストで機械化する
- 対象の現物100株を用意(ETF可)。
- イベントカレンダー(決算・配当)を確認。決算週はパスまたは遠目のΔ。
- IVPを測る(70%以上ならフル、40%未満なら軽く)。
- Δ0.25±0.05のストライクから選定し、プレミアム月率0.8〜1.2%を満たすかを併用チェック。
- DTE 30〜45日でエントリー。
- 利確90%・DTE15日・ストライク接近のいずれかでロール。
- 配当前2〜3営業日にITMの時間価値を点検、必要なら回避措置。
- ポジション比率は銘柄ごとに上限(例:保有の70%まで)。
11. 応用:ダイアゴナルとホイール
中級者以上は、ダイアゴナル(遠い満期のコール買い+近い満期のコール売り)でボラ・期限の差を取りに行ったり、ホイール(プット売り→約定で現物取得→コール売り)で取得コストを下げる発想も活用できます。ただし、管理複雑度と手数料が増える点は認識しておきましょう。
12. サイジングとドローダウン想定
本戦略は現物ロングにコールショートを重ねるため、下落局面の防御は限定的です。ゆえに銘柄分散と現金比率の確保が効きます。簡易には、1銘柄=口座評価の10〜20%、総カバード比率=50〜70%程度から開始し、運用履歴に応じて調整します。最大ドローダウンは、現物の下落幅−受取プレミアムが下限イメージです。
13. まとめ:年率の“土台”を作る
カバードコールは「爆発的な大当たり」を狙う戦略ではありません。ボラに応じて厚くなるプレミアムを定常的に回収し、年率の土台を安定化するための仕組みです。Δ基準のストライク選定、IVPによる建玉濃淡、配当前の早期行使回避、ロール基準の固定化を実装すれば、初心者でもブレない運用が可能になります。最初の1単位から、履歴を可視化しながら拡張してください。


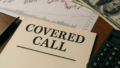
コメント