本稿では、個人投資家でも実践可能で、かつ「一般論」に終わらない具体的な収益機会として、IPO(新規上場)後のロックアップ解除に着目したイベント投資を解説します。ロックアップ解除日は、大株主やベンチャーキャピタル等が保有株を市場で売却できるようになる節目であり、需給の変化が予見しやすいことが特徴です。初心者でも再現できるように、調べ方・カレンダー化・売買ルール・資金管理・検証手順まで、手順書レベルで落とし込みます。
注意点として、本記事は教育・情報提供であり、特定銘柄の売買助言ではありません。記載内容の正確性・完全性は保証されず、投資判断は各自の責任でお願いします。過去のパターンが将来も通用するとは限りません。
1. ロックアップ解除とは何か(初心者向けの基本)
IPO時点で上場企業の大株主(経営陣、VC、事業会社など)には、一定期間、保有株を市場で売れない「ロックアップ」(売却制限)が付されるのが一般的です。典型的な期間は90日または180日、一部では1年以上のケースもあります。さらに、価格条件付き解除(例:公開価格の1.5倍到達で一部解除)のような条項が付く場合もあり、上場後の株価推移によってはロックアップが早期解除されることもあります。条項は銘柄ごとに異なるため、目論見書・上場時の開示資料で事前確認が必須です。
解除日(または解除条件成立)を境に、潜在的な売り圧力が顕在化する可能性があります。一方で、「解除=必ず下落」ではありません。業績トレンド、需給、空売り動向、テーマ性、需給イベントの重なり方次第では、下落・上昇・乱高下のいずれも起こり得ます。重要なのは、事前に分かる情報を系統的に整理し、シナリオごとに戦術を用意することです。
2. どこでロックアップ条項と解除日を確認するか
実務では、次の一次資料・公式情報を起点にします(操作は各サイトの最新UIに従ってください)。
- 目論見書(新規上場時):ロックアップ対象株主、期間、価格条件等の条項が明記されます。
- TDnet等の適時開示:上場承認時、またはその後の訂正・補足で条件が更新される場合があります。
- 有価証券報告書・四半期報告書:大株主構成や保有比率の変化、持株の移動などを確認できます。
特に目論見書の「ロックアップに関する事項」には、解除日、解除割合、例外(価格条件等)がまとまっています。解除対象株式数と想定フリーフロート(浮動株)の関係を算出することで、需給インパクトの相場観を持てます。
3. 需給インパクトの見積もり:5つの指標
解除イベントの強度を評価するために、最低限、以下の5つを計算・分類しましょう。
- 解禁株数:解除対象の株式数(例:○○万株)。
- フリーフロート比(FFR):市場で実際に流通している株式の概算比率。推定式の一例は、
FFR ≒ 発行済株式数 − (役員・主要株主・戦略保有分)を分子にし、発行済株式数で割る形です。 - 日次流動性:直近20営業日などの平均売買代金(例:5〜20日移動平均)。
- 解禁フロー比:
解禁株数 × 想定売却割合 ÷ 日次平均売買代金。1日で捌けるか、複数日かの見取り図になります。 - ショート・インタレスト:空売り残(公表値や証券会社データ等)と貸借区分。空売りが積み上がっていると、解除後の踏み上げリスク(逆方向)が生じます。
初心者は、解禁フロー比が高い(=需給の受け皿が小さい)のに、テーマ性・需給支援要因が弱い銘柄を「回避」する、という守備的な使い方から始めると良いです。逆に、強い下押しが出た後の戻り(需給の反動)を短期で狙う戦術もあります。
4. カレンダー運用:Excel/スプレッドシートでの実装
解除日を一覧にし、毎週メンテナンスするだけで、初心者でも「先回り」できます。シートの推奨カラムは以下のとおりです。
- 銘柄コード / 名称
- 上場日
- 解除日(90日 / 180日 / 1年 等)
- 解除株数(推定)
- 発行済株式数 / FFR(推定)
- 直近20日平均売買代金
- 貸借区分 / 空売り残 概況
- 価格条件付き解除の有無(例:1.5倍条件)
- 直近決算/業績トレンド
- テーマ性(AI、半導体、グリーン等)
- 備考(イベント重なる日など)
毎週末に翌週の解除予定を抽出し、「強い売り圧の可能性」/「需給の反動狙い」/「ノートレード」の3分類に仕分け、週次プランを作成します。慣れると、1週間分の警戒・狙い目リストが30分程度で整います。
5. 初心者向け2つの基本戦術
5-1. 守備型:回避と観察(学習重視)
まずは「危ない日」を避けるリスク管理から。解除前後はボラティリティが高まりやすく、板薄の小型株では特にスリップや逆指値の飛び約定が起きがちです。解除当日に用事がある日は、そもそも新規建てをしない判断が合理的です。観察に徹し、翌日以降の板回復を見極める方が、初心者の資本保全には有効です。
5-2. 攻撃型:需給の反動を短期で取る
解除当日〜数日で過剰に売られた銘柄は、出来高ピークアウトと共に短期リバウンドを狙えることがあります。典型パターンは次のとおりです。
- 解除当日、寄りまたは寄り後に大出来高で急落。
- 引けにかけて下げ渋り、翌日ギャップダウンが限定的。
- 2日目の前場で出来高が減衰、陰線の短縮や下髭が出る。
- 3日目以降で短期リバ(リバウンド)が出やすい。
この場合のエントリーは、出来高減衰+下げ止まりサインを条件化。エグジットは「2〜5営業日」「直近戻り高値」「平均回帰(5日移動平均)」などのルールで固定しておくと、初心者でもブレにくいです。
6. 具体例(架空データ)で理解する
以下は「A社(仮)」の架空事例です。実在銘柄ではありません。
- 上場日:4月1日
- 公開価格:1,000円
- ロックアップ:主要株主は180日、VCは90日。価格条件:株価が公開価格の1.5倍以上で一定日数維持の場合、VC分は早期解除。
- 発行済:2,000万株、想定FFR:25%
- 解除対象株数(180日):500万株
- 直近20日平均売買代金:15億円
仮に株価1,200円、出来高平均100万株/日(売買代金12億円)だとします。解除対象のうち30%が短期で売りに出ると想定すると、500万株 × 30% = 150万株。これは日次の平均出来高100万株を上回り、解禁フロー比 = 1.5日分です。需給的には一時的な下押しが出やすいシナリオになります。
一方で、空売り残が十分に積み上がり、当日寄り付きで需給が一気に掃けた場合、短期反発もあり得ます。初心者は「寄り成りで飛びつかない」「リバ狙いは出来高とローソクの縮小を待つ」など、観察→条件成立→機械的執行を徹底しましょう。
7. 売買ルールの雛形(コピペして使える)
7-1. ウォッチ条件
- 解除対象株数 ÷ 直近20日平均出来高 ≥ 1.0
- FFR ≤ 30%(浮動株が少ないほど需給は脆弱)
- 決算直前・直後は原則ノートレード(ファンダの変化が需給を上書きするため)
- 空売り残が直近で増勢 or 貸借銘柄
7-2. エントリー
- 解除日当日〜3営業日のみ検討対象
- 2日連続で実体陰線が短縮、かつ出来高が前日比−20%以上
- 終値が5日移動平均からの乖離率 −7%以内に縮小
7-3. エグジット
- 最大保有日数:5営業日
- 利確目標:エントリー価格比 +3%〜+6%の範囲
- 損切り:エントリー価格比 −2%(指値で厳格執行)
- ギャップダウンで損切り幅を超えた場合、寄り付きでクローズ
上記は一例です。最初は極小サイズ(例:想定最大損失が1日あたり口座資産の0.3%以内)で運用し、月次でルールを点検・改善してください。
8. 口座準備と実務フロー(初心者向け)
8-1. 証券口座の作り方(要点)
- ネット証券で口座申込(総合口座 + 特定口座[源泉徴収あり推奨])。
- 本人確認書類とマイナンバーをアップロード。
- 取引開始後は、信用口座の審査も通しておく(空売り残や貸借区分の実務で役立つ)。
8-2. 毎週の運用手順(テンプレ)
- 週末に翌週の解除銘柄を抽出(カレンダー更新)。
- 解禁フロー比・FFR・日次流動性・イベント重複をチェック。
- 「観察/狙い/回避」に色分けし、シナリオと執行条件を書面化。
- 各日、寄り前に板気配とニュースを点検。予定外イベント(業績・提携等)があれば見送り。
- 執行後はトレードノートを記録(根拠・感情・良かった点/改善点)。
9. リスクとよくある誤解
- 「解除=必ず下がる」は誤り。空売りの買い戻し、需給の出尽くし、テーマ強度で逆行も普通にあります。
- 流動性ショック:板の薄い小型株は、成行・逆指値の飛び約定が起こりやすい。指値中心、数量を刻む工夫が必須。
- イベント重複:決算・指数入替・大口ロックアップ複数解除が重なると、価格挙動は予測困難に。
- 条件読み違い:価格条件付き解除などの条項は、必ず一次資料で確認。
- 過度な集中投資:同一週の似た銘柄に同方向で偏らない。相関管理を徹底。
10. 検証(バックテスト)のやり方:手作業でも可能
厳密なシステム検証が望ましいものの、初心者は手作業ベースでも改善サイクルを回せます。
- 過去2〜3年のIPO銘柄をリストアップ。
- 各銘柄の解除日・解除株数・価格条件有無を記録。
- 解除日を「0日」として、前後−10〜+10営業日の価格・出来高を取得。
- 前掲の売買ルールで仮想エントリー/エグジットを記録。
- 勝率、平均損益、最大DD、保有日数、1トレードの期待値を算出。
「勝率は5割でも、損小利大で期待値+」という形を目指します。最大損失の制御(損切りの一貫性)と、想定外イベント時の撤退を徹底してください。
11. 応用:暗号資産・海外株への横展開
暗号資産では、トークンのベスティング解除(アンロック)が似た需給イベントです。開発チーム・投資家の配布分が解除されるスケジュールを見える化し、流通量の増加=売り圧候補として観察します。海外株でも、IPO後のロックアップ解除は一般的で、米国では90日/180日が多い印象です。いずれも、一次情報(ホワイトペーパーや目論見書・SEC/EDGAR等)での確認が出発点です。
12. まとめ:初心者が今日からできる3ステップ
- IPO銘柄のロックアップ条項を一次資料で確認し、解除カレンダーを作る。
- 解禁フロー比・FFR・流動性・空売り残で「観察/狙い/回避」を仕分け。
- 小さく実行 → ルールを固定 → 月次で期待値を点検・改善。
イベント投資の強みは「事前にわかる日付」を使えることです。カレンダー運用に落とし込み、焦らず、ブレず、資本保全を最優先に習熟してください。

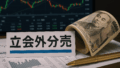

コメント