この記事では、夜間PTS(私設取引システム)での約定価格と、翌営業日の寄り付き価格の乖離(ギャップ)に注目し、統計的に優位性のある売買ルールを構築する方法を、初心者でも実践できるレベルまで分解して解説します。裁量の勘に頼らず、再現性と検証可能性を重視した手順です。過度なレバレッジを使わず、小さく始めて学びながら改善することを前提にしています。
1. この戦略のアイデア(なぜ機能し得るのか)
夜間のPTSは参加者が限定的で、板が薄く、情報の非対称性が大きくなりがちです。そのため、終値→PTS→翌日寄り付きの三者間で価格が「行き過ぎ」たり「戻り過ぎ」たりすることがあり、ここに小さな期待値が生まれます。具体的には、PTS終盤の価格と出来高、メインチャネル(東証)終値からの乖離率、翌朝の気配・板などから、平均回帰またはモメンタム継続のどちらが起こりやすいかを条件化します。
重要なのは「確率で戦う」姿勢です。単発の勝ち負けではなく、100回・1000回と同じルールを回したときの総合損益で判断します。そのために、あとで説明する検証(バックテスト)が不可欠です。
2. 前提知識の整理:用語と市場構造
2-1. PTSとは
PTS(私設取引システム)は、証券取引所以外での株式売買を可能にするシステムです。日本では夜間に取引できるPTSがあり、東証の立会時間外に価格が動きます。代表的には、証券会社の提供する取引画面からアクセスします。
2-2. 寄り付き(板寄せ)
東証の寄り付きは板寄せ方式で成立します。成行・指値注文が集められ、最大出来高となる価格で一気に約定します。寄り直前の気配値はあくまで暫定であり、直前の注文フローで大きく変化することがあります。
2-3. ギャップの定義
本記事では、終値、夜間PTS終盤の約定価格(例:21:59〜23:59の加重平均など)、翌日寄り付き価格の差を扱います。例えば、終値からPTSが+2%上に乖離し、翌朝の寄り付きで+1%まで戻る、という動きです。
3. 必要な準備:口座・ツール・データ
3-1. 証券口座の準備
まずは、東証の通常取引とPTS取引の両方に対応した証券口座を用意します。口座開設では、本人確認、マイナンバー提出、特定口座(源泉徴収あり/なし)の選択、NISAの有無などを順に完了します。手数料体系や夜間取引の可否、発注種別(寄成・不成・逆指値など)の対応状況を必ず確認してください。
3-2. 取引ツール
スマホだけでも可能ですが、分析はPC推奨です。板・歩み値・前日終値との乖離率を素早く確認できる画面レイアウトを作ります。寄り付き直前の板監視はミスを減らす要です。
3-3. データ源と記録
検証・改善のために、以下を毎日ログ化します。
- 対象銘柄の前日終値
- 夜間PTSの終盤価格(例:22:00〜23:59の加重平均、または最終約定価格)と出来高
- 翌日寄り付き価格・出来高
- 売買判断の根拠(乖離率、出来高閾値、ニュースの有無など)
- 実際の約定価格(成行到着価格)とスリッページ
- 手数料・貸株/信用金利・税引後損益
最初はExcelやGoogleスプレッドシートで十分です。慣れてきたら簡易スクリプトで半自動化します。
4. コアとなる売買ロジック
4-1. 乖離率ベースの平均回帰(リバート)
終値→PTSで一定以上の正乖離(例:+2%以上)が発生し、かつPTS出来高が閾値以上(例:東証の一日出来高の0.3%以上)なら、翌朝に逆方向(売り)でエントリーして、寄り付き〜ザラ場前半での平均回帰を狙う戦略です。逆に負乖離(-2%以下)では買いを検討します。
4-2. モメンタム(継続)
特定の条件(例:高出来高の情報イベント同伴、PTS連続成り買い、上位気配の厚い板)では、翌朝に乖離方向へ継続しやすいケースがあります。平均回帰とモメンタムを別ルールとして切り分け、事前にどちらを採用するか条件表を作るのが実務的です。
4-3. 銘柄フィルタ
流動性が極端に低い銘柄はスリッページが大きく、検証と実運用の乖離が起きやすいです。出来高・売買代金・スプレッドで最低基準を設定し、取引対象外リストを作ります。新興市場の急騰・急落銘柄は別ルール扱いにします。
5. 期待値の作り方:条件設計のステップ
- 母集団を定義(例:TOPIX Core30/100、売買代金上位◯銘柄、直近3か月でPTS出来高が一定以上)
- 特徴量を設計(終値比乖離率、PTS最終約定価格、PTS終盤VWAP、PTS出来高比率、気配板の厚み、直近ニュースの有無など)
- シグナル生成(平均回帰 or 継続を判定する二値/連続スコア)
- エントリー/クローズ条件(寄成 or 不成、前場10分で自動クローズ、または固定利確損切り)
- 資金配分と同時保有上限(1銘柄あたり上限金額、同時保有最大数、相関回避)
- コスト反映(手数料、スプレッド、到着価格、税金)
「乖離が大きいほど平均回帰が強い」という直感が通用するかは、必ずデータで検証します。閾値は0.5%刻みでスキャンし、勝率×損益比=期待値が最大になる帯を採ります。
6. 検証(バックテスト)の実務
6-1. データの作り方(手動→半自動)
最初の2週間は手で集めて構造を理解します。慣れたら、PTS終盤の約定履歴を毎晩コピーして集計し、翌朝に寄り付き価格を追記するフローをテンプレ化します。ExcelならVLOOKUP/XLOOKUP、ピボットで十分です。
6-2. 指標の読み方
- 勝率(%)
- 平均損益(円/%)と分布
- 最大ドローダウン(連敗と金額)
- プロフィットファクター(総利益/総損失)
- 日次・銘柄ごとの相関(同時エントリー数の最適化に関係)
検証では到着価格を保守的に置きます(例:寄成で気配が飛ぶ想定を-0.05〜-0.15%で調整)。また、ニュース伴う極端事例は除外ルールの条件として別集計しておきます。
6-3. 過剰最適化を避ける
条件を細かくしすぎると、見かけ上の成績だけが良くなります。期間分割(開発期間/検証期間)、銘柄分割(開発銘柄/検証銘柄)、モンテカルロでロバスト性を確認しましょう。
7. 実行フロー:寄り付きまでのチェックリスト
- 前日引け後にウォッチリストを更新(対象銘柄・流動性基準の見直し)
- 夜間PTS終盤で候補抽出(乖離率・出来高・連続約定)
- 候補ごとに「平均回帰」か「継続」かを事前ルールで判定
- 翌朝8:30〜8:59に板と気配を確認(異常ニュース・特別気配・気配の厚み)
- 寄成/不成の発注、もしくは寄り後◯分の成行/指値
- クローズ条件の自動化(逆指値・時刻指定成行)
- 約定後は必ずログに記録(根拠→結果→改善点)
8. 具体例:シンプル版ルールと結果のイメージ
以下は学習用の最小構成ルールです。
- 対象:売買代金上位200銘柄(直近3か月の平均)
- シグナル:前日終値比でPTS終盤VWAPが+1.5%以上かつPTS出来高が日中出来高の0.5%以上
- アクション:翌朝「平均回帰」を想定して寄成で売り(現物保有なら一部利確の代替)
- クローズ:前場30分で成行買い戻し(または+0.6%利確/-0.4%損切り)
このルールはあくまで教材例です。実際には、銘柄特性やイベント有無で結果が大きく変わるため、自分のデータで判定帯や利食い・損切り幅を最適化してください。
9. 発注の実務:寄成・不成・逆指値
寄り付き直後の価格飛び(ギャップ拡大/縮小)に備え、寄成は到着価格のブレを許容する前提です。スリッページを抑えたい場合は不成(成行化)を活用し、約定優先と価格管理のバランスを取ります。逆指値は想定外の継続トレンド時の保険として設定します。
特別気配が出た場合は無理に追いません。板寄せは一度の判断で大量に約定するため、想定外の価格でつかむリスクが上がります。
10. リスクと落とし穴
- 流動性リスク:板が薄い銘柄は見送る。出来高基準と気配の厚みでフィルタ。
- イベントリスク:決算・開示・レーティング変更は別ルールに。平均回帰が効きにくい。
- 到着価格のズレ:寄成の約定は気配より不利になることがある。検証時に保守的に見積もる。
- 同時エントリー過多:相関で損益が偏る。最大同時ポジション数を制限。
- 手数料・税金:小さな期待値がコストで消えないように、必ず実コストで検証。
11. 初心者向けの資金管理
1銘柄あたりのリスクを資産の0.5%以内に抑える目安から始めます。例えば100万円なら、1トレードの想定損失は最大5,000円。損切り幅と数量から逆算して建玉サイズを決めます。連敗を前提に、口座破綻確率を下げる運用を徹底します。
12. ログテンプレート(そのまま使える)
| 日付 | 銘柄 | 終値 | PTS終盤VWAP | 乖離率% | PTS出来高比% | 判定 | 発注 | 寄付 | クローズ | 損益% | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YYYY-MM-DD | XXXX | 1,000 | 1,016 | +1.6 | 0.8 | 平均回帰 | 寄成売 | 1,014 | 1,004 | +0.98 | 板厚十分 |
勝率だけでなく、損益分布と連敗の深さを可視化すると継続しやすくなります。
13. 自動化の方向性(任意)
半自動から始め、次の順で効率化します。
- データ収集のテンプレ化(コピー&ペーストの固定手順化)
- スプレッドシートの関数化(乖離率・条件判定を自動計算)
- 売買候補の自動リスト化(色付け・通知)
- 最終判断のみ手動、発注は定型(寄成/不成+逆指値)
いきなり全自動にせず、監督された自動化でミスを減らします。
14. よくある質問(FAQ)
Q1:小資金でも効果はありますか?
A:可能です。ただしコスト比率が高くなりやすいので、流動性の高い銘柄のみ、最小限の回数から始めます。
Q2:ニュースの影響は?
A:決算などの情報イベントは平均回帰が崩れやすいです。イベント銘柄は除外か別ルールで。
Q3:いつ検証を更新すべき?
A:相場環境の変化(ボラ・出来高)の節目ごとに3か月ローリングで見直します。
Q4:信用・空売りは必須?
A:売りを使う平均回帰ルールでは有効ですが、リスクが上がるため、現物の利確代替(保有の一部売り)から学ぶ選択もあります。
15. まとめ:小さく始め、確率で積み上げる
夜間PTSと翌日寄り付きのギャップは、市場構造上の歪みから生まれる小さな期待値です。再現性のあるルールと堅実な資金管理で、統計的に利益を積み上げることを目指します。日々のログと検証が、最強の武器になります。
最初の一歩は、「昨日の終値」「PTS終盤VWAP」「翌朝寄り付き」の三点を10銘柄だけで2週間、記録してみることです。そこから、あなた自身の優位性が見えてきます。
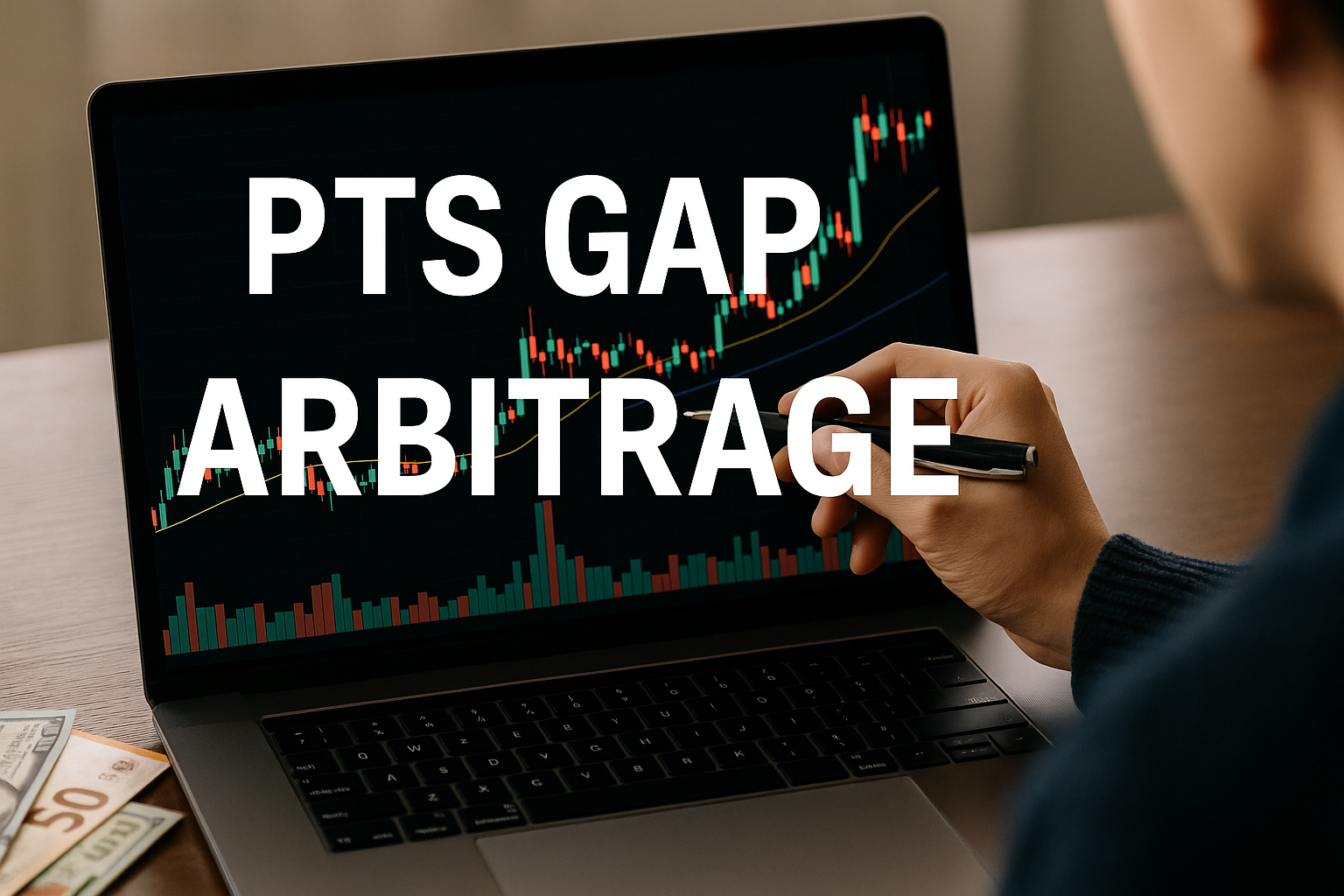
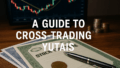
コメント