債券価格と金利のシミュレーション例
ここで、具体例を挙げます。
ケース設定
- 額面:100円
- クーポン:2%(年2円支払)
- 残存期間:5年
- 市場金利(割引率):1%、2%、3%の場合
計算式適用
債券価格 = 各年のクーポンと償還元本を市場金利で割り引いた合計。
市場金利別に債券価格を求めると:
| 市場金利 | 債券価格(概算) |
|---|---|
| 1% | 約104.7円 |
| 2% | 約100.0円 |
| 3% | 約95.4円 |
→ 金利が上がると価格が下がることが数値でもはっきり確認できる。
(※正確な値はディスカウントファクターを各年ごとに適用して足し合わせる。)
実務での金利リスク管理:ヘッジとデュレーションマッチング
金融機関やプロ投資家は、金利リスクをコントロールするために以下を行う。
デュレーションマッチング
負債側(例:年金支払いなど)と資産側(保有債券など)のデュレーションを一致させる。
→ 金利変動による資産と負債の価値変動を相殺し、リスクを中立化。
例:
- 負債の平均デュレーションが7年なら、債券ポートフォリオのデュレーションも7年に調整。
債券先物・金利スワップによるヘッジ
- 債券先物を売ることで、保有債券の価格下落リスクをヘッジ。
- 金利スワップ(固定支払い・変動受取り)で金利上昇リスクをカバー。
逆イールドカーブと債券市場の意味
通常、長期債の金利>短期債の金利。
しかし時に逆転する現象を**逆イールド(逆ザヤ)**と呼ぶ。
逆イールド発生時の市場解釈
- 「将来景気後退リスク」が高まったシグナル。
- 金融政策(短期金利)だけが高止まりし、長期の成長期待が低下している状態。
逆イールドは高い確率で景気後退を予告してきた歴史的事例が多数存在(例:米国リセッション直前)。
債券価格に影響するその他の要素
金利以外にも、以下要素で価格は変動する。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| クレジットリスク(信用リスク) | 発行体が倒産するリスク。リスクが高いとスプレッド(上乗せ金利)が要求され、価格は下落する。 |
| 流動性リスク | 売買が成立しにくい債券はプレミアムを失いやすい。 |
| 税制 | 利子にかかる税率変更による影響。 |
| 早期償還リスク(コーラブル債) | 発行体が有利な時点で繰上げ償還する可能性がある債券は、上昇余地が制限される。 |
特に、社債市場では金利変動+信用リスクプレミアムの複合影響で価格が大きくブレる。
【注意点】よくある誤解
「金利上昇ならすべての債券が暴落」は誤り
- 残存期間が短い(たとえば1年未満)の短期債は、金利上昇でも価格変動が軽微。
- フローティング債(変動金利債)は逆に価格安定しやすい。
「利回りが高い債券は常にお得」も誤り
- 高利回り=高リスク(信用リスク・流動性リスク)が内包されている可能性が高い。
- 例:ジャンク債(投資不適格級債券)は高利回りだが、デフォルト率も高い。
【ここまでの全体像まとめ】
債券価格=将来キャッシュフロー÷(1+金利)
- 金利と価格は逆方向に動く。
- 金利だけでなく信用リスク・流動性リスク・政策動向も価格に影響。
- デュレーションで金利感応度を管理。
- 実務ではヘッジやデュレーション調整でリスクコントロール。

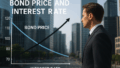
コメント