バフェットの「通貨嫌い発言」は偶然ではない
2025年のバークシャー株主総会で、ウォーレン・バフェットは異例とも言える明確な通貨観を表明した。彼は日本円について「今後どうなるか容易に想像できる」と述べ、米ドルについては「地獄行きの通貨だ」と断じた。これは通常、特定の通貨について公の場で語ることを避けてきた彼にとって、明らかな変化である。
この発言の裏にあるのは、通貨の信用そのものがグローバルに劣化し始めているという確信だ。
「信用通貨の限界」を見抜いた巨人
バフェットはインフレが本格化し始めた2020年以降、明らかにマクロ経済を意識した行動を取り始めた。特に象徴的なのは、日本の五大商社への投資だ。この投資は日本円建てで、なおかつ借入(低利の円ローン)で行われた。
この戦略は、円安とインフレを見越した**「円キャリートレードの応用形」**である。彼は円の価値が長期的に毀損されることを見越し、円建て負債を実質的に減価させながら、実物資源を扱う企業に投資するという二段構えのポジションを取ったのだ。
これにより彼は、通貨の信用低下そのものをヘッジ可能な「マクロ・アルファ戦略」を構築したことになる。
米ドルは本当に「地獄行きの通貨」なのか?
米国も例外ではない。FRBの急激な利上げが注目される中で、実質金利は低下傾向にあり、バフェットの目には「国債乱発 → 市場の通貨希薄化 → 実質負債の帳消し」というMMT的インフレ財政の出口戦略が映っている。
これは金融抑圧(Financial Repression)の現代版であり、富の実質的な再分配を意味する。つまり、インフレによって「通貨を持つ者が損をし、負債を持つ者が得をする」世界がすでに始まっている。
バフェットはこれを見抜いたうえで、「通貨を信用するな。実物を買え」と言っているに等しい。
個人投資家が学ぶべき3つの戦略
① 通貨建て資産から実物建て資産へシフト
現金や預金、債券の比率が高いポートフォリオは、インフレ下では構造的に不利になる。代わりに、株式(特にコモディティやリアルアセット系)、金、不動産など、実体価値のある資産への分散が有効となる。
② 円キャリートレードの個人版
日本の低金利は変わらず、円建てローンの実質コストは極めて低い。これを利用して海外ETFや金、コモディティ連動ファンドに投資するなど、**「借りて買う戦略」**が現実味を帯びてくる。ただし為替リスクには十分な管理が必要。
③ 通貨分散の徹底
円もドルも「相対的にはマシ」というレベルに近づきつつある。これは裏を返せば、絶対的な信用を置ける通貨は存在しないという状況。USドル、シンガポールドル、スイスフランなどへの通貨分散、ステーブルコインを使った短期金利運用(USDC, USDTなどのレンディング)も選択肢として浮上する。
結論:バフェットの発言は通貨の終わりを示唆しているのか?
バフェットは明言こそしていないが、「通貨はもはや信頼できる価値保存手段ではない」と認識している。これは中央銀行の過剰介入、財政赤字の慢性化、地政学的分断による通貨ブロックの形成といった背景から導かれる必然的帰結だ。
個人投資家も今後、**「資産を増やす」ではなく「資産を守る」**という視点を持つ必要がある。そしてその鍵は、まさに通貨リスクをどうヘッジするかにかかっている。

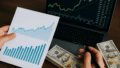

コメント