本記事は、ADR(American Depositary Receipt)と現地株のパリティ裁定を、個人投資家が再現性高く運用することを目標に、理論・オペレーション・執行・ヘッジ・バックテスト・検証体制までを端から端まで解説するものです。単なる等価式の紹介に留めず、税引後配当・借株レート・デポジタリ費用・清算差・執行スリッページ・イベントといった実務要因を式に落とし込み、bp(ベーシスポイント)で管理する運用フレームを提示します。
- 1. 戦略の射程と前提(なぜ個人で成立するのか)
- 2. パリティ式の厳密化(等価価格と調整項)
- 3. 税引後配当・デポジタリ費用の実務
- 4. 借株市場のメカニクス(GCとSpecial)
- 5. マイクロストラクチャと時間帯リスク
- 6. 検出アルゴリズム(ボラ連動・在庫連動)
- 7. 執行アルゴ:同時性と為替ヘッジ
- 8. 保有・クローズのルール
- 9. ケーススタディ(数値で読む3例)
- 10. バックテスト設計(落とし穴を潰す)
- 11. オペレーション設計(口座・受渡・資金繰り)
- 12. 監視ダッシュボード仕様(必要な指標)
- 13. リスク整理(15項目)
- 14. よくある落とし穴と対策
- 15. 拡張:GDR、二重上場、香港経由
- 16. 実装テンプレ(設定→計算→執行)
- 17. 日次・トレード前チェックリスト
- 18. まとめ
1. 戦略の射程と前提(なぜ個人で成立するのか)
ADRと現地株は同一企業のキャッシュフロー権にリンクします。機関投資家は大規模裁定で乖離を圧縮しますが、時間帯のズレ・借株在庫の制約・配当税務・細かなコストが作る局所的ギャップは取り残されます。個人が狙うのは、分単位〜数日単位の中頻度裁定であり、以下の特性を狙います。
- 現地市場の休場/薄商い時間帯に米国サイドだけが動いた時の遅延
- 配当権利付き/落ち前後での税引後価値のズレ
- 特殊在庫化による一時的なショートコスト上昇に伴うパリティ歪み
- ADR比率変更・スピンオフ・分割等で過去系列の連続性が切れた直後の誤配
以上は情報の入手と式の整備で再現可能であり、1トレードあたり20〜80bp程度を狙う現実的な期待値設計が可能です(あくまで設計の話であり、将来の成果を保証するものではありません)。
2. パリティ式の厳密化(等価価格と調整項)
ADR1枚が現地株R株に相当すると定義します(例:R=1,2,5,10 等)。為替はADR通貨→現地通貨のFXで統一します。基本形は次の通りです。
Par_local = Price_ADR × R × FX
Adj_div = PV( Div_local × (1 - t_local) ) - PV( Div_ADR × FX × (1 - t_ADR) )
Adj_borrow = Notional_short × ( r_short - r_rebate ) × (HoldDays/365)
Adj_fees = Notional_total × ( fee_bp / 10,000 )
Adj_depo = ADR特有のデポジタリ費用 × R × FX(配当時の控除も含む)
Adj_clear = 受渡/資金繰り差の金利相当(資金拘束の時間価値)
Eq_local = Par_local + Adj_div + Adj_borrow + Adj_fees + Adj_depo + Adj_clear
Misprice_bp = ( Price_local - Eq_local ) / Eq_local × 10,000
運用上は Misprice_bp ≥ Entry で片側ショート/ロングを同時構築、Misprice_bp → 0でクローズします。Entry/Exitは後述のボラティリティ連動で動的にします。
3. 税引後配当・デポジタリ費用の実務
配当は税引後ベースかつ同一通貨で比較します。ADRはデポジタリ銀行の費用(ADR fee)が配当支払時に控除されることがあり、これは1枚あたりの固定セントまたは保有割合連動で差し引かれます。現地株側も源泉税率に従って課税後の受取額にします。支払通貨・時点が異なれば、割引現在価値で合わせます。
PV(配当) = 配当額 × (1 - 源泉税率) × exp(-r_dom × Δt)複数の配当イベントが保有中に跨ぐ場合、それぞれを加算します。スクリップ配当やオプション配当は、受領手段で税務が変わるため事前に前提を固定します。
4. 借株市場のメカニクス(GCとSpecial)
ショート側には借株料(または現金担保のリベート控除後レート)が発生します。一般担保(GC)水準は低いですが、需給逼迫でSpecial化すると年率が二桁に跳ねます。裁定ではエントリー前の在庫確保(Locate)と、在庫切れ時の強制クローズ条件を明確化します。
BorrowCarry = Notional_short × (r_short - r_rebate) × HoldDays/365短期勝負(数日)ならCarry負担は軽微ですが、配当跨ぎやイベント跨ぎは一気に重くなります。借株レートのシナリオを複数用意し、Entry閾値に上乗せします。
5. マイクロストラクチャと時間帯リスク
日本市場(現地株)と米国市場(ADR)の時間帯は重なりが限定的です。板厚・スプレッド・ティックサイズ・呼値ルールの差がスリッページを生みます。設計として、時間帯ごとにEntry閾値を上げ、米国寄り・現地前場寄りでの執行は注意度を引き上げます。
6. 検出アルゴリズム(ボラ連動・在庫連動)
Mispriceをbpで算出し、ボラティリティ(実現/インプライド)と在庫状況で閾値を自動調整します。
Entry_bp = k0 + k1 × RealizedVol_20d + k2 × SpecialDummy + k3 × EventRiskDummy
Exit_bp = min(α × Entry_bp, 固定値)SpecialDummyは借株レートが閾値超過時に1、EventRiskDummyは決算・配当・比率変更前に1とします。これにより、リスク上昇局面では自然にハードルが引き上がります。
7. 執行アルゴ:同時性と為替ヘッジ
- 同時成行(クロス):リッチ側を先取りショート→即Cheap側ロング。板監視で複数枚に分割。
- 指値・参加率制御:参加率(Participation Rate)を30〜50%に制限し、過度な価格インパクトを抑制します。
- 為替ヘッジ:FXスポット/先物/NDFで名目為替露出を即時にゼロ化。短期は自然ヘッジでも可ですが、イベント時は厳格にヘッジします。
- スリッページ予算:1トレードあたりの許容bpを事前に定め、発注時に残余bpをリアルタイム更新します。
8. 保有・クローズのルール
クローズは以下の複合条件の最初にヒットしたもので実行します。
- Misprice_bpがExit_bp以下(収斂達成)
- 借株レートが閾値超過(Carry悪化)
- イベント前のタイムアウト(n営業日前)
- ボラ急騰でEntry_bpが動的に引き上がり、現保有の想定リスクリワードを下回った場合
9. ケーススタディ(数値で読む3例)
9.1 標準ケース(R=1, GC、非イベント期)
現地株 = 12,800 JPY
ADR = 81.00 USD
USDJPY = 158.50
配当 = 現地70 JPY(税後63)、ADR0.45 USD(税後0.405)
借株 = 3%/年、保有5日(ショート側にのみ)
費用 = 往復30bp、デポジタリ費用=0.02 USD/ADR(配当時)
Par = 81×158.5=12,838.5
DivAdj = 63 - (0.405×158.5) = 63 - 64.2 = -1.2
Fees = 12,838.5×0.003 = 38.5
Depo = 0.02×158.5 = 3.17
Borrow = 12,800×0.03×5/365 = 5.26
Eq = 12,838.5-1.2+38.5+3.17+5.26 ≈ 12,884.2
Mis = (12,800-12,884.2)/12,884.2×10,000 ≈ -65.2bp → 現地ロング/ADRショート9.2 配当跨ぎ(ADR側の配当が大きい)
ADR配当が大きいとDivAdjはマイナスに振れ、ADRショート側のコストが嵩みます。権利付き最終日前はEntry_bpを+20〜40bp上げ、ショートを避けます。
9.3 借株Special化
借株年率 18%、保有7日 → Borrow ≈ Notional×0.18×7/365
Mispriceが+80bpでも、Carryで相殺される可能性大 → Entryを120bpに引上げ10. バックテスト設計(落とし穴を潰す)
- 系列整備:ADR比率変更・株式分割・スピンオフをイベントで分割し、別系列として扱います。
- 先見バイアス除去:配当・借株レートは告知時点の情報でのみ反映。配当実績で後知恵を入れない。
- コスト過大評価:手数料・スリッページ・借株は実運用より厳しく置く(例:+10〜20bp上乗せ)。
- 板再現:参加率・指値の不出来を再現(部分約定、キャンセル、滑り)
- サブサンプル:通常期/決算期/配当期/高ボラ期で性能を分解。
勝率・平均獲得bp・保有日数・最大DD・Turnover・容量(1日の許容回転額)を主要KPI化。11. オペレーション設計(口座・受渡・資金繰り)
- ADR用の米ドル建て口座と、現地株用の現地通貨口座を用意します。
- 受渡(T+2等)の差で資金が一時的に片側拘束される点を想定し、短期の金利コストをAdj_clearに入れます。
- ブローカーとの借株在庫とレートの確認は発注前に行います(Locate番号の記録)。
- 配当の受領通貨が異なる場合は、実際のFX変換手数料もAdj_feesに含めます。
12. 監視ダッシュボード仕様(必要な指標)
- Misprice_bp(リアルタイム)/閾値(Entry/Exit)/残余bp(コスト控除後)
- 在庫:借株年率・在庫量・Specialフラグ
- イベント:配当日、決算日、比率変更予定、休場情報
- 執行KPI:参加率、平均滑り、VWAP差、Fill率
- ポジション:通貨別名目、為替ヘッジ残、キャッシュ拘束
13. リスク整理(15項目)
- 借株在庫切れ・レート急騰
- 配当税務の取り違え(税率・控除・デポジタリ費用)
- 為替急変・ヘッジ漏れ
- 決算ギャップ・ガイダンスショック
- 比率変更・スピンオフ・合併
- 清算・受渡の遅延や資金拘束
- ブローカーの規制制限(空売り規制、アップティックルール)
- 板薄による約定不能・誤発注
- ハードフォーク的な権利(希少、扱い不確実)
- 配当通貨差による為替コスト
- デポジタリ手数料の事後控除
- 税務更正・遡及処理
- データ欠損・誤系列による誤検出
- オペレーションエラー(片側のみ約定)
- 想定外の市場休場
14. よくある落とし穴と対策
- 落とし穴:ADR比率の古いまま運用 → 対策:日次で比率同期、履歴で系列切替。
- 落とし穴:配当の税後換算を忘れる → 対策:税率テーブルを銘柄マスタに持つ。
- 落とし穴:在庫を取らずに発注 → 対策:Locate必須フラグ。
- 落とし穴:スプレッド縮小前に板が消える → 対策:参加率制御+段階指値。
15. 拡張:GDR、二重上場、香港経由
GDRや二重上場(米国・英国・香港など)のクロスも同様の枠組みで扱えます。取引規制・通貨規制・保管振替可否の差をAdj_clear/Adj_feesへ反映します。
16. 実装テンプレ(設定→計算→執行)
# 設定 YAML 例
symbol: XYZ
ratio_R: 1
fx_pair: USDJPY
fees_bp: 30
borrow_rate: 0.03
rebate_rate: 0.00
hold_days_max: 5
entry_bp_base: 40
exit_alpha: 0.5
event_buffer_days: 2
# Misprice 計算(擬似)
Eq_local = ADR*R*FX + DivAdj + Borrow + Fees + Depo + Clear
Mis_bp = (Local - Eq_local)/Eq_local*10000
# 閾値
Entry = entry_bp_base + 1.5*RealizedVol20d + 40*Special + 25*Event
Exit = min(exit_alpha*Entry, 60)
# 執行
if Mis_bp <= -Entry: # 現地割安
short(ADR); buy(Local); hedge_fx()
elif Mis_bp >= Entry: # ADR割安
short(Local); buy(ADR); hedge_fx()
17. 日次・トレード前チェックリスト
- 比率・配当・税率・デポ費用・在庫・借株レートを更新したか
- イベントカレンダー(決算・配当・休場)を反映したか
- 閾値が当日のボラ・在庫状態に連動して再計算されているか
- 執行口座・為替ヘッジ手段・資金繰りを確認したか
- ストップアウト基準(在庫切れ、レート急騰)が明文化されているか
18. まとめ
ADR–現地株パリティ裁定は、「小さな要因」を全て式に載せてbp管理することで、再現性のあるリスクリワードに変換できます。重要なのは、税後配当・借株・デポ費用・清算差の4点を常に最新化し、時間帯・イベントに応じてEntryを調整する運用規律です。小規模で始め、ログとKPIで改善を回すことを推奨します。

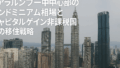
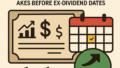
コメント