本稿は、日本株のβニュートラル個別株×指数先物ペアトレードを、個人投資家のオペレーションに落とし込むための完全実務ガイドです。一般論は排し、β推定の数理・整数制約下のヘッジ設計・イベント管理・約定品質・コスト把握・バックテストの落とし穴・日次運用手順まで、現場で躓く論点を順番に潰します。狙いはただ一つ、市場方向(ベータ)を剥ぎ取り、固有リターン(アルファ)のみを抽出して獲得することです。
- 0. 全体像(3行まとめ)
- 1. 数理設計とヘッジ比率(単因子・二因子)
- 2. 整数丸めの厳密化(過不足ヘッジを最小化)
- 3. 市場マイクロストラクチャ(約定品質をKPI化)
- 4. ユニバース選定(流動性・貸借・イベント耐性)
- 5. データパイプライン(個人向け最小構成)
- 6. β推定の実務上の罠と対処
- 7. シグナル定義(残差Zとダイナミック閾値)
- 8. ボラティリティ・ターゲティングとサイズ管理
- 9. コストの設計とKPI運用
- 10. 具体シミュレーション(数値で腹落ちさせる)
- 11. イベント・禁止期間・例外処理
- 12. リスク管理(定量ルールを紙に落とす)
- 13. バックテスト設計(やり直しの効く枠組み)
- 14. マルチ銘柄・ポートフォリオ化
- 15. 運用オペレーション(日次・週次・月次チェック)
- 16. 失敗例カタログと是正策
- 17. 具体ワークフロー(テンプレート)
- 18. さらに踏み込む拡張
- 19. 実務チェックリスト(配布用)
- 20. まとめ
0. 全体像(3行まとめ)
- ロングしたい銘柄iの市場感応度(β)を、日経225/TOPIXでロバスト推定。
- 金額ベースで先物の枚数を整数丸めし、残存βを±5%以内に抑える。
- 残差のZスコアで仕掛け・手仕舞い、イベントとコストを徹底管理。
1. 数理設計とヘッジ比率(単因子・二因子)
時点の株式リターン r_i(t) と市場リターン r_m(t) に対し、OLSで r_i = α + β r_m + ε を推定。二因子版は r_i = α + β_NK r_NK + β_TX r_TX + ε 。βは対数収益基準で60営業日ローリング、外れ値を5%ウィンザー化、推定はHuber回帰を推奨。
金額ヘッジの基本式:
市場リスク金額 = β̂ × 現物時価、先物エクスポージャー = 先物価格 × 乗数 × 枚数。
単因子なら k = round( (β̂ × 現物時価) / (先物価格 × 乗数) )。二因子なら各指数で同様に算出し、k_NK, k_TX を整数丸め。
乗数:日経225ミニ=100円、TOPIX先物=1,000円。乗数は収益感度のスケールそのものなので、発注前に必ず当日の約定値で再計算。
2. 整数丸めの厳密化(過不足ヘッジを最小化)
先物枚数は整数のため、丸め方向が残存βに直結します。推奨は、丸め候補 {floor, round, ceil} をすべて試し、残差分散の推定最小を選ぶ手順です。
- 候補ごとの残存β
β_res = β̂ − (先物金額/現物時価)を計算。 - 直近60日で
Var(ε + β_res·r_m)を推定。 - 最小の候補を採用(同値ならコストの低い方)。
二因子でも同様に、(k_NK, k_TX) の近傍格子点を探索し、分散最小の組合せを選定します(探索点は各±1で十分)。
3. 市場マイクロストラクチャ(約定品質をKPI化)
東証の板は呼値制約・板厚・時刻帯で性質が変わります。重要なのは、スプレッドの半分以内での約定と、先物→現物の時間差によるβ取りこぼしを抑える順序です。
- 時間帯:寄付き・引けはギャップと指値密度が高い。日中は板が薄く一撃コストが大きくなりがち。
- 順序:通常は現物→先物でヘッジを合わせる。シグナルが先物主導の場合は逆順で滑りを抑える。
- KPI:実質スプレッド(約定値−中値)/中値、到達率(目標価格±Xbp内で約定した割合)、平均実現スリッページ(bp)。
4. ユニバース選定(流動性・貸借・イベント耐性)
実務で最初に効くのは流動性の厳格フィルタです。
- 出来高・売買代金:20日平均売買代金が5億円以上(最低ライン)。
- 貸借:制度信用の有無、貸借銘柄は逆日歩リスクを監視(本戦略はロングのみが基本だが、ショートも使う拡張を想定)。
- イベント頻度:決算が四半期に偏る銘柄はイベント禁止期間が多くなるため不利。
- 指数適合性:日経寄与度が高い大型株は225ミニ、業種分散の高いバスケットはTOPIXが適合。
5. データパイプライン(個人向け最小構成)
- 価格:終値・出来高の時系列(現物・先物)。
- 企業イベント:決算予定、臨時IR、分割・併合、インデックス入替。
- 派生:対数収益、ローリングβ、残差、Z、実現ボラ。
- 永続化:日次CSVでログ(エントリー根拠は必ず記録)。
β更新は週次、イベント週は臨時更新。残差とZは日次更新。約定ログは取引毎に追記。
6. β推定の実務上の罠と対処
- 外れ値:決算や一時的急落はβを壊す。ウィンザー化+Huberで耐性を付ける。
- 構造変化:事業転換・M&Aでβが飛ぶ。R²の閾値(例:0.2未満で除外)を運用ルールに埋め込む。
- 縮小推定:Vasicekの考え方でβを市場平均1に縮めるとノイズ低減(β* = w·β̂ + (1−w)·1)。
- 非同期:先物と現物の価格タイムスタンプずれ。日足なら終値同期、分足なら先物主導の遅延を1本分補正。
7. シグナル定義(残差Zとダイナミック閾値)
残差 ε を60日で標準化して Z = (ε−μ)/σ。固定閾値 |Z|≥1.5 でも良いが、ボラ regime で調整するのが実務的です。
- 低ボラ regime:
|Z|≥1.2 - 標準 regime:
|Z|≥1.5 - 高ボラ regime:
|Z|≥1.8
イグジットは Z→0 回帰、または時間切れ10〜15営業日、または |Z|≥3 の異常で損切り。
8. ボラティリティ・ターゲティングとサイズ管理
ポジションサイズは残差の実現ボラでスケーリングします。標準偏差 σ_ε(年率)と目標ボラ σ* の比で現物金額を決め、そこから先物枚数を求めると、銘柄間で均質なリスク配分が可能になります。
現物時価 ≈ 口座資産 × リスク配分比率 × (σ*/σ_ε)
9. コストの設計とKPI運用
本戦略はコスト鈍感だとすぐ死にます。月次でbp集計し、残差ボラに対する比率で管理してください。
| コスト項目 | 評価方法 | 対策 |
|---|---|---|
| 手数料 | 売買代金×定率+最低手数料 | 手数料の低いプランに統一 |
| スプレッド | 中値からの乖離bp | 指値・板厚確認、寄引け活用 |
| スリッページ | 目標価格との差bp | 分割発注、発注順序の固定化 |
| 先物ロール | 限月スプレッド | ロール週の新規抑制、事前移管 |
| 金利・配当差 | 先物の理論価格との差 | ロング期間を短く保つ |
経験則として、総コスト < 残差年率ボラの1/4 を超えない運用を心掛けると、シャープが潰れにくいです。
10. 具体シミュレーション(数値で腹落ちさせる)
10.1 大型テック系(単因子ヘッジ)
前提:銘柄Aを1,000株ロング、株価13,500円、現物時価=1,350万円。β̂=1.10(225)。225ミニ価格38,000、乗数100。
必要枚数 k = round( (1.10×13,500,000) / (38,000×100) ) = round(14,850,000/3,800,000) = 4枚。残存βの概算は β_res ≈ 1.10 − (4×3,800,000/13,500,000) ≈ 1.10 − 1.1259 ≈ −0.026(許容内)。
翌日、市場+2%、銘柄+0.5%(相対弱)。
現物P&L=+67,500円、先物P&L=−(2%×3,800,000×4/乗数補正)=概算−304,000円(実際は乗数×価格単位で計算)。合算は−、だが残差Zは縮小→手仕舞いで損小。逆に市場−2%、銘柄−0.5%なら合算+に傾く。ここで重要なのは、市場方向ではなく相対性能だけが効いていること。
10.2 二因子ヘッジ(β_NK=1.0, β_TX=0.3)
現物1,350万円、225ミニ38,000、TOPIX2,700。
k_NK = round( (1.0×13,500,000)/(38,000×100) )=4、k_TX = round( (0.3×13,500,000)/(2,700×1,000) )=2。
分散計算で4枚/2枚と3枚/2枚の候補を比較し、残差分散最小の組合せを採用。
11. イベント・禁止期間・例外処理
- 決算・臨時IR:前後±3〜5営業日は新規禁止。既存ポジは縮小。
- 入替・分割・併合:βが飛ぶため除外、またはβを臨時再推定。
- PO/TOB:需給が歪み統計性が消える。直ちに手仕舞い。
12. リスク管理(定量ルールを紙に落とす)
- 最大残存β:±5%(超過でヘッジ再調整)。
- 1銘柄当たりの許容損失:口座資産の0.5〜1.0%(Z=3到達で損切り)。
- 同一セクター集中:ウェイト上限25%(相関事故回避)。
- 先物ロール週のリスク縮小:総エクスポージャーを30%削減。
- ギャップ耐性:寄り前に逆指値再セット、気配監視。
13. バックテスト設計(やり直しの効く枠組み)
過去検証は「できる前提にしない」が鉄則です。
- 情報遅延:β推定は前日終値まで、シグナルの執行は翌日寄りか日中に限定。
- コスト:スプレッド半分+手数料+ロールコストを銘柄ごとに付与。
- 整数制約:先物枚数は整数、現物は売買単位(100株等)に合わせる。
- 評価指標:年率シャープ、Sortino、Calmar、勝率、PF、平均保有日数、ターンオーバー。
- 停止ルール:ドローダウン15%・連敗10回で一時停止→パラメタ見直し。
14. マルチ銘柄・ポートフォリオ化
単銘柄は統計ぶれが大きい。20〜50銘柄の分散が効率的です。βは銘柄別に推定するが、ヘッジはポートフォリオ合算で一括計算すると残存βが縮まります。
加えて、銘柄間の相関を取り入れたリスクパリティや最小分散配分を使うと、Zの閾値は保守的でも資本効率が上がります。
15. 運用オペレーション(日次・週次・月次チェック)
- 日次:Z更新、イベント確認、残存βチェック、約定ログのKPI更新。
- 週次:β再推定、R²/分散の健全性、ポジション再評価。
- 月次:コストbp集計、残差ボラ比、ドローダウンレビュー、パラメタ調整。
16. 失敗例カタログと是正策
丸めバイアス放置:常に繰り返し最小分散丸めで是正。
コスト軽視:スリッページを記録し、発注手法(寄引け/板厚時刻/分割)を毎週見直し。
イベント突入:自動禁止期間の実装。
ユニバース過大:流動性閾値を引き上げ集中度を管理。
17. 具体ワークフロー(テンプレート)
- ユニバース作成(流動性・貸借・イベント耐性でフィルタ)。
- β推定(60日・Huber・5%ウィンザー・必要なら二因子)。
- 残差・Z算出、ボラ regime で閾値調整。
- エントリー候補抽出(|Z|≥1.5相当)。
- 金額ベースで先物枚数計算、整数丸めは分散最小ルール。
- 現物→先物の順に約定、KPI記録。
- イグジット:Z→0、または最大15営業日、または|Z|≥3で損切り。
- 週次でβ・R²・残存β・コストをレビュー、必要に応じパラメタ更新。
18. さらに踏み込む拡張
- 因子ニュートラル:サイズ/バリューの代替指数(または代表銘柄)で補助ヘッジ。
- 機械学習:非線形の残差ドライバをGBM等で学習、Shapleyで可視化。
- 夜間先物→翌日現物:夜間の先物情報で翌日の寄り実行(ギャップ取り)。
- オプション重畳:小さなロングガンマで残差ボラを取りにいく(コスト管理前提)。
19. 実務チェックリスト(配布用)
- 残存β±5%以内/R²閾値クリア/イベント禁止期間遵守。
- 約定KPI:実質スプレッド半分以内、到達率70%以上。
- ロール週の建玉縮小・事前移管計画。
- 証拠金余力・追証リスクの常時監視。
20. まとめ
βニュートラル個別株×指数先物は、市場方向を当てずに収益化するための現実的な裁定アプローチです。鍵は、β推定の精度、整数丸めの分散最小化、イベント管理、約定品質とコストのKPI運用。本稿のワークフローをテンプレートとして、まずは小ロットで日次検証→週次改善を回してください。
注:本稿は情報提供のみを目的とし、特定銘柄の推奨ではありません。

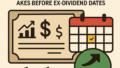

コメント