本稿は、米国株オプション市場において配当落ち(ex-dividend)前夜に発生する「早期行使(early exercise)の非効率」を個人投資家が戦術的に活用するための増補版ガイドです。単なる概念説明ではなく、パリティと割引現在価値に基づく意思決定式、建玉と約定サイズから推定するリテール比率、借株(ボロー)コスト、板厚とスプレッドを考慮した執行、日次PL分解、Python擬似コード、バックテスト設計、運用KPI、失敗事例まで、現実の運用で役立つレベルに落とし込みます。
対象は、株式・オプションの初学者から、イベントドリブン裁定・ミクロ構造・実務オペレーションまで踏み込みたい上級者まで。読み手が今日から運用に移せるよう、具体的手順と数値例・チェックリスト・KPIを提示します。
配当直前の深いITMコールは、時間価値が極小になりやすく、かつ翌日に受け取る離散配当Dが経済価値として大きくなります。合理的な保有者は前夜に早期行使して株を受け取り、翌日の配当を確保するのが最適です。しかし現実には、情報・仕組み・コスト・注意不足などの理由で、行使すべきコールが行使されないケースが残存します。
あなたが株ロング+ITMコールショート(カバード)で跨ぐと、相手が行使してこなかった部分の株数で配当を受領し、同時にコールの時間価値はほぼ残らないため、配当相当の超過収益がPLに上乗せされます。これが本戦略のアルファです。重要なのは、配当そのものではなく、「本来起きるべき早期行使が起きないミス」を収益化している点です。
離散配当Dを考慮した近似的パリティは、C - P = S - PV(K) - PV(D)。配当直前ではPV(D) ≈ D(一日程度の割引は微小)とみなせます。
早期行使の合理性はおおむね、D > r·K·τ + b·S·τ + 残存時間価値 + 取引コスト を満たすかで判定します(τは残存日数/年換算、bは借株率の近似)。深ITMでは残存時間価値が極小のため、Dが少しでも大きいと早期行使が合理になりやすい状況が多い。
よって、合理的世界ではほぼ全件行使が期待されますが、実務の制約(自動行使閾値、行使手数料、口座種別、夜間の対応可否、リマインダーの有無など)により、一部が行使しない=行使ミスが生じます。
ポジション:Long S − Short C(K)(カバードコール)。配当日前夜に保有。行使率をq(0〜1)とすると、未行使割合は(1−q)。配当受領は(1−q)·D·株数。一方、コールの残余時間価値は極小(深ITM)。手数料とスリッページ、割当の不確実性を差引いた期待値が正であればエッジが成立。
期待日次PL(概算):
E[PL] ≈ (1−q)·D·N − Cost_exec − Cost_borrow − Slippage − Risk_buffer
ここでNは保有株数。qが1に近づく(行使徹底)ほどPLはゼロに収れんします。したがって、qが低くなりやすい文脈=ミスが残りやすい銘柄・環境を同定するのが戦略の核心です。
翌営業日にex-divを迎える銘柄から、深ITMコールのある銘柄を抽出し、以下の代理変数で「行使ミス確率」をスコア化します(UEPS: Under-Exercise Probability Score)。
- 配当対株価比 D/S:大きいほど合理的行使が強く、行使しないと損失が目立つため、逆にミスは小さくなる傾向。ただし高配当常連では自動化が進みミス縮小。中程度の配当×小口多めの銘柄に着目。
- ITMコールの未決済建玉 OI_call_ITM:小口に人気のストライクに偏在している場合、ミスが残りやすい。
- 同ストライクのプット建玉 OI_put_sameK:機関の裁定参加が厚いと、反対売買や行使徹底が行われやすい→ミス縮小。
- 借株(ボロー)指標 b:Hard-to-Borrowでは裁定者の参加が制限、ミスが残存しやすい。
- リテール代理変数 RetailProxy:平均約定数量が小さい、出来高に対する小口比率が高い、板で小口の指値が多い等。
- 時間価値の残存:ITMコール理論価格−内在価値(市場IVを使った近似)。残存が小さいほど合理的行使の閾値を超えやすい。
擬似スコア:
UEPS = w1·g(D/S) + w2·log( OI_call_ITM / (1 + OI_put_sameK) ) + w3·1(b>b*) + w4·RetailProxy − w5·TimeValueResidual
係数は歴史データで回帰推定。g()は非線形変換(例:凹関数)。
理想は行使・割当の実績ですが、個人での網羅取得は困難です。代替として:
- 翌日配当カレンダー:銘柄・D・権利付最終日・配当性質(四半期/特別)。
- オプションチェーン:期近のITM帯の気配(Bid/Ask/Mid)、出来高、建玉、IV。
- 板関連:スプレッド、約定サイズ分布(可能ならブローカー別フロー代理)。
- 借株レート:日次のb。代替として融資率や空売り比率の代理を使う。
欠損時の保守的な扱い:bが不明なら0.5〜1.0%/年相当で仮置き、RetailProxyは平均約定サイズの下位分位をもって代替等。
- 前場終盤:翌日のex-div銘柄を抽出し、ITMコールの時間価値とスプレッドを粗スクリーニング。
- 引け2時間前:UEPSを更新。板厚・出来高・小口比率を再評価。イベント(決算など)を除外。
- 引け1時間前〜引け:板の厚い時間帯を使い、Long S + Short ITM Callを分割約定。ミッド→必要時テイカー。
- 夜間:ブローカーの自動行使ルール/アラートを再確認。
- 翌朝:割当(Assignment)結果を確認。未割当分で配当受領。寄り〜前場で段階的にクローズ、または継続。
- 日次レビュー:割当率、実現PL、スリッページ、板消費比率を記録し、次回の重みを更新。
株価S=100、翌日配当D=0.90、借株・金利等コスト合計0.05、ITMコールの残存時間価値0.02。合理的判定は 0.90 > 0.07 → 早期行使推奨。実際の行使率q=0.88と観測(代理)。未行使12%分は配当受領対象。
| パラメータ | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| S | 100.00 | 引け近辺 |
| D | 0.90 | 翌日ex |
| Costs | 0.05 | 金利+ボロー+手数料 |
| Time Value | 0.02 | 深ITMで極小 |
| 行使率 q | 0.88 | 代理推定 |
| 未行使率 | 0.12 | (1−q) |
期待PL概算(株数N=10,000):(1−q)·D·N − 費用 = 0.12·0.90·10,000 − 費用 ≈ 1,080 − 費用。一銘柄で数百〜千ドルの期待値が出るなら、複数銘柄分散で日次PLの分布を平滑化できます。
本戦略では薄利多売になるため、TCMの精緻さが勝敗を分けます。
- スプレッド:コール売りはミッド−εを目安に。板の空洞時間を避け、厚い瞬間に入れ替える。
- インパクト:板消費比率(自分の出来高/市場出来高)をKPI化。1銘柄での占有率が高くなりすぎないよう分散。
- 手数料:行使/割当手数料の差はPLに直結。取引所・ブローカーの条件差は事前に把握。
- 借株:bの変動で当夜の合理性が変わる。直前のbは必ず再確認。
実務での優位はしばしば約定の技術から生まれます。
- タイムスライス:引け前60分を5分×12バケットに分割し、板厚/スプレッド/出来高に応じて執行比率を変化。
- コール売り順序:スプレッドの狭いストライクから先に、板の戻りを見ながら段階的に。
- VWAP/POV:株買いはVWAP、コール売りはPOV(出来高比率)を参考にする折衷。
- シグナル漏洩の回避:同一銘柄の同一ストライクに固執せず、複数銘柄に小分け。
行使実績がない前提での保守的テスト手順:
- イベント生成:過去数年のex-divイベントを抽出。
- スクリーニング:ITMコールの時間価値≦閾値、板実行性≧閾値、b≦上限、ニュース除外。
- 割当率の代理:qはベース0.95など保守的に固定、もしくは回帰で推定。
- PL合成:
(1−q)·D·N − TCMで日次PLを出し、分布を集計。 - クロスバリデーション:期間・銘柄ごとに分割し、係数過学習を回避。
回帰モデル例:実現PL_i = α + β1·(D−Cost−TV)_i + β2·Retail_i + β3·HTB_i + β4·板指標_i + ε_i。βの符号と頑健性を確認。
def screen_events(div_list, option_chain, borrow_table):
candidates = []
for sym in div_list: # 翌日ex銘柄
for k, quote in option_chain[sym].items(): # 期近ITMストライク
tv = max(0.0, quote.mid - max(0.0, spot[sym] - k)) # 時間価値近似
costs = rate* k * tau + borrow_table.get(sym, 0.0)*spot[sym]*tau + fees
if (dividend[sym] - costs) > tv:
ueps = score(sym, option_chain, borrow_table, micro)
if ueps > threshold:
candidates.append((sym, k, ueps, tv, costs))
return sorted(candidates, key=lambda x: x[2], reverse=True)
def execute(cands):
for sym, k, score, tv, costs in cands:
size = sizing(score, liquidity[sym])
buy_stock(sym, size, algo="VWAP")
sell_call(sym, k, size, algo="POV")
ケースA(大型・板厚・高配当常連):行使オペが自動化され、qが高止まりしやすい。サイズを入れやすいがエッジは薄い。分散数で期待値を積む。
ケースB(中型・板厚普通・小口比率高め):本戦略のスイートスポット。UEPSが効きやすく、qがブレる。スプレッドも許容。
ケースC(小型・HTB):bの変動リスクでエッジが蒸発しやすい。原則回避。少量検証に留める。
- 全面割当:想定よりqが高く、配当の受領がゼロになる。PLはコール売りのプレミアムに収れん。
- 想定外ニュース:決算・訴訟・規制報道でギャップ。イベント銘柄は除外するルールを厳守。
- Pin Risk:行使境界付近での引けピン。翌朝のデルタ残存を許容できるサイズ配分。
- TCM劣化:薄い板を叩いてスプレッド拡大。板消費KPIを守る。
- イベント参加件数/週、採用率(スクリーニング→採用)。
- 平均期待超過bp、実現超過bp、差分の要因分解(q推定誤差、TCM、ニュース)。
- 板消費比率、平均スプレッド、実現スリッページ。
- 最大DD、カルマ―比、キャパシティ(1日当たり処理可能イベント数×平均建玉)。
- 翌日exリスト作成、配当金額と性質を確認。
- ITMコールの時間価値と板指標を算出。
- b・ニュース・イベントを精査。除外ルール適用。
- UEPS上位から分散採用、分割執行。
- 自動行使ルールと割当コストを確認。
- 翌朝の割当結果を速やかに確認、ヘッジとクローズをルール通り実施。
- 日次レビューで重みを更新。
在庫や口座制約に応じ、ロング株 ≈ ロングコール+ショートプットの関係を使い、同等エクスポージャを構成。プット側の建玉分布や板厚が有利なら、Put-Callの相対ミスを利用できる。さらに、デビット・クレジットスプレッドでガンマ・ベガを抑え、イベント由来の価格変動リスクを低減。
- 同ストライクのプットOIが極端に高い場合、機関の裁定が厚くqが高い可能性→見送り。
- 約定サイズ分布が小口優位ならRetailProxyを引き上げ。
- 板の気配更新速度が遅い時間帯は避ける。
- 配当が特別配当の場合、時間価値のズレが出やすいが、同時にニュース感度も上がる。
失敗1:ニュース除外が甘い→ 決算日・指針・大型訴訟は除外リストに。
失敗2:bの急上昇を見落とす→ 前日終盤で再取得。閾値を超えたらキャンセル。
失敗3:板消費が過剰→ 1銘柄に集中せず、サイズ上限と同時参加銘柄上限を設ける。
失敗4:想定よりqが高い→ UEPSの重みを再推定。RetailProxyの代理変数を改善。
日次PL = 配当寄与 + デルタ・ガンマ寄与 + ベガ寄与 − TCM − 借株 − ニュース損。配当寄与は (1−q)·D·N で近似。デルタは寄りギャップへの感応度、ガンマは寄り後のボラによる短期損益、ベガはIV変動。寄与度分解を日次で行い、どこで負けたかを特定します。
この戦略のキャパシティはミスの絶対量×あなたの板消費許容で決まります。スイートスポットの銘柄群に均等配分しても、日次イベント数は数件〜十数件。複合戦略(例:配当再投資のモメンタム回帰、カレンダー化でのIV歪み捕捉)と組み合わせると、同一日での資本回転が向上します。
- データ取得経路の確立(配当・チェーン・板・b)。
- UEPSの初期重みを過去1〜2年で校正。
- TCMのパラメータ(スプレッド、インパクト、手数料)を保守的に設定。
- 小額でパイロット、KPIをモニタ、重み更新。
- サイズ拡大時は板消費KPIにリミットを設定。
WordPress本文に貼って運用記録を残す簡易テンプレ:
<div class="trade-log">
<p>銘柄: TICKER / ストライク: K / 期近 / 予定配当: D / 候補UEPS: 0.62</p>
<p>執行: Long S @x, Short Call @y (サイズ n)</p>
<p>結果: 割当率 0.84 / 実現PL $zzz / コメント: 板厚良好、RetailProxy高め</p>
</div>配当落ち前夜の早期行使ミスは、完全裁定ではなく、条件付きで発生する薄い非効率です。再現性は、UEPSでの選別、TCMの厳格運用、分散とサイズ管理、ニュース除外、継続的な係数更新で高められます。日々の小さなエッジを積み上げ、安定的なイベントドリブン収益に仕立ててください。

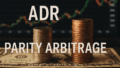

コメント