本記事は、社債ETFを中核に据えたロールダウン戦略を「机上の理屈」から「実際に回せる運用工学」へと橋渡しすることを目的に、方法論・数量設計・検証・日々の運用手順までを一貫して解説します。ロールダウンは、残存期間の短縮によって利回りがより低い区間へ自然に移行し、その結果として価格が上昇する現象を収益化する戦略です。社債では、金利カーブに加えてクレジットスプレッドカーブにも傾きがあるため、二層のスロープから収益機会を獲得できる可能性があります。この記事では、金利スロープ・クレジットスロープ・キャリー・ショックの4要素に分解し、個人投資家でも再現できる「DV01ヘッジ付きロールダウン」の構築方法を詳細に示します。
- ロールダウンの収益源:4要素分解
- なぜ社債ETFなのか:分散・単位・コスト・実務
- 数量設計の骨格:DV01で合わせ、スロープを刈り取る
- 簡易数式と近似:Modified DurationとDV01
- ロール寄与の推定式
- 数値例(年次→月次の刻み)
- 実務フロー:月次・四半期の定型オペレーション
- コストモデルの作り方
- 為替ヘッジ設計の論点
- ケーススタディ1:中期IGロールの四半期リレー
- ケーススタディ2:ハイイールド比率を抑えた「β管理」
- ストレステスト:ショックマトリクスの作成
- PNL要因分解テンプレート
- しきい値ルール:やる/やらないの判定
- 疑似バックテスト(ローリング近似)の作り方
- 実務チェックリスト(運用日・週・月・四半期)
- 執行の実務:板の厚みと時間帯の選択
- NAVプレミアム/ディスカウントの扱い
- β管理:クレジットの濃度を薄める工夫
- 極端事象と「やめる勇気」
- Q&A:現場で出やすい疑問への回答
- ミニ実装:疑似バックテストの擬似コード
- ケーススタディ3:残存3〜7年ラダーの分散ロール
- データ辞書:最低限そろえる項目
- KPI:運用の健全性を測る指標
- 失敗例と回避策
- 運用テンプレ:月次レポートの雛形
- まとめ:個人が扱える定常戦略としてのロールダウン
ロールダウンの収益源:4要素分解
債券(または社債ETF)の1期間のリターンは、おおむね次の要素で説明できます。
リターン ≒ キャリー(クーポン再投資)+ 金利ロール(国債カーブの傾き × 経過時間 × DV01)+ クレジットロール(スプレッドカーブの傾き × 経過時間 × Credit-DV01)+ ショック(Δ金利・Δスプレッド・為替)+ コンベクシティ項 です。ここでDV01は利回り1bp変化当たりの価格感応度、Credit-DV01はスプレッド1bpの感応度を指します。ショックがゼロで、カーブの形状が一定なら、キャリーとロールだけで前向きの期待値が生じます。これがロールダウン戦略の理論的な出発点です。
なぜ社債ETFなのか:分散・単位・コスト・実務
個別債券でも同様の設計は可能ですが、最低売買単位が大きく、銘柄分散・情報コスト・売買スプレッドを鑑みると、個人には荷が重くなりがちです。ETFは指数連動により即時分散が効き、デュレーションやクレジット特性が比較的安定します。加えて、残存年数バケットが近い複数ETF(短期・中期・長期)を組み合わせると、「より長いETFを買い、時間経過で短くなったら売って、また長いETFに乗り換える」というロールの機械化が容易になります。
数量設計の骨格:DV01で合わせ、スロープを刈り取る
金利変動がロールの果実を覆い隠すのを避けるため、国債先物や国債ETFを用いて金利DV01を概ね中立に調整します。この時、社債ETFのポートフォリオDV01と、ヘッジ手段のDV01を同じ土俵に乗せて数量を決めることが肝要です。DV01は「価格の相対変化率」でも「金額ベース」でも構いませんが、運用全体で一貫した単位を採用します。中立化の許容バンドを±10%程度に置き、リバランス時に乖離が大きい場合のみ調整します。
簡易数式と近似:Modified DurationとDV01
ETFのモディファイド・デュレーションをDur、基準価格をPとします。DV01(%ベース)はおおむね DV01 ≒ 0.0001 × Dur × 100 = 0.01 × Dur に近似できます。たとえばDur=5なら、1bpの利回り低下で理論価格が約+0.05%動くイメージです。金額DV01は、保有金額×(%DV01)で算出します。クレジット側の感応度は、ベンチマークOASに対する変化を用い、Credit-DV01 ≒ DV01とみなす近似が実務上よく用いられます(厳密には違いがありますが、第一義の管理には有用です)。
ロール寄与の推定式
金利ロール寄与の近似は RollRates ≒ (対象残存区間の国債利回りスロープ)× 経過年数 × DV01、クレジットロール寄与は RollCredit ≒ (OASスロープ)× 経過年数 × Credit-DV01 です。スロープは「上の年限 − 下の年限」を年率bpで取り、符号は一般に短期の方が低利回り・低スプレッドであるため負です。負のスロープ × DV01 × 経過年数は価格にプラス寄与を与えます。
数値例(年次→月次の刻み)
投資適格社債の5年ポイント国債利回りが2.8%、4年が2.6%とし、OASは5年で120bp、4年で110bpと仮定します。Dur=4.5、クーポン利回り2.5%、経過年数1年のロールとすれば、金利ロールは +0.20% × 4.5 = +0.90%、クレジットロールは +0.10% × 4.5 = +0.45%、キャリーが+2.5%で合計+3.85%の期待寄与となります。月次に均すと約+0.32%です。売買コストや為替コストを差し引いても、環境が安定なら前向きの期待が残る構造です。
実務フロー:月次・四半期の定型オペレーション
実際の運用はチェックリスト化すると安定します。月次では、①国債カーブとOASカーブの代表点を更新、②各ETFのDur・推定DV01を更新、③ポートフォリオの金額DV01を集計、④ヘッジ比率が許容バンド内かを確認、⑤しきい値(合計スロープ×DV01×期間が「年間総コスト」を上回るか)を評価、⑥執行ウィンドウを設定して分割指値で発注します。四半期では、残存が短くなったコアETFの一部を売却し、より長いデュレーションのETFへ再延伸します(これを「リレー」と呼びます)。
コストモデルの作り方
売買コストは、スプレッドの半分+約定ずれ+ブローカー手数料+為替コストでモデル化します。現実的には年率で0.4〜1.0%のレンジを仮置きし、バックテストに反映します。為替ヘッジを使う場合は、先物やフォワードのポイント差(ヘッジコスト)も加算します。コストを過小評価すると、カーブが平坦化した局面で簡単に負け筋に陥るため、保守的な見積もりを推奨します。
為替ヘッジ設計の論点
円建て投資家が外貨建て社債ETFを保有すると、為替ボラティリティが戦略のPnLに大きく乗ってきます。ロールダウンは比較的薄利多売の戦略であるため、為替ショックで収益がブレない設計が望ましいです。ヘッジ比率は固定50〜100%の範囲でポリシーを定め、ロール執行のタイミングに合わせて調整します。分配金が外貨で支払われる場合、ヘッジロールの更新順序(分配受領→必要額のみ両替→ヘッジ更新)を決めて余分な両替コストを避けます。
ケーススタディ1:中期IGロールの四半期リレー
設計:残存4〜6年をターゲットとする投資適格社債ETFをコア(70%)に、短期IG(20%)と低比率ハイイールド(10%)を補助に配置します。金利DV01は国債ETFのショートで60〜80%中立化します。四半期ごとに、コアの一部を売却して長めのIGETFへ乗り換え、残存を再延伸します。
仮定:四半期当たりの国債スロープ -5bp、OASスロープ -3bp、Dur=3.8、キャリー四半期+0.6%とします。ロール寄与は金利 +0.19%、クレジット +0.11%、合計+0.30%。キャリー込みで+0.90%。ここからコスト0.20〜0.30%を控除しても、平均的にはプラス期待が残る設計です。実際はスロープが伸縮しますので、毎四半期しきい値テストを通過した場合のみリレーを実施します。
ケーススタディ2:ハイイールド比率を抑えた「β管理」
景気減速局面ではハイイールドのスプレッドがボラタイルになり、ロール寄与を上回るドローダウンが出やすいです。これに対し、ハイイールド比率を10%以下に抑える、またはプットオプションを薄く持つ、という二段構えでベータ管理を行います。投資適格中心でも、OASが急拡大する局面ではドローダウンが出るため、金利ヘッジでカバーできない信用ショックのシナリオをストレスに入れます。
ストレステスト:ショックマトリクスの作成
運用前に、「Δ金利 × Δスプレッド」の二次元マトリクスでPnL感応度を事前に把握します。たとえば、金利+100bp、スプレッド+150bpの複合ショックで月間-2.5%以内に収まるか、などの閾値を決めます。マトリクスの各セルは Δ価格 ≒ -DV01×Δ金利 – Credit-DV01×Δスプレッド + コンベクシティ項 で近似し、ヘッジ込みのネットDV01で評価します。許容を超えるセルが多い場合、コアのデュレーションを短くするか、ヘッジ比率を上げるか、ハイイールド比率を更に落とします。
PNL要因分解テンプレート
月次の損益報告は次の粒度で記録します。
①キャリー(分配金・クーポン)/ ②金利ロール寄与/ ③クレジットロール寄与/ ④金利ショック/ ⑤スプレッドショック/ ⑥為替影響/ ⑦売買コスト/ ⑧ヘッジコスト/ ⑨残差(モデル誤差)です。これを継続的に記録することで、戦略が「ロール由来の期待値」で稼げているかを検証できます。
しきい値ルール:やる/やらないの判定
ロールを実行する基準は、(金利スロープ+OASスロープ)× 期間 × 近似DV01 > 年間総コストです。例えば、合計スロープが -60bp/年、ロール間隔が半年(0.5年)、DV01=4.0%、年間総コスト0.8%なら、左辺は 0.60% × 0.5 × 4.0 = 1.2% で、ネット+0.4%の超過が期待されます。これが連続して観測できる限り、ロールは続行。逆に、合計スロープが -10bp/年程度まで平坦化したら、キャリー主体の保有に切り替えます。
疑似バックテスト(ローリング近似)の作り方
個別債券データを持たなくても、ETFの月次リターン、Dur(または指数ファクトシートのデュレーション)、国債利回りの代表点、投資適格のOAS代表値の4系列があれば、ロール寄与の近似バックテストは可能です。概要は次の通りです。
1. 月次でDurからDV01を近似し、DV01_tを得ます。
2. 国債カーブの対象レンジでスロープを取り、RollRates_t ≒ SlopeRates_t × (Δ年数) × DV01_tを計算します。
3. OASカーブのスロープで同様にRollCredit_tを求めます。
4. 市場ショックの近似として、金利変化Δy_t、OAS変化Δo_tを用い、-DV01_t×Δy_t – DV01_t×Δo_tをショック項とします。
5. ETFの実リターンからショック項を控除し、残差がキャリー+ロールで説明できるかを検証し、スケールを調整します。
6. 取引コスト・ヘッジコストを差し引き、ネットでの超過の有無を判定します。
バックテストは厳密である必要はありません。重要なのは「どの程度のスロープなら、どのくらいの速度で、どれほどのネット超過が残るか」をオーダー感で把握し、実運用の意思決定に使えるかどうかです。
実務チェックリスト(運用日・週・月・四半期)
日:市場急変時のみヘッジの乖離を点検します。過剰な日次調整はコスト過多に直結するため、バンド内なら触りません。
週:出来高とスプレッドの状況、ETFのプレミアム/ディスカウント(基準価額との差)を観察します。薄い日に成行は避けます。
月:カーブ更新、DV01集計、しきい値判定、ロール発注の準備、約定コストの記録、PNL要因分解の更新を行います。
四半期:長めのバケットへのリレー、ヘッジの再設計、ストレスマトリクスの再計算、ドローダウン対策の棚卸しを行います。
執行の実務:板の厚みと時間帯の選択
流動性の厚い時間帯(現地市場のコアタイム)に分割指値を用い、VWAPに近い約定を狙います。月末・四半期末は指数連動の資金フローが集中するため、数営業日に分散して執行するとスリッページを抑制できます。板薄の時間帯の成行は避けます。
NAVプレミアム/ディスカウントの扱い
ETFは二重市場(一次:APによる創設・償還、二次:取引所)を持ちます。需給により取引価格が基準価額から乖離することがあり、ロール執行日にプレミアム買い・ディスカウント売りを続けるとコストが積み上がります。乖離が大きい日は見送る、または出来高が立つ時間帯へ調整するなど、価格の質を選びます。
β管理:クレジットの濃度を薄める工夫
投資適格主体の構成にし、ハイイールドの比率を低く抑えます。環境に応じてハイイールドのプットを薄く持つことも検討します。金融環境の悪化シグナル(例:スプレッド指数の急拡大)が出た場合、ロール実行を一時停止し、キャッシュ比率を引き上げます。
極端事象と「やめる勇気」
ロール戦略は「平常時に効く」設計であり、急激な利上げや信用ショックに弱い面があります。想定外のイベントで許容損失を超える兆候が出たら、ポジションを半減し、ヘッジを厚くし、執行頻度を下げます。いつでも再開できる設計こそが個人投資家にとっての最大の防御になります。
Q&A:現場で出やすい疑問への回答
Q1. DV01はどの程度の精度で必要ですか? A. 近似で十分です。同じ近似ルールを一貫して使い、許容バンド内に収まっているかを見ます。
Q2. どのロール間隔が最適ですか? A. 四半期がコストと期待寄与のバランスが取りやすいです。月次はコスト過多になりがちです。
Q3. どの通貨でやるべきですか? A. 為替ヘッジ手段・コスト・分配金通貨を踏まえ、ヘッジの運用がしやすい通貨圏を選びます。
Q4. いつやめますか? A. 合計スロープが平坦化してコストを上回れないと判定された時、またはショックマトリクスの許容を超えると見込まれる時です。
ミニ実装:疑似バックテストの擬似コード
以下は、ExcelやPythonで実装できる簡易版の擬似コードです。実務ではファイル入出力や欠損処理、休日調整を追加します。
入力:
月次データ:ETF価格(配当込み)、Dur、国債利回りの代表点、OAS代表点
取引パラメータ:ロール間隔(例:3ヶ月)、コスト年率、ヘッジ許容バンド
処理:
for t in 月次:
DV01_t = 0.01 * Dur_t # %価格ベース
slope_rates_t = y(上位年限)_t - y(下位年限)_t
slope_oas_t = oas(上位年限)_t - oas(下位年限)_t
roll_rates_t = (-slope_rates_t/100) * (Δ年数) * DV01_t
roll_credit_t = (-slope_oas_t/100) * (Δ年数) * DV01_t
shock_t = -DV01_t * (Δy_t + Δoas_t)
pnl_model_t = carry_t + roll_rates_t + roll_credit_t + shock_t
コスト控除:pnl_net_t = pnl_model_t - cost_monthly
しきい値判定:if (slope_rates_t + slope_oas_t)*Δ年数*DV01_t < cost_annual: ロール停止
出力:累積リターン、要因分解、ドローダウン、感応度
ケーススタディ3:残存3〜7年ラダーの分散ロール
単一の年限に集中すると、指数リバランスや需給でコストが跳ねることがあります。3〜7年の複数バケットに配分して、ロール日程を分散させると、執行コストの分散効果を得られます。ラダーの各ピラーでDV01を算出し、合算DV01をヘッジで中立化します。これにより、単一ETFの特性変化(指数ルール変更など)への耐性も高まります。
データ辞書:最低限そろえる項目
①ETF配当込み価格または月次トータルリターン、②Dur(または実効デュレーション)、③国債利回り代表点(対象レンジ)、④投資適格OAS代表点(対象レンジ)、⑤為替終値(ヘッジ評価用)、⑥売買実績とコストのログです。これだけで意思決定の質は大きく向上します。
KPI:運用の健全性を測る指標
ロール寄与率(リターンに占めるロールの割合)、ネット超過(ロール+キャリー−コスト)、年率ボラティリティ、最大ドローダウン、カーブ平坦化期の損益、執行スリッページ総額、ヘッジ乖離時間比率などをトラッキングします。指標が劣化したら設計を見直します。
失敗例と回避策
①ヘッジを追いすぎてコスト過多になる。→許容バンドを広げ、月次または四半期のみで調整します。
②指数イベント日に執行が集中しスリッページが拡大する。→数営業日に分散し、板厚の時間帯を選びます。
③為替を無視して戦略の薄利を吹き飛ばす。→ヘッジ方針を明文化し、分配金とヘッジの運用順序を定型化します。
④スロープが平坦化しているのに慣性でロールを続ける。→しきい値ルールを機械的に適用します。
運用テンプレ:月次レポートの雛形
冒頭にパフォーマンス(ネット・グロス)、続いて要因分解(キャリー、金利ロール、クレジットロール、ショック、コスト)、ヘッジ乖離と調整の記録、執行スリッページの実測、ストレスマトリクスの更新、翌月の実行可否判定(しきい値)を記載します。過去の月報を横並びで比較し、スロープの状態とネット超過の関係をモニターします。
まとめ:個人が扱える定常戦略としてのロールダウン
社債ETFロールダウンは、金利とクレジットの二層スロープから期待超過を収穫する定常戦略です。DV01で数量を整え、ヘッジでノイズを抑え、コストを保守的に見積もり、しきい値で機械的に実行・停止する。これらの運用規律を守れば、裁量依存度を下げながら、長期にわたり繰り返し実行できる戦略になります。重要なのは「ルール化」と「記録」です。自分のデータで検証し、運用フローを磨き上げてください。

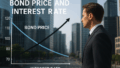

コメント