本記事では、社債ETFを用いた「ロールダウン戦略」を個人投資家の実務レベルにまで具体化して解説します。ロールダウンとは、同一の金利・信用環境が続く前提のもとで、時間経過により残存期間が短くなることに起因する利回りの自然な低下(一般にイールドカーブやクレジットスプレッドカーブが右上がり=期間が短いほど利回りが低い・スプレッドが小さい構造)を捉え、価格上昇分を収穫する手法を指します。株式のファクターとは異なり、期待収益の源泉が明確に分解可能で、かつ再現性をもって運用へ落とし込みやすい点が強みです。
ロールダウンの基本メカニズム
債券価格は利回りと逆相関にあります。残存期間が短くなるにつれて、同じ信用力・同じクーポンの債券は、イールドカーブが一定の形状である限り、利回りが低い領域へ「自然に移動」します。この移動に伴い、同じ利回りショックがなかったとしても価格が上昇し、これがロールダウン・リターンとして観測されます。社債の場合は、国債に対する信用スプレッドにも期間構造(クレジットスロープ)が存在し、短期のほうがスプレッドが狭いことが多いため、二重のロールダウン(国債カーブのロールダウン+クレジットスロープのロールダウン)を享受できる可能性があります。
期待リターンの分解フレーム
ロールダウン戦略の1期間(たとえば1か月)の期待リターンは、概ね次の和に分解できます。
価格変化 ≒ キャリー(クーポン再投資利回り)+ 金利ロール(国債カーブのスロープ × 経過時間 × DV01)+ クレジットロール(スプレッドカーブのスロープ × 経過時間 × Credit-DV01)+ 期間中のショック(Δ金利・Δスプレッド)+ コンベクシティ項
ここでDV01は「利回りが1bp動いたときの価格変化額(または%)」、Credit-DV01はスプレッド1bpの価格感応度を指します。重要なのは、ショック項(相場変動)をゼロとおいたときにも、キャリーとロールが正なら期待超過リターンが理論上は存在しうる点です。
簡易モデルでの数値例
仮に、投資適格社債の5年ポイントの国債利回りが2.8%、4年ポイントが2.6%で、同じくクレジットスプレッドが5年で120bp、4年で110bpだったとします。5年→4年へ1年分ロールダウンする過程で、単純化のためにカーブ形状が固定、ボラティリティゼロ、クーポンは年2.5%とし、5年債のDV01を4.5%(利回り1%で価格が約4.5%逆方向に動くイメージに相当)と近似します。
このとき、国債カーブのスロープは -20bp/年(短期ほど利回りが低い)なので、金利ロール寄与はおおむね +0.20% × 4.5 = +0.90% 程度の価格押し上げ効果が見込めます。同様に、クレジットスロープは -10bp/年ですから、スプレッドロールの寄与は +0.10% × 4.5 = +0.45% 程度。クーポン2.5%のうち価格上昇と切り分けると、1年トータルの「環境が不変での期待値」は、キャリー(2.5%)+ 金利ロール(0.9%)+ クレジットロール(0.45%)= 約3.85% となります。月次に均し、手数料・スプレッド等を差し引いても、プラス期待が成立しやすい構造だと分かります。
実務ではDV01は残存の短縮で低下し、またクーポンの再投資利回りは市場金利で変動します。そこで厳密な推定には、月次でDV01を更新しながら逐次計算するのが妥当です。
社債ETFでの実装が有利な理由
個別債券で同様の運用を行うことも可能ですが、銘柄分散・最低取引単位・売買スプレッド・発行体ごとのニュースリスクなどで個人投資家には高コストになりがちです。社債ETF(投資適格・ハイイールド・残存年数別など)の活用により、以下の点で実装が容易になります。第一に、ETFは指数連動で分散が効き、単一銘柄のネガティブニュースの影響を薄められます。第二に、残存期間バケットごとの商品(例:短期・中期・長期)が用意されているため、狙うロールダウンの「距離」を設計できます。第三に、先物や国債ETF等との組み合わせで金利ヘッジ、クレジット感応度の調整がしやすくなります。
設計の中核:残存期間ターゲットとロール間隔
ロールダウンは「高いスロープ区間」を「短い時間間隔」で繰り返すほど効率が上がる一方、売買コストが増えます。実務的には、残存3〜7年の区間は多くの局面でカーブが素直で、ロールによる押し上げが安定しやすいことが多いです。月次ロールはコストが嵩むため、四半期ロールや半期ロールで費用対効果のバランスを取る設計が現実的です。ETFでラダー(複数の残存年数バケットに分散)を組み、ロールのタイミングを分散させる方法も有効です。
金利ヘッジで「純クレジット・ロール」を抽出する
金利レベルの変動はロールダウンの果実を一時的に覆い隠します。ここで国債先物や国債ETFの売り(もしくはインバースETFの買い)を用い、ポートフォリオの金利DV01をゼロ付近に調整することで、クレジットスロープ由来の収益をより安定的に抽出できます。実務ステップは次の通りです。まず、保有する社債ETFのポートフォリオDV01を推定します。次に、対象とする金利ヘッジ手段のDV01を確認し、売買数量を比率で決めます。最後に、月次または四半期ごとにリバランスし、DV01が大きくズレていないかを点検します。ヘッジは過剰でも不足でも望ましくないため、許容バンド(たとえば±10%)を定義すると運用が安定します。
クレジット・ベータの管理
クレジット環境が悪化し、全体のスプレッドが拡大した場合、ロールダウンのプラス寄与を上回る損失が発生します。これを抑えるための現実的な手段として、ハイイールドETFのプットオプションの保有や、ハイイールド比率を抑えるアロケーション、投資適格の短期バケットを中核とする設計が挙げられます。個人でも実行可能な範囲では、「短期IGバケット中心+金利ヘッジ」が、クレジットベータ過多になりにくいバランスになりやすいです。
為替ヘッジとコストの扱い
外貨建て社債ETFを円で保有する場合、為替変動がリターンのボラティリティを左右します。為替ヘッジの有無は投資家ごとの方針に依存しますが、ロールダウンという比較的薄利多売の戦略では、想定外の為替変動に戦略のPnLが飲み込まれないよう、少なくとも主要通貨ペアでのヘッジ手段の可用性とコスト(先物・FXフォワードのスプレッドやヘッジコスト)を定量化しておくべきです。ヘッジを行うならば、ヘッジ比率は固定ではなく、ロールのタイミング(発注時)に合わせて調整するほうが実務上は運用しやすくなります。
バックテストの設計図(近似法)
高頻度のティックデータや個別債券の全ユニバースを扱わずとも、近似バックテストで意思決定に使える水準の評価は可能です。手順は次の通りです。
第一に、対象ETFの過去の月次リターン系列と、期間ごとの国債利回り・クレジットスプレッドの代表値(たとえば投資適格指数のOAS)を収集します。第二に、各月の「ロール寄与」を、近似DV01 × (カーブスロープ × 経過年数)で推定します。第三に、金利・スプレッドの当月ショックを、近似DV01 × Δ利回り、Credit-DV01 × Δスプレッドで控除します。第四に、残差が概ねキャリーとロールで説明できているかを検証し、推定DV01のスケールを調整します。この枠組みで、スロープが急な局面ほどロール寄与が拡大し、売買コスト控除後でも優位性が残るかを評価します。
ケーススタディ:中期IGロールの四半期運用
想定:投資適格社債の残存4〜6年をターゲットとするETFを中核に、四半期に一度、保有ETFの一部を売却し、より残存期間の長いETFへ乗り換えます。目標は、常に残存5年前後のゾーンを維持しながら、四半期ごとのロール寄与を積み上げることです。
仮定値:四半期あたりの国債カーブスロープが -5bp(5年→4.75年相当)、クレジットスロープが -3bp、ETFのDV01が3.8%とします。すると金利ロール寄与は +0.05% × 3.8 = 約+0.19%、クレジットロール寄与は +0.03% × 3.8 = 約+0.11%。クーポンからのキャリーが四半期で+0.6%とすれば、ショックが平均ゼロの世界では、四半期合計で約+0.9%の期待寄与が推定されます。年率換算の表面値は約+3.6%です。ここから売買コスト(往復スプレッド・手数料・為替)を控除しても、構造的なプラス寄与が残りやすい設計だと分かります。
売買コスト・スリッページの現実的見積もり
ETFでは、板の気配と出来高によってコストが変わります。約定のコツは、場中の流動性が厚い時間帯に、指値を使ってVWAP±αを狙うことです。ロールの実行を月末・四半期末に集中させると指数連動資金とぶつかりスリッページが拡大する傾向があるため、数営業日を分散して執行する設計が有効です。コスト見積もりは、スプレッドの半分+約定ずれ+手数料+為替コストを合算して、年率で0.4〜1.0%程度のレンジを仮置きし、バックテストのネット・パフォーマンスに反映させます。
金利ショックとロールの関係
ロールは「環境が大きく動かない」ほど取りやすい収益です。急激な利上げやスプレッド拡大では、ロール由来のプラス寄与が相殺されることがあります。もっとも、金利カーブの平行シフトであれば、ヘッジによって中和できます。カーブのツイスト(2年と10年で方向が異なる動き)に対しては、ヘッジのデュレーションを中期に合わせたり、複数の国債ETFを組み合わせて2因子ヘッジ(たとえば2年領域と10年領域の重みを調整)を検討します。
ポートフォリオ構築の具体例
例として、次のような構成を考えます。コアは中期IG社債ETF70%、短期IG社債ETF20%、ハイイールド低比率10%。金利ヘッジとして国債ETFのショートをDV01比で60〜80%程度設定します。四半期ごとに、コアの中期IGを部分的に売却し、より長めのIGバケットに入れ替えて残存期間を再延伸し、ロールを再スタートさせます。ハイイールドはクレジットベータを上げすぎないよう、ロールが有利な局面(スプレッドが十分に広い・景気減速が一服)に限定的に配します。
リスク管理と「いつやめるか」の基準
ロールダウンの優位性は、スロープが平坦化すると薄れます。運用ルールとして、金利スロープ+クレジットスロープの合計が一定の閾値(たとえば年率 -10bp 未満)になった場合はロールの強度を落とし、キャリー主体の保有へ移行する、といった「やめる基準」を明確にします。加えて、ヒストリカルの最大ドローダウンに対し、資金規模・許容損失・ヘッジ手段の可用性を踏まえたストップ基準(例:金利・スプレッドの複合ショックで想定損失がX%を超える場合はポジションを半減)を設けます。
税務・配当再投資の実務
社債ETFはクーポンに対応する分配金が支払われます。分配金の課税・再投資のタイミングにより、税引後の複利リターンに差が出ます。配当再投資型のプランや自動再投資機能がある場合は、ロールの執行日と分配金スケジュールの整合を取ることで余剰現金の遊休期間を短くし、現金ドラッグを抑制できます。分配金の受領通貨と為替ヘッジの付け外しの順序には留意し、不要な両替コストが発生しないように設計します。
実務フロー:月次・四半期の運用スケジュール
運用は定型化するほどヒューマンエラーを減らせます。実務フロー例は次の通りです。月中:市場環境の確認、スロープの更新、DV01の推定、ヘッジ比率の点検。月末3営業日前:売買ウィンドウの設定、執行方針(指値・分割)を決定。月末前後:リバランスを実行し、約定コストを記録。翌営業日:PnL要因分解(キャリー・金利ロール・クレジットロール・ショック・コスト)を更新し、しきい値に対する乖離を評価します。四半期末には、より長期バケットへの乗り換え実行と、ヘッジの再設計を併せて行います。
スクリーニングの考え方
ETF選定では、①対象デュレーションの一貫性、②出来高・スプレッド、③分配金ポリシーの安定性、④信託報酬、⑤指数ルール(新規組入・除外の頻度と基準)、⑥貸株・オプション取引の可否(必要なら)を評価します。加えて、為替建ての場合は、為替ヘッジ付き商品とヘッジなし商品の双方を比較し、総コスト(信託報酬+ヘッジコスト)で判断します。
しきい値ルールの定量化
ロールのメリットがコストを上回る条件を、簡易式で見積もります。必要条件は、(金利スロープ+クレジットスロープ)× 期間 × 近似DV01 > 年間総コストです。たとえば、合計スロープが -25bp/年、ロール間隔が半年(0.5年)、DV01が4.0%、年間総コストを0.8%とすると、左辺は 0.25% × 0.5 × 4.0 = 0.5% で、ネットは -0.3%となり不十分です。逆に、スロープが -60bp/年なら左辺は 0.60% × 0.5 × 4.0 = 1.2% となり、コストを上回る期待超過が見込めます。こうした閾値を毎月更新し、実行/停止を機械的に判断します。
コンベクシティと極端事象
デュレーションが長いほど、コンベクシティ(利回り変化に対する価格の二次効果)が効いてきます。ロールの対象を中期に置く理由のひとつは、コンベクシティの恩恵をほどほどに受けつつ、金利ショックの一次影響(デュレーション損失)を抑えるバランスが取れるためです。極端事象に対しては、キャッシュ・バッファ、ヘッジの段階的積み増し、実行停止ルールを併用し、「絶対に無理はしない」運用規律を徹底します。
実務の落とし穴
流動性の薄い時間帯の成行発注は避けます。ヘッジ比率を「日次で追いかけすぎる」こともコスト増に直結します。ロールの執行タイミングが一極集中すると、You are the market になりやすい点にも注意します。また、ETFの指数ベンダーがルールを変更した場合、デュレーションやクレジットの特性が変化します。ファクトシートの定期確認は運用の必須タスクです。
まとめ
社債ETFのロールダウン戦略は、金利カーブとクレジットカーブという二つの傾きから構造的な期待超過リターンを引き出す設計です。個人投資家でも、DV01ベースの数量設計、四半期ロール、金利ヘッジ、コスト管理という実務の柱を押さえれば、過度な裁量に頼らない運用が可能になります。環境認識としきい値ルールを明確に定め、ルーティン化したフローで粛々と実行することが、この戦略を長期にわたり機能させる鍵になります。

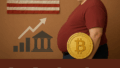
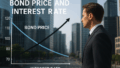
コメント