本稿では、暗号資産市場で「お削り(微小優位の積み上げ)」を狙う低ボラ戦略の設計・検証・運用までを体系的に解説します。派手なボラ依存ではなく、手数料構造、資金調達コスト、価格歪み、約定ロジックといった“仕組み”に寄り添い、日次でブレの少ないリターンを狙います。裁量トレードの大勝ちよりも、地味だが高再現性の収益を重視する投資家向けの内容です。
1. お削りの定義と前提
お削りとは、1トレードあたりの期待値が小さくても、勝率・頻度・資本回転の掛け算で収益を押し上げる発想です。一般的には次の3層で組み立てます。
- 構造的優位:メイカー手数料のリベート、資金調達(Funding)の受け取り、スプレッド縮小局面の約定優位など。
- 実務オペレーション優位:キュー先頭確保、部分約定の積み上げ、キャンセル&リプレイスの最適化、レイテンシ管理。
- リスク制御優位:デルタ中立、規模管理、急変時の自動縮小、約定遅延時の強制撤退。
2. 代表的な収益源(ユースケース)
2.1 メイカー・リベート活用のマーケットメイキング(簡易版)
USD建てパーペチュアルで、最良気配に薄く数量を置き、メイカー約定を中心に回転させてリベートを収益源化します。鍵は「価格の置き方」と「キュー位置」です。
- 価格の置き方:スプレッドの半分以内、かつ約定しすぎない浅さに調整。
- キュー位置:同値ライバルが多い板では、
post-only+reduce-onlyの使い分けで滑りを抑えつつ先頭を確保。 - 在庫管理:約定が買いに偏ればヘッジでデルタを戻す。ヘッジ先は現物・他取引所先物・同一所の反対建てなど。
リスク:急変時に板が飛ぶと一方向に抱え込みます。在庫上限・損切り・クールダウンを事前に自動化し、過大在庫を絶対に許容しない仕組みを組み込みます。
2.2 資金調達(Funding)受け取りのデルタ中立回転
パーペチュアルの資金調達率が正(多くがロング)なら、ショート・パーペチュアル+ロング現物のデルタ中立を組み、Fundingを受け取ります。逆に資金調達が負なら構成を反転します。
実運用では、手数料・スリッページ・資金貸借コストを差し引いた純益がプラスであるかの判定が肝です。資金調達率は変動するため、直近実績の移動平均とボラを併用して「期待値がプラスになる時間帯だけ」稼働させます。
2.3 ミニ・ベーシスの瞬間捕捉
同一銘柄の複数取引所間、あるいは先物・現物間の価格差(ミニ・ベーシス)を、狭い閾値で自動検出し、レイテンシの低い発注で瞬間的に捕捉します。優位は小さいので、誤差(手数料・資金移動コスト・引き出し遅延)を徹底的に削る必要があります。
2.4 流動性マイニングや手数料フリー枠の“ハコ”化
取引所やプロモーションの手数料フリー枠、LP報酬のボーナス期間などを、日次の回転箱として使います。勝ち筋は「回転を落とさないこと」。条件変更リスクに備え、自動の条件監視と撤退を組み込みます。
3. 数量・価格・在庫:3変数の最適化
お削りは小さい期待値×大量試行が前提です。数量を増やせば破綻確率も上がるため、次の3変数を連動最適化します。
- 価格(置き幅):ティックサイズ、板厚、直近ボラ、イベント有無で動的決定。
- 数量:板の吸収力に応じた上限・下限。分割約定を前提に小口に刻む。
- 在庫:ネット・デルタのバンド管理。閾値到達で自動ヘッジ。
4. 入出庫と資金配置の現実解
複数取引所・銘柄を跨ぐお削りは、入出庫の遅延と手数料がボトルネックです。現実的には次の戦略で回避します。
- 在庫を各所に常駐配備し、入出庫に依存しないヘッジルートを確保。
- USDT/USDCのチェーン選択(手数料・詰まりに応じて)を動的に切替。
- 相関銘柄(例:BTCと強相関の大型アルト)をヘッジ代替として使い、現物移動を減らす。
5. 執行(Execution)設計:勝ち筋は“先頭”と“撤退”
約定効率はリターンの直結KPIです。主な設計要素は以下です。
- キュー先頭取り:同値競争ならミリ秒単位のリプレイス、価格優位なら
post-onlyでテイカー化回避。 - 撤退条件:スプレッド縮小、出来高減少、イベント前後の急変で自動縮小。撤退の速さが損益分布の左尾を短縮します。
- 滑り耐性:急変時はIOC/POCの使い分けで不必要な成行化を避ける。
6. リスク管理:左尾を“短くする”具体策
お削りは「負けの大きさ」をいかに抑えるかが全てです。
- 在庫上限:銘柄毎・全体で二重上限。閾値で自動クローズ。
- ボラフィルター:ATRや1分足の実現ボラが閾値超えで新規停止・縮小。
- 障害時フェイルセーフ:片側だけ約定した孤立在庫を検出し、クロス所のヘッジや成行撤退へフォールバック。
- イベント遮断:経済指標・主要発表時はスイッチ全OFFの時間帯を明確化。
7. 日次KPIとアラート設計
日次の追尾指標は次の通り。
- 純手数料(メイカー受取−テイカー支払)
- Funding純額(受取−支払)
- 在庫回転率(約定数量/平均在庫)
- 勝率・平均損益・最大ドローダウン
- 約定レイテンシ分布(P50/P90)
これらは全てアラート閾値を設定し、負のドリフト兆候(例:純手数料が3日連続マイナス)で自動縮小・検証モードへ移行します。
8. 検証プロセス:ヒストリカル+ライブA/B
お削り戦術はバックテスト単体では不十分です。板のキュー位置や約定順序はログ粒度に依存するため、ライブの少額A/Bで約定効率を直接比較します。
- ヒストリカルで「置き幅・数量・在庫バンド」の粗設定。
- ライブで同条件を2系統(例:置き幅±1ティック)でA/B。
- 約定効率・左尾の長さ・純手数料の差で採用案を決定。
9. 具体例:BTC-PERPのFunding受取回転(実装イメージ)
前提:直近7日で平均Fundingが+0.015%/8h、テイカー手数料0.04%、メイカー-0.01%(受取)。以下の運用ロジックを例示します。
- 条件:Funding期待値が+0.01%/8h以上かつ実現ボラが閾値以下の時間帯のみ稼働。
- 構成:ショートPERP10万USDT規模+現物ロング10万USDT規模(デルタ中立)。
- 執行:ヘッジ側は成行でなく浅い指値でメイカー化を狙い、純手数料をプラスに寄せる。
- 撤退:Funding反転・ボラ急騰・約定効率悪化でポジション縮小→停止。
損益の主因はFunding純額と手数料純額。価格変動はデルタ中立で抑えますが、ヘッジ遅延による残余デルタは必ず発生するため、許容レンジ(例:±5,000USDT相当)を機械的に戻します。
10. よくある失敗と対策
- 在庫抱え込み:片側だけ約定して逆方向に走る。→在庫バンド狭め、強制ヘッジを厳格化。
- 手数料負け:テイカー比率が上がる。→PO/IOCの自動切替、深い板だけ参加。
- 条件改定:取引所の手数料/資金調達仕様変更。→監視ジョブで自動停止。
- 入出庫停止:ネットワーク詰まりでヘッジ不能。→常駐在庫+代替ヘッジルートを確保。
11. 運用チェックリスト(毎朝3分)
- 取引所告知(手数料・資金調達ルール・メンテナンス予定)
- 前日KPI:純手数料、Funding純額、在庫回転、左尾
- 在庫配置:各所の残量と偏り、ヘッジ可能性
- イベントスケジュール:高ボラ想定時間帯の事前停止設定
12. 小規模から始めて段階的に拡張する
最初は1銘柄・小サイズ・限定時間帯で、約定効率をKPIに磨き込みます。次に銘柄と時間帯を増やし、最後にマルチ所・マルチ戦術(メイカー回転+Funding+ミニ・ベーシス)を重ね、収益源を分散します。お削りは「速く大きく」ではなく「壊れず長く」が正解です。
付録A:最小構成(擬似コード)
while market_open:
update_orderbook()
if vol_filter_pass and funding_edge > threshold:
place_maker_quotes(width=dynamic_width, size=base_size)
manage_inventory(band=delta_band)
if tail_risk or spec_event:
shrink_or_stop()
log_kpis()
付録B:導入ロードマップ(14日)
- Day1-3:環境整備(API、資金配備、監視)
- Day4-7:置き幅A/B、在庫バンド試験
- Day8-10:Funding回転の条件最適化
- Day11-14:ミニ・ベーシス併用、KPIとアラート固定
以上が「お削り」戦術の全体像です。重要なのは、小さく、早く、壊れない。長期で見ると、この地味な積み上げが資産曲線の滑らかな右肩上がりを生みます。

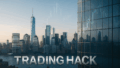
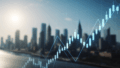
コメント