「なぜ自分の逆指値だけピンポイントで刈られるのか?」——その答えは“見える”場所に置いているからです。暗号資産先物・パーペチュアル市場では、オープンインタレスト(OI)クラスターと呼ばれる建玉の密集帯が価格の磁石として機能し、流動性を取りに来たアルゴに吸い寄せられるように一掃されます。本稿では、OIクラスターの特定→回避→活用までを、初心者でも実行できる手順で徹底解説します。
前提:用語を30秒で整理
オープンインタレスト(OI)は未決済建玉の総数です。値段帯ごとの建玉密集を可視化したものをここではOIクラスターと呼びます。清算ヒートマップは強制清算が連鎖しやすい価格帯を示す指標、板気配/板厚は指値の量と深さ、スリッページは注文と約定の価格乖離です。
核心:ストップ狩りのメカニズム
ストップ注文は通常、直近安値/高値のすぐ外、心理的節目(例:$70,000、¥1,000,000)、移動平均線の少し外など、誰もが思いつく場所に集中します。これがOIクラスターを形成し、そこに到達すると流動性が一気に出て約定が進むため、短時間でヒゲが伸びやすくなります。結果、狩られた後に価格は元の方向へ戻りがちです。
ワークフロー:5段階で“見える罠”を避ける
① マップを重ねて全体像を作る
以下の3レイヤーを同時に確認します。
- OIクラスター:価格帯ごとの建玉密度(出来れば取引所横断)
- 清算ヒートマップ:強制清算トリガーの集積帯
- 板厚:見せ板を排除しつつ、抜けやすい薄い帯を特定
目的:「一掃ポイント」(OIと清算が重なる帯)と、「無風の回廊」(板が薄く走りやすい帯)を同定します。
② エントリー位置は“前”でなく“後”に置く
典型的な失敗は、クラスター手前でロングし、直下に逆指値を置くこと。推奨は、一掃後の再テストで入ることです。流動性狩りのヒゲが出て、クラスターが消化された直後に、板が回復し出来高が細るのを待ってからエントリーします。
③ 逆指値はクラスターの“外側2〜3刻み”
クラスター直下/直上に置くのは自殺行為。ATRの0.25〜0.4倍を目安に、「一掃の最大想定幅」よりさらに外側へ。板厚と過去の狩り幅(過去20回のスパイク幅中央値)を加味して決めると実務的です。
④ 利確は“カベの手前”と“伸び代”の二段構え
最初の利確は、次のOIクラスター手前(到達前の反発を想定)で部分利確。残りは板が薄い“回廊”の先端まで伸ばします。トレーリングストップは直近の小クラスターの外側に移動。
⑤ サイズ配分はボラと混雑率で動的調整
同じセットアップでも、クラスター密度(混雑率)と24h実現ボラでサイズを落としたり上げたりします。混雑が極端に高い日はケリー×0.25などの保守係数で制御。
ケーススタディ:BTCパーペチュアル(架空データ)
2025年11月1日 10:00(JST)。BTCは$68,200。OIクラスターは$68,000・$67,850・$67,500に密集、清算帯はロング側が$67,820〜$67,880、板は$67,900〜$67,950が薄い。
- 観察:$68,000直下にストップ密集。まずは$67,950までの薄帯を抜け、$67,880付近でロング清算が連鎖する可能性。
- 方針:狩りの後を待つ。$67,860までのヒゲで一掃→$67,900再テスト→出来高細り+1分足で下ヒゲ連発を確認。
- エントリー:$67,905成行(小さめサイズ)。
- 逆指値:$67,760(大クラスター外+過去スパイク幅0.3×ATR分外側)。
- 利確①:$68,120(次クラスター手前で50%利確)。
- 利確②:$68,320(薄帯先端、トレール10刻み)。
結果:最大含み損−$55(0.08%)、実現益+$215(0.31%)。勝率ではなく、リスクリワードと狩られない位置の一貫性がポイントです。
道具立て:無料で始める可視化
以下は一般に入手しやすい可視化の例です(具体のサービス名は各自で調査してください)。
- OI分布:取引所別の建玉密度を価格帯ごとに表示
- 清算マップ:ロング/ショートの清算しやすい帯を色分け
- 板厚ヒートマップ:瞬間の見せ板に過度に引きずられない設計
- マルチ取引所統合:Binance/Bybit/OKXなどの横断で一致帯を探す
設計テンプレ:毎回同じ手順で
1. 地図を作る
- 直近2〜3日のOIクラスターを抽出(出来れば5分解像度)
- 清算帯を重ね、重合ポイント(一掃予備軍)に印をつける
- 板厚から薄い回廊をメモ
2. 入口を決める
- 狩りが起きそうな帯の“外”で待つ
- ヒゲで一掃→再テスト失敗(戻りの勢い鈍化)を確認
- エントリーは小さめ、追加は再テストで
3. 逆指値を置く
- 大クラスター外+ATR×0.25〜0.4
- 過去20回のスパイク幅中央値よりさらに外
- 板厚の壁を背に置かない(壁直前は狩られやすい)
4. 利確とトレール
- 次クラスター手前で部分利確
- 薄帯の先端で残りを伸ばす
- トレーリングは“小クラスターの外側”へ順次移動
5. サイズ配分
- 混雑率(クラスター密度)と24h実現ボラで係数を決定
- イベント(CPI/FOMC)は係数を半分以下に
- 連敗時は自動でベットを縮小(ボラターゲティング)
NG例と修正
NG①:誰もが見る直近安値の1刻み下に逆指値
修正:最低でも大クラスターの外+ATR係数で。
NG②:一掃前に突っ込む成行フルサイズ
修正:一掃→再テスト→出来高細り→小サイズ→利の乗りで段階追加。
NG③:利確を“壁の向こう”に置く
修正:手前で50%利確、残りを薄帯の先端で。
初期設定チェックリスト
- タイムフレーム:1分/5分+15分のトレンド確認
- 指標:ATR、出来高、OIクラスター、清算マップ、板厚
- 逆指値距離:ATR×0.25〜0.4+スパイク幅中央値
- サイズ:ケリーの25〜50%(保守係数込み)
- イベント:CPI/FOMCは係数0.5、発表直後は新規を控える
応用:資金調達率・乖離率を重ねて精度を上げる
OIクラスター単独では「どちらに走りやすいか」は決まりません。資金調達率や先物乖離を重ね、極端に傾いた側の清算帯を優先して狙うと精度が上がります。レバレッジが片側に集中し、資金調達が同側に極端なとき、そこへの吸引が強まりがちです。
リスク管理:テール防御は別レイヤーで
狩り回避とテール防御は別問題です。OTMプットの保険や、小さな損切りを多数受け入れるボラターゲティングを併用します。ひとつの指標に依存しないこと。
まとめ:勝つ場所ではなく“負けない場所”を選ぶ
OIクラスターの外側に逆指値を、クラスター消化の後に入口を、壁の手前で利確を——この3点を徹底するだけで、初心者の最大の悩み「なぜ自分だけ狩られる」が激減します。毎回同じ手順を繰り返し、データで距離とサイズを決める。それが暗号資産先物で生き残る最短ルートです。
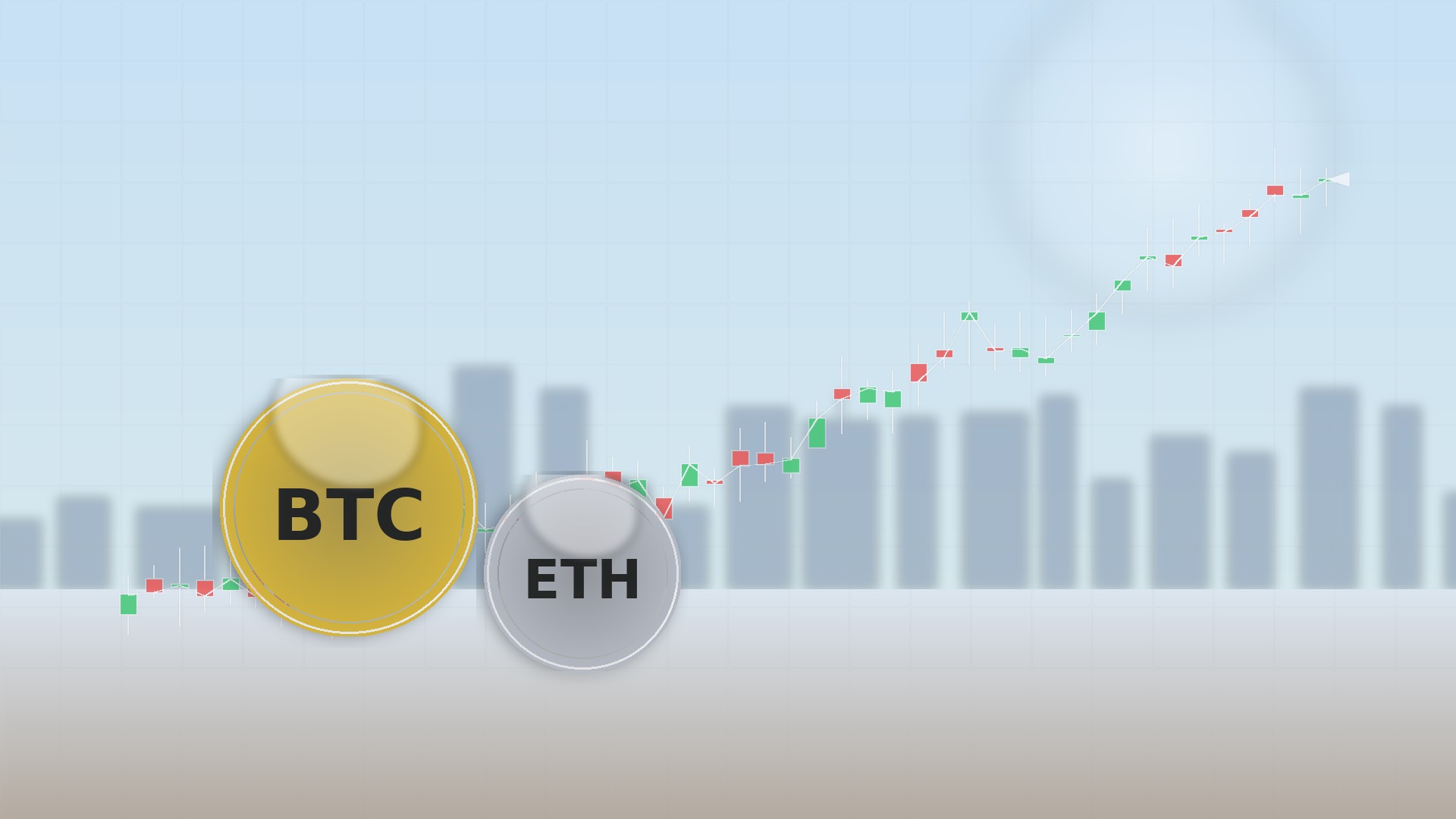


コメント