本記事では、夜間PTS(私設取引システム)の価格と翌営業日の東証寄り付き価格の「乖離」に着目し、初心者でも再現しやすい逆張り型のデイトレ戦略を、手順レベルまで徹底的に解説します。目的は「仕組みを理解し、再現性のある手順を自分で運用できるようにする」ことであり、特定銘柄の推奨や利益の約束ではありません。読了後には、実際に使える売買ルール、注文方法、損益管理、検証手順、トレード日誌テンプレートまで一通り自力で回せるようになります。
- 戦略の要旨
- なぜ夜間PTSなのか
- 必要な環境と口座
- 取引対象の選定(ユニバース)
- 売買ルール(基本型:買い限定)
- 数量の決め方(ポジションサイジング)
- 注文の実務
- ニュースと例外規定
- 実例シミュレーション(数値は仮定)
- バックテストと検証の考え方
- よくある失敗と回避
- 実運用チェックリスト
- 初回セッティングの具体例
- 日誌テンプレート
- 発展:売りパターン・ボラ調整・複数ポジション
- 費用・コストの考え方
- リスクの全体像
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- 付録:スターター・ルール(コピペ可)
- 付録:トレード日誌テンプレ(コピペ可)
- マーケット・マイクロストラクチャ(初心者向けに平易化)
- 呼値(ティック)と滑りへの実務対応
- リハーサル運用(紙上トレード)
- ケーススタディ①:-2.5%の軽度乖離
- ケーススタディ②:-4.8%の中度乖離
- ケーススタディ③:-6.0%の強い乖離(見送り例)
- 手順の擬似コード
- トラブルシュート
- 用語集(本記事で使った語の簡易定義)
- バックテストの手作業プロトコル(再現可能版)
- メンタル運用の設計
- 応用:ボラ調整の数式イメージ
- 応用:時間分散のエグジット
- 応用:分割エントリー
- ケーススタディの反例:ルール逸脱の代償
- 最後に:小さく速く検証し、守りながら拡張する
- 付録B:チェックポイント集(再掲と拡張)
- 付録C:ミニチェック
戦略の要旨
夜間PTSで東証終値より一定割合下落した銘柄に注目します。翌日の東証寄り付きでは、過度な乖離の一部が平均回帰(リバウンド)しやすいという傾向を前提に、寄り付きで買い、短い保有(当日内)で合理的な利確・損切りを行う設計です。空売りや信用取引が不要な「買い限定」の基本型から始めるため、初心者が扱いやすいのが特徴です。
なぜ夜間PTSなのか
夜間PTSは、場が閉じた後もニュースや外部市場の動きに反応して価格が動きます。ただし参加者は限定的で板も薄く、急峻な値動きが生じやすい一方で、流動性の回復する翌朝の東証寄り付きでは、その極端な価格が見直されることが少なくありません。ここに「統計的に説明できる小さな歪み(平均回帰の余地)」が生まれ、短時間・限定リスクで狙う余地が出てきます。
必要な環境と口座
本戦略を始めるのに必須なのは、現物取引口座です。信用口座や先物・オプションは不要です。夜間PTSの板を閲覧できる環境があると理想ですが、厳密には翌日の寄り付きでエントリーするため、PTSでの約定自体は必須ではありません。以下の準備があるとスムーズです。
- 現物口座(オンライン本人確認を済ませ、即日~数日で利用開始できる体制)
- 寄り付きの板状況・前日終値が確認できるプラットフォーム
- 逆指値・OCO(またはIFD-OCO)に相当する注文機能
- 前場寄り付き直後に操作できる時間の確保(5~15分程度)
取引対象の選定(ユニバース)
対象銘柄は、価格の飛びやすさと流動性のバランスが重要です。初心者向けには次のような基準を推奨します(あくまで出発点の目安です)。
- 直近の東証での出来高が一定以上(例:30万株超)。出来高が少ないと板が飛びやすく、滑りやすくなります。
- 株価帯はおおむね300円~3,000円。呼値と歩み値のバランスが取りやすい帯域です。
- 夜間PTSで前日終値対比の価格変動が「大きすぎず小さすぎない」こと(例:-2%~-6%の下落)。過度な変動(-10%超など)はニュース要因の影響が強く、平均回帰の期待よりもリスクが先行しやすいです。
- 夜間PTSの出来高がゼロではないこと。薄いながらも「取引が成立した価格情報」がある方が指標として有効です。
売買ルール(基本型:買い限定)
以下は、初心者が最初に運用するための「最小ルールセット」です。見直しが容易で、機械的に実行しやすい構成にしています。
- 前夜シグナルの定義:夜間PTS終値(または加重平均)が東証終値に対して-2%~-6%の範囲で下落。
- 翌朝のエントリー:東証の寄り付き(成行は避け、寄付き成行に相当する注文方法または寄り直後の指値)で買い。約定後すぐに利確・損切りの条件注文を同時設定。
- 利確ルール:寄付き価格から+0.8%~+1.2%上昇、または前日終値との差の半分を埋めた時点(窓埋め50%)のいずれか早い方。
- 損切りルール:寄付き価格から-1.0%(上級者は板の厚みとボラで-0.6%~-1.2%に最適化)。
- 時間切れクローズ:前引け時点で利確・損切りにかからなければ、原則クローズ(当日中に手仕舞い)。
この基本型は「期待値の源泉=乖離の平均回帰」を明確に捉えつつ、当日内に必ず出口を作ることで、翌日に持ち越すニュースリスクやギャップリスクを避ける設計です。
数量の決め方(ポジションサイジング)
初心者は「固定金額」か「口座残高の一定割合」を基本にします。例として、1トレードあたり口座残高の2%のリスク許容を設定し、損切り幅(例:-1.0%)から逆算して数量を決定します。こうすることで、どの銘柄でも「負けた時の金額」が一定になり、メンタルの乱れを抑えられます。
注文の実務
寄り付きの成行は板が薄い銘柄で不利になりがちです。可能であれば、寄り付いた直後の最良気配付近に「板の厚みを観察しながら」指値を置きます。約定直後にOCO(利確と損切りの両方)を同時に発注しておくと、手動操作の遅れでルールから外れるのを防げます。指値は飛びやすいので、板の空白が多いと感じたら数量を分割するのが安全です。
ニュースと例外規定
夜間の大幅安が「決算下方修正」「重大事故」「監理・規制に関わる開示」など、継続的な価値変化のニュースに起因する場合、平均回帰の期待よりトレンド継続のリスクが高くなります。初心者は明確な悪材料や規制関連の開示が出た銘柄を除外してください。逆に、一時的な需給や外部指数の動きで説明できる軽微な乖離は、平均回帰の対象として比較的扱いやすいです。
実例シミュレーション(数値は仮定)
仮にA社株が東証終値1,000円、夜間PTS終値960円(-4.0%)だったとします。翌朝、寄り付きは955円でスタート。寄り付きで955円×1,000株を買い、OCOで利確+1.0%(964円)/損切り-1.0%(945円)を同時設定。結果、寄り付き後5分で961円まで上昇し、前日終値とのギャップ(1,000-955=45円)の半分=22.5円をほぼ埋めたと判断して964円の指値に到達、+9円×1,000株=+9,000円(税コスト前)で手仕舞い……といった流れです。
バックテストと検証の考え方
理想は、過去データから「PTS対比の乖離」「翌朝の寄り付き変化」「当日高値・安値」の関係を検証することです。最低限、次の評価軸を用意します。
- 勝率:利確>損切りになった割合
- 平均利益・平均損失:1回あたりの損益の平均
- 期待値:勝率×平均利益-(1-勝率)×平均損失
- 最大ドローダウン:残高の最大落ち込み
- 連敗数の分布:メンタル許容の把握
検証のコツは「ルールを固定」し、「シグナルの発生条件(乖離率・出来高基準)」と「出口(利確・損切り幅)」だけを少しずつ動かして感度を測ることです。過剰最適化を避けるため、パラメータは粗めに刻みます(例:乖離率は-2%、-3%、-4%、-5%、-6%の5通り)。
よくある失敗と回避
- 成行一発で大ロット:寄り直後の薄い板で大きく滑りやすい。分割指値と数量上限を厳守。
- ニュースを見ない:継続的な悪材料は平均回帰を無効化しやすい。開示確認と除外規定を明文化。
- 損切り先送り:逆指値を最初から置き、機械的に処理。期待値は「損切りの小ささ」で守る。
- 持ち越し:翌朝のギャップは読めない。日中内に手仕舞いする原則を崩さない。
実運用チェックリスト
- 対象銘柄の出来高と価格帯の基準を満たすか
- 夜間PTSの下落率が基準内か(-2%~-6%)
- 明確な悪材料ニュースが出ていないか
- 寄り前の板の厚み・歩み値の飛びを確認したか
- OCO(利確・損切り)を同時に入れたか
- 数量は1トレードあたりのリスク許容内か
- 前引けで時間切れクローズの準備をしたか
初回セッティングの具体例
最初の10営業日は「練習モード」で、数量を通常の30%以下に抑えます。1日の最大トレード数は2回まで、同時保有は1銘柄。寄り直後の5分以外は原則エントリーしません。勝率ではなく「ルール遵守率」をKPIにします(90%以上を目標)。
日誌テンプレート
以下の項目を毎回記録してください。数週間で癖と改善点がデータ化されます。
- 銘柄コード/名称
- 東証終値/夜間PTS価格/乖離率/PTS出来高(判る範囲で)
- 寄り付き価格/約定価格/数量
- 利確価格・損切り価格・OCO設定の可否
- 最大含み益/最大含み損
- 手仕舞い理由(利確、損切り、時間切れ)
- ルール逸脱の有無と内容
- 気づき(板の薄さ、滑り、ニュース)
発展:売りパターン・ボラ調整・複数ポジション
習熟後は、夜間PTSで大幅高(+2%~+6%)の銘柄を翌朝に短期で売りから入る対称的な戦略も検討できます。ただし空売りには規制・貸借の条件、逆日歩等のコストが絡むため、最初は買い限定での経験蓄積を優先してください。また、銘柄ごとに日中のボラティリティは異なるため、ATR等で利確・損切り幅を動的にスケーリングする方法もあります。複数ポジションを同時に持つ場合は、口座全体のリスクが重ならないように「同一セクターに偏らない」「同一方向に偏らない」という制約を追加します。
費用・コストの考え方
超短期では、売買手数料とスプレッドが成績に与える影響が大きくなります。手数料体系は各社で異なるため、取引回数・約定代金に合ったプランを選ぶほか、指値での約定品質を高める工夫(板読み、数量分割)でスプレッドコストを抑えることが重要です。貸株や金利は本戦略の基本型(当日手仕舞い・現物)では影響が限定的です。
リスクの全体像
- イベントリスク:寄り付き前後に新しい材料が出るとシナリオが崩れます。
- 流動性リスク:板が薄く、想定価格で約定できない可能性があります。
- システム・操作リスク:回線やツールの不調で注文が遅れることがあります。OCOの活用で被害を限定します。
- 心理リスク:数回の損切りで焦ってルールを破りがちです。KPIを「ルール遵守率」に置き、数量を下げて継続することが期待値の源泉になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 夜間PTSの出来高が極端に少ないのですが?
A. 取引がゼロでなければ参考値として使えますが、滑りやすさを考慮して数量を下げるか見送ってください。
Q. 窓埋めが進まず横ばいのまま前引けになりました。
A. 原則通り前引けでクローズします。時間で切るのは、ニュースやトレンドへの暴露を減らすためです。
Q. 損切りが連続するとメンタルがきついです。
A. 連敗は発生します。数量を下げ、同時に「チェックリストと日誌」を厳密化してください。多くの場合、ルール逸脱が減るだけで損益は安定します。
まとめ
夜間PTSと翌日寄り付きの乖離を利用する逆張りデイトレは、ニュースで恒常価値が変わるケースを除外し、機械的な入口・出口・数量ルールを守るほどに再現性が高まります。本稿のステップをそのまま写経し、小さな数量で「ルール遵守率」をKPIに回す。これが初心者にとって最も堅実な第一歩です。慣れてきたら、乖離率・利確幅・損切り幅の最適化や、ボラ調整・売りパターンの追加など、段階的に拡張してください。
付録:スターター・ルール(コピペ可)
【対象】直近出来高30万株以上、株価300~3,000円、夜間PTS下落-2%~-6% 【入口】東証寄り付き直後、板の厚みを確認しつつ指値で買い 【出口】利確+1.0% or 窓埋め50%到達の早い方/損切り-1.0%/前引けで時間切れクローズ 【数量】1トレードの想定損失=口座残高の2%以内になるよう逆算 【除外】明確な悪材料や規制関連の開示がある銘柄 【KPI】勝率ではなくルール遵守率(90%以上)
付録:トレード日誌テンプレ(コピペ可)
日付: 銘柄コード/名称: 東証終値: 夜間PTS価格: 乖離率: PTS出来高: 寄り付き価格: 約定価格: 数量: 利確価格: 損切り価格: 手仕舞い理由(利確/損切り/時間切れ): 最大含み益: 最大含み損: ルール遵守(はい/いいえ): 逸脱内容: 気づき(板、滑り、ニュースなど):
マーケット・マイクロストラクチャ(初心者向けに平易化)
寄り付き価格は、前場開始時点の板(買い注文と売り注文)を突き合わせる「板寄せ方式」で決定されます。ここでは、約定可能な価格帯の中で出来高が最大化される水準が選ばれます。夜間PTSの極端な価格は、寄り付きの大規模な注文とぶつかることで薄まる(平均回帰)ことが多く、乖離が縮小する原理的背景になります。
一方で、寄り付き前に特別気配・連続気配といった異常気配が宣言されるケースでは、寄り付きまでに時間を要し、指値のギャップが広がることがあります。この場合、本戦略の「買い限定・短期回帰」の前提が崩れやすいため、初心者は特別気配・連続気配が発生したら見送りとするのが無難です。
呼値(ティック)と滑りへの実務対応
株価300~3,000円帯では、呼値(1ティックの刻み)が比較的細かく、指値コントロールがしやすくなります。例えば1,000円付近なら1ティック=1円で、+1.0%の利確はおよそ+10円です。板の空白が目立つ時は、利確・損切りの指値位置を「板の厚み」や「直近の出来高溜まり」に合わせて1~2ティック内側に寄せるとヒット率が上がります。
リハーサル運用(紙上トレード)
本番前に10営業日分の紙上トレードを推奨します。夜間の乖離を確認し、翌朝の寄り付き価格で仮想エントリー、利確・損切りルールを適用して「その日のうちにクローズ」までシミュレーションします。手を動かしてみると、板の薄さや時間の流れ、OCOの重要性が肌感覚で理解できます。
ケーススタディ①:-2.5%の軽度乖離
前日終値800円、夜間PTS終値780円(-2.5%)。寄り付きは779円。買い→利確+1.0%(787円)/損切り-1.0%(771円)。寄り後の歩みは、まず781円で揉み合い、板の厚い785円手前で一度押されるが、前日終値との窓(21円)の半分=10.5円を埋める水準785円超に到達。最終的に787円にタッチして利確成立。軽度乖離は平均回帰幅が小さい分、滞留しやすい価格帯を板で確認し、利確を欲張りすぎないことがポイントです。
ケーススタディ②:-4.8%の中度乖離
前日終値1,200円、夜間PTS終値1,142円(-4.83%)。寄り付きは1,138円。買い→利確+1.0%(1,149円)/損切り-1.0%(1,126円)。寄り直後に1,145円まで反発、その後1,133円まで押し戻される展開。逆指値に触れずに再浮上し、1,149円で利確。中度乖離は「一度押し戻される」揺り戻しが起きやすいため、数量分割や指値の再設計を事前に決めておくとルールがぶれません。
ケーススタディ③:-6.0%の強い乖離(見送り例)
前日終値2,000円、夜間PTS終値1,880円(-6.0%)。寄り前に悪材料の追加開示が出て、気配が特別気配へ移行。寄り付きが遅延し、板の飛びも大きい。これは除外規定に該当するため見送り。平均回帰の前提が脆弱なニュース主導のケースでは、勝ちやすく見えても参加しないのが期待値の守り方です。
手順の擬似コード
if (出来高 >= 基準) and (株価帯 in 300-3000) and (PTS乖離率 in [-6%,-2%]) and (悪材料なし) and (特別気配なし):
open = 寄付価格
buy(open)
set_take_profit(open * 1.010) # +1.0%
set_stop_loss(open * 0.990) # -1.0%
if (窓埋め率 >= 50%) and (価格 < 利確価格):
exit_market() # 先に到達した方を優先
if (前引けまでに未約定):
exit_market()
else:
skip()
トラブルシュート
OCOが誤作動/設定漏れ:約定直後に順序立てたマクロ化(「約定→OCO入力→記録」)を癖付けます。発注画面のテンプレ保存機能があれば活用してください。
板が薄すぎる:乖離率が基準内でも、板の空白が多い場合は数量を1/2に縮小、または見送りにします。
寄り天(寄ってから下落し続ける):逆指値に任せます。損切りを狭くする代わりに、利確幅も一定に保ち、勝ち負けのバランスで期待値をコントロールします。
用語集(本記事で使った語の簡易定義)
PTS:取引所外での株式売買システム。夜間に価格がつくことが多いが、板は薄い。
寄り付き:その日の最初の約定価格。板寄せ方式で決定される。
平均回帰:一時的に行き過ぎた価格が元の水準に戻る統計的性質。
OCO:利確と損切りを同時に出す注文。どちらかが約定すると他方が自動取消。
窓埋め:前日終値と当日の寄り付きの差(窓)が取引時間中に縮まる現象。
バックテストの手作業プロトコル(再現可能版)
- ランダムに30営業日を選定し、毎日「終値・夜間PTS価格・翌朝寄り・当日高安」を記録。
- 乖離率が-2%~-6%の銘柄だけ抽出。
- 寄り付きから+1.0%/-1.0%の到達可否、窓埋め50%到達の有無を判定。
- 日ごと・銘柄ごとに損益とKPI(勝率、平均損益、最大DD、連敗)を集計。
- 基準を満たさなかった日の理由(出来高不足、悪材料、特別気配)も必ず記録。
このプロトコルは、初心者が最短で「自分の数字」を得るために設計しています。最初の30日で感触を掴み、90日分で再現性の有無を見極めます。
メンタル運用の設計
連敗が続くと、利確を引き伸ばし、損切りを遅らせるという典型的な逆最適行動が出ます。これを防ぐ設計として、朝の寄り付きの前に「数量」「入口」「出口」「時間切れ」の4点を紙に書き、トレード中は一切条件を触らないというルールを提案します。終わったら日誌に結果だけを書き、翌日以降に検討します。
応用:ボラ調整の数式イメージ
ATR(14)を用い、損切り=0.5×ATR、利確=0.5×ATR+α(最小でも+0.8%)のように設定して、銘柄のボラに合わせて幅を自動調整する方法があります。初心者はまず固定幅(±1.0%)で始め、サンプルが溜まってから段階的にボラ連動へ移行してください。
応用:時間分散のエグジット
利確指値にタッチしないが、価格が寄り付きから+0.5%~+0.8%で横ばいを続ける場合、時間基準の部分利確(例:10分経過で半分利確)を導入すると、膠着での機会損失を抑えられます。残り半分は本来の利確/損切りに委ねます。
応用:分割エントリー
寄り付き直後に1/3、2分後に1/3、窓埋め20%到達で残り1/3という時間分散のエントリーは、初動の乱高下に強い反面、想定より早く利確に到達する局面では取りこぼしが出ます。手法としては有効ですが、まずは単発エントリーでKPIを作成してから採用を検討してください。
ケーススタディの反例:ルール逸脱の代償
寄り付き後すぐ+0.9%まで上昇。利確+1.0%に1ティック届かずに反転し、逆指値まで下落して損切りに。ここで「惜しかったから」と利確幅を0.8%に広げたり、逆指値を遠ざけると、長期的に期待値を損ないます。1回の悔しさでルールを変えないことが、再現性のコアです。
最後に:小さく速く検証し、守りながら拡張する
本戦略は、構造的な優位(夜間の行き過ぎ×寄り付きの板寄せ)を小さくすくい取る設計です。最初は数量を極小で、手順の固定化と日誌の充実に集中してください。数字が積み上がるほど、勝ち筋と負け筋が言語化でき、規模の拡張に耐える運用へ近づきます。
付録B:チェックポイント集(再掲と拡張)
- 乖離率の測定方法は一貫しているか(終値対比、四捨五入ルールの統一)
- 寄り付き方法(成行/指値)はルール化されているか
- OCOの入力順序とテンプレは固定されているか
- 数量の逆算は毎回同じ式で算出しているか
- 見送り条件(悪材料、特別気配、板の空白)は書面で可視化しているか
- KPIは勝率ではなく、遵守率・最大DD・連敗数も併記しているか
付録C:ミニチェック
寄り前3分で気配が急変した場合は、板の空白とニュース有無を再確認し、数量を半分に調整してから臨んでください。迷ったら見送りです。


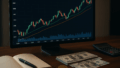
コメント