はじめに:グローバルM2とは
「M2」という指標は、現金(M0)をはじめとする比較的すぐに使えるお金の総量を指します。具体的には、現金に加えて当座預金や定期預金など、支払い能力のある資金のことを言います。これに対し、「グローバルM2」とは、世界全体の通貨供給量を指します。米国、欧州、日本、中国などの主要通貨圏を合算したものであり、この数値が増えることは、言い換えれば「世界中で金余り」が進行することを意味します。
この増加した通貨供給量は、最終的に市場にどのような影響を与えるのでしょうか。その影響のひとつとして、ビットコイン(BTC)の価格上昇が挙げられます。では、なぜビットコインはグローバルM2に遅れて追従するのか、そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。
ビットコインがグローバルM2に遅れて追従する理由
下のグラフはビットコインの価格(青線)とグローバルM2の3ヵ月遅行させたグラフを重ねたものです。ビットコイン価格がグローバルM2に追従していることがはっきりと分ります。

資金余剰がリスク資産に波及するラグ(時間差)
グローバルM2の拡大が始まると、まずその余剰資金は株式、債券、不動産といった伝統的なリスク資産に流れます。これは、リスクを取る投資家が最初に注目する市場です。その後、リスクを取る投資家の選択肢として、よりボラティリティの高い資産、つまり暗号資産やコモディティ(商品)へと資金が波及します。
ビットコインは伝統的な資産に比べ、ポートフォリオ上での優先順位が低いため、余剰資金は最後にビットコインに到達します。そのため、グローバルM2が拡大しても、ビットコインの価格上昇が始まるのは時間を要するというわけです。
市場構造的な要因
ビットコイン市場は、株式や債券市場に比べると規模がまだ小さく、流動性も薄いため、大口の資金流入に対して非常に価格感応度が高いです。そのため、グローバルM2が増加した直後にビットコインの価格が即座に反応することは少なく、むしろ「伝統市場でリスクオンの態度が顕著になった後」に、ようやく暗号資産市場に資金が波及する形になります。このため、価格が上昇するタイミングにラグ(遅れ)が生じます。
マクロトレーダー(機関投資家)の行動パターン
多くのマクロファンドや機関投資家は、グローバルM2の拡大を「インフレ」や「実物資産の買い」のサインとして認識します。最初に彼らが注目するのは、金や銀、原油などのリアルアセット(実物資産)です。これらの資産が上昇した後、さらにリスクを取れる状況になれば、ビットコインやイーサリアムなど、デジタル資産に手を出し始めるのです。
したがって、M2が拡大した後、数カ月遅れてビットコイン価格が上昇するというパターンが繰り返されるわけです。
センチメントと価格弾性
ビットコインは「ストーリーで動く資産」としても知られています。たとえば、「デジタルゴールド」としての評価や、未来の価値の高まりに対する期待など、マーケットのセンチメントが価格を動かします。グローバルM2の拡大だけでは、即座にビットコインの価格が上がるわけではありません。
インフレ懸念や法定通貨への不信、または金融緩和政策の期待といったストーリーが社会全体に浸透してから、ようやくビットコインへの投資家の関心が高まります。この過程でセンチメントが変化するため、ビットコインの価格上昇には数か月以上のラグが生じることになります。
実務的なまとめ
ビットコインがグローバルM2の拡大に遅れて上昇する現象を理解することは、投資家にとって重要です。このメカニズムを理解することで、より効果的な投資戦略を立てることができます。
応用戦略
- 分割買い戦略: M2が増加したタイミングで、ビットコインを現物ベースで分割して買う戦略は有効です。数ヶ月後には利益を享受できる可能性が高まります。
- 逆の動きに注意: 逆に、M2が減少基調に転じると、ビットコインは必ず重くなります。その際は、BTCを売るなどして、リスク管理を行う必要があります。

また、「グローバルM2の6か月移動平均」と「BTC価格」を重ね合わせることで、非常に強い相関が見えることが確認できます。この戦略を実践に活かすことで、より精度の高い投資判断が可能になります。


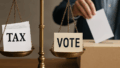
コメント