本稿は投資教育・リサーチ目的の一般情報です。特定の金融商品の取得・売却・勧誘を目的とするものではありません。運用判断は自己責任で行ってください。
暗号資産のベーシストレード完全ガイド:現物×先物でつくるデルタニュートラル利回り
ベーシストレード(basis trade)は、現物(スポット)と先物の価格差(ベーシス)に着目し、その乖離を収益源にする裁定手法です。クリプトでは、パーペチュアル(無期限先物)のファンディングレートや、四半期先物のコンタンゴ/バックワーデーションが常に発生し、伝統市場よりも機会が多いのが特徴です。ポジションの本質はデルタ・ニュートラルであり、価格方向に賭けずに、資金調達コストと先物プレミアムから「利回り」を取りに行きます。
なぜ利回りが生まれるのか:市場構造の歪み
クリプト先物は、個人投資家のレバレッジ需要とヘッジャーの需給でプレミアムが付きやすく、強気局面では先物が現物より高く(コンタンゴ)、弱気局面では割安(バックワーデーション)になりがちです。無期限先物ではロングとショート間の資金授受(ファンディング)が定期的に発生し、需給に応じてロングがショートへ、あるいはその逆へ支払います。先物買い需要が強い=ロング優勢なら、ショート側がファンディングを受け取れるため、現物ロング+先物ショート(キャッシュ・アンド・キャリー)で年率数%〜二桁%の期待利回りが狙えます。
ポジションの型:キャッシュ・アンド・キャリーとリバース
キャッシュ・アンド・キャリーは、現物を買い、先物を同数量ショートして価格変動を相殺し、先物のプレミアムやファンディング受取を収益源にする基本形です。逆に、先物が大幅ディスカウントで、無期限のファンディングもショート支払い方向なら、リバース・キャリー(現物ショート+先物ロング)を検討します。ただし、現物ショートには借株・貸仮想通貨の可用性と費用が必要で、個人は実務上ハードルが高めです。
収益の基本式(概念)
年率換算の概算収益は、次の和(または差)で捉えます。
想定年率 ≒ 先物プレミアム(年率化)
+ ファンディング受取(年率化)
- 手数料(建玉・清算・資金移動)
- 借入金利・レンディングコスト
- スリッページ・価格ズレ
先物がプレミアムで、ファンディングも受け取り方向で安定している銘柄(例:強気地合いのBTC/ETH)では、複合的にプラスが積み上がります。逆に、地合い悪化やポジション偏りで急変し、年率が一気に低下することもあります。
数値例①:BTCのキャッシュ・アンド・キャリー
想定:BTCスポット=¥10,000,000、四半期先物=スポット比+1.5%(残存90日)、無期限ファンディングはショート受取 0.01%/8h(1日3回・日次0.03%想定)。
- 先物プレミアム(年率化):1.5% × (365/90) ≒ 6.1%
- ファンディング受取(年率化):0.03% × 365 ≒ 10.95%
- 概算粗利回り:6.1% + 10.95% = 17.05%(諸費用前)
ここから手数料・スリッページ・資金移動コストを差し引きます。実務では建玉時の手数料(スポット買い+先物ショート)、先物ロール時のコスト、資金引き出し手数料を合算し、ネットの年率を常に更新します。
実装フロー:現場での手順
- 取引所選定:流動性、手数料、保全、保険基金、ADL(自動デレバ)頻度、API安定性で比較。スポットと先物を同一所内で完結させると担保効率が上がります。
- 手数料レート:メイカー/テイカーの差、VIPティア、先物資金調達に関する細則(上限制・変動幅)を確認。手数料の差で年率は大きく変わります。
- 資金配分:現物の全額購入に対し、先物は証拠金で建てられるため、余剰証拠金を短期国債利回り代替のステーブルコイン運用に回すなどの最適化が可能(ただしカウンターパーティ・デペッグリスクを常に考慮)。
- 注文設計:スプレッドの薄い時間帯で建玉。スポット買い→先物ショートを極力同時執行(OCO/スプレッド発注、APIバスケット)でベータズレを抑える。
- ヘッジ比率:名目1:1が基本。無期限と四半期でヘッジする場合は金利感応度(ベーシス感応度)がズレるため、期間分散とサイズ調整で吸収。
- ロール運用:四半期先物は満期前に差し替え。ベーシスの季節性(ロールウィークの歪み)を利用してコスト縮小。
- 資金の入出金動線:法定通貨↔ステーブル↔取引所の摩擦を最小化。KYCレベルにより限度額や出金待機が変わるため、停止時の代替経路を事前に設計。
リスク管理:儲けを守るボトルネック
- ファンディング反転リスク:ロング優勢が崩れると、ショート側が支払う立場へ。過去分布のヒストグラムとイベントカレンダーでシナリオ管理。
- 先物カーブの変形:強いコンタンゴが薄まり、年率が圧縮。ロール時のスプレッドも拡大する可能性。
- 清算・ADL:高レバロングの連鎖清算で先物だけ急変。証拠金は過剰に、保険基金残高とADL規則を監視。
- 取引所カウンターパーティ:ハッキング、経営、規制。所内分散、資金の定期退避、コールド/マルチシグ管理で低減。
- ベーシス乖離の一時拡大:建玉直後のスプレッド悪化は想定内。強制的な解消を避け、玉の滞留耐性を用意。
- ステーブルコイン・チェーンリスク:デペッグ、ブリッジ障害、チェーン停止は想定。銘柄・チェーンの冗長化、オフ取引所保管のルール化。
銘柄別の癖:BTC・ETH・アルト
一般にBTCは先物の歪みがマイルドで、ETHはイベント(大型アップグレード)近辺で歪みが拡大しやすい傾向。アルトはファンディングの振れが激しく、小型銘柄ほど瞬間風速は大きいが継続性は低いため、サイズは抑えて短期回転に徹します。
スクリーニングとモニタリング
- 無期限のファンディング・ボードを監視し、安定して受取方向かをチェック(直近7〜30日の加重平均)。
- 四半期先物のベーシスをスポット比%で時系列化し、年率換算して閾値(例:ネット年率8%超)を超えるタイミングだけ建玉。
- 手数料・取引税・出金手数料を関数化し、ネット年率のリアルタイム見積をダッシュボード化。
- イベントカレンダー(FOMC、CPI、半減期、ハードフォーク)でリスク・ウィンドウを避ける。
実務のコツ:小さく始めて設計を磨く
- ミニサイズで検証:少額で1〜2週間の観察運用。年率の「実測値」と理論値の乖離を特定。
- メイカー重視:スプレッドが薄い時間帯は指値中心でコスト最適化。ボラ急騰時はテイカーでヘッジ優先。
- ヘッジドリフトの補正:現物と先物の名目一致を日次で再調整。配当相当の調整金や分岐イベント時は特別ルールを確認。
- 監査ログ:建玉根拠・年率・費用・ロール結果を日報化。「なぜこの玉?」に即答できる体制を作る。
ケーススタディ:3つのシナリオ
シナリオA:順風(プレミアム維持+受取ファンディング)
年率は理論値に近づく。サイズを段階的に拡大しつつ、清算リスクは常時ゼロ近傍に。
シナリオB:横ばい(プレミアム縮小)
四半期のプレミアムが薄れる。無期限の受取で相殺できるかを再評価、閾値割れなら縮小や解消。
シナリオC:逆風(バック化+支払ファンディング)
ネット年率がマイナス化。迅速に縮小し、再び条件が整うまで待機。「やらない勇気」が累積成績を守る。
よくある失敗パターン
- 建玉の同時性が低く、価格ドリフトで隠れた方向性リスクを抱える。
- ヘッジ比率が合っておらず、現物と先物の名目がズレる。
- 手数料・出金コスト・為替を見落としてネット年率を誤算。
- イベント日にフルサイズで滞留し、ADLや急変動に巻き込まれる。
簡易シミュレーター(ロジック例)
入力:
現物価格S、先物価格F、残存日数D、日次ファンディングf(受取+、支払−)
片道手数料(スポットcs、先物cf)、建玉サイズQ
計算:
先物プレミアム年率 = ((F/S) - 1) * (365 / D)
ファンディング年率 = f * 365
取引コスト年率 ≒ (cs + cf) * 回転頻度(ロール等)
想定年率 = 先物プレミアム年率 + ファンディング年率 - 取引コスト年率
期待損益(名目)= 想定年率 × (S × Q)
表計算でも十分に再現できます。重要なのは、毎日データを更新して意思決定を自動化することです。
まとめ:待つ・測る・小さく始める
ベーシストレードは、相場観に依存せず、市場構造の歪みから利回りを得る手法です。鍵は、(1)ネット年率の精緻な見積、(2)同時執行によるドリフト抑制、(3)イベント回避と所内外リスク分散。条件が整わないときは何もしない。これだけで成績は大きく変わります。


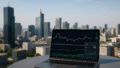
コメント