本稿は、ステーブル間金利スプレッド裁定(CeFi/DeFi横断)を、最小限の価格リスクで利回りを拾う運用として体系化します。ビットコインやアルトのボラを取りに行かず、「同じ1ドル」の金利差に注目して利ざやを刈り取るのが肝要です。初めてでも再現できるよう、構造、手順、計算式、KPI、失敗パターン、退出基準まで具体的に示します。
1. 何を狙うのか:定義と収益ドライバー
本戦略のターゲットは、同一または近似の価値単位(例:USDT・USDC・DAIなど)に対して発生する「貸借金利」や「資金調達率」のズレです。代表的な収益源は以下のとおりです。
- CeFi定期・フレキシブル金利 vs DeFi貸出金利の乖離:中央集権取引所(CEX/CeFi)の利回りと、Aave/Compound等の供給APYとのスプレッド。
- DeFi同士の金利格差:AaveとSpark/Compoundなど、プール需給の歪みから一時的に広がる供給・借入金利差。
- ステーブルスワップLP+ヘッジ:CurveなどのAMMで手数料・インセンティブを得つつ、建値あるいはデルタをヘッジしてネットで金利キャリー化。
- パーペチュアル資金調達率の活用:市場中立で金利分のみを回収(例:現物orステーブル建てでのΔゼロ化)。
重要なのは、価格トレンドを当てにしない点です。収益の源泉は相場観ではなく、市場の需給ひずみ、プールの利用率、交換コストの差にあります。
2. 前提装備と運用体制
2.1 必要装備
以下を準備します。
- 自己保管型ウォレット(例:ハードウェアウォレット推奨)。
- 少なくとも1つの国内取引所口座と、裁定経路に応じた海外CEX口座。
- 主要L1/L2でのガス代をカバーする少額のネイティブ通貨。
- ステーブルコイン(USDT/USDC/DAI等)。
2.2 口座・チェーン配備の考え方
スプレッドは「今そこにある」機会です。跨チェーン&跨プラットフォームで即応できる配備(資金の前方配置)がリターンの分水嶺になります。特に、ガスコスト・ブリッジ時間・KYC処理時間は見落としがちです。
3. スプレッドの見つけ方:ボトルネックと指標
観測すべきはシンプルに以下です。
- 供給APY・借入APY(Aave/Compound/Sparkなど)
- 利用率(Utilization):高すぎると変動リスク増、低すぎると収益性低下。
- 手数料・インセンティブ:インセンティブ終了・減額のカレンダー。
- 資金調達率(Funding):パーペチュアルの符号・振れ幅。
- ブリッジ・ガス総コスト:往復でのネットコスト。
ネットAPY=(貸出APY+インセンティブ)−(借入コスト+手数料+ガス年換算)。
このネットAPYが十分に正であり、変動幅・回転頻度・運用額に照らして意味のある水準かを見極めます。
4. 代表的プレイの設計図
4.1 DeFi同士の金利差キャリー
手順:AaveでUSDCを借りる(借入APY b%)→別プロトコルでUSDCを供給(供給APY s%)→s−bを回収。必要に応じて、借入を担保化(例:ETHステーブルのデルタ管理)。
注意:利用率急変でbが跳ね上がること、インセンティブが縮小すること。借入側のLTVと清算閾値に余裕を持たせる(Health Factor>1.6目安など)。
4.2 CeFi vs DeFiの裁定
例:CEXでUSDT年6%のフレキシブル、DeFi供給が年10%。入出金料・ロック期間・上限・信用リスクまで年換算し、ネットがプラスなら回す。CeFiは突然の条件変更・上限到達があるため、分散配備が基本です。
4.3 ステーブルスワップLP+ヘッジ
Curve等の安定ペアでLPし、手数料+インセンティブを獲得。プール比率の偏りやデペグで含み損が出得るため、在庫偏りをヘッジ(先物・オプション・逆方向スワップ)してネット金利化します。
4.4 Fundingキャリー(市場中立)
資金調達率が恒常的に正(多くはロング優勢)の銘柄で、Δゼロを作ってFundingを受取る設計。ただし反転・急変があるため、短期回転+日次再評価が原則です。
5. 数値で確認:ケーススタディ
初期資金10,000 USDC、期間30日、以下を仮定します。
- 借入(Aave):年6.0%(可変)、日割り。
- 供給(別プロトコル):年12.0%(可変)、日割り。
- インセンティブ:年2.0%相当。
- 往復ガス・入出金等コスト:30日で合計20 USDC。
30日間の概算利回り:
受取利息=10,000×(12%+2%)×(30/365)=10,000×0.14×0.08219≒115.1 USDC
支払利息=10,000×6%×(30/365)=10,000×0.06×0.08219≒49.3 USDC
ネット金利=115.1−49.3=65.8 USDC
総コスト控除後=65.8−20=45.8 USDC(≒0.458%/30日、年換算≒5.6%)
要点:手数料と変動に潰されない幅を確保できるか。ネット5〜8%年換算が安定して見込める局面に絞るのが現実的です。
6. リスク体系とヘッジ設計
本戦略は「価格を張らない」分、運用設計とオペレーションが成否を分けます。
- 金利変動リスク:利用率急騰で借入APYが跳ねる/インセンティブ終了。日次でネットAPYを再評価し、閾値割れでクローズ。
- デペグ・清算リスク:担保/借入の通貨と清算閾値の相関に留意。Health Factor目標値と自動アラートを設定。
- スマートコントラクト/オラクル/ブリッジ:分散配置、監査履歴の確認、片方向に大きく賭けない。
- 流動性と上限:天井に当たるとAPYが崩れる。複数プロトコルに分散。
- オペミス・キー管理:マルチシグやハードウェアウォレット、少額テスト、送金先の指差し呼称。
7. エントリー/エグジットとサイズ最適化
7.1 閾値設計
例として、ネットAPY>=年7%を新規エントリー条件、年4%割れで退出。過去30〜60日の分布で持続性のあるゾーンに限定します。
7.2 サイズ配分
ケリーの保守版として、金利差の平均μ、日次変動σ、ドローダウン許容dから、ボラターゲティングで月次損益の標準偏差を上限制御。単純には、最大DD想定の1/2〜1/3を初期サイズ。
8. 執行の最適化:スリッページとルーティング
大口はTWAP/POVで分割し、DEXはアグリゲータを使って最良経路へ。手数料が高いチェーンはL2優先。片道で3〜10bpsのコスト差は、年間のパフォーマンスを数%動かします。
9. 監視ダッシュボード:KPIセット
- ネットAPY(年換算):中核の意思決定指標。
- Health Factor/LTV:清算安全域を維持。
- 利用率(U):上昇は借入コスト上振れの前兆。
- 報酬カレンダー:インセンティブ減額・終了日。
- ブリッジ待機時間と失敗率:資金機動性に直結。
10. よくある失敗と回避策
(失敗)ガス・ブリッジ費用の過小見積もり → (対策)最低運用期間・最低ロットを定義し、年換算コストを毎回シート計算。
(失敗)金利反転に気づかず放置 → (対策)ネットAPY閾値の自動通知+定時点検。
(失敗)単一プロトコル集中 → (対策)プロトコル・チェーン・カストディの三重分散。
11. プレイブック(簡易)
- 対象ステーブルとチェーンを決め、資金を前方配置。
- 観測KPI(供給/借入APY、Funding、U、ガス年換算)を日次取得。
- ネットAPYが閾値以上ならエントリー、条件悪化で段階的に縮小。
- 清算安全域(HF>1.6)・ヘッジ有無を常時モニタ。
- 週次でサイズ調整、月次で稼働戦略の入替え。
12. まとめ
ステーブル間金利スプレッド裁定は、相場観に依存せず「ひずみ」を刈り取る運用です。価格の大暴れを避けつつ、計測・分散・閾値管理で淡々と積み上げる。派手さはありませんが、ポートフォリオの底上げとして機能します。今日からは、ネットAPYの可視化と即応できる配備を最優先に整備してください。


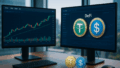
コメント