フラット35の逆ザヤ構造とは何か
2025年現在、フラット35を巡る金利構造において、極めて異常な状況が続いています。本来であれば、フラット35は住宅金融支援機構が機構債(MBS)を発行し、その調達コストに管理費用や信用リスクプレミアム、金融機関の手数料などを加えた水準で貸出金利を決定します。しかし現状は、機構債の金利が2%を超えているのに対し、フラット35の貸出金利は1.9%前後に抑えられており、金利差が逆転する「逆ザヤ」が恒常化しているのです。
通常の金利決定メカニズムとの乖離
過去の慣例からすれば、MBSの利回りに0.5〜1.0%程度を上乗せすることでフラット35の貸出金利が決まってきました。これは、機構の運営経費・証券化のコスト・保証制度の維持費などを考慮すると合理的なスプレッド幅です。したがって、MBS金利が2.0%であれば、フラット35貸出金利は最低でも2.5%、場合によっては3.0%程度が自然なラインといえるでしょう。それにもかかわらず実際の貸出金利が1.9%台に留まっていることは、政策的な意図なしには説明がつきません。
低金利維持の背景にある政策的要因
なぜこのような市場原理に反する金利水準が維持されているのか。その背景には、政府による住宅政策上の強い意向が存在すると考えられます。インフレ局面において金利上昇をそのまま反映させれば、住宅ローンの借入負担が急増し、住宅購入需要が急速に冷え込みます。これは建設業界、不動産業界への打撃となり、ひいては日本経済全体の景気後退リスクを高めます。これを避けるため、政府は住宅金融支援機構に対して「赤字を承知でも貸出金利を低く維持せよ」と事実上の指導を行っている可能性が高いといえます。
逆ザヤ構造がもたらすリスク
このような逆ザヤ状態が長期にわたって継続すると、以下のような深刻なリスクが発生します。
- 財務リスク: 機構は毎月の利払いにおいて赤字を計上し続け、内部留保を取り崩すことを余儀なくされます。累積赤字は信用不安を招き、機構債の利回りがさらに上昇するという悪循環を生む可能性があります。
- 財政リスク: 独立行政法人である機構の最終的な裏付けは政府です。赤字が拡大すれば税金による補填が必要となり、すでに膨張している財政赤字を一層悪化させます。
- 住宅市場の歪み: 人為的な低金利が住宅価格を下支えし、本来であれば調整局面に入るべき不動産市場の健全な価格形成を阻害します。その反動として、将来的に金利を正常化した際に一気に市場が冷え込むリスクがあります。
リーマンショックとの比較と違い
2008年のリーマンショックでは、サブプライムローンを証券化したMBSが大量に不良化し、世界的な金融危機に発展しました。フラット35のMBSは国の保証が付与されているため、同様の信用崩壊を招く可能性は低いです。しかし問題は別の次元にあります。すなわち「日本は金利を正常化できない国だ」という市場からの評価です。このレッテルが貼られれば、海外投資家は円を売り、輸入コストを通じてインフレが加速する可能性が高まります。
ハイパーインフレリスクの構造
歴史的にハイパーインフレは、政府が巨額の財政赤字を中央銀行に直接引き受けさせ、通貨信認を急速に失わせた時に発生してきました。日本は外貨建て債務が少ない点では一定の安全性がありますが、日銀が国債を大量に保有し事実上の財政ファイナンスを行っている現実は無視できません。フラット35の低金利維持は「金利を絶対に上げない国」という政策的メッセージを強める役割を果たしており、それ自体が市場に対して円安を織り込ませる要因となり得ます。
短期・中期・長期のシナリオ
- 短期: 政府が赤字を容認し、住宅市場を守るため低金利政策を維持する。借り手にとっては恩恵が大きいが、機構の赤字は確実に積み上がる。
- 中期: 機構の財務悪化が顕在化し、国庫補填か金利引き上げの選択を迫られる。どちらを選んでも国民経済に負担が及ぶ。
- 長期: 財政赤字と金融抑圧が限界を迎え、国債市場の信認が揺らぐ。金利急騰と円安が同時進行し、輸入インフレが制御不能な領域に入る可能性がある。
まとめと警鐘
結論として、フラット35の低金利維持は短期的には住宅購入者を救済する政策ですが、長期的には日本経済全体に重大なリスクを内包しています。逆ザヤ構造の継続は財務・財政・住宅市場の三重の歪みを生み出し、最終的には通貨への信認低下を通じてハイパーインフレに近いリスクを高めるのです。「リーマンショックの再来」ではなく「財政危機とインフレリスクの顕在化」という、日本独自のリスクシナリオに直面していると認識すべきでしょう。


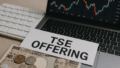
コメント