暗号資産の世界において鋭い視点を持つ元BitMEX CEO、アーサー・ヘイズ氏が、最近の市場分析で「Persistent Weak Layer(持続的弱層)」という概念を取り上げました。
これはもともと雪崩リスクの科学用語ですが、彼はこの概念を市場の構造的な脆弱性を表す比喩として使っています。特定の要因が長期間見過ごされ、積み重なった末に、何かの拍子で大きな価格変動やボラティリティを引き起こすというものです。
ビットコインマイニングとハッシュレートの耐性
氏は、かつて中国がマイニングを事実上禁止し、ビットコインのハッシュレートが一時的に60%以上減少した出来事を引き合いに出し、ネットワークの適応力の高さを強調しています。
たとえ局地的にマイニングが停止しても、他地域のマイナーが稼働を増やすことで、ハッシュレートは回復し、価格にも長期的な悪影響はなかったと述べています。これは、ネットワークが自律的にバランスを保つ強固な設計を持つ証左と言えるでしょう。
エネルギー価格との連動性:BTCは「デジタル・エネルギー」
ヘイズ氏は、ビットコインを「蓄積されたデジタルエネルギー」と位置付け、エネルギー価格が高騰する局面では、ビットコインもその価値を保ち、あるいは上昇するとしています。
「すべてのマイナーが等しく電力コストの上昇に直面する以上、マイニングの難易度が下がることで新規参入者にとっても採算が合いやすくなる。市場は自然と調整する」と分析しています。
1970年代のエネルギー価格高騰と金価格の相関を例に取り、ビットコインにも同様の動きが期待できるとし、「BTCはエネルギーに連動して動く価値尺度になる可能性がある」と主張しています。
マクロ経済と中央銀行のバランスシート
ビットコインの長期的な成長ドライバーとして、氏は「通貨供給の増加=中央銀行のバランスシート拡大」との連動性に注目しています。
「過去、金融危機や大規模経済対策の度にバランスシートは拡大し、そのたびにビットコインは法定通貨に対して価値を高めてきた」とヘイズ氏は述べています。
以下のチャート(※掲載可能であれば)では、FRBのバランスシートとビットコイン価格の相関性が視覚化されており、BTCはその期間中に約25,000%のパフォーマンスを記録しています。
ポートフォリオ構築のヒント:「無視できない構造リスクに備える」
氏は、自身のポートフォリオ管理において「予測できない外的要因に対して過剰にリスクを取りすぎないこと」が重要だとし、「短期的なノイズではなく、構造的な変化と通貨供給のトレンドを重視すべき」と語ります。
現在は、安定資産であるBTCを軸に据えつつ、イールド戦略や新規トークンのプレセール案件などに一部資金を配分しているとのこと。
まとめ:「BTCは持続的弱層の上に咲く強靭な花」
アーサー・ヘイズ氏の視点は一貫しています。構造的リスクが潜在的に存在する現在の市場環境において、重要なのは資産の選別と資本の防衛です。
エネルギーコスト上昇、金融政策の変動、マイニング動態といった複数のマクロ要因を踏まえた上で、ビットコインの耐性と適応力をどう評価するか。この視点は、今後のポートフォリオ戦略を考える上で非常に示唆に富んでいます。

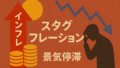

コメント