この記事では、現物ロング+無期限先物(パーペチュアル)ショートを組み合わせて、資金調達率(Funding)と先物ベーシスから期待値を積み上げる「キャッシュ&キャリー(C&C)×資金調達率アービトラージ」を、個人投資家が再現可能な粒度で実装する方法を解説します。単なる概論ではなく、口座準備→建玉構築→リスク制御→再バランス→ボット運用までを具体的手順で示します。
1. 戦略の骨子:どこからお金が生まれるのか
本戦略の収益源泉は大きく2つです。
- 資金調達率(Funding)の受け取り:無期限先物で多くのトレーダーがロングに偏る局面では、ショート保有者にFundingが支払われることが多い。
- ベーシス(現物と先物の価格差)の解消:期近や四半期先物がコンタンゴであれば、期日までに先物が現物に近づく分が期待値となる。
同時に、価格変動リスクは現物ロングと先物ショートで相殺(デルタニュートラル)します。理屈上は価格中立ですが、実務では「約定・手数料・スリッページ・乖離・清算リスク・為替」を管理する必要があります。
2. 必要口座と準備
- 現物を扱える口座(例:BTC/USDTのスポット取引口座)。
- 無期限先物の口座(USDT建・USD建・コイン建てのいずれか)。
- 二要素認証、APIキー(読み取り/取引権限の分離)、出金ホワイトリスト。
- 証拠金管理:レバレッジは最大でも2倍以下を推奨。清算余裕を広く確保。
- 資金分散:単一取引所集中を避け、現物と先物を別取引所に分ける選択肢も検討。
日本在住者は、各サービスの利用可否・提供形態・表示通貨・KYC要件・契約相手方やリスク説明の内容を必ず確認してください。
3. 取引の基本形と損益分解
基本形:同数量の現物ロング+無期限先物ショート。
理論損益(簡易):
日次期待値 ≈ Funding受取 − 手数料 − スリッページ − 借入/金利コスト ± ベーシス収縮分資金調達率は通常8時間ごと等で発生します。年率換算は (1+Funding_8h)^(3×365) − 1 のように概算できます(小数点近似可)。
4. 実行フロー(手順)
- 資金配分を決める:例として元本100万円、先物側はレバレッジ1.5倍以内、清算価格までのバッファは最低15〜20%を確保。
- 現物を取得:スプレッドと手数料の低い板を選び、指値で段階的に買付。
- 先物を同数量ショート:マーク価格基準の清算仕様・資金調達タイミング・手数料構造を確認。
- デルタ確認:名目金額(現物数量×価格)と先物名目が一致しているかを常時計測。
- 再バランス規律:乖離が±1〜2%に達したら微調整。急騰急落時は段階的に3回に分けて修正。
- 資金調達率モニタリング:直近と予測(予告)を監視。マイナス転化が継続する時はクローズや取引所切替を検討。
- 証拠金アラート:維持率閾値(例:45%)で通知、40%で強制縮小の自動ルール。
- 出金と記録:週次でPnLを確定、ログと台帳(タイムスタンプ・数量・価格・手数料・Funding)を保存。
5. 数値モデル:100万円での概算
前提:BTC=10,000 USDT、USDJPY=160、手数料(片道)0.04%、Funding平均+0.01%/8h、先物レバ1.5倍。
- 名目:100万円 ≒ 6,250 USDT。
- 建玉:現物0.625 BTCロング、先物0.625 BTCショート。
- Funding年率の粗い目安:0.01%×3×365 ≒ 10.95%(単利近似)。
- 手数料往復:0.08%×名目(年内の回転回数に依存)。
実際の年率は、手数料・微調整回数・逆転Funding・価格乖離時の補正コストで目減りします。“取りに行ける期待値”が常に存在するとは限らない点は肝要です。
6. リスク管理の要点
- 取引所リスク:破綻・出金停止・清算エンジン不具合。資金分散と出金頻度のルール化。
- 清算リスク:コイン建て・USDT建ての区別、マーク価格仕様、資金移動の遅延。
- 価格乖離:現物・先物の一時的乖離で一時的損失が出る可能性。再バランスは小口・分割で。
- Funding反転:中長期でマイナスが続く相場環境。ポジション縮小や別銘柄へ回す選択肢。
- 為替リスク:円評価の損益はUSDJPYで変動。円建てヘッジ(FX)や外貨建て評価を採用。
- オペレーション:API権限の最小化・キー保管・アラート冗長化・監査ログ。
7. ボット運用の設計(疑似コード付き)
最小限の構成は「監視→判定→発注→記録」。以下はロジック例です。
# 疑似コード(ccxt想定)
while True:
price_spot = get_price("BTC/USDT", venue="spot")
price_perp = get_mark_price("BTC/USDT", venue="perp")
funding_now, funding_next = get_funding("BTC/USDT")
delta = notional(spot_qty, price_spot) - notional(perp_qty, price_perp)
if abs(delta) >= threshold_notional:
order_small_rebalance(delta) # 分割発注
if funding_next < funding_floor or risk_flags_on():
reduce_position() # 自動縮小
if margin_ratio <= 0.45:
notify("追加証拠金 or 縮小")
log_everything()
sleep(300) # 5分間隔再バランスの粒度は滑らかに、“成行で一発約定”は禁止が原則。板の厚い価格帯に指値を置き、約定速度よりコスト最適化を優先します。
8. 変種:ベーシス回収/取引所間Funding裁定
- 期先先物のベーシス回収:四半期先物ショートでコンタンゴを取りに行く。期日時のロールコストと手数料に注意。
- 取引所間Funding裁定:取引所Aでショート受取、同時に取引所Bでロング支払いを受ける構成。ただし資金・清算・価格乖離リスクは倍増。
- スポット利回り付与×ショート:ステーキング報酬のあるトークンでスポット利回り+先物ショートの合成。ただしアンロックやスラッシング規約に要注意。
9. 運用ルール例(チェックリスト)
- レバレッジ上限:1.5〜2.0倍以内。
- 再バランス閾値:名目乖離±1.5%/一括禁止・分割3回。
- 資金調達率フロア:次回予告が0%近辺で2回連続なら縮小検討。
- 証拠金維持率:45%で警報、40%で自動縮小。
- 週次でPnL確定と出金、ログ保存、異常時の事後レビュー。
10. 具体的な失敗例と対策
- 上昇相場で「どうせFundingはプラス」と思い込み、マイナス転化後に放置 → 予告値の監視と自動縮小。
- 清算価格が近いのに増し玉でごまかす → レバを上げない、縮小を最優先。
- 取引所ダウン時に同時約定できずに乖離 → 分散とバックアップ回線、キューイング。
- 為替を忘れ円評価が悪化 → 評価通貨の統一・為替ヘッジ・報告書の二軸評価。
11. 実装メモ(台帳と監査)
最低限の台帳項目:日時/TxID/取引所/市場/売買/数量/価格/手数料/資金調達率/建玉残/証拠金比率/ドル円。CSVでエクスポートし、週次で突合します。
12. まとめ
キャッシュ&キャリーと資金調達率アービトラージは、相場観に依存しにくい「期待値の源泉」を狙う手法です。ただし、約定コスト・清算・為替・運用オペレーションを軽視すると、理論値は簡単に損なわれます。小さく始め、再現性のある手順とログで仕組み化しましょう。
用語ミニ解説
- 資金調達率(Funding):無期限先物で、ロングとショートのどちらかが一方に支払う調整金。
- ベーシス:現物と先物の価格差。コンタンゴ(先物高)/バックワーデーション(先物安)。
- デルタニュートラル:価格変動に対して理論上中立となる建玉構成。

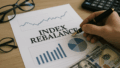

コメント