要約:本稿は、暗号資産(仮想通貨)のマーケットで「価格予想をしない」まま利回りを狙う手法として知られるキャッシュ&キャリー(現物買い+先物売り)を、初学者でも再現できる粒度まで分解した実践ガイドです。具体的には、仕組み・数式・手数料と税金の考え方・発注手順・日次運用・撤退基準・自動化の設計図・よくある失敗と対策まで、運用に本当に必要な内容のみを漏れなく整理しました。
- 1. なぜ「キャッシュ&キャリー」なのか
- 2. 仕組みの全体像(3分で把握)
- 3. 用語最速辞典(本文を読み切らなくても使える)
- 4. 収益の正体を数式で確認
- 5. 取引所と銘柄の選び方(失敗しないための基準)
- 6. ヘッジ比率1.0の作り方(名目一致)
- 7. 実行手順(最短10分、ただし最初は紙に書いてから)
- 8. 計算例(100万円で開始)
- 9. リスクと対策(ここが最重要)
- 10. 日次~週次の運用ルーティン
- 11. 自動化の設計図(ノーコード/ローコード)
- 12. よくある質問(FAQ)
- 13. 発注前チェックリスト(印刷推奨)
- 14. 退出戦略(勝ち逃げの定義)
- 15. ミスの実例から学ぶ
- 16. 記録テンプレート(列見本)
- 17. まとめ
1. なぜ「キャッシュ&キャリー」なのか
多くの個人投資家は「上がる・下がる」を当てに行きます。しかし、予想の精度を上げることは難しく、学習コストも高い。一方で、本手法はデルタ(価格方向)をほぼゼロに抑え、資金調達率(Funding)や先物ベーシス(Basis)の歪みを収益源にします。運用のキモは「ポジション構造」と「オペレーションの正確さ」であり、相場観ではありません。
- 想定読者:現物の売買経験はあるが、先物は未経験~初級。
- 必要資金:数十万円から開始可能(例示あり)。
- 目標:ミスなくヘッジ比率1.0で組成し、Fundingやベーシスの受け取りで「年率換算の実効利回り」を最大化する。
2. 仕組みの全体像(3分で把握)
キャッシュ&キャリーの基本形は次の通りです。
- 現物を買う(例:BTCを100万円分)。
- 同額名目の先物を売る(例:BTC無期限先物を名目100万円分ショート)。
- 価格が上がっても下がっても、現物の含み益と先物の含み損が相殺し、理論上はデルタ中立。
- ポジションを保有している間、資金調達率(Funding)や限月先物のベーシスから収益(またはコスト)が発生する。
この「歪み」から得られる収益が本手法のソースです。方向性を当てる必要はありません。
3. 用語最速辞典(本文を読み切らなくても使える)
- 資金調達率(Funding)
- 無期限先物の価格が現物に乖離しないよう、ロングとショート間で定期的に支払い/受け取りを行う仕組み。多くの取引所で8時間ごとに発生。先物が現物より割高ならロングがショートへ支払うのが一般的。
- ベーシス(Basis)
- 限月先物価格 − 現物のスポット価格。限月までの金利・保管・需給が反映される。キャリー(Carry)の源泉。
- マーク価格
- 清算判定に用いられる参照価格。板の異常や瞬間的スパイクに影響されにくい。
- 分離マージン/クロスマージン
- ポジションごとに証拠金を分ける方式(分離)と、口座全体で共通化する方式(クロス)。本手法の初学者には分離マージン+レバレッジ1~2倍を推奨。
4. 収益の正体を数式で確認
名目をN、保有日数をD、1日あたりの資金調達率(年率換算)をfd、売買手数料をc(往復、名目比率)とすると、単純化した期待収益(税引前)は概ね次式で表現できます。
期待収益 ≈ N × (f_d × D / 365) − N × c − 資金機会コスト
無期限先物のみで運用するならfdはFundingの実効日次換算値、限月先物ならベーシス/日がfdの代わりになります。現実にはFundingは変動し、ベーシスも収斂速度が一定ではないため、ローリング平均と下振れストレスを併用した保守見積もりが必要です。
5. 取引所と銘柄の選び方(失敗しないための基準)
- 出来高と板厚:名目100万円を瞬時に建ててもスリッページが1bp以内に収まるかを板で確認。
- 手数料:メイカー/テイカー、先物/現物、手数料トークン割引、VIP段位の要件。
- Fundingの表示仕様:過去実績の可視化・API取得可否・計算タイムスタンプ。
- 清算エンジン:ADL(強制減少)の発動基準、保険基金の規模。
- 担保資産:現物担保で先物ショートが建てられるか(現物担保型一括口座が最も扱いやすい)。
6. ヘッジ比率1.0の作り方(名目一致)
最も多いミスは「名目不一致」です。名目の合わせ方は次の通り。
- 現物の購入数量
Q_spotを決める(例:0.1 BTC)。 - 先物の契約仕様から、1枚あたりの名目
Nominal_per_contractを確認(例:1枚=0.001 BTC)。 売るべき契約枚数 = Q_spot / Nominal_per_contractを四捨五入し、端数を現物側で調整する。
これで理論デルタはほぼゼロになります。
7. 実行手順(最短10分、ただし最初は紙に書いてから)
- 口座準備:KYC、二段階認証、出金ホワイトリスト、手数料トークン有効化。
- 資金配分:現物用70~80%、先物証拠金用20~30%、予備キャッシュ5%(清算回避用)。
- 板確認:現物・先物それぞれのスプレッド、深さ、成約ペースを30秒観察。
- 同時発注:
- 手順A:現物成行買い → 直後に先物成行売り(最も単純)。
- 手順B:先物売り指値→約定通知をトリガーに現物買い(スリッページ最小化)。
- ヘッジ比率確認:名目一致をダッシュボードで再確認。
- 取引ログ保存:スクショ、約定履歴、手数料、Funding履歴をその場でCSVに書き出す。
8. 計算例(100万円で開始)
前提:BTC=10,000,000円、100万円で0.1 BTCを購入。無期限先物を0.1 BTCショート。Fundingは平均0.01%/8h(≒日次0.03%)、現物/先物の往復手数料合計は0.08%と仮定。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 名目 | 1,000,000 円 |
| 日次Funding(期待) | 1,000,000 × 0.0003 = 300 円/日 |
| 往復手数料(初回のみ) | 1,000,000 × 0.0008 = 800 円 |
| 10日保有の粗収益 | 300 × 10 − 800 = 2,200 円 |
| 年率換算(単利) | 0.0003 × 365 ≒ 10.95% |
Fundingがマイナス(ショートが支払う側)に転じた日は収益が削られます。ローリング30日平均などで「下振れストレス」を見ながら運用期間を決めるのが実務です。
9. リスクと対策(ここが最重要)
- 清算・ADLリスク:レバレッジを1~2倍に抑え、分離マージンで清算価格を遠くに置く。価格急変時は一時的にヘッジを厚く(ショート超過)する判断も。
- 名目不一致:建玉変更や配当(ステーキング報酬)で数量が変わる場合がある。毎日ログで名目差を確認。
- Funding反転:イベント前後で急反転する。受取のローリング平均が閾値を下回ったら縮小。
- スプレッド/滑り:出来高の薄い時間帯を避ける。成行は「先物→現物」の順でコストを抑えやすい。
- 取引所リスク:分散(2取引所)と出金ホワイトリスト。保険基金や停止歴を定期点検。
- ステーブルコインのデペグ:余剰資金を分散保有。フィアットとステーブルの両方を用意。
- API/自動化の暴走:サンドボックスで検証→本番は最小名目で段階導入。
10. 日次~週次の運用ルーティン
- 日次(5分):Funding見込み、名目一致、清算価格距離、損益、ログ保存。
- 週次(15分):30日ローリング利回り、最大ドローダウン(理論)、取引所リスクチェック、手数料ランク更新。
- イベント時:高ボラが予見される場合は名目を半分に落とすか、一時クローズ。
11. 自動化の設計図(ノーコード/ローコード)
本稿は特定取引所のAPI名を挙げませんが、構成はどこでも同じです。
- データ取得:現物・先物の最新価格、Funding予想、口座残高、建玉数量。
- 判定ロジック:
- 名目差が0.1%超 → 先物枚数を微調整。
- ローリング30日Funding年率がX%未満 → ポジション半減。
- 清算価格が現値から±Y%以内 → 証拠金追加 or 名目縮小。
- 発注:成行/指値のスイッチ、スリッページ上限、同時送信。
- ログ・通知:約定結果、手数料、Funding受取/支払、評価損益をスプレッドシートに追記し、閾値でプッシュ通知。
12. よくある質問(FAQ)
Q1. Fundingがマイナス続きのときは?
A. 名目を削るか、限月先物のベーシス狙いへ切り替え。ローリング平均で判断。
Q2. 何かを「ロングだけ」「ショートだけ」でやるのと何が違う?
A. 本手法は価格方向のリスクをヘッジするため、方向性の的中は不要。収益源は歪みの解消です。
Q3. どの銘柄が向いている?
A. 出来高、板厚、Fundingの安定性で選ぶ。一般に大型銘柄ほど運用が安定します。
13. 発注前チェックリスト(印刷推奨)
- 二段階認証・出金ホワイトリストは有効か。
- 名目一致:現物数量×価格 = 先物名目(±0.05%以内)。
- 清算価格は現値から十分遠いか(想定ボラ×3倍)。
- スプレッドと板厚は許容内か。
- ログ保存の仕組みは用意したか。
14. 退出戦略(勝ち逃げの定義)
「いつ閉じるか」を事前に決めます。
- ローリング30日Funding年率が期待値の50%未満になったら一部または全閉鎖。
- 清算価格が近づき、証拠金追加が不要・不可能な場合は即時縮小。
- 取引所のシステム・規約変更や担保仕様変更のアナウンスが出た場合はポジションを軽くする。
15. ミスの実例から学ぶ
- 名目差を放置:配布報酬で現物残高が増え、デルタがロングに傾き損失。対策は「日次で名目差を自動検知」。
- 清算価格が近い:低資金で高レバにした結果、瞬間変動でADL。対策は「レバ1~2倍、分離マージン、余剰担保」。
- イベントでFunding反転:重要イベント直前に縮小するルールが無かった。対策は「イベントカレンダー連動の名目上限」。
16. 記録テンプレート(列見本)
日付, 銘柄, 現物数量, 現物平均価格, 先物枚数, 先物平均価格, 名目差(%), Funding受取(支払), 手数料, 評価損益, 清算価格距離(%), コメント
17. まとめ
キャッシュ&キャリーは相場観ゼロでも始められる稀有な手法です。肝は「名目一致」「レバ抑制」「記録とルール」。本稿の手順どおりに小額から始め、運用プロセスを整えたうえで名目を段階的に引き上げてください。価格を当てる勝負ではなく、オペレーションの精度で勝つ戦いです。
付録A:用語集(簡潔版)
- デルタ中立:価格変動に対してポジションの価値がほぼ変わらない状態。
- ADL:異常事態での強制減少。保険基金が尽きると発動。
- スリッページ:注文価格と約定価格の差。
付録B:簡易シミュレーション式
名目 N、保有日数 D、日次Funding f_d、往復手数料率 c のとき
期待粗利 ≈ N × (f_d × D / 365) − N × c


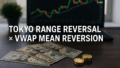
コメント