結論: 現時点で上場の純粋プレーはほぼ存在しません。利益を狙うなら、ピック&ショベル(周辺サプライチェーン)に資金を配分するのが実務的です。具体的には、超伝導(REBCOテープ)・極低温(ヘリウム冷凍)・真空・レーザー/光学・高機能金属・計測の6レイヤーです。
前提と投資方針
- 核融合は商用化の時間軸が長い一方、研究装置の建設・改修・運用でサプライヤーは継続的に受注が発生。
- テーマドリブンの資金流入を取りに行くより、実需が積み上がる装置・部材に集中。
- 個別銘柄は「核融合専業」ではなく、複数セグメントを持つ大手が多い。過度なテーマ依存を避けつつ、カタリスト(実機の進捗・契約・補助金)に乗る。
産業マップ:私ならどこで稼ぐか
- 超伝導(REBCO/HTS):CFS/SPARC等で採用が進む。日本勢はテープ製造に強み。
- 極低温(ヘリウム冷凍/配管):ITER/JT‑60SAなど大型装置の必須インフラ。
- 真空(クライオポンプ、配管):トカマク/ヘリカル装置の排気・不純物管理の要。
- レーザー/光学:慣性閉じ込め(レーザー核融合)と計測のコア。
- 高機能金属(W、Be、Cu合金等):ダイバータ/ファーストウォールなど高熱負荷部材。
- 計測・検出:プラズマ診断、フォトン/中性子計測。
米国:注目銘柄(ピック&ショベル)
- LIN(Linde plc):極低温のグローバル大手。ITER向け冷凍・コールドボックス納入実績。テーマ耐性が高い。
- AIQUY(Air Liquide ADR):ITERの巨大クライオプラント主要サプライヤー。受注→据付→試運転の長期案件パイプライン。
- COHR(Coherent):レーザー/光学でNIF・ITER等と連携実績。高出力レーザー/光学材料の供給網を持つ。
- LASR(nLIGHT):高輝度半導体レーザー/ポンプダイオード。IFEのドライバーコスト低減テーマで中長期の勝ち筋。
- MTRN(Materion):高純度Be/合金。実験炉(例:JET等)での使用実績があり、高熱負荷材の需要恩恵。
- BWXT(BWX Technologies):核燃料・放医研材・国家安保分野。直接の融合売上は限定も、核分野の装置・人材・品質保証が強み。
日本:注目銘柄(ピック&ショベル)
- 7011(三菱重工):ITER向けトロイダル磁場コイルを製作・出荷。大型重工・据付で優位。
- 7013(IHI):ITER向け超臨界ヘリウム循環ポンプなど極低温機器の実績。
- 6502(東芝):ITERの巨大TFコイル製作実績、JT‑60SAの組立にも関与。
- 5801(古河電工):米子会社SuperPowerがREBCOテープ(HTS)を量産。CFS等への供給で存在感。
- 5803(フジクラ):REBCOテープの大口サプライヤー。量産体制の構築が鍵。
- 6728(ULVAC):クライオポンプ/真空で装置需要のベースを押さえる。
- 6965(浜松ホトニクス):プラズマ診断・検出(PMT等)で研究炉の計測ニーズを取り込む。
- 5724(A.L.M.T.):ITER向けタングステン・モノブロック供給実績。高熱負荷部材のど真ん中。
主なカタリストと工程表(投資トリガー)
- JT‑60SA:2023年10月に初プラズマ達成。現在は2026年後半の本格実験に向け改修・装備増強中(加熱・診断等)。部材・装置の継続発注に波及。
- ITER:巨大クライオプラントや冷凍配分設備の据付・試運転が段階的に進行。周辺サプライヤー(極低温・真空・配管)に長期の仕事。
- NIF(米):2022年12月の点火達成以降、繰り返し検証とスケールアップ研究が続く。レーザー/光学・ターゲット材の需要。
- 民間:Helion×Microsoftの2028年PPA(≥50MW)等、ビッグテックの需要シグナルは周辺サプライヤー再評価の呼び水。
売買戦略(例)
- コア:極低温・真空(LIN/AIQUY/6728)を配当・安定性重視で。
- サテライト:HTS(5801/5803)とレーザー(COHR/LASR)をイベントドリブンで上乗せ。
- 材料:高熱負荷材(5724/MTRN)は建設・改修ニュースで増減配分。
主要リスク
- ITERなど大型案件の工程遅延/設計変更(受注時期・仕様のズレ)。
- HTS量産の歩留まり/コスト改善の遅れ、原材料コスト高騰。
- レーザードライバーのコスト/効率ブレークスルー待ち(研究開発費の先行)。
- 為替(円安/ドル高)による評価損益の振れ。


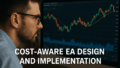
コメント