米ドル建てマネー・マーケット・ファンド(MMF)は、ドル資金の「駐車場(パーキング)」として最有力の選択肢です。本稿では、個人投資家が実際に使いやすいSBI岡三・USドル・マネー・マーケット・ファンドとブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンドを、利回り・コスト・流動性・実績という4軸で徹底比較し、具体的な使い分けまで落とし込みます。
いきなり結論
総合力:ブラックロックに軍配。日次で最新利回りにアクセスしやすく、運用体制・情報開示・約定/受渡の安定性で優位。
一方でSBI岡三はコスト上限が軽めで、長めのドル置き場としては魅力。意思決定は「その日の直近7日利回り」と実効費用の確認が前提。
なぜ今、米ドルMMFか
短期金利が十分に高止まりしている局面では、待機資金に金利を効かせることが機会損失の抑制につながります。MMFは証券口座内で完結し、為替取引との連携が容易。株・債券・FX・暗号資産に展開する前段として、「資金効率 × 機動性」を両立できます。
商品設計の違いと立ち位置
SBI岡三・USドルMMF
- 2024年ローンチの新鋭。オンライン投資家の導線を意識した設計。
- 管理費用等の上限が相対的に軽め(例:年0.58%上限)。実効負担の最適化余地がある。
- 情報掲示窓口が限定的で、最新利回りは販社ベースで要確認。
ブラックロック・スーパーMMF
- グローバル規模の短期運用インフラに接続。日本の主要販社で利回りが日次掲示されやすく可視性が高い。
- ストレス時の流動性確保や約定/受渡の安定性を重視する設計思想。運用レコードが厚い。
- コスト上限はやや重いクラスもあるが、規模や運用効率でカバーされることが多い。
利回りの見方(直近7日年率)
両者とも「直近7日間の平均分配を年率換算」した表示が基本です。投資家が意思決定に使うのは当日の表示値であり、更新頻度とアクセス性が重要です。
- ブラックロック:大手販社で日次掲示が一般化。意思決定のスピードに直結。
- SBI岡三:掲示窓口が限定的。発注前に当日の直近7日利回りを確認する運用が前提。
参考レンジ(執筆時点の確認例):ブラックロック 3.6%前後、SBI岡三 3.7%前後。※実際の利回りは市場金利・運用状況で日々変動します。
コスト(上限と実効の使い分け)
MMFのコストは最終的に実効利回りに内包されます。よって、上限値だけでなく「同一日の直近7日利回り」で実務比較することが合理的です。
- SBI岡三:管理費用等の上限合計が軽め。中長期でコスト最適化の余地。
- ブラックロック:上限で不利なクラスがあっても、運用効率・規模効果で利回りに反映される場合が多い。
流動性・実務耐性(ここがプロは最重視)
MMFは「安全資産」ではありません。だからこそ、大量解約時の売却可能性、受渡の平滑性、掲示・約定ラインの強さが肝です。
- ブラックロック:世界規模の短期市場アクセスと日本国内での運用・掲示体制が強み。高額運用や高頻度ローテに向く。
- SBI岡三:実績蓄積フェーズ。ネット証券との親和性が高く、静的なドル置き場としては魅力。
ケース別推奨
短期・高頻度でドルを回す(トレードの駐車場)
ブラックロック。日次掲示で利回り把握が容易、約定/受渡の安定性に優れるため、機動的な出し入れに対応。
中長期のドル保有でコスト効率を詰めたい
SBI岡三を検討。当日の直近7日利回りと実効負担を確認してから意思決定。
併用(ヘッジファンド的な配車)
メインをブラックロックに置き、コスト優位が明確なタイミングのみSBI岡三へ一部スイッチ。短期金利動向に合わせて比率を可変にする運用が合理的。
発注前チェックリスト
- 販社サイトで当日の直近7日利回りを確認(両ファンド)。
- 購入手数料/信託財産留保が不要であることを確認(一般的には不要)。
- 受渡(翌営業日)と注文締切時刻を確認(販社ルール準拠)。
- 為替手数料・スプレッドは別勘定。往復コストを把握。
- 高額資金は分割発注で執行リスクを軽減。
最終評価
- 流動性・実績・可視性:ブラックロックが優位
- コスト効率(潜在):SBI岡三に分
- 総合:ブラックロック(ただし利回りと費用のその日比較は必須)
編集後記(運用のコツ)
MMFは地味ですが、資金効率の起点です。「最新利回り × 発注締切 × 受渡」を常に押さえ、状況が変われば迷わず配分を更新してください。結果に直結します。
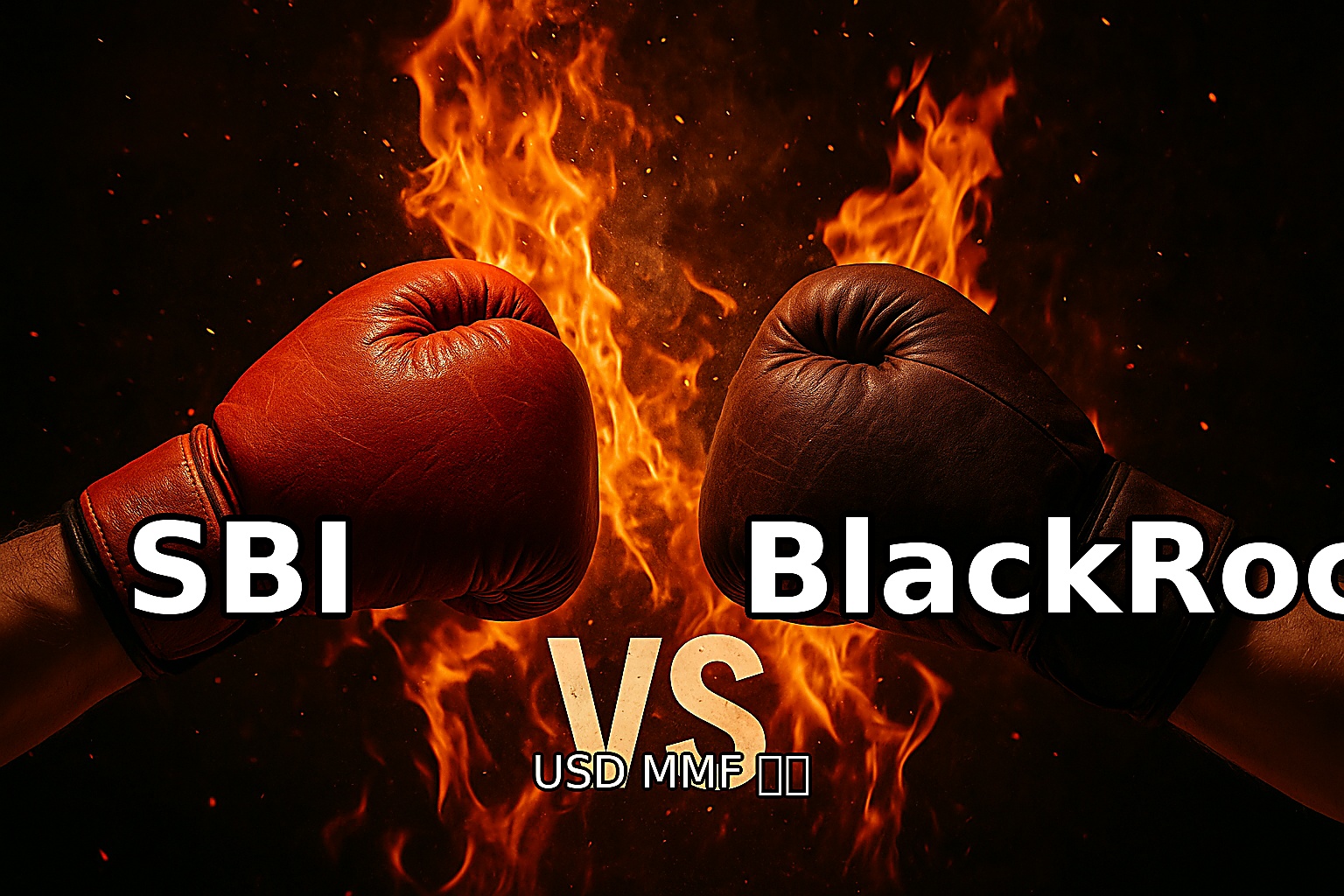


コメント