本記事は、定期積立の進化版「バリュー平均法(Value Averaging, 以下 VA)」を、投資初心者でも今日から運用できるレベルまで徹底的に落とし込んだ実践ガイドです。VAの肝は、資産評価額の「目標成長パス」をあらかじめ定め、そのラインに到達するように毎回の入金額(または売却額)を機械的に調整する点にあります。結果として、値下がり局面では多く買い、値上がり局面では少なく買う(場合によっては一部売却)という、価格に逆らわない賢い資金配分が自動化されます。
1. この記事で得られること
- VAの設計思想・数式・運用ルールを、数式よりも直感重視で理解できます。
- 月次で「いくら口座に入金し、いくら買う(売る)か」を具体的に算出する手順が分かります。
- Excel / Googleスプレッドシートで動く完全な算式を提示します(コピペで即利用可能)。
- 手数料・税金・NISA・配当・分配金の扱い、複数銘柄や為替を絡めた応用まで、実運用で詰まりやすい論点を網羅します。
- 自動化ワークフロー(IFD/OCO、積立予約、アラート)まで含めて現実解を提示します。
2. ドルコスト平均法(DCA)との違い
DCAは毎回の拠出額が一定です。一方でVAは毎回の評価額の目標を定め、実際の評価額との差分を埋めるように拠出額(または売却額)を調整します。よって、価格が下がったときは多く買い、上がったときは少なく買う(場合により売る)というボラティリティに順応した買付になります。
理屈上、価格変動(ボラティリティ)が一定以上ある市場では、DCAよりも平均取得単価を下げやすく、目標リターン到達確率を高められる可能性があります。ただし、資金計画の上下振れが発生するため、キャッシュ・マネジメントが鍵になります。
3. VAの仕組み:ターゲット成長パス
月t(t=1,2,3, …)における目標評価額を T_t とします。初期評価額を V_0、毎月の目標増分(線形の場合)を g とすると、
T_t = V_0 + t × g実際の月末(または買付時点)の評価額を V_t とすると、その月に投じる(または引き出す)金額 I_t は、
I_t = T_t - V_{t-1} × (1 + r_t)ここで r_t は月次リターン(配当・分配込み、税引前/後は方針に依存)。I_t > 0 なら入金・買付、I_t < 0 なら一部売却・出金を意味します。売却発生を避けたい初心者は、目標パスを控えめに設定し、上限入金額を決めるのが現実的です。
4. まず決めるべき3つの設計パラメータ
- 対象資産:個別株よりは、まずは幅広いインデックスETF(例:TOPIX/日経平均/全世界/全米など)を推奨。為替の影響を許容できるかで国内/海外を選択。
- 目標成長パス:線形(毎月一定額の評価増)か指数(年率目標)か。初心者は線形が直感的。
- キャッシュ上限と緩衝バッファ:「月いくらまで入金できるか」「売却は原則しない」などの制約を先に宣言。緩衝用の現金プール(例:3か月分の上限入金額)を別口座で用意すると運用が安定します。
5. スプレッドシート実装(コピペ可)
以下は Googleスプレッドシート想定の例です(Excelは関数名を適宜置換)。列は左から、月(t), 価格(P_t), 保有数量(Q_{t-1}), 評価額(V_{t-1}), 目標(T_t), 必要投資額(I_t), 約定数量(ΔQ_t), 新保有(Q_t), 新評価額(V_t)。
/* 前提セル */
B1: 初期価格
B2: 初期数量(=0可)
B3: 月次目標増分 g(例: 50,000)
B4: 最小発注金額/最小単位(例: 100円、1株など)
B5: 取引コスト率(例: 0.001)
B6: 入金上限額(例: 100,000)
B7: 売却可否(TRUE/FALSE)
/* 行 t の計算(t は 1 始まり、ヘッダは0行とする) */
E_t: 目標 T_t = V_0 + t * g
F_t: 必要投資 I_t = T_t - V_{t-1}
F_t = MIN(MAX(F_t, -IF(B7, 10^9, 0)), B6) // 上限/売却制限を適用
G_t: 取引後必要数量増分 ΔQ_t = FLOOR( F_t * (1 - B5) / P_t , 発注最小単位 )
H_t: 新保有 Q_t = Q_{t-1} + ΔQ_t
I_t: 新評価 V_t = H_t * P_t価格列 P_t は、日々の終値から月末終値を参照しても、GOOGLEFINANCE関数で月次取得しても構いません。端数処理と手数料を必ず反映してください。
6. 具体例:国内ETFに毎月最大10万円、目標増分5万円
前提:
- 対象:国内上場の広範指数ETF(例)。
- 初期評価額:0円、月次目標増分
g = 50,000円、入金上限100,000円、売却はしない方針。 - 価格は月末終値で約定、手数料率0.1%を仮定。
相場が下落する月は I_t が上振れ(10万円の上限に張り付く可能性)、上昇する月は I_t が小さくなり、心理的に買いづらい下げ相場でしっかり買える仕組みになります。キャッシュが不足しないよう、別枠の現金プールを1.5〜3か月分確保しましょう。
7. VAを失敗させない4つのコツ
- 目標パスは控えめに:収入・支出の季節性を加味。ボーナス月だけ増やす等の可変パスも有効。
- 売却回避設計:初心者は「売却なし」で設計し、上振れ時は買付停止で吸収。税コストと手間を削減。
- 現金バッファの二重化:証券口座側と銀行側に分けて用意。緊急時も自動入金で不足を防止。
- 自動化の5点セット:(a)定期アラート、(b)定期積立設定、(c)IFD/OCOのテンプレ、(d)月末の価格参照自動化、(e)約定記録テンプレ。
8. 複数銘柄・為替の応用
二資産(国内株ETF+海外株ETF)の場合、ポートフォリオ全体に目標パスを敷く方法と、各資産に個別パスを敷く方法があります。初心者は資産別パスが運用しやすいでしょう。為替が絡む場合は、価格列を「円換算価格」に統一し、為替レート列(例:USDJPY)を掛け合わせて評価額を計算します。
9. 配当・分配金の扱い
配当・分配金は、(A)現金プールに積み増し、翌月の I_t 計算に反映する、または(B)自動再投資で数量を増やし評価額に含める、のいずれかで一貫性を保ちます。税引後ベースで評価額を管理するとズレが少なくなります。
10. 手数料・税・最小単位・スプレッド
- 手数料:スプレッド・売買手数料・為替手数料を見積もり、
I_t算式にコスト率を乗せる。 - 税:売却を伴う設計では譲渡損益や配当課税が発生し得ます。初心者は「売却なし」設計でシンプル化を推奨。
- 最小単位:端数はFLOOR/ROUNDで調整。ミニ株/単元未満株を使える環境なら柔軟性が高い。
- スプレッド:成行一辺倒は避け、指値+日中の板流動性でコストを抑える。
11. よくある質問(FAQ)
Q1. 相場がずっと上がり続けたら?
目標パスを控えめに設定すれば、買付停止の期間が発生するだけで、致命的な問題は起きません。長期で見れば調整局面は訪れます。
Q2. 逆にずっと下がり続けたら?
上限入金額に張り付く期間が続きます。ここで焦ってパスを引き上げないこと。キャッシュプールの厚みが効いてきます。
Q3. DCAと併用できる?
可能です。コアはDCAで固定、サテライトとしてVAを追加し、落ちた時だけ強化買いの役割を持たせる設計が現実的です。
12. 実装テンプレ(擬似コード)
// 入力: P[t] 価格, g 目標増分, cap 上限入金, fee 手数料率, sell=false
V = 0; Q = 0
for t in 1..N:
T = t * g
I = T - V
I = max(min(I, cap), sell ? -10**9 : 0)
dQ = floor( (I * (1 - fee)) / P[t], 発注最小単位 )
Q = Q + dQ
V = Q * P[t]13. 月次運用チェックリスト
- 月末価格の確定(前営業日終値でも可)
- シートで
I_t、ΔQ_tを算出 - IFDで指値注文をセット(板状況に応じて分割)
- 約定結果を記録、数量と評価額を更新
- キャッシュプール残高の点検
14. まとめ
VAは「将来の評価額」を先に決め、そのラインに寄せるように入金・買付額を調整するだけのシンプルなルールです。下落相場で多く買える心理的ハードルを取り除く効用が大きく、DCAしか知らなかった投資家に強力な選択肢を与えます。まずは単一のインデックスETF+売却なし+控えめパスから小さく始め、運用プロセスに慣れてから複数資産や為替の応用に広げていきましょう。

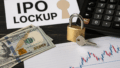
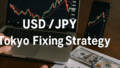
コメント