- 1. PTS価格乖離アービトラージの考え方
- 2. 価格がズレるメカニズム(初心者向けに要点だけ)
- 3. 準備:口座・ツール・板情報
- 4. よく使う専門用語(超簡潔)
- 5. 戦略A:東証引け → PTS夜間の均衡回帰狙い
- 6. 戦略B:PTS夜間 → 東証寄り付きでの裁定
- 7. 戦略C:PTS市場間(JNX vs CIX等)の瞬間乖離
- 8. 銘柄選定とエントリー基準
- 9. 具体的な発注フロー(現物版)
- 10. 信用取引を併用する場合の注意
- 11. リスクと失敗パターン
- 12. 記録テンプレ(コピペ可)
- 13. ケーススタディ(シミュレーション)
- 14. 半自動化のヒント
- 15. FAQ(初心者のつまずき)
- 16. まとめとチェックリスト
1. PTS価格乖離アービトラージの考え方
PTSは、取引所(東証)とは別に運営される電子市場です。東証がクローズした後もニュースや先物、海外市場(米国株ADRや先物指数)の値動きは続きます。情報が更新されると、PTS参加者の評価が変わり、「東証終値」からの乖離が発生します。翌朝の東証寄り付きでその乖離が修正(均衡回帰)されることが多く、ここに裁定の余地が生じます。
狙いはシンプルです。
(A)東証引け → PTS夜間で“過剰に売られた・買われた”価格差を拾い、翌朝の東証寄りでクローズ。
(B)PTS夜間 → 東証寄りで、PTSの過度な先走りを逆張り/順張りで取りに行く。
(C)PTS市場間(ジャパンネクスト vs チャイエックス等)の一時的な乖離を刈り取る。
本稿は初心者向けのため、特別なAPIやアルゴは前提としません。指値・逆指値・IFD-OCOなど標準的な注文機能と、板・歩み値・PTSの出来高が見られるツールがあれば十分です。
2. 価格がズレるメカニズム(初心者向けに要点だけ)
- 情報の非同時到達:引け後の決算、開示、レーティング、為替変動、先物の変動でフェアバリューがズレます。
- 流動性の薄さ:PTSは板が薄く、一方向の成行で価格が飛びやすい。過剰反応が出やすい。
- 参加者層の偏り:短期筋が多い時間帯は、感情的なプライスアクションが増え、歪みが拡大しやすい。
- ヘッジ不可・制限:PTSは取引ルールや利用可能な注文が証券会社ごとに異なり、効率的な裁定が働きにくい。
この「情報更新 × 薄商い × 参加者偏り × 制度差」が、翌朝の東証で均衡回帰しやすい価格差を生みます。完全ではありませんが、傾向として機能します。
3. 準備:口座・ツール・板情報
前提は「PTS取引に対応した証券口座」と「板・歩み値・PTS出来高が確認できる取引ツール」。スマホのみでも可能ですが、細かい板の変化を追うためにPC環境(複数ウィンドウ表示)が望ましいです。口座開設の一般的な流れは以下の通りです。
- 本人確認書類・マイナンバーの準備(スマホ撮影可)。
- オンライン申込(現物+信用口座の同時申請推奨)。
- 審査・ID発行後、取引ツールのセットアップ(板表示・逆指値・IFD-OCOの有効化)。
- PTS夜間の取引時間帯を確認(証券会社により開始/終了時刻が異なる)。
手数料体系は「現物」「信用」「PTS料」などで異なります。1回の期待値が小さい戦略なので、低コスト口座を選ぶほど優位性が積み上がります。
4. よく使う専門用語(超簡潔)
- PTS(私設取引システム)
- 東証の外にある電子市場。夜間も稼働。
- 乖離
- 基準価格(東証終値/気配)からのズレ。
- 気配
- 寄り付き前の売買予定価格帯。
- 板(オーダーブック)
- 価格帯ごとの買い/売り注文量。
- 歩み値
- 約定の時系列記録。勢いと連続性を観察。
- 呼値・ティック
- 価格刻み。銘柄と価格帯で異なる。
- 成行/指値/逆指値
- 成行は即約定、指値は待ち、逆指値は損切り等の自動発注に使う。
- IFD-OCO
- 新規→決済(利確/損切)の連動自動発注。
- VWAP
- 出来高加重平均価格。過熱・均衡の目安。
5. 戦略A:東証引け → PTS夜間の均衡回帰狙い
狙い:引け後にPTSで過剰反応した価格が、翌朝の東証寄りで戻る傾向を利用。
前提:出来高が一定以上・板が極端に薄すぎない・翌朝に寄り付きが見込める。
手順
- 15:00の東証引け後、決算・開示・為替の材料をチェック。
- スクリーナーで、東証終値比±2%以上のPTS乖離が出ている銘柄を抽出。
- 板と歩み値で、成行一発で飛んだだけか、継続的に買い/売りが入っているかを判定。
- 過剰と判断した側に逆張りの指値を置く(追いかけ成行は非推奨)。
- 約定後は、翌朝の東証寄り成行でクローズするか、寄り付き直後の気配で逆指値を上書き。
撤退ルール:材料が強くトレンド継続の可能性が高いと判定したら、寄り前の板気配で損切り水準を厳格化。想定外のギャップ拡大時に備え、事前に許容損失(%)を明文化しておく。
6. 戦略B:PTS夜間 → 東証寄り付きでの裁定
狙い:夜間PTSで十分な出来高を伴ったトレンドが出ている場合、寄り前気配がPTS方向に寄ることが多い。順張りで寄り付きまで引っ張る、または寄りでクローズ。
手順
- 夜間のPTSで出来高急増+連続約定を確認(歩み値の連続性)。
- 翌朝8:30以降の板・気配を監視。気配がPTS方向に寄っているかをチェック。
- 寄り成行/寄り前指値で参戦。寄り付き後1〜3分での利確ルールを事前定義。
- 失速時は逆指値で即撤退。寄り直後の板は厚薄の入れ替わりが速い。
寄り付きはギャップで滑りやすい時間帯です。指値の置き直しと発注キューの確認(変更→取消→再指値のラグ)を体で覚えましょう。
7. 戦略C:PTS市場間(JNX vs CIX等)の瞬間乖離
同一銘柄でもPTS事業者間で板厚・参加者が異なり、一時的なスプレッド差が出ます。片方で買ってもう片方で売る両建てが理論上は可能ですが、約定の非対称性や速度差で片張りが残るリスクがあります。初心者はまず単場での均衡回帰から練習し、慣れたら市場間の価格差を観察に加えるのが無難です。
8. 銘柄選定とエントリー基準
- 出来高条件:東証の平均出来高が多い主力・準主力を優先。
- 乖離閾値:東証終値比±2%(地合いで可変)。
- 板の質:厚い価格帯が連続しているか。飛び値の連続は要注意。
- 材料の質:決算・開示は内容を要約して“方向性”と“持続性”を5段階で主観評価。
- 注文設計:初回は小ロット、同値〜小幅撤退のメンタルを作る。
最初は「勝つ」より「正しく撤退できる」ことをKPIに置くと、長期的に期待値が安定します。
9. 具体的な発注フロー(現物版)
- 候補リストを5〜10銘柄作成(監視リスト登録)。
- 板・歩み値で“飛び約定”ではなく継続的な偏りかを判定。
- 東証終値からの目安乖離%を手計算(またはシート)で記録。
- 指値を置く。約定したら翌朝寄りでのクローズ方針を自動化(寄り成行・逆指値併用)。
- 寄り前の気配で利確/撤退の価格帯を更新。
- 寄り直後1〜3分でクローズし、滑りとインパクトを最小化。
10. 信用取引を併用する場合の注意
信用を使うと柔軟性は増しますが、逆日歩・金利・強制決済などのコスト/リスクが追加されます。最初は現物で手順を固め、撤退の機械化ができた段階で信用を検討しましょう。
11. リスクと失敗パターン
- 出来高不足:PTSで約定したものの、翌朝の寄りが薄く想定より滑る。
- 材料の継続性誤認:一時的と思ったニュースが翌朝も拡大解釈され、逆行。
- 板の見誤り:見せ板や瞬間的な厚板に騙される。
- 発注ミス:成行の誤用、OCOの片側未設定、数量ミス。
対策は、数量を小さく・撤退を早く・記録を詳細にの3点です。
12. 記録テンプレ(コピペ可)
日付 / 銘柄 / 東証終値 / PTS約定値 / 乖離% / 約定時刻 翌朝寄付 / クローズ値 / 利益% / スリッページ% / 理由メモ(材料・板の質・歩み値連続性) 撤退ルール遵守(Yes/No) / 改善点
13. ケーススタディ(シミュレーション)
例1:引け後に-3.5%まで売られた主力株
東証終値1,000円 → PTS約定965円(-3.5%)。材料は為替の一時的逆風。翌朝の寄り気配は980〜990円に集中。寄り成行で988円クローズ(+2.38%)。学び:過剰反応+出来高維持なら均衡回帰が起きやすい。
例2:PTSで+4%の買い上がり
東証終値2,500円 → PTS2,600円(+4%)。材料は上方修正。翌朝の板は厚く、寄り付きは2,640円。寄り直後に失速し2,620円でクローズ(+0.8%)。学び:強材料でも寄り直後の利確圧力に注意。
例3:市場間乖離の瞬間
JNXの買い板が厚くCIXが薄い場面で、同銘柄に一瞬の価格差。片側だけ約定し、もう片側が逃げて同値撤退。学び:両建ては約定非対称リスクを前提に数量縮小。
14. 半自動化のヒント
- 取引ツールのアラート(終値比±2%超、出来高急増)。
- IFD-OCOで利確/損切りを自動化、寄り成行の予約。
- スプレッド/乖離%のGoogleスプレッドシート管理(関数で色分け)。
15. FAQ(初心者のつまずき)
Q. 板が薄すぎて指値が置けません。
A. 価格帯を分割して少量ずつ。約定優先よりも撤退しやすさを重視。
Q. 寄り直後に滑ります。
A. 成行多用を避け、成行→指値の使い分けを徹底。寄り後1〜3分のルール化。
Q. ニュース評価が難しい。
A. 内容の方向性(ポジ/ネガ)と持続性(即時/短期/中期)を簡易スコア化。
16. まとめとチェックリスト
- 乖離の源泉=情報更新×薄商い×参加者偏り×制度差。
- 最優先は撤退の機械化(逆指値と時間ルール)。
- 数量は常に小さく、検証と記録を継続。
以上のプロセスを“同じやり方で繰り返す”ことで、判断のばらつきが減り、戦略全体の期待値が見える化します。まずは小さく、そして正確に。

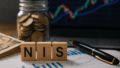

コメント