本稿は、株式の基本指標であるPER、PBR、ROE、そして配当利回りを「バラバラ」ではなく一体として評価し、初心者でも再現しやすい選定ロジックに落とし込む実践ガイドです。テーマは「割安×質×配当」の同時取り。単一指標の落とし穴(高配当の罠、低PERバリュートラップ等)を避け、総合点で勝ち筋を作ることに集中します。
1. まずは土台:4指標を正しく理解する
1-1. 配当利回り
算式は「一株当たり年間配当 ÷ 株価」。数字が高いほど投資家にとって魅力的に見えますが、減配リスクや一時的要因(特別配当、利益の前倒し等)で見かけ倒しになることがあります。重要なのは、配当の源泉が持続可能かを確認することです。
1-2. PER(株価収益率)
算式は「株価 ÷ 一株当たり利益(EPS)」。一般に低いほど割安ですが、一過性の利益でEPSが膨らむとPERは見かけ上低くなります。逆に、成長投資期はPERが高くても妥当なケースがあります。
1-3. PBR(株価純資産倍率)
算式は「株価 ÷ 一株当たり純資産(BPS)」。1倍割れは「解散価値割れ」とされますが、資産の質(含み損益、のれん、在庫)や収益力の低さがあると永遠に低PBRのまま放置されることがあります。
1-4. ROE(自己資本利益率)
算式は「当期純利益 ÷ 自己資本」。資本効率の良さを示します。ROEが高く、かつ継続性がある企業は、長期的な価値創造の可能性が高いとされます。ただし、過度なレバレッジでROEを水増ししていないかに注意。
2. 単独指標の落とし穴を避ける
高配当の罠(Yield Trap):業績悪化で株価が下がり利回りが高く見えるだけ、という典型。減配で一気に崩れます。
低PERの罠(Value Trap):構造不況業種・収益性の低さが理由で、永続的に低評価に留まるタイプ。
高ROEの罠:自己資本を削って見かけのROEを上げているだけ。資本政策で上げ下げできる指標です。
これらの罠を避けるため、複数指標を同時に満たすバランスが必要です。
3. 統合スコア「QVYスコア」の設計
本稿では、初心者でも手計算・表計算で再現しやすいQVYスコア(Quality × Value × Yield)を提案します。成長(Growth)はROEの安定性とEPS推移で内包的に評価します。
3-1. 正規化(スケーリング)の考え方
各指標を0〜100点にスケーリングし、最終スコアを加重平均します。目安は以下。
- Value点(最大40点):PERが低いほど高得点。PBRが低いほど高得点。ただし極端な低PER・低PBRはペナルティ。
- Quality点(最大40点):ROEが高いほど高得点。3年平均ROEで安定性を加点。
- Yield点(最大20点):配当利回りが高いほど高得点。ただし配当性向やFCFで持続性チェック。
例示スコア式(シンプル版):
QVY = 0.4×Value + 0.4×Quality + 0.2×Yield
3-2. 個別サブスコア例
Value(PER・PBRを各20点):
- PERサブスコア(0〜20):PER≦10なら20点、≦15なら15点、≦20なら10点、≦25なら5点、それ超は0点。PER≦5は「一過性利益の疑い」で-3点ペナ。
- PBRサブスコア(0〜20):PBR≦1.0で20点、≦1.5で15点、≦2.0で10点、≦2.5で5点、それ超は0点。PBR≦0.6は「資産の質疑い」で-3点ペナ。
Quality(ROEを中心に40点):
- ROEサブスコア(0〜25):ROE≧15%で25点、≧12%で20点、≧8%で15点、≧5%で10点、それ未満は5点。
- 安定性加点(0〜15):過去3年のROE標準偏差が低いほど高得点。EPSの赤字年がある場合は-5点。
Yield(配当で20点):
- 表面利回り(0〜12):利回り≧4%で12点、≧3%で9点、≧2%で6点、≧1%で3点。
- 持続性(0〜8):配当性向≦60%で満点。FCF黒字継続で+3点。減配履歴があれば-3点。
3-3. ペナルティ設計
以下に該当する場合、合計から減点します。
- 直近3年で2回以上の減配:-5点
- 営業CFマイナスかつ投資CFが大型先行投資:一時的要因なら-0、構造要因なら-5
- 有利子負債/自己資本比率が極端に高い:-3〜-7点
4. スクリーニング手順(初心者向けの最短ルート)
Step 1:ユニバース定義
まずは投資対象(例:国内プライム市場)を定義。売買代金が薄い小型株は初心者には非推奨。
Step 2:一次フィルター
以下の簡易条件で候補を絞ります。
- PER≦20、PBR≦2.0、ROE≧8%、配当利回り≧2%
- 時価総額≧1,000億円、平均売買代金≧3億円
Step 3:二次評価(QVYスコア)
候補に対して前章のスコアを機械的に付与し、総合70点以上を優先。
Step 4:個別チェック
直近決算の注記、セグメント、配当方針(還元性向、自己株買い)を確認。「なぜ安いのか」に必ず答えを出す。
Step 5:売買ルールに落とす
エントリー、利食い、損切り、持ち越し条件を事前に固定。恣意的裁量を極小化します。
5. 具体例(架空データで手順を完全再現)
以下は理解を深めるための架空例です。
| 銘柄 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 配当性向 | 3年ROE安定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 13 | 1.2 | 12% | 3.0% | 45% | 安定(±2%) |
| B社 | 9 | 0.8 | 5% | 4.5% | 80% | 不安定(±8%) |
| C社 | 22 | 2.1 | 16% | 1.5% | 30% | 安定(±3%) |
A社:Value点=PER(15点)+PBR(15点)=30、Quality=ROE(20点)+安定性(12点)=32、Yield=表面(9点)+持続性(7点)=16。合計78点で合格。
B社:Value=PER(20)+PBR(20)=40、Quality=ROE(10)+安定性(3)=13、Yield=表面(12)+持続性(2)=14。配当性向80%で-2点ペナ。合計65点で保留。
C社:Value=PER(5)+PBR(0)=5、Quality=ROE(25)+安定性(10)=35、Yield=表面(3)+持続性(8)=11。合計51点で除外。
このように、単独指標では見えない総合のバランスが可視化されます。
6. エントリー/エグジット規律
6-1. エントリー
QVY≧70かつ直近決算で上方修正、自己株買い実行中等のモメンタム要因が重なる場合に分割で入る(例:3回に分けて各25%・25%・50%)。
6-2. 損切り
想定外の減配・業績未達・ガイダンス下方修正は理由発生ベースで即撤退。価格ベースでは-8%で一旦カット、再評価。
6-3. 利食い
ターゲットは「配当込み年率8〜12%」の再現性。評価益+20%到達時に半分利確。残りはトレーリングストップ(過去20日安値割れ)。
6-4. 保有延長条件
ROEが維持・改善し、増配基調なら中長期で保有。反対に、ROE低下+配当性向悪化が見えたら粛々と乗り換え。
7. 権利落ち・税引き後を考慮した「手残り」利回り
表面利回りのみで判断すると、権利落ち後の値動きと税引き後の手取りを見誤ります。権利確定日前後は需給が歪みやすく、短期での逆行も珍しくありません。初心者は「長期の配当累積+増配トレンド」に焦点を絞り、単発のイベントドリブンは避けるのが無難です。
8. ポートフォリオ構築:分散と相関の管理
業種分散(例:金融・商社・通信・インフラ・製薬等)と、配当政策の多様性(累進配当・安定配当・機動的還元)を織り交ぜます。相関の低い組み合わせでボラティリティを抑え、最大ドローダウンを浅く保つことが最終リターンに効きます。
9. よくある失敗と対策
利回りだけで突撃:配当性向・FCF・減配履歴を必ず確認。最低限のデューデリはルール化。
低PBR放置株に粘着:改善カタリスト(資本効率改善、構造改革、還元方針)が見えなければ見送り。
決算未読:ハイライトだけでなく注記・セグメント収益を読む習慣を付ける。
売買ルールの後出し:事前に定め、必ず記録する。破ったら縮小・休む。
10. 再現シート(Excel/スプレッドシート)設計例
最低限の列:ティッカー、株価、EPS、BPS、配当、PER、PBR、ROE、配当性向、3年ROE標準偏差、FCF、自己資本比率、QVYスコア。条件付き書式で70点以上を緑にハイライト。ピボットで業種別平均を確認。
ワークフロー:月初に一次フィルター→四半期決算後に二次評価→ルールに従い発注。毎月「除外・保留・採用」を棚卸。
11. Q&A(初心者が詰まりやすいポイント)
Q. PERが高いのに買って良いことはある?
A. ROEが高く、持続的な成長投資が回っている場合はあり得ます。高PER=即NGではなく、質と成長の裏付けを確認。
Q. 高配当ETFと個別株、どちらが良い?
A. 個別は当たり外れが大きい一方、ETFは分散利点。初心者はETF+上澄み個別の併用が実務的です。
Q. いつ売るべき?
A. ルールで決めるのが正解。理由発生ベース(減配・ガイダンス下方)か、価格ベース(-8%・20日安値割れ)。
12. まとめ:再現性のある「勝ち筋」を作る
本稿の肝は、単一指標に依存せず、PER・PBR・ROE・配当利回りを統合して総合点で選ぶこと。仕組み化し、毎月同じ手順で繰り返すことでぶれない投資行動が身に付きます。割安×質×配当は、初心者でも始めやすく、かつ中長期で効きやすい王道です。

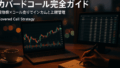
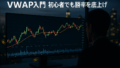
コメント