本稿では、暗号資産デリバティブ取引における「清算価格(Liquidation Price)」を、実務で使える数式と
手順、ケーススタディで徹底的に解剖します。清算価格は、強制ロスカットが発動する価格帯を示すもので、
トレードの存続を左右する最重要の閾値です。清算のメカニズムを理解し、あらかじめ計算しておくことは、損失の下振れを
制御し、リスクリワードを改善し、資金効率を高めるうえで不可欠です。この記事は初級者が読んでも実装可能なレベルまで
噛み砕いて説明します。
この記事の狙い
清算価格の定義、算出式、取引所ごとの差、クロス(全額証拠金)と分離(アイソレーテッド)、USDT建て無期限の線形契約、
逆数(インバース)契約の考え方、メンテナンス証拠金とレバレッジ、保険基金とADL、部分清算、手数料・資金調達の取り扱い、
実装用のExcel式、誤差要因、運用チェックリストまで、実務で役に立つ内容だけをまとめます。
清算価格とは何か
清算価格とは、口座(またはポジション)の証拠金残高がメンテナンス証拠金(必要維持証拠金)に達したときに、
取引所がポジションを強制的にクローズする境界価格のことです。清算は価格スパイク時の連鎖や、過度なレバレッジ運用の
歯止めとして機能しますが、トレーダーにとってはゲームオーバーの価格でもあります。
線形(USDT建て)無期限の基本式
まずは最も実務で使う機会が多い、USDT建ての線形無期限契約(いわゆるUSDT-M Perpetual)の分離マージンを前提に、
代表的な近似式を提示します。取引所により細部は異なりますが、考え方を固めるには十分です。
記号
- E:建値(エントリー価格, USDT)
- P:評価価格(清算価格を求める対象, USDT)
- Q:ポジション数量(ベース通貨建て, 例:BTC数量)。ロングは正、ショートは負とします。
- M:ポジションに割り当てた分離証拠金(USDT)
- mmr:メンテナンス証拠金率(Maintenance Margin Rate)
- Fee:清算に関連して差し引かれる手数料等の近似(ゼロ近似も可)
未実現損益と証拠金残高
USDT建て線形契約では、ロングの未実現損益は UPnL = Q × (P - E) で表せます(Q > 0)。
ショートなら UPnL = |Q| × (E - P) です。分離証拠金において、清算判定は概ね
M + UPnL ≤ |Q| × P × mmr + Fee という関係で近似できます。
ロングの清算価格(近似)
ロング(Q > 0)の場合、上式をPについて解くと、
Pliq,long ≒ (Q × E + Fee - M) ÷ (Q × (1 - mmr))
Feeを0と近似する実務もあります。mmrはノッチごと(ポジション規模のティア)に上がるため、大きいサイズほど
清算価格は建値側へ近づきます。
ショートの清算価格(近似)
ショート(Q < 0)の場合、|Q| = -Q として整理すると、
Pliq,short ≒ (|Q| × E + M - Fee) ÷ (|Q| × (1 + mmr))
こちらもFeeを0と置けばハンド計算が容易です。ショートは価格上昇側に清算価格が位置します。
ケーススタディ:数値で腹落ちさせる
ケース1:ロング0.5BTC、分離、USDT建て
前提:E=60,000、Q=0.5、M=5,000、mmr=0.005、Fee=0とします。式に代入すると、
Pliq ≒ (0.5×60,000 - 5,000) ÷ (0.5×(1 - 0.005)) = (30,000 - 5,000) ÷ 0.4975 ≒ 50,251.26
清算水準は約50,251USDTです。もしmmrが0.01に上がれば、分母が小さくなるため清算価格はさらに建値側へ寄ります。
ケース2:ショート1BTC、分離、USDT建て
前提:E=60,000、|Q|=1、M=4,000、mmr=0.005、Fee=0。
Pliq ≒ (1×60,000 + 4,000) ÷ (1×(1 + 0.005)) = 64,000 ÷ 1.005 ≒ 63,681.59
建値より上の63,682付近で清算が走るイメージです。
レバレッジと清算の関係
レバレッジは L = |Q| × E ÷ M と近似できます。Mを小さくすればLは上がりますが、
同時に清算価格は建値へ接近します。つまり「高レバ=清算余裕の縮小」です。
清算余裕(建値と清算価格の距離)を一定以上確保するために、Mとサイズを共同で最適化する必要があります。
クロス(全額証拠金)と分離の違い
クロスでは口座残高全体が損益吸収に使われるため、分離より清算耐性が高くなりがちです。ただし、他ポジションの
損失でも共倒れになるリスクがあるため、ポジション間の相関・偏り管理が前提になります。分離は、ポジション単位で
損益を切り分けてリスクを封じ込めますが、同額の初期証拠金で比べると清算までの余裕はクロスより狭くなります。
メンテナンス証拠金率(mmr)ティアと部分清算
多くの取引所はポジション規模に応じてmmrを段階的に引き上げます。一定水準に達すると「部分清算」でサイズを
自動的に落とし、必要維持証拠金を減らして延命させます。部分清算は便利ですが、激しい変動では一度に複数段が
飛ぶことや、板流動性が薄いとスリッページが拡大することに留意します。
ADL(自動デレバレッジ)と保険基金
清算執行でも市場で約定できず破綻価格を割り込むと、保険基金が穴埋めします。それでも足りない場合はADLで
反対側のレバレッジポジションが自動的に縮小されます。ADLの順番は、一般に利益・レバレッジの高い順で
優先されます。保険基金が厚い銘柄ほどADL発動の頻度は下がる傾向ですが、ゼロとは言えません。
逆数(インバース)契約の考え方
インバース契約(例:BTC建てで、損益・証拠金がBTC)の場合、未実現損益は UPnL(BTC) = Q × (1/E - 1/P) の
形になり、証拠金・維持証拠金もBTC建てで評価されます。清算条件は M(BTC) + UPnL(BTC) ≤ mmr × |Q| ÷ P のような
形で現れます(各所の仕様で係数や定義が異なるため厳密式は取引所ドキュメントに従います)。実務では
「建値から遠いほどBTC建て残高の価値が目減り/増加する」という逆数効果を理解し、USDT建てより清算余裕の変動が
直感とズレやすい点に注意します。
よくある誤解と落とし穴
- 資金調達(Funding)は清算価格そのものを直接ずらすのか? ― 多くの設計では、Fundingは時間経過で残高に加減算され、
間接的に清算余裕を変えます。式そのものに投入するより、残高・証拠金の変化として扱うのが実務的です。 - 手数料は無視してよいのか? ― 高頻度の部分清算や大きなスリッページが見込まれる地合いでは影響が表面化します。
バックテストや電卓ではFee=0近似でも、実戦ではバッファを加えておくべきです。 - mmrは固定か? ― 規模ティアで上がります。サイズを増やすほど清算は近づきます。
段階境界を跨ぐ発注で一気に清算余裕が縮むことがあります。 - クロスなら安全か? ― 口座全体のドローダウンで全滅することがあり、相関の高いポジションを多数抱えると危険です。
Excelで清算価格を即計算する
USDT建て線形・分離のロング近似式をExcelで実装する例です(Fee=0近似)。
セル定義:
E2=建値, Q2=数量, M2=分離証拠金, mmr2=維持率
ロング清算: = (Q2*E2 - M2) / (Q2*(1 - mmr2))
ショート清算: = ((ABS(Q2)*E2 + M2) / (ABS(Q2)*(1 + mmr2)))
mmrは取引所のティアテーブルからVLOOKUPやXLOOKUPで引き込みます。サイズ変更時に自動でmmrが切り替わるよう
設計しておくと実戦向きです。
取引所差分をどう吸収するか
建値の定義(マーク価格 vs ラスト)、清算トリガー、破綻価格、部分清算の刻み、mmrテーブル、保険基金の運用など、
設計差分は必ずあります。実務では「保守的に見積もる」「バッファを確保する」「小さく試す」で
吸収します。最終的な真値は、約款・ヘルプセンター・実売買ログで検証してください。
ポジション設計の手順(実務フロー)
- 想定最大ドローダウン(価格変動幅)を先に決めます。
- 清算余裕(建値から清算までの距離)をそのドローダウンより広く確保する目標を置きます。
- サイズQと証拠金Mの組み合わせを探索し、LとPliqが目標条件を満たす点を選びます。
- mmrティアを跨がない発注サイズに分割し、部分清算発動でも致命傷にならない構成にします。
- 資金調達・手数料の実績を週次で棚卸し、バッファを再設定します。
チェックリスト
- 清算トリガーはマーク価格か?インデックス価格か?
- mmrティアの境界はどこか?サイズ変更で変わらないか?
- 部分清算の刻みと上限回数は?
- 保険基金残高とADL発動条件は?
- クロス時に他ポジションの損益相関はどうか?
- 手数料とFundingの実績は?清算バッファをどれだけ積むか?
ケーススタディ:実戦シナリオ3連発
シナリオA:ニュースショックで5%急落
ロング0.5BTC・E=60,000・M=5,000・mmr=0.005で、価格が57,000→54,000へストレートに落ちました。
清算余裕は約50,251まであるので継続可能ですが、部分清算が刻んで発動する可能性があります。
追証を入れるより、サイズを落としてmmrティアを下げる方が生存率は上がります。
シナリオB:急騰・逆走でショートが踏まれる
ショート1BTC・E=60,000・M=4,000・mmr=0.005で、価格が62,000→65,000へ上昇。
清算水準は約63,682なので、65,000到達時にはすでに清算済みか、部分清算でサイズが縮んでいます。
あらかじめ建値からの距離で逆指値の買い戻し(損切り)を置く方が合理的です。
シナリオC:ボラ拡大・スプレッド拡大・板薄
清算執行はマーク価格でトリガーされても、実際の約定は板流動性に依存します。板が薄い時間帯に清算されると、
破綻価格を割り込んで保険基金・ADLに波及することがあります。ボラ拡大時はサイズ圧縮とレバ低下で臨みます。
リスクリワードの設計
清算価格はあくまで「最後の防波堤」です。実務では、清算の何%手前で損切りするかを先に決め、その水準での損失額が
口座全体の許容リスクに収まるよう、サイズと証拠金を調整します。例えば「清算手前20%に逆指値」「日次許容損失1%」
といったガードレールを先に設定します。
まとめ
清算価格は、レバレッジ運用の実質的な生命線です。数式で腹落ちさせ、Excelで即座に検証し、バッファと手順を
明文化することで、偶発的な全損を大幅に減らせます。取引所固有の仕様差は保守的な仮定で吸収し、小さく試してから
サイズを増やす。この規律が最終的な資産曲線を守ります。
付録:実務リファレンス(テンプレート集)
1. 清算余裕(Distance)
Distance = |E - Pliq| / E と定義し、最低でも想定ボラの1.5~2倍を確保する目標を置きます。
2. バッファ設計
FeeとFundingの月次実績平均を算出し、清算余裕に対して2~5%分の追加マージンを上乗せします。
3. mmrティアの擬似テーブル例
ノッチ1:mmr=0.50%(~100k USDT)
ノッチ2:mmr=0.65%(~500k USDT)
ノッチ3:mmr=0.80%(~1M USDT)
…(取引所仕様に依存。実運用では必ず現行表を確認)
4. 発注分割の型
サイズQを3~5本に分け、ティアの境界を跨がないように調整します。清算ラインの集中を避けるため、
エントリー価格にも段差を付けます。
5. 運用ルーチン
- 毎朝:Fundingと手数料の推移を集計、バッファ再計算。
- 毎週:mmr境界・保険基金推移の確認。
- イベント前:サイズ半減、逆指値の再設定、清算距離の再測定。
Q&A:現場でよくある質問
Q1:清算はマーク価格基準ですか?
多くの取引所で清算トリガーはマーク価格基準です。マーク価格はインデックスと資金調達を加味して滑らかに更新され、
極端なラスト取引の影響を抑える目的があります。
Q2:資金調達がマイナスのときは?
残高から時間とともに差し引かれていくため、クロスでは口座全体の清算余裕が徐々に目減りします。
長期保有前提のポジションは分離で管理し、定期的に資金を再配分します。
Q3:異常時の手動対応は?
清算水準の20~30%手前に逆指値を置き、同時に手動クローズ用のホットキーやAPIを準備します。
板が崩れた場合は指値ではなく成行・IOCで逃げる方が生存率が高いことが多いです。
Q4:どの程度のレバレッジが適正?
想定ボラ、口座サイズ、日次許容損失から逆算します。清算余裕が想定ボラの2倍未満なら、基本的にレバレッジが高すぎます。
Q5:インバースは避けるべき?
避ける必要はありませんが、評価がベース通貨建てになるため、USDT建てより清算余裕の把握が難しいです。
ヘッジやサイズ調整が素早くできる体制で扱います。

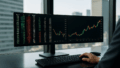

コメント