インパーマネントロス(Impermanent Loss, IL)は、AMM型DEXに流動性提供(LP)を行う投資家が直面する最大のボトルネックです。本稿では、ILの発生メカニズムを数式と数量例で解きほぐし、永続先物(パーペチュアル)やオプションを用いた動的ヘッジで、収益源を「取引手数料+流動性インセンティブ+ファンディング差益」に再構成する実務フレームを提示します。読後に、再現可能な手順と指標チェックリストをそのまま運用に落とし込めるように設計しています。
1. なぜILは「損失」なのか:相対価値で測る
ILは「プールに入れずに保有していた場合(HODL)」と比較した相対損益です。二資産50:50の定積曲線型AMM(x·y=k)で、価格比がp→p′に変化するときの理論ILは、
IL(p→p′) = 2·√(p′/p) / (1 + p′/p) − 1
で近似されます。例えばETH:USDCでETH価格が1,800→2,700(+50%)になると、理論ILは約−2.02%です。価格が大きく動くほど、プールは高値でETHを売り安値でETHを買い戻すため、HODLに劣後しやすくなります。
2. 実測で理解する:具体例(手数料年率を上回れるか)
前提:初期にETH 10枚+USDC 18,000を50:50で提供、AMMの取引手数料は0.3%、日次回転率(プール出来高/TVL)は0.8%、流動性マイニングのトークン報酬が年率3%相当とします。ETHは30日で+40%変動(1,800→2,520)。
このとき30日間の手数料収入の期待値は概算で
年率収益 ≈ 0.3% × 回転率0.8 × 365 ≈ 0.876%/年、
30日換算で約0.0728%です。インセンティブ年率3%は30日で約0.246%。一方、理論ILは
IL ≈ 2·√1.4 / (1 + 1.4) − 1 ≈ −1.41%。
つまり、放置すると手数料+インセンティブの合計約0.319%ではILの−1.41%を埋めきれません。ここでヘッジが必要になります。
3. 収益分解:LPのP/Lを三項に分ける
LPの損益は、(A)取引手数料とインセンティブ、(B)価格変動に伴うIL、(C)ヘッジポジションの損益に分解できます。狙いは、(B)の変動リスクを(C)で抑え、(A)を確実に積み上げる「キャリー化」です。市場局面次第では、永続先物のファンディング・プレミアムや先物カーブのベーシスも収益源に加わります。
4. 動的ヘッジの骨格:δ(デルタ)とβ(ベータ)
二資産プールの時価ウェイトは価格変化とともに滑ります。定積曲線では価格上昇で高騰資産ウェイトが低下するため、LP全体の実効デルタはHODLより控えめです。簡便近似として、ETH:USDC 50:50のプールの初期デルタは約0.5、価格が2倍になるとデルタはさらに低下します。従って、ヘッジでは「ETHロングのデルタをどれだけ打ち消すか」を都度再計算し、永続先物のショート枚数を調整します。
実務では、必要ショート = プールのETHエクスポージャ(枚) × ヘッジ比率h と置き、hを0.6〜0.9の範囲で動かします。上振れ局面ではhを高め、横ばい〜低ボラ局面ではhを下げます。これをβ調整と呼び、ILを抑制しつつ、手数料やインセンティブの取りこぼしを最小化します。
5. 手順:CEXのパーペチュアルでヘッジし、DEXでLPする
① プール選定:出来高/TVLが高いプールを選びます。日次回転率が0.5%以上あると手数料寄与が見込めます。インセンティブは将来の減衰(エミッション低下)も織り込んで保守的に評価します。
② エントリー:LP投入と同時に、CEXのETHUSDパーペチュアルでショートを建てます。必要証拠金は分散させ、強制ロスカット幅を広く取るためレバレッジは2〜3倍程度に抑えます。
③ リバランス:価格が±5〜10%動いたら、LP側の実効デルタを再推計し、ショート枚数を微調整します。板薄時間や発注集中時間帯のスリッページを避けるため、TWAPで分割実行するのが安全です。
④ 資金繰り:ファンディングレートがプラス(ショート受取)ならヘッジ側がキャッシュフローを生みます。マイナスのときはコストになるため、回転率やインセンティブ見込みと照合し、hを下げてコスト最適化を行います。
6. ケーススタディ:30日間のP/Lシミュレーション
条件:前述の初期条件に加え、パーペチュアルの平均ファンディング年率が+4%(ショートが受取)とします。ヘッジ比率hは0.8で固定、±10%の価格変化ごとにTWAPで再調整。
結果(概算):(A) 手数料+インセンティブ = +0.319%(30日)、(B) IL = −1.41%、(C) ヘッジ損益 = +1.23%(価格上昇でショートは損ですが、デルタ控えめのLPに合わせた枚数で損失は縮小、さらにファンディング受取が+0.33%寄与)。合算で+0.139%。放置ではマイナスだったLPが、ヘッジによりプラスへ反転します。
7. 実装ディテール:指標と計測
・回転率:出来高/TVL。過去30〜90日の中央値を使い、スパイクに惑わされない。
・有効スプレッド:AMM手数料率とアクティブLP帯域(集中流動性の場合)の関数。狭帯域ほど回転率は上がるが再配置コストとガス代が増える。
・ヘッジ誤差:再調整間隔が長いほど追随誤差が増える。価格加速度(二階微分)をトリガに条件付きで再調整するロジックが有効。
・ファンディング:時間加重平均(8時間や4時間の複利換算)。ショート受取の市場ではhを引き上げる余地がある。
・清算耐性:証拠金口座のフリーコラテラル比率をモニターし、急騰時でも追証が不要な水準に。
8. オプションを使う代替案:ILの上下をキャップする
パーペチュアルの代わりに、ETHのコール・プットを組み合わせ、LPポジションの上下をキャップする手法もあります。例:上昇局面のILを抑えるためにOTMコール・スプレッドを買い、急落局面にはOTMプットを少量買う。ガンマが効くため急変動に強い一方、プレミアムの持ち出しが発生するため、手数料やインセンティブと相殺できるかを前もって見積もる必要があります。
9. リスク管理:何が壊れうるか
相関崩壊やペッグ外れ(例:ステーブルコイン側のデペグ)は、デルタ・ヘッジでは抑制できません。ブリッジ障害やオラクル異常で価格が一時乖離する場合も想定するべきです。さらに、CEX側の約定・API障害、資金調達率の急騰、上場先の保全リスク(カストディやKYC/AML要件)も加味し、証拠金とLP元本は分散管理します。
10. 手順テンプレート:日々の運用オペレーション
取引前チェック(例):(1) プール回転率中央値、(2) 直近ファンディング年率の方向と分散、(3) 予定ヘッジ比率h、(4) 証拠金フリー比率、(5) ガス代と再配置コスト想定。実行後は、価格±5〜10%またはボラティリティ急変で再調整。週次でP/L分解を更新し、(A)〜(C)の寄与がプラスになる設計を維持します。
11. まとめ:LPを「キャリー戦略」に変換する
インパーマネントロスは「避けるもの」ではなく「設計して抑え込むもの」です。LPの実効デルタを見積もり、パーペチュアルやオプションで動的に中和することで、手数料・インセンティブ・ファンディングのキャリーを安定的に刈り取るポジションへ変換できます。重要なのは、過度なレバレッジを避け、リバランス頻度とコストの最適点を探ることです。これにより、AMM流動性提供は単なるパッシブ運用から、再現性の高い収益エンジンへと進化します。

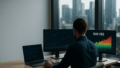

コメント