本稿では、分散型取引所(DEX)における流動性提供(LP)の実務を、償却されがちな「手数料収入」「価格変動に伴う損益(インパーマネントロス:IL)」「ヘッジコスト」「リバランス設計」の4軸で統合的に捉え、再現可能な手順まで落とし込みます。裁量ではなくルールを定義し、コストを数式で管理することが目的です。
前提:AMMとLPトークンのキャッシュフロー
定数積AMM(x・y=k)でプールに資産A/Bを50:50で供給すると、LPはプールシェアに応じた手数料(例:0.05%〜0.3%/トレード)と引き換えに、価格変動に伴う在庫リスク(デルタ)と価格の二乗効果(ガンマ)を負います。LPトークンはこの持分証券であり、焼却(バーン)時に基準価額に相当する引出額が決まります。
インパーマネントロス(IL)の定義と直感
価格比率を p=Pnew/Pstart とすると、50:50プールのILは IL(p)=
2·√p/(1+p) − 1 で近似できます。p≠1のとき、HODL(現物ホールド)に対してAMM在庫再配分が生む相対劣後分がILです。上昇でも下落でも発生しますが、手数料収入がILを上回れば総合では黒字です。
数値例:ETH/USDC 50:50
開始時ETH=2,000USDC、プール手数料0.3%、日次回転率(プールの出来高/TVL)を20%と仮定します。ETHが+25%(p=1.25)動いた場合、
IL ≈ 2·√1.25/(1+1.25) − 1 ≈ 1.1180/2.25 − 1 ≈ -2.42%(概算)
一方、手数料APRはおおむね APR_fee ≈ 0.3% × 回転率 × 365。回転率20%なら ≈ 0.003×0.20×365 ≈ 21.9%/年。25%の価格変動期間が10日間で起きたと仮定すると、10日分の手数料収入は ≈ 21.9% × (10/365) ≈ 0.60%。この期間に限定すれば、手数料0.60% − IL2.42% ≈ -1.82% と赤字。つまり出来高/手数料水準と価格ボラのバランスが収益性を決めます。
ブレークイーブンの考え方
所与の期間手数料収入(Rfee)に対し、許容価格比 p の範囲を解くのが実務です。
条件: Rfee + IL(p) ≥ 0。
たとえば10日でRfee=0.6%なら、|IL(p)| ≤ 0.6% となるp範囲へ価格が収まる必要がある。これを表で可視化すれば、「このボラならLPをやる/やらない」の判断が機械的にできます。
集中流動性(Uniswap v3系)のレンジ設計
集中流動性では、指定した価格レンジ内でのみ在庫が有効になります。狭いレンジほど手数料集中でAPRが上がる一方、レンジアウト時に手数料が止まり、方向片側の在庫に偏ります。実務は ①基準価格、②想定ボラ、③再入場ルール を事前に数式化します。
- ATR(14)や実現ボラから±nσ帯でレンジ幅を決定
- 価格が外れたらクールダウン時間tを置いて再設定(レンジ追随の過剰トランザクションを抑制)
- 再設定時のガスコスト≦想定追加手数料の現在価値 を満たすときだけ実行
デルタ・ヘッジ:パーペチュアルの活用
LPは実質的に両資産の在庫リスク(デルタ)を持ちます。方向リスクを薄めたいときは、CEXのパーペチュアルでデルタオフセットを取るのが定石です。
- 現在のLP在庫量(A,B)から基軸(例:USD)に対するデルタを算出
- 同額逆方向のパーペチュアル建玉を構築(例:ETH現物ロング気味ならETH-PERPをショート)
- 建玉調整はΔ閾値(例:|Δ|がTVLの1%超)でのみ実行し、過剰リバランスを防ぐ
留意点は資金調達金利(Funding)。ファンディングがプラス側で受取れればヘッジがむしろ収益に寄与、支払い側ならコスト化します。これを含めたネット収益 R = 手数料 − |IL| − Funding ± スリッページ − ガス を常時計測。
Excelでの再現レシピ
下記セルに入力すれば、誰でも同じ判定が可能です。
- 入力:p(価格比=現在価格/開始価格)、fee(手数料率/トレード)、turnover(日次回転率)
- IL式(B2にp):
=2*SQRT(B2)/(1+B2)-1 - 手数料APR(C2=fee, D2=turnover):
=C2*D2*365 - 期間t日の手数料(E2=t日数):
=(C2*D2*365)*(E2/365) - 損益判定:
=IF(E3+F3>=0,"OK","NG")(E3=期間手数料, F3=IL)
実務フロー(運用ルール)
- 閾値定義:Δ閾値(例:1%TVL)、ガス上限(例:$50/回)、再設定クールダウン(例:6時間)
- 執行:価格がΔ閾値超→パーペチュアルで部分ヘッジ/解除
- レンジ管理:価格がバンド外→クールダウン後にレンジ再設定
- 停止条件:出来高低下でAPR期待値がIL閾値を下回る場合は撤退
よくある失敗と対処
- 出来高を見ずにTVLだけで判断:回転率×手数料がAPRの源泉。履歴データで季節性を確認。
- 資金調達金利の反転:Fundingは日内で変化。固定間隔ではなく閾値で調整。
- ガスコスト無視:再設定多発は致命傷。1回の設定で回収すべき最低手数料を明文化。
ケーススタディ:ETH/USDC 集中流動性+部分ヘッジ
初期TVL$50,000。レンジ±10%(ATR準拠)、Δ閾値=1%、ガス上限=$40。日次回転率15%、手数料0.3%。10日運用で価格+18%(p=1.18)。
IL ≈ 2·√1.18/(1+1.18)-1 ≈ -1.64%。期間手数料 ≈ 0.003×0.15×10 ≈ 0.45%。Funding受取年率2%相当→期間+0.055%。再設定2回でガス$60(超過$20は逸失利益扱い)。
概算:0.45% + 0.055% − 1.64% − 0.12%(ガス換算) ≈ -1.26%。
学び:このボラと出来高なら、レンジを広げるか、ヘッジ比率を高めてΔを抑える必要がある。
実装の最小セット
- データ:価格、出来高、プール手数料、Funding、ガス(チェーン別)
- 判定器:IL関数、期間手数料推定、Δ閾値、ガス上限
- 執行:レンジ再設定とヘッジ調整の自動化(閾値トリガ)
まとめ
LPの勝ち筋は「手数料の源泉(出来高×レート)が十分に太い市場で、価格ボラとガス・Fundingを閾値制御する」ことに尽きます。感覚ではなく、事前に数式で可否を判定し、超えたら実行・超えなければ待機。これを守るだけで、LPの期待収益分布は大きく改善します。

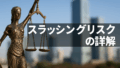

コメント