レンディングは「需給が作る金利」を投資家が収益化するビジネスです。誰かが資金を借りたいからこそ金利が発生し、私たちはその対価を受け取ります。本稿では、金利の正体を構造から解き、清算を避けて利回りを積み上げるための実務を、初心者でも運用できる水準まで具体化します。
1. 金利の源泉を分解する
金利は以下の需要から生まれます。
- レバレッジ需要:現物・先物・パーペチュアルでポジションを拡大したい参加者。
- マーケットメイク/裁定:価格乖離やファンディングレートを取りに行く短期資金需要。
- 資金決済/在庫ファイナンス:取引所やOTCの在庫・決済用の短期資金。
DeFiの代表的モデル(Compound/Aave型)では、利用率 u = 需要/供給 が上がるほど借入金利 r_borrow が上昇し、供給側の金利 r_supply は r_supply ≈ r_borrow × (1 - reserve_factor) × u で決まります。CeFiは簿外の審査・社内ポリシーで決まりますが、本質は同じく需給です。
2. APRとAPY:同じ土俵で比較する
表示が年率単利(APR)か複利(APY)かで見かけが変わります。比較は必ず同じ尺度で行います。
APY = (1 + APR / n) ^ n - 1 (n = 複利回数/年)
近似:APY ≈ e^{APR} - 1(連続複利)
例:APR 10% を日次複利(n=365)で回すと APY ≈ 10.52% です。
3. リスクマップ:損失源と回避策
- 清算リスク:担保価格下落でLTVがしきい値を超えると清算。対策は低LTV・価格バッファ・通知・自動返済枠。
- スマートコントラクト/オラクル:バグ・価格参照の歪み。対策は監査履歴・バグバウンティ・分散オラクル。
- カストディ/再質権(CeFi):貸出先の信用・再貸出の連鎖。対策は情報開示・資産隔離・過度集中の禁止。
- ステーブルコイン・ペッグ:担保や準備の信用。対策は複数銘柄のバスケット運用と上限設定。
- ガバナンス/権限:管理鍵の権限移譲・投票攻撃。対策はタイムロック・マルチシグ・権限の最小化。
- レイヤー/ブリッジ:L2やブリッジのセキュリティ差。対策はチェーン分散と上限。
4. 清算価格とLTVを一発で把握する
担保価値を C(USD)、負債を D、清算しきい値LTVを L* とすると、許容下落率は:
許容下落率 = 1 - D / (C × L*)
具体例:BTC 1枚を$60,000で担保、30%借入(D=$18,000)、清算L* = 60% の場合、許容下落率は 1 - 18000 / (60000 × 0.6) = 1 - 0.5 = 50%。つまりBTCが$30,000まで下がっても清算されません。安全域は「目標LTV(例:25〜35%)」「追加担保/部分返済のトリガー」を事前に決めて運用します。
5. 手数料・ガスと最小有利差
移動コスト(ガス/手数料の総額)を F、投下元本を P、運用日数を d とすると、必要な金利差(年率換算)は:
必要差APR ≈ (F / P) × (365 / d)
例:往復$20のコストで$10,000を30日運用なら、(20/10000)×(365/30) ≈ 2.43%。差がこれ以下なら動かない方が合理的です。
6. 実践レイアウト:3つのモデル
6-1. ステーブルコイン単体で安定運用
USDC/USDT等を分散して供給する最もシンプルなモデルです。目標は「分散」「稼働率」「回収容易性」。チェーン/プロトコル/銘柄の三層で上限を設け、どれか一つが障害でも全体に波及しない構造を作ります。
6-2. 現物ロングの利回り化(ノンレバ)
BTC/ETHの長期保有者が、担保にして少額を借り、別口座で安全資産や短期運用へ回す方法です。ターゲットLTV 25〜35%に限定し、急落時は即時返済できる現金・ステーブルの待機枠を確保します。
6-3. 金利アービトラージの設計
借入金利と別市場の収益機会(例:別プラットフォームの供給金利、先物/パーペチュアルの正のファンディング)に差があるときに狙います。
- 借入:USDTを年率8%で借りる。
- 裁定:別プロトコルで年率12%で貸す(あるいは正のファンディングが見込めるデルタニュートラル構築)。
- ネット:差は+4%から手数料・スリッページ・資金調達の変動分を控除。上の「必要差APR」を超えるかで意思決定。
変動要因が多いため、差が縮んだときの撤退条件(例:差が2%未満になったら畳む)を先に決めてから入ります。
7. 数式で納得する利回りとリスク
7-1. ネット利回り
ネットAPY ≈ (1 + r_supply)^{t} - (1 + r_borrow)^{t} - コスト
(t = 運用年数、コスト=ガス/手数料/価格乖離等を年率化)
7-2. 清算バッファ
バッファ(%) = 現在価格下落率で清算に達するまでの余地 = 100 × (1 - D / (C × L*))
8. プラットフォーム選定フレーム
以下をスコア化して相対評価します。
- 透明性:オンチェーン残高、監査、新規機能の権限設計。
- 流動性:総供給額、借入残、利用率の安定性。
- 価格参照:オラクルの分散性、更新頻度、異常時のセーフモード。
- 回収性:ロック期間、引出しキュー、停止条件。
- 運用コスト:チェーン手数料、入出金の摩擦。
9. 配分と上限:壊れないポートフォリオ
一例として、40/40/20の分散を提示します。
- 40%:ステーブルコイン供給(短期)
- 40%:担保化した現物ロングの利回り化(低LTV)
- 20%:金利差/裁定の機会枠(常に現金化しやすい設計)
チェーン上限(例:1チェーンあたり最大35%)、プロトコル上限(最大20%)、単一銘柄上限(最大25%)の三重上限で破綻耐性を高めます。
10. デイリー/週次の運用チェックリスト
- 清算レシオと価格バッファの確認(しきい値から+15%の安全域を維持)。
- 利用率・金利カーブの変化(急騰時は早めの縮小)。
- 入出金キュー/停止アラートの有無。
- ガバナンス提案・権限変更の監視。
- ポジション台帳の更新(原資・評価・損益・コストの記録)。
11. よくある失敗と回避法
- 高LTVでの長期放置 → 低LTV+自動通知+返済余力で対応。
- 単一ステーブルの過集中 → 銘柄分散・デペグ時の返済計画。
- 利回りだけで選定 → 回収性・停止条件・オラクルを併せて評価。
- 差が縮んだ裁定の握り潰し → 事前に撤退条件を明文化。
12. ミニ演習:数字で意思決定
状況:$10,000を30日。候補AはAPR 7%(日次複利、出入金$12)。候補BはAPR 10%(日次複利、出入金$20)。どちら?
- AのAPY ≈ 7.25%、30日利回り ≈ 7.25% × 30/365 = 0.595%。税・手数料前利益 ≈ $59.5。コスト$12。ネット ≈ $47.5。
- BのAPY ≈ 10.52%、30日利回り ≈ 0.865%。利益 ≈ $86.5。コスト$20。ネット ≈ $66.5。
差額 ≈ $19。上式の「必要差APR」でも検証し、Bを選ぶ合理性があります。
13. 税・規制への一般的メモ
利息やインセンティブの取扱いは居住地の制度や利用サービスの規約に依存します。帳簿化と証憑の保存、取引履歴のエクスポート体制を必ず整えてください。
14. 実装タスクリスト
- 目的を定義(安定運用/利回り化/裁定)。
- 配分と上限(チェーン/プロトコル/銘柄)。
- しきい値(目標LTV、撤退条件、最小有利差)。
- チェック体制(通知・台帳・二重承認)。
- テスト金額でドライラン→本投入。
「よく分かる」ではなく「壊れない」。この姿勢でレンディングを設計すれば、変動相場でもぶれない収益エンジンになります。


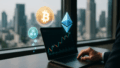
コメント