本稿では、暗号資産における「ベーシストレード(Basis Trade)」を、実務の順番で徹底解説します。ベーシスは「先物価格 − 現物価格」で定義され、先物に固有のキャリー(資金調達コスト、保管・保険相当、需給の歪み)を反映します。狙いは価格そのものではなく、価格差の収斂(または持続)です。裁定色の強い手法ですが、ボラティリティの高い暗号資産では設計と運用次第で安定した期待値を狙えます。
ベーシスの型:期限付き先物とパーペチュアル
暗号資産の先物は大きく「期限付き(Quarterly/Monthlyなど)」と「パーペチュアル(無期限)」に分かれます。期限付き先物のベーシスは満期に向けて理論的に現物へ収斂する傾向があり、キャリー相場(コンタンゴ)では「現物買い+先物売り」により年率換算の利回り(年換算ベーシス)をロックしやすいのが特徴です。パーペチュアルは代わりにファンディングレートが付与され、ロング/ショートのどちらかが定期的に相手へ金利を支払います。従って、ペルプ(perp)は「ベーシス=直近のインパクト価格差+ファンディングの期待値」で捉えます。
基本式と指標
- ベーシス(期限付き):
B = F - S(F=先物、S=現物)。満期まで日数をD日とすれば、年換算利回りはAPY ≈ (F - S) / S × (365 / D)。 - パーペチュアルの実効キャリー:
APY_perp ≈ 年間期待ファンディング − 借入/機会コスト。短期ではファンディングの変動幅・回数(通常8時間ごと等)を加味。 - ロールダウン:期限付き先物を保有し、時間経過でベーシスが自然に薄まる収益。期近→期先のロールも考慮。
- 取引コスト:手数料、スプレッド、滑り、資金移動コスト、借入金利、為替コスト(円転など)。
戦略アーキテクチャ:現物買い+先物売り(キャリー)
代表的な構成は「現物を買い、同数量の先物を売る」デルタ中立です。先物がプレミアム(コンタンゴ)のとき、満期に向けた収斂または金利相当分を狙います。構築のポイントは以下です。
- 同一銘柄・同一名目(例:BTC 1枚の現物ロングに対し、BTC 1枚の先物ショート)。コイン建てかUSDT建てかで名目一致を厳密に確認。
- マルチ取引所分散:発注・保管・法定通貨出金の観点で1社集中を避ける。
- 証拠金タイプ(分離/クロス、USDT/コイン証拠金)を戦略と一致させる。
- 担保バッファ:先物ショート側の急騰時マージン増に耐える十分な余力。
数値例(期限付き先物)
現物BTCがS=8,000,000円、3か月先物がF=8,240,000円だとします。D=90日なら、APY ≈ (240,000 / 8,000,000) × (365/90) ≈ 12.17%。ここから手数料・スプレッド・資金移動・借入金利を差し引き、ネット年率を評価します。
数値例(パーペチュアル)
現物ロング+パーペチュアルショート。直近の価格差は小さく、ファンディングがショート受け取りで年率期待6%、一方で現物保有の機会コスト・借入は2%なら、APY_perp ≈ 6% − 2% = 4%。ただし、ファンディングはトレンド局面で符号反転・急変し得るため、レンジ想定期間やヘッジ強度を可変にします。
ベーシスが生まれる理由:需給と資金制約
上昇相場では先物ロング需要が膨らみ、先物が現物より高く(コンタンゴ)なりやすい一方、恐怖局面では保険需要(ショートヘッジ)や資金引き上げでバックワーデーション化します。さらに、資金調達コストやUSD金利、取引所間のリスクプレミアム、先物限月特有の受給イベント(四半期末のポジション解消)もベーシスを歪めます。
実行フロー(チェックリスト)
- 対象銘柄の選定:BTC/ETHが第一候補。流動性とベーシスの安定性が相対的に高い。
- 限月と建玉の一致:先物の限月・契約サイズ・通貨建てを確認し、名目を一致。
- ベーシスの計測:板気配・出来値から
F − Sを取得。年換算利回りと取引コストを同一単位で評価。 - 執行:現物買い→先物売り。スプレッドの狭い時間帯を優先(ロンドン/NY時間の重なりなど)。
- モニタリング:証拠金率、清算価格、ファンディング予告、限月のロール期限、取引所のメンテ情報。
- 解消/ロール:収斂が十分、または期近の期限接近で解消。期限付き→期先へロール、ペルプはファンディングの符号が悪化したら縮小。
リスク管理:中立でもリスクは残る
- 取引所リスク:システム障害、清算エンジン、保険基金、出金制限。分散と余裕資金、一部の自己保険を前提。
- ベーシスの反転:バックワーデーション化でキャリー消失。早期解消のルール(例:APYが閾値
2%を下回る連続n回で縮小)。 - 清算・マージンリスク:ショート側に急騰が直撃。担保の通貨分散、分離証拠金、ストップ設定。
- 金利・借入コスト:現物調達を借入に依存すると利回りを侵食。自己資本回転とレバレッジのバランス。
- 資金移動・為替:円⇄USDT/USDC、ブリッジ、ネットワーク混雑。移動コストと遅延を前提計上。
シナリオ別の戦術
強気トレンド(コンタンゴ拡大)
先物プレミアムが厚く、キャリー妙味。現物+先物ショートの規模を増やし、APYの下限を決めて選別。ペルプではファンディングがロング支払いになりがちなので、受け取り優位の銘柄・取引所を探すか、期限付き中心へ。
恐怖局面(バックワーデーション)
先物ディスカウント時は、現物ショート+先物ロングの逆キャリーが成立します。ただし借券・現物ショートの実務制約が大きいので、現実的には「ヘッジ弱め+ディップ買い」か「短期のベーシス反転狙い」の戦術に限定。
レンジ相場
価格方向性が薄いほど中立戦略の相性が良い。期限付きはロールダウン、パーペチュアルは安定したファンディング受け取りを重視。
実装テンプレ:最小構成
- 口座とAPI整備:少なくとも2取引所+コールド保管。APIは発注・残高・ファンディング取得を自動化。
- 日次ルーチン:利回り表の更新(銘柄×限月×取引所)、ロールカレンダー、担保比率のチェック。
- 執行ルール:スプレッド閾値、サイズの分割、成行と指値の使い分け、板薄時間帯の回避。
- 縮小ルール:APYが連続で閾値割れ、または取引所イベント(保守、規約変更)が発生したときは全縮小または半減。
数値で学ぶミニケース
ケースA:BTC現物8,000,000円、3か月先物8,320,000円。年間換算は約13.87%。往復手数料0.04%、スプレッド0.02%、移動コスト0.02%を引くと約13.79%。担保に対して実効レバレッジ1.5倍までなら、清算リスクを抑えつつ年率の見込みを上げられます(過度は禁物)。
ケースB:ETHペルプの資金調達が+0.010%/8hで安定。年換算で概算0.010% × 3 × 365 ≈ 10.95%の受け取り。一方、現物調達の機会コスト年率2%、出来高が薄く滑り0.1%発生と見積もれば、ネットは約8.85%。資金調達がマイナスへ反転した場合の縮小トリガを事前に設定。
検証(バックテスト)の考え方
- 必要データ:現物終値、各限月先物終値、ペルプのファンディング履歴、手数料テーブル。
- ロジック:APY上位からの採用、取引所分散、最大建玉制約、ロールタイミングの固定。
- 評価指標:日次リターン、シャープレシオ、最大ドローダウン、95%/99%VaR、相関(BTC方向リスク残存の有無)。
- ストレス:極端な急騰急落日(清算域近接)、ファンディング符号反転の連続、スプレッド急拡大。
よくある失敗と対策
- 名目不一致(USDT建てとコイン建ての混在)→ 約定数量を名目で一致。
- 担保不足→ 証拠金率アラートと自動追加入金のフローを準備。
- ロール忘れ→ カレンダーで自動通知。期限1週間前を標準化。
- 過信によるサイズ過多→ 一回でフル投入しない。段階的に増減。
運用チェックリスト(保存版)
- 各銘柄のベーシスと年換算利回り(ネット後)
- ファンディングの直近・過去14日平均・分散
- 証拠金維持率/清算価格からの距離
- ロール期限・イベント(四半期末)
- 取引所のリスク指標(保険基金残高、障害履歴の公開)
まとめ:方向性ではなく価格差を獲る
ベーシストレードは「上がる/下がる」を当てるのではなく、市場の歪みと時間経過を収益源にします。正しい名目管理、余裕ある担保、退出規律、そしてデータに基づく選別が、安定運用の核心です。まずは小さく始め、ネット利回り基準で再現性を検証してください。

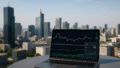

コメント