ビットコインのハルビング(Halving)は、約4年ごとにマイニング報酬が半減する供給ショックです。供給の変化は即時の需給タイト化だけでなく、期待・資金フロー・デリバティブ市場のカーブ形状を通じて中期の価格形成に影響します。本稿では、ハルビング前後に観測されやすい指標の動きと、現物・先物・オプションを使った実務的な戦い方を、初学者でも実装できるレベルまで落とし込みます。
なぜハルビングは「稼げるイベント」になりやすいのか
価格は単に需給だけでなく、投機需要、ボラティリティ、金利(資金調達コスト)、ベーシス(先物と現物の乖離)に影響されます。ハルビングはこれらを同時に動かす「複合イベント」です。典型的には以下の順で歪みが発生します。
- 期待先行のプレ・ラン:イベント数か月前から現物買い・パーペチュアルのロングが増え、ファンディングがプラスに偏りやすい。
- ボラ上昇とコール偏重:需要の先回りでIV(インプライド・ボラティリティ)が上がり、短期はコール高止まり。
- イベント直前〜直後の「織り込み剥落」:材料出尽くし的な乱高下や、過熱ポジションの巻き戻しが起きやすい。
- 中期のマクロ連動フェーズ:流入・政策・リスク資産サイクルに回帰しやすく、先物カーブやベーシスが平常化。
ハルビングで見るべき市場指標(3本柱)
1) ベーシス(先物プレミアム/ディスカウント)
年率換算ベーシスは次式で概算できます。
Annualized Basis (%) = ((F / S) - 1) * (365 / T) * 100
# F: 期先先物価格, S: 現物価格, T: 残存日数
ハルビング前は強気期待で順ザヤ(コンタンゴ)が拡大しやすく、キャリー(売り先物×買い現物)が機能しやすい一方、急変時は逆ザヤ(バックワーデーション)転化に注意が必要です。
2) ファンディングレート(パーペチュアル)
Annualized Funding (%) ≈ funding_rate_per_interval * intervals_per_day * 365 * 100
プラス偏重=ロング過多のサインです。プラスが続く局面では、ロング・キャリーの利回りは低下し、ショートで資金受取の妙味が出ます。ただしイベント前後は急反転リスクが高まります。
3) インプライド・ボラティリティ(IV)とスキュー
イベント前はIV先高になりやすく、短期IV>中期IVの逆転(インバート)もあり得ます。コール・プットのスキューを観察し、片側に偏った保険需要を読み解きます。
時系列プレイブック:D-150 〜 D+150
| フェーズ | 市場の癖 | 注力戦術 | 主なリスク |
|---|---|---|---|
| D-150〜-60 | 期待先行の上昇+順ザヤ拡大 | 現物+ヘッジ売り先物のデルタ調整キャリー/保守的なカレンダースプレッド | 過熱→巻き戻し、金利上昇 |
| D-60〜-10 | 短期IV上昇、ファンディング高止まり | IV高でのオプション売り(限定リスク型)/資金受取ショートのバッファ付き | イベント前の急騰急落 |
| D-10〜+10 | 乱高下・スパイク、スキュー歪み | ロング・ガンマでの捕捉(デビット・スプレッド)/デルタ中立のショート・ボラ解消 | スリッページ、板薄 |
| D+10〜+90 | 織り込み剥落→トレンド再構築 | 新トレンドの順張り+プットプロテクション/ベーシス正常化のキャリー | だまし、政策や流動性ショック |
| D+90〜+150 | マクロ回帰 | 裁定・キャリーの平常運転/損益曲線のフラット化 | 外部要因(ETFフロー、規制) |
3つの実戦ストラテジー
A. 現物×期先売りのキャリー(順ザヤ取り)
条件:順ザヤが年率換算で無リスク金利+手数料+借入コストを上回ること。
手順:
1) 現物を購入し、同等ノーションで期先先物を売る。
2) 価格変動でデルタがズレたら再ヘッジ。
3) 満期でキャリー収益を実現。
注意:急落でバック化した場合のロール損・証拠金繰りの負荷。
B. ファンディング受取ショート(バッファ付き)
条件:資金調達が長期にプラス偏重、かつ下落時のショートカバーに耐えるバッファ(現金・ヘッジ)を確保。
手順:
1) パーペチュアルを部分ショート。
2) 価格上昇に備え、低デルタのコール買い(保険)を添える、または期先先物の買いでカバー。
3) ファンディング受取と保険コストのネットで評価。
注意:イベント跨ぎのスパイクと急反転で損益が変動。
C. オプションのデビット・スプレッド(限定リスクでの方向取り)
例:上方向ならコール・デビット・スプレッド(ATM買い+OTM売り)。IV高止まりでも、売りレッグでコストを抑えられる。下方向はプットで同様。
利点:損失限定、ガンマ正でイベントの急変対応。
弱点:目標値到達前に時間価値が剥落しやすい。
数値例(概算)
想定:現物S=10,000、90日先物F=10,800、T=90日、手数料往復=0.10%、借入コスト年率=5%。
年率ベーシス ≈ ((10800/10000) - 1) * (365/90) * 100 = 約32.5%
実効利回り ≈ 32.5% - 5.0% - 0.10%(手数料) = 約27.4%(概算)
この水準なら、ヘッジのズレとロールコストを管理できる前提でキャリー妙味が生じます。なお実務では清算価格、証拠金余力、板厚を都度確認します。
建玉・資金管理(実務)
- 証拠金余力 2.0倍以上:最大逆行を想定し、追加証拠金なしで耐える設計。
- 分割建て:D-90、D-60、D-30の3点で分散。イベント直前の一括は避ける。
- ロスカット規律:先物ショートはIVスパイクや資金調達反転で想定外の逆行が起きるため、価格×IV×ファンディングの複合トリガーで縮小。
- 取引所分散:カウンターパーティ・リスク低減。保全資産は自己管理。
観測ダッシュボード(最低限)
- 先物カーブ:期近〜期先のコンタンゴ幅(年率換算)。
- ファンディングレート:日次推移と市場全体の偏り。
- IVターム構造:1週・1か月・3か月の相対関係とスキュー。
- フロー:現物ETF資金流入/流出、取引所残高、マイナーの送金推移。
簡易バックテストの考え方
厳密な検証にはヒストリカルの先物・オプション・ファンディング時系列が要ります。最低限の再現可能なルール化が重要です。
# 擬似コード(キャリーストラテジー)
if Annualized_Basis > threshold and Funding >= -cap:
enter long spot, short futures
hedge when |delta| > band
exit at expiry or when basis < floor
オプション戦略は、イベント窓のIVとガンマを意識して、エントリーはD-14〜-7、利益確定はD+3〜+7など時間で縛ると過剰最適化を避けられます。
よくある落とし穴
- 「ハルビング=必ず上がる」前提:相場は事前に織り込みます。織り込み剥落は常に警戒。
- 資金調達の片張り:プラス偏重の逆回転は破壊的。保険か縮小で対応。
- 清算価格の軽視:ストップロスと維持証拠金の二重管理を。
- 板薄時間帯の建玉:イベント時はスプレッド拡大・滑り拡大。
実行のチェックリスト
- 取引所と保管:現物保全と証拠金の住み分け。
- ベーシス・ファンディング・IVの3指標で同時確認。
- 建玉サイズは資産の1〜5%から開始し、段階的に。
- エグジット条件を事前定義(価格・IV・日付)。
- 実績をログ化し、次回ハルビングに再利用。
ハルビングは「語られる物語」と「測れる歪み」が重なるイベントです。測って、分割し、限定リスクで実行。この基本だけで、過剰な賭けを避けつつ収益機会を積み上げられます。


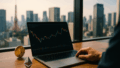
コメント