ベーシストレードとは何か
同一原資産(例:BTC)の現物と先物(もしくはパーペチュアル)に同時に反対ポジションを取り、価格乖離やファンディングレートからリターンを得る市場中立型の戦略です。基本形は「現物ロング+先物ショート」。現物の上昇損益と先物の下落損益が概ね相殺され、残るのは(1)先物が現物より高いときのベーシス縮小分、(2)パーペチュアルの正のファンディングの受取分、から生じるキャリー収益です。
基本構造:現物先物キャリー
- 現物を買う(例:BTCを100万円相当)。
- 同名柄の先物(またはパーペチュアル)を同名目で売る(デルタを中立に)。
- 満期まで保有(先物)または継続保有(パーペチュアル)。期間中、ベーシス縮小やファンディング受取を狙う。
- 満期時に先物と現物の価格差が収斂すれば、差益が収益化される。パーペチュアルなら保有中のファンディングが収益になる。
ポイントは「名目の一致(デルタ中立)」と「コストの最小化」。建玉の名目ずれは相場急変時の損益ブレを増幅します。
パーペチュアル版:ファンディング捕獲
パーペチュアル(無期限先物)は先物プレミアムの代わりに、8時間ごと等の間隔で資金のやり取り(ファンディング)が発生します。多くの局面でロングが支払う正のファンディングになるため、現物ロング+パーペチュアルショートはファンディング受取を期待できる構造です。ただし局面により負に転じるため、モニタリングと閾値ルールが重要です。
数値例(想定)で理解する
前提(例示・概算):
- 現物価格:BTC = 10,000,000円
- 四半期先物価格:10,300,000円(満期まで90日)
- 先物手数料:片道0.02%(往復0.04%)
- スポット手数料:片道0.10%(往復0.20%)
- 現物保有コスト:0(保管料等は便宜上無視)
- 資金コスト(円調達の機会費用等):年3%相当
このとき、年率ベースの先物プレミアムは概算で:
プレミアム = (10,300,000 − 10,000,000) / 10,000,000 = 3.0%(90日)。年率換算 ≒ 3.0% × (365/90) ≒ 12.2%
コスト控除前の理論キャリー ≒ 年率12.2%。ここから手数料(概ね0.24%程度)、資金コスト(年3%)、実務のスリッページ等を引くと、年率おおむね8〜10%程度が目安になります(相場・板厚・ロール手法に強く依存)。
収益源の分解
- ベーシス縮小(キャッシュ&キャリー):期限先の先物が現物より高い場合、満期接近で差が縮む傾向。
- ファンディング受取(パーペチュアル):ロング優勢局面でロング→ショートへ支払い。ショート側が受取。
- 安定的な手数料レベルの最適化:VIPティア、メイカー化、リベート活用。
主なコストとリスク
- 手数料・資金調達コスト:建玉・ロールの度に発生。資金金利やステーブル借入金利を必ず控除。
- ベーシス変動リスク:途中で先物安(逆ザヤ)になると評価損。満期で収斂してもメンタルに影響。
- 清算・ADL・マーク価格仕様:先物の清算はマーク価格基準。極端な変動で強制減算の可能性。
- 取引所信用・カウンターパーティリスク:分散、保険基金、コールド保管、監査レポート等で評価。
- 流動性・板厚:名目サイズが大きいほどスリッページが効く。メイカー運用で緩和。
- 資金移動・チェーン遅延:入出金停止や混雑でロール不能リスク。複数ルートを確保。
- コンタンゴ→バックへの転換:構造変化時はクローズないしヘッジ切替ルールを明確化。
取引所選定と口座設計
判断軸は以下です:
- 先物/パーペチュアルの建玉上限・証拠金制度(クロス/分離)。
- マーク価格・清算仕様・保険基金の厚み。
- スポット市場の板厚・入出金の安定性・手数料テーブル。
- API品質(レート制限、フェアリミット、注文種別、ポジションモード)。
- KYC要件・地域制限・監査/証明(PoRなど)。
実務フロー(運用前チェックリスト)
- (1)対象銘柄と限月(もしくはパーペチュアル)を決める。
- (2)名目を一致させる(例:BTC 1.000 現物買い/先物売り)。
- (3)手数料ティア・資金金利・借入金利を取得・更新。
- (4)板厚とスリッページ前提を確認(発注ロット分割プランを用意)。
- (5)清算価格マージンの余裕(IM/MM)とADLルールを確認。
- (6)リスク上限(評価損幅・ベーシス逆転・ファンディング反転)を数値化。
- (7)異常時のクローズ手順(同時成行、IOC、TWAP、クロス取引所ヘッジ)。
シミュレーション:キャッシュ&キャリー
名目1BTCで開始。初期現物買いと先物売りの建玉合計コスト(手数料)を0.24%、資金コストを年3%と仮定。90日後に先物と現物が同値で決済され、先物の初期プレミアム3.0%がそのまま縮小したとする。
粗利(90日)= 3.0% − 0.24% − 3.0%×(90/365) ≒ 3.0% − 0.24% − 0.74% = 約2.02%
年率化 ≒ 2.02% × (365/90) ≒ 約8.2%。スリッページやティア改善で変動します。
パーペチュアル:ファンディング捕獲の運用則
- 直近7〜30日の時間加重平均ファンディング(TWAF)を採用し、閾値(例:+0.01%/8h以上)でエントリー。
- 直近の資金借入金利・ステーブル運用利回りを控除してネット利回りを確認。
- 反転(負のTWAF)で縮小・クローズ。イベント前後はポジション縮小。
ロール戦略:四半期先物の継続運用
満期の1〜3日前から次限月へ段階的にロール。カレンダースプレッドを観測し、スプレッド拡大時にヘッジ側から先回りする。ロールコスト(手数料+スリッページ)を年率換算し、ネットキャリー > ロールコストを維持する限り継続。
クロス取引所運用と資金最適化
取引所Aでスポット、取引所Bで先物という組み合わせは、値洗い・保険基金・ダウンタイムの分散に有効。ただし送金・担保移動の遅延がボトルネックになるため、複数のステーブル・複数チェーン・複数入金ルートを用意。資金効率向上のため、ステーブルの短期運用(T-bill連動型や所内Earn等)の年率を常に比較し、ネットキャリーで意思決定します。
ダッシュボード指標
- 先物ベーシス(各限月の年率換算スプレッド)
- パーペチュアル・ファンディング(実効:メイカー/テイカー費用を控除)
- 取引所別:手数料ティア、保険基金、建玉上限
- スリッページ推定(ロット別の市場インパクト)
- イベントカレンダー(FOMC、雇用統計、ETFフロー等)
典型的な失敗と対策
- 名目不一致:先物がコイン建て/USDT建てで名目換算を誤る。常に名目とデルタをダッシュボード表示。
- 清算マージン不足:片側が逆行して評価損が拡大。証拠金は余裕を持ち、分離で管理。
- 負のファンディング持ち越し:ルール化し自動縮小。イベント前はノットラ。
- ロール遅れ:期近の板が薄くなる前に段階ロール。
- 片側の約定だけ先行:IOC/TWAPやスプレッド注文で同時性を高める。
スモールスタート手順(例)
- 名目0.1BTC程度でテスト。現物買い→即時に同名目でパーペチュアル売り。
- 1週間、ファンディングと評価損益の推移を記録。ネット利回りがプラスか確認。
- ロット拡大は板厚・ティア改善・資金金利低下の順で。
撤退基準
- TWAFが閾値を下回る/負転し、ネット利回りがマイナス化。
- 取引所の信用イベント兆候(入出金遅延、証拠金仕様変更、保険基金急減)。
- イベント前後の極端なボラでADLリスク上昇。
まとめ:運用の肝
ベーシストレードは、価格予想ではなく「仕組み」に収益源を求める戦略です。勝ち筋は、(1)名目一致とコスト最適化、(2)規律あるエントリーと撤退、(3)運用インフラ(板、API、資金ルート)の整備。小さく始めてデータで意思決定し、ネットキャリーの安定化を第一に設計してください。

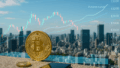

コメント