本稿は、暗号資産の価格変動を「オンチェーン分析」で先回りするための実務フレームワークを、できるだけ手を動かしやすい形でまとめたものです。専門用語を最小限に抑え、再現可能な手順・数式・閾値例・売買ルールの雛形まで提示します。
オンチェーン分析とは何か
オンチェーン分析は、ブロックチェーンに記録された移転履歴・残高・年齢(コインが最後に動いた時点からの経過時間)などの公開データを用いて、市場参加者の行動を定量化する手法です。価格や出来高のような「相場データ」だけでなく、資金がどこから来てどこへ向かっているかを読み解ける点が優位性になります。
基本思想はシンプルです。大きなフロー(例:取引所への流入増=売り圧の増加、取引所からの流出増=保管意図の強化)や、含み益/含み損の偏り(例:買いコスト分布)を定量化し、短期〜中期の需給を推定します。
最低限覚えるコア指標(暗記コストの低い4本柱)
1. 取引所ネットフロー(Exchange Netflow)
定義:一定期間の「取引所流入 − 流出」。正の拡大は売り圧増を、負の拡大は買い圧/保管意図を示唆します。
見るコツ:7日移動平均のトレンド転換点。加えて価格と先物建玉(Open Interest, OI)の同方向拡大が重なると、短期のボラ拡大シグナルになりやすいです。
2. MVRV(Market Value to Realized Value)
定義:時価総額 ÷ 実現時価総額。全体の含み益/損の偏りを表します。
実務目安:BTCではMVRVが「1.0~1.2」近辺は割安圏、「2.0」付近は過熱圏になりやすい傾向(絶対ではない)。ETHでも同様の発想でレンジを観察します。
3. SOPR(Spent Output Profit Ratio)
定義:売却価値 ÷ 取得価値。1より大きければ利益確定優勢、1未満なら損切り優勢。
実務目安:上昇トレンドではSOPRが1.0付近で反発(利益確定が一巡)しやすく、下降局面では1.0がレジスタンスになりやすい。
4. ステーブルコイン循環供給と取引所残高
定義:USDT/USDC 等の発行量と、取引所上のステーブル残高。
示唆:供給増+取引所残高の積み上がりは「待機資金の拡大」を示唆し、上昇相場の燃料になりやすい。逆に供給減や残高の減少はリスク回避や規制・信用ショックの可能性に注意。
最小構成のダッシュボード設計
まずは以下の4レイヤーに分け、各レイヤーで1~2指標に絞ります。
- 需給レイヤー:取引所ネットフロー、ステーブル残高
- 評価レイヤー:MVRV、URPD(未実現損益の価格帯分布に近い考え方)
- 行動レイヤー:SOPR、ホルダー年齢(Dormancy, CDD)
- 先物レイヤー:OI、資金調達率(Funding)、清算データ
各レイヤーで「改善/悪化/中立」の3値フラグを付け、合計点で売買スタンスを決める簡易合議制にします。
即戦力の売買レシピ(ルール雛形と数値例)
レシピA:短期逆張り(フロー×デリバティブ)
条件:
(1) 7日平均の取引所ネットフローが直近30日レンジの上位20%に突入(売り圧急増)
(2) 同日に価格が-3~-7%下落
(3) OIが直近3日で+10%以上増(レバ玉が溜まる)
アクション:スキャル/デイで買い回転。
出口:翌営業日のVWAP付近 or 価格が+2~+4%反発で半分利確、SOPRが1.0回復で全利確。
レシピB:スイング順張り(評価×資金燃料)
条件:
(1) MVRVが1.2前後で横ばい→上抜け、かつ20日MAが上向き
(2) ステーブル残高(対時価総額比)が直近1~2週間で増加傾向
アクション:押し目買い(20日MA付近で分割)。
出口:MVRVが1.8~2.0に接近、SOPRが1.05超で利確分割。
レシピC:イベント・ショック時の段階買い
条件:ステーブル供給が横ばい~微増の中で、ネットフローが一時的に強い流入(上位10%)かつ価格急落。
アクション:3分割で拾い、反発で1/3ずつ戻り売り。
無効化:ステーブル供給が同時に急減している場合は見送り。
ケーススタディ(仮想データでの再現例)
以下はBTCの仮想週次データです。
週初価格: 7,000,000円 → 週末: 6,650,000円(-5.0%)
ネットフロー(7日MA): +12,000BTC(30日レンジの上位15%)
OI: +13%
SOPR: 0.98 → 1.01 回復
ステーブル残高(対時価総額比): +0.15pt
上記はレシピAのセットアップに近く、翌週の反発+3%で半分利確、その後SOPRが1.0回復で残り利確、という運用が合理的です。
バックテストの超簡易プロトコル
- 各指標を標準化(Zスコア)し、閾値(例:ネットフローZ > 1.0)でシグナル化。
- 合議スコア(+1/0/-1の合計)を作り、+2以上で買い、-2以下で売り、0は建玉縮小。
- 週次リバランス。スリッページは0.1~0.3%で控えめに仮定。
- 最大ドローダウン、勝率、プロフィットファクター、平均保持日数を記録。
いきなり完全自動化するより、まずはExcel/Googleスプレッドシートで週次更新→手動執行が現実的です。
ETH・アルトコインへの横展開
ETHは手数料市場(ガス消費)の景気が効きやすいので、ガス使用量のトレンドとL2ブリッジ流入を補助指標に。アルトの場合はチェーン固有のステーブル流入とトークンの実需(NFT・DeFi TVL・アクティブアドレス)の変化を重視します。
落とし穴と無効化条件
- 取引所アドレスの誤分類:内部移転を「流入」と誤読しないよう、短期の単発スパイクは慎重に扱う。
- ステーブルのチェーン移動:マルチチェーン間のブリッジ移動は「供給減」とは限らない。
- デリバティブの偏重:OIやFundingの極端な変化は清算連鎖を生むが、同時に逆指標化もしやすい。
- 政規制・技術イベント:フォーク、アップグレード、規制報道はファンダが一変するため、指標に優先してヘッドラインを確認。
実装チェックリスト
- 4レイヤー×2指標=計8枚のチャートを毎週同じ時間に確認。
- ルールA/B/Cのトリガーと無効化条件をシートに明文化。
- 合議スコアとポジションサイズ(例:+3で通常の70%、0で30%)を機械的に更新。
- 月次で勝率・DD・PFをレビューし、閾値を微調整。
まとめ
オンチェーン分析の強みは「フローと評価の非価格情報」を直接読むことにあります。本稿の4本柱(ネットフロー、MVRV、SOPR、ステーブル残高)と3レシピ(A/B/C)だけでも、裁量のブレを減らし、再現性のある意思決定に近づけます。まずは小さく始め、ダッシュボードと合議スコアを毎週更新するところから始めてください。

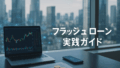
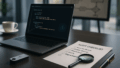
コメント