本稿は、トークンのベスティング(Vesting)とクリフ(Cliff)に起因する「ロック解除(Unlock)」イベントを利用し、売り圧・買い圧を先回りで読んで取るイベントドリブン戦略を、初歩から実務レベルまで一気通貫で解説します。IPOのロックアップ解除と同様、クリプトでも割り当てトークンが市場に流入するタイミングは需給ショックの源泉です。適切に検証し、サイズを抑えたうえで運用すれば、裁量・システムのどちらでもリスクリワードの良い非相関リターンを狙えます。
1. 用語の整理:ベスティング/クリフ/エミッション
ベスティングは、チーム・投資家・アドバイザー・コミュニティ向けに配布されたトークンが、時間経過に応じて段階的に引き出し可能になる仕組みです。クリフは最初に解除可能になるまでの待機期間で、一般に6〜12か月が多く、その後は毎月・毎週の線形ベスティングが続きます。エミッション(発行/放出)はマイニング/ステーキング報酬・インセンティブ等を含む流通量増加の総称で、ベスティングと合わせて供給スケジュールを形成します。
2. なぜリターン機会になるのか:価格形成と需給の力学
価格は需給で動きます。ロック解除は「供給の前倒し可視化」という情報ショックであり、直前に期待と恐怖が交錯します。典型的なパターンは以下の3つです。
(A)解除前の先回り売り:大口保有者のヘッジ・一部利確により、クリフ直前から下押し圧力。
(B)解除後のオーバーリアクション:解除日当日に出来高が急増し、流動性の薄い板で下へのスリッページが拡大。
(C)需給悪材料の「通過」:解除後、売り需要が一巡するとショートカバーと新規買いでリバウンド。
この3相構造を理解すれば、「いつ、どの方向で、どのサイズで」仕掛けるかの設計図が見えてきます。
3. 情報源:解除カレンダーと一次資料をどう集めるか
実務では、(1)プロジェクトのホワイトペーパー/トークノミクス資料、(2)ベスティング契約(SAFT等)や投資家向けスケジュール、(3)各種アグリゲータが提供するロック解除カレンダー、(4)オンチェーンの配布/移転履歴、の四層で整合性を取ります。アグリゲータだけに依存せず、一次資料で必ずクロスチェックするのがプロの作法です。
4. 解除イベントの「重さ」を数式で捉える
売り圧の一次近似として、フロート希薄化率と潜在売却圧を定義します。
フロート希薄化率 ≒ 解除予定枚数 ÷ 現行フロート(流通枚数−長期ロック)
潜在売却圧 ≒ 解除予定枚数 × 想定売却比率(ベンチャー/チーム/LPの行動仮説)
さらに、時価総額感応度 = (潜在売却圧 × 想定平均売却価格) ÷ 流動時価総額、と置けば、価格に対するショックの相対規模が見えます。想定売却比率は「直近の資金調達環境」「当該セクターのモメンタム」「プロジェクトのガバナンス提案(延長/再ロック)」でベイズ更新します。
5. 仕掛けの基本設計:5つのアプローチ
(1) 先回りショート(解除前):解除2〜3週間前から段階的にショートを構築。ファンディングレートが正→プラスのまま上昇なら、ショートのコストが嵩むためサイズは抑制。上髭連発+出来高増はエントリーの合図。リスクは「延期/スケジュール改定」。
(2) イベント当日の板読みスキャル:解除当日の数時間、オーダーブックの厚みと成行フローを観察。スプレッド拡大時は小さめの利幅で回転。AMMプールでは価格インパクトに注意し、複数CEX/DEXのルーティング比較を常に。
(3) 解除後のリバウンド狙い:初動で過剰に売られた場合、VWAP乖離や30分足の出来高クライマックスを指標に逆張り。解除直後にショート金利(FR)が急低下〜マイナス転化したら、売り一巡の兆候。
(4) ベーシス/裁定の併用:先物コンタンゴ拡大時にショート先物+スポットロングを組み、イベント通過でベーシス縮小を取りに行く。ボラ高騰時はオプションでプロテクション。
(5) ガバナンスの再ロック提案を読む:解除前にDAO提案で延長/再ロック/線形化が可決されるケースがある。投票クオラムや大口の投票動向をトラッキングすると、シナリオ確率更新に役立つ。
6. データ準備:オンチェーン/オフチェーンのKPI
最低限、以下を時系列で整理します。
・総供給、循環供給、ロック残高、トレジャリー残高、将来解除スケジュール(テーブル化)
・上位保有者の移転/入金アドレス(CEX入金タグの有無)
・DEXプールのTVL・スリッページ曲線、LPの入退場、価格インパクト
・CEXの板厚/スプレッド/メイカー・テイカー比率、清算閾値分布
・先物/パーペチュアルのFR、OI、ベーシス、清算マップ
一次資料のPDFやGitHubのトークノミクス表と矛盾があれば、保守的(悪い方)に解釈します。
7. エントリー/エグジット手順:チェックリスト
エントリー前:①解除カレンダー確定(UTC/ローカル時差を確認)、②解除枚数と希薄化率を算出、③直近のFRトレンド、OI増減、④CEX/DEXの板とルーティング、⑤ガバナンス提案の有無、⑥ヘッジ手段(先物/オプション/相関ヘッジ)を決める。
エントリー:分割で入る(3〜5回)。ショートの場合は上昇で追加、ロングの場合は下落で追加は原則避ける。必ず最大損失(証拠金×許容%)を先に決める。
エグジット:イベント前後は流動性が歪むため、指値の梯子を用意。VWAP・当日高安・ピボットで利確帯を事前定義。ニュース/提案可決などの状態遷移が起きたら即時でシナリオ更新。
8. 具体例(モデルケース)
仮想の「ABC」トークン。時価総額2億ドル、循環供給1億枚。30日後に1,500万枚が解除、うち投資家割当1,000万枚(想定売却比率50%)、チーム割当500万枚(想定売却比率20%)。
・フロート希薄化率 ≒ 1,500万 ÷ 1億 = 15%
・潜在売却圧 ≒ 1,000万×50% + 500万×20% = 600万枚
・時価総額感応度($2.00想定) ≒ 600万×$2 ÷ ($2.00×1億) = 0.12(=12%)
この規模は警戒レベル。戦術は、T-21日から先物で段階ショート、T-3日でサイズ縮小、当日プライスアクション次第でリバウンドを逆張り。FRが+0.03%/8h→0.01%/8h→-0.01%/8hに低下すればショート一巡のサインとして一部利確。
9. 実装のミニ手順(半裁量/半システム)
①CSVで解除カレンダー(銘柄、解除日UTC、解除枚数、種別、フロート、希薄化率、想定売却比率)を作成。
②PythonでFR・OI・出来高・価格の時系列と結合、T-30〜T+7のイベントウィンドウで平均超過リターンを算出。
③「希薄化率≥8% かつ OI増 かつ FR低下」などの条件でシグナル化し、サイズは口座の1〜3%に限定。
④ガンマ急変時はオプションでヘッジ、強制清算の距離は常に>3σを確保。
10. 失敗パターンと回避策
・スケジュール誤読:タイムゾーン/夏時間/誤情報に要注意。一次資料に立ち返る。
・再ロック提案の見落とし:投票締切前後は価格が荒れる。クオラム達成見込みを監視。
・薄い板でのオーバーサイズ:約定スリッページが損失の主因に。分割と価格帯指値で補正。
・レバレッジ過多:FRコストと清算距離の二重リスク。サイズ管理が戦略の半分。
11. リスクと遵守事項
本戦略はイベント依存の短期売買であり、価格変動・スプレッド拡大・清算・資金調達コストのリスクを伴います。各国の規制や各取引所のルール、税務ルールの変更にも留意が必要です。自己責任原則のもと、原資産の理解、証拠金管理、最悪時の損失許容を明確にしたうえで実施してください。
12. まとめ:需給は「読める」イベントから始める
ベスティングとクリフは、予め公表されやすい読める需給です。解除前後の3相パターン、フロート希薄化率と潜在売却圧の定量化、FR/OI/板厚の補助指標、DAO提案の有無を組み合わせれば、過度な勘に頼らず再現性のある意思決定が可能です。まずは小さなサイズで検証し、手順を標準化してからスケールしてください。
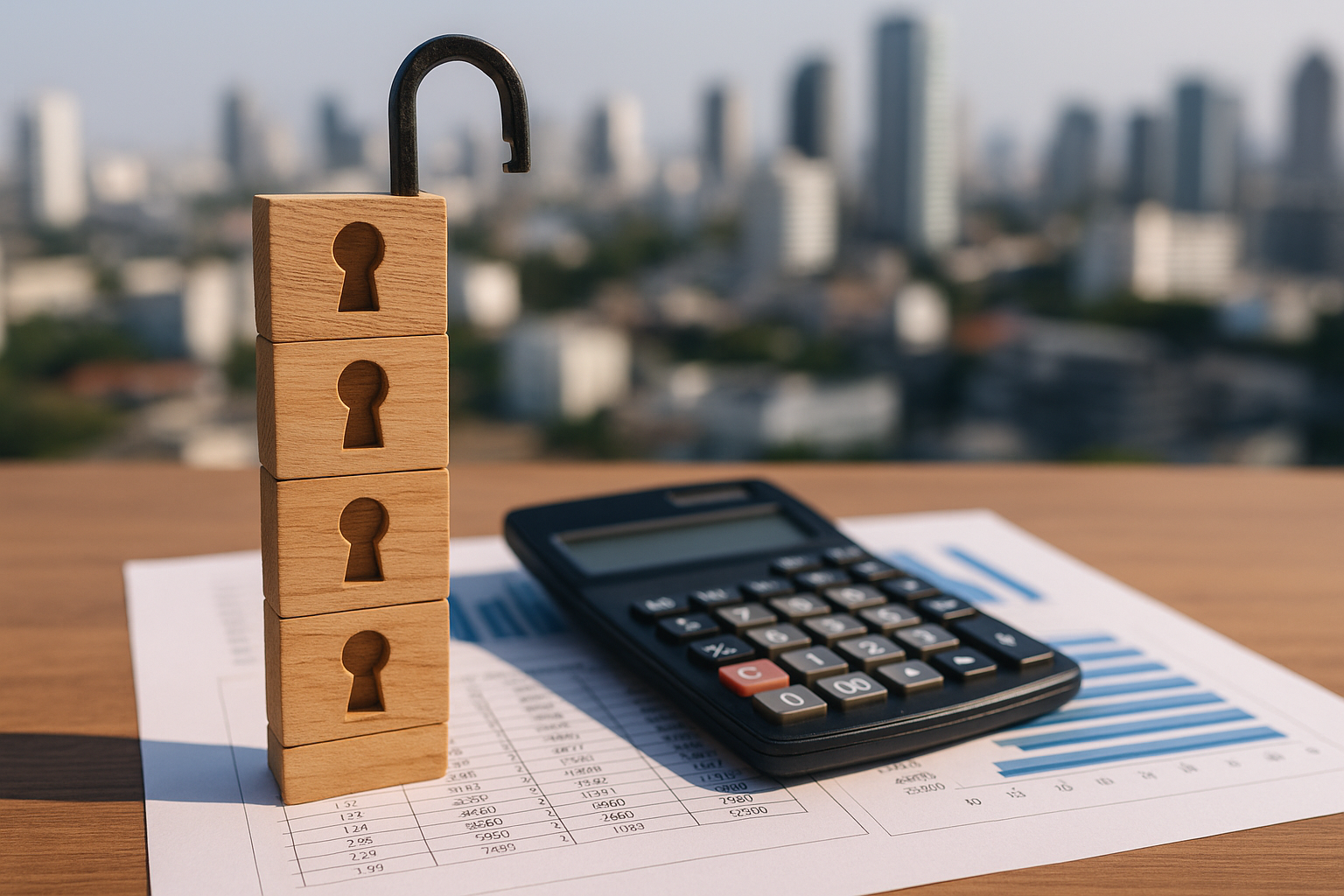


コメント