1. なぜインパーマネントロスが起きるのか
AMMでは、価格が動くとプールの資産比率が自動で再配分され、結果として「HODLした場合の価値」よりも低くなる現象が生じます。これがインパーマネントロス(IL)です。価格が元の水準に戻れば損失は理論上解消しますが、トレンド相場では恒常的に発生します。
代表的な一定積(x*y=k)型AMMにおいて、価格変化率をr = P_1 / P_0とすると、LPポジションの価値は理論上、HODL比で
IL(r) = 2*sqrt(r)/(1+r) - 1 と表現され、rが1から乖離するほど負になります。これはデルタ(価格感応度)を内包するポジションであることを意味します。
2. ヘッジの基本設計:現物LP × 先物ショート
コアの考え方はシンプルで、LPポジションに含まれるネットの暗号資産エクスポージャー(デルタ)を、先物ショートで相殺することです。これにより、価格変動に対してほぼ中立の構造を作り、残る収益源としては取引手数料(および一部のプールではリワード)が中心になります。
実務的には、以下の3段階で実装します。
- 対象ペアとプールの選定:出来高、手数料率、TVL、手数料/APRの安定性、レンジ設定(Uniswap v3など)を精査。
- LPの想定デルタ推定:価格帯別の資産配分から、想定保有量(ETH/USDCなど)を近似し、
Δ_LPを計算。 - 先物ショート建て:
Δ_fut ≈ -Δ_LPとなるように枚数を調整。パーペチュアルの場合は資金調達率(ファンディング)の収支も織り込みます。
3. 数式で押さえるヘッジ比率
最も単純化したETH/USDCの等価プール(価格P)で、LPが実効的に保有するETH量をq(P)とします。Uniswap v2型なら、LPトークン価値Vに対して概ね半分がETH、半分がUSDCから構成され、価格が上がるほどETH比率は減少します。微分で感応度を取れば、Δ_LP = ∂V/∂Pに相当するデルタを近似できます。
実装では、数値近似で十分です。小さな価格変化εに対して、LP価値の差分から
Δ_LP ≈ (V(P+ε) - V(P-ε)) / (2ε) を取ります。これに対し、先物は1枚あたりΔ_fut = -契約サイズのデルタ(ショート)を持つため、枚数 = Δ_LP / 契約サイズで目安を得られます。
4. 実装パターン:パーペチュアル vs 期先先物
4.1 パーペチュアル(無期限先物)
価格連動が素直でヘッジしやすく、随時ロール不要。ただし、ファンディングの支払い・受け取りにより損益が変動します。ロング優勢の相場ではショートが受け取りになるケースもありますが、逆相場では支払いになる点に留意します。
4.2 期先先物(四半期など)
ベーシス(先物-現物の鞘)が発生し、期近化で収束します。ヘッジの忠実度はやや落ちる場合もありますが、ベーシス収益(またはコスト)を取りに行く設計も可能です。ロールのオペレーションが必要です。
5. 具体例:ETH/USDC 0.3%プール × パーペチュアル
前提:ETH価格3000 USDC、日次出来高比率20%、手数料率0.3%、LP元本10,000 USDC相当。Uniswap v3で±15%の狭いレンジを設定し、価格がレンジ中心に留まるケースを想定します。
- 手数料見積り:出来高に0.3%が課され、LPシェアに応じて配分。出来高がTVL比20%/日なら、理論上の粗い日次手数料利回りは0.06%/日(=0.3%×20%)のオーダー。LPシェア・レンジ外時の不稼働を控除して、0.03~0.05%/日を目安に設定。
- Δ_LP推定:レンジ中心付近ではETHとUSDCの比率が概ね半々。元本10,000なら、おおむねETH1.67相当とUSDC5,000前後の組み合わせ(価格3000)。よって、
Δ_LP ≈ +1.67 ETH程度。 - 先物ショート:パーペチュアルで
約1.67 ETHをショート。実装では2 ETHショート→約0.33 ETH現物買い戻しなど、端数調整でデルタを詰めます。 - ファンディング管理:日次で受け払いを記録。受け取り>支払いの局面では利回り上乗せ、支払い超過では利回り目減り。ヘッジの必要経費として扱い、月次で評価。
この設計により、価格が上がっても下がっても、LP側の含み差損益と先物の逆方向損益が概ね相殺され、手数料収益の安定取りに集中できます。
6. 実運用の落とし穴と対策
6.1 レンジ外れ
狭レンジは歩留まりが高い一方で、価格が外れるとLPが一方資産に偏り、デルタが膨らむことがあります。対策は、(1) レンジを広げる、(2) 自動レンジリバランス機能のある戦略を用いる、(3) 先物枚数を増減して追随する、のいずれかです。
6.2 スリッページと手数料二重化
先物の調整で頻繁に売買すると、手数料とスリッページが積み上がります。許容バンド(例:±0.1 ETHのデルタ)を定義し、超えたときのみ調整する運用ルールを設けます。
6.3 清算リスク(証拠金管理)
先物ショートは証拠金と清算価格の管理が必須です。過小証拠金は厳禁で、最低でも維持証拠金×2~3倍の余裕を確保。急変時には一時的にヘッジ比率を下げる判断も選択肢です。
6.4 ベーシス歪み
パーペチュアルと現物の乖離、期先ベーシスの拡大・収縮は、ヘッジの忠実度に影響します。価格源の参照先を複数用意し、乖離監視と異常値フィルタを設けます。
6.5 スマートコントラクト・カストディ
LP側はスマートコントラクト・リスクが不可避です。監査状況、過去のインシデント、アップグレード権限、マルチシグ運用、セルフカストディの保護手順(ハードウェアウォレット、シード分割保管など)を整備します。
7. 日次・週次の運用ルーチン
- 日次:価格・デルタ許容バンド、ファンディング実績、ポジション一覧(LP/先物)、証拠金率、未実現損益をチェック。逸脱があれば最小ロットで調整。
- 週次:出来高/TVL、実際の手数料収益、稼働率(レンジ内滞在時間)、ヘッジコスト(手数料+スリッページ+ファンディング)を集計し、純利回りを評価。
- 月次:戦略のKPI(年換算利回り、最大ドローダウン、相関、テール損失事例)を更新。レンジ再設計・プール変更・先物銘柄の見直しを検討。
8. ケーススタディ:ETHトレンド上昇局面
ETHが3000→3600(+20%)へ上昇。レンジ中心は維持、LP内のETH比率が低下しつつ手数料を獲得。一方、先物ショートは含み損。ヘッジ比率が適切なら、ネットの価格影響は小さく、収益源は手数料+(場合により)ファンディング受け取り。上昇でファンディングがプラスに傾く場合、ショート側が受け取りとなり、利回りを押し上げます。
9. ケーススタディ:急落・レンジ外れ
価格が3000→2400(-20%)へ急落しレンジ外へ。LPはETH偏重になり、先物ショートが利益を出す一方、LPの稼働停止で手数料が止まります。対処は、(1) レンジ再設定、(2) 買い下がりでLPを再稼働、(3) デルタ縮小で様子見、の三択。清算回避のため証拠金を厚めにし、調整時の一括取引を避けて分割約定を徹底します。
10. 監視・自動化の設計
- アラート:価格乖離、デルタ閾値超え、証拠金率、ファンディング急変。
- リバランスBot:最小数量・クールダウン時間・スリッページ許容をパラメータ化。過剰最適化を避け、手数料・滑りの総コストを最小化。
- 記録:取引履歴、日次PL、KPIを自動集計し、月次の意思決定に反映。
11. リスク管理フレーム
- 流動性リスク:薄い時間帯・小規模プールでの大口約定は避ける。
- 先物カウンターパーティ:上場/信用力、保険基金の規模、破綻時の想定を事前に確認。
- スマコン・運用権限:アップグレード鍵、緊急停止権限、マルチシグ構成の透明性。
- 規制順守:取引地域のルール・税務の把握、個人情報・セキュリティ対策。
12. 収益分解とKPI
戦略のパフォーマンスは、(A) 手数料収益、(B) ファンディング収支、(C) ヘッジ誤差(ベーシス・遅延・レンジ外時間)、(D) 取引コスト(手数料・滑り)に分解して把握します。KPIは、年換算純利回り、シャープ・ソートィノ、最大DD、稼働率など。ヘッジでボラを抑えられるため、安定的なRFに近いリターンの獲得が目標です。
13. ステップバイステップ導入
- 小額でテスト:レンジ選定・ヘッジ比率・日次ルーチンを確認。
- 記録テンプレを整備:日次PL、デルタ、証拠金率、ファンディングを自動収集。
- サイズ拡大:許容損失・証拠金基準・最大同時ポジション数をルール化。
- リスク分散:複数プール(ETH/USDC、BTC/USDT等)と取引所分散。
14. まとめ
LPの価格方向リスクを先物で打ち消すことで、手数料という構造的収益にフォーカスできます。鍵は、(1) 適切なレンジとプール選定、(2) デルタ許容バンド運用、(3) ファンディングと証拠金の精緻な管理、(4) 自動化と記録の徹底です。少額テストから始め、KPIで検証しながら段階的に拡張していきましょう。

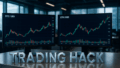

コメント