「DEXのLPは手数料で稼げるが値動きが怖い」──この悩みを数理とデリバティブで潰します。本稿は、LPトークンの価格感応度(デルタ)を先物・パーペチュアルでヘッジして、手数料収益+(場合により)ファンディング収益を積み上げ、実質的にステーブルに近いキャッシュフローを狙う実務ガイドです。初学者でも再現できるように、用語を平易に、手順はチェックリストで具体化します。
1. 前提:LPのリスク分解とインパーマネントロス
AMM(例:Uniswap v2/v3)の50/50プールに資金を供給すると、ポートフォリオは常に等価額になるよう自動調整されます。価格が片側に動くと在庫が傾き、価格追随の「デルタ」と、再配分による凸性(おおむねガンマ)を帯びます。
LPと「HODL(単純保有)」の比較で生じる損益差がインパーマネントロスです。価格比をr = Pnew/Poldとすると、理論的なIL(比率)は:
IL = 2×√r / (1 + r) − 1
例えばETHが+25%上昇(r=1.25)すると、LPの評価額はHODLに比べて目減りします。ただし、取引手数料収入と、後述のデリバティブ・ヘッジを組み合わせると、この目減りを相殺または上回れる場合があります。
2. 戦略の骨子:LPデルタを先物/パーペで中和
方針はシンプルです。(A)LPで手数料を稼ぐ一方、(B)LPが保有する現物相当の価格感応度を先物・パーペチュアルで反対売買してヘッジします。結果、価格方向のブレを抑えつつ、取引手数料(+資金調達収益/ベーシス)を取りに行く、という構図になります。
- LPの中身を把握:現在のプール価格で、LPが保有する各トークン数量を見積もります(v2は単純、v3はレンジ内在庫)。
- デルタ推定:片側(例:ETH)のドル換算在庫=LPのネット・ロング。
- デリバでオフセット:ETH先物/パーペをショートして、価格感応度(デルタ)をおおまかに打ち消します。
- ドリフト修正:価格変化でLP在庫が連動して動くため、定期的にヘッジ数量を微調整します(例:±5%ずれで再調整)。
3. 必要ツールと市場選定
- DEX:手数料水準・TVL・出来高が安定しているプール(例:ETH/USDC)。スリッページとガスを抑えやすいチェーンを選ぶ。
- CEX/パーペ取引所:流動性が深く、資金調達(ファンディング)履歴が安定。保険基金・清算エンジンの設計も確認。
- 価格データ:プール価格、出来高、v3ならレンジ内在庫、パーペのファンディング率、先物ベーシス。
- 自動化:アラート(価格・デルタ乖離・ファンディング反転)、日次/週次のヘッジリセット。
4. 数式の最小セット(使うところだけ)
4.1 LP在庫の近似
v2型50/50プールで総価値V、価格Pのとき、在庫は概ね等価配分:価値の半分がETH、半分がUSDC。すなわちETH数量QETH≈(V/2)/P。
4.2 ヘッジ比率
先物/パーペのショート数量Hは、H≈QETH(1:1ヘッジ)。実務では手数料収入やファンディング方向を踏まえ、0.8~1.2倍の範囲で微調整します。
4.3 インパーマネントロスの直観
価格上昇時はLPがETHを売ってUSDCを増やすため、上昇の取り分がHODLより減る=IL。逆に下落時はETHを買い増すため、底値付近でETH在庫が増えやすい性質があります。
5. 実践フロー(チェックリスト)
- プール選定:過去30~90日の出来高/TVL、手数料年換算(例:0.3%×回転数)を試算。
- 証拠金口座準備:十分な余力(強制ロスカットを避けるため、必要証拠金の2~3倍を目安)。
- 初期ヘッジ:LP注入後、即座に先物/パーペをショート(またはロング)してネットデルタを小さく。
- ドリフト監視:価格変動・出来高に応じてLP在庫が動く。乖離±5%~10%でヘッジ再調整。
- ファンディング捕捉:プラスが続く市場ではショートの支払いに注意。ベーシスの有利な限月先物に切替も検討。
- コスト最適化:ガス代が安い時間帯に実行、スリッページ許容幅を適切化、トランザクションの優先度手数料は控えめに。
6. 数値例:ETH/USDC(v2型50/50)× パーペ・ショート
初期条件:ETH=2,000 USDC。LPに総額20,000 USDC相当を提供(ETH=10,000/USDC=10,000)。
よってETH在庫は約QETH=5、先物ショートは5 ETHで開始。
ケースA:ETHが+20%(2,400)に上昇、30日経過
- LP側:インパーマネントロスが発生。ただし出来高回転により手数料収入(例:年率20%相当 → 30日で約1.67%)を獲得。
- デリバ側:ショート5 ETHに+400 USDC/ETHの評価益=+2,000 USDC。ファンディングが+年率5%なら30日で約+0.41%が上乗せ。
トータルでは、LPのIL(負)+手数料(正)+ショートの評価益(正)+ファンディング(市場次第)の合算で、価格方向のブレが圧縮されることが分かります。
ケースB:ETHが−20%(1,600)に下落、30日経過
- LP側:在庫がETH寄りにシフト。HODLよりは下げ耐性があるが、評価額は低下。
- デリバ側:ショートの評価益が拡大。ファンディングがマイナスならコスト増だが、先物限月への切替で抑制可能。
示唆:価格がどちらに動いても、評価損益の多くを相殺でき、残差として手数料(+ベーシス/ファンディング)が残りやすい構造をつくれます。
7. 実務のツボ
- ヘッジ過不足に敏感に:LP在庫は価格で動く。完全1:1より、やや控えめ(0.9倍)から開始して調整。
- ファンディング反転に備える:ショート支払いが重くなれば限月先物に切替、もしくはデルタ調整を小まめに。
- 手数料と回転率を優先:同じTVLでも出来高の多いプールを。v3は狭レンジで回転率を上げるが、レンジ外リスクに注意。
- ガス・MEV対策:混雑時間を避け、最大手数料上限とスリッページ許容をタイトに。必要に応じてプライベートRPC。
- ステーブルの選定:USDC/USDT/DAIなどはペッグ崩れ確率とブリッジ/チェーン固有リスクを把握。
8. 集中流動性(v3)での応用
v3では価格レンジを指定して流動性を集中でき、同資本で手数料効率を引き上げられます。一方、レンジ外に出ると実質片側在庫となりデルタが跳ねます。対策は:
- レンジを段階分割:中心±5%、±10%など複数レンジで在庫の断層を形成。
- 自動リバランス・ボット:価格乖離や出来高をトリガーに小刻みに補充。
- ヘッジ連携:各レンジの想定在庫に対してヘッジ比率のプリセットを用意。
9. リスク一覧
- 清算・追証リスク:デリバの証拠金不足は禁物。余力広め、レバ低め。
- ファンディング変動:長期の支払い超過はリターンを侵食。先物乗換えで抑制。
- スマートコントラクト・ブリッジ:監査・実績・分散度・運営体制を確認。
- ステーブルペッグ・チェーン固有:チェーン停止、手数料急騰、MEVの極端化など。
- レンジ外化(v3):片側在庫化でヘッジ過不足が急拡大。
10. まとめ:価格を“いなして”回転を取る
LP単体は価格方向に弱みがありますが、先物/パーペでデルタを打ち消すと、価格をいなしながら出来高に応じた手数料を取りにいけます。ファンディングや先物ベーシスが味方すれば、さらに上積みが期待できます。鍵はヘッジの精度とコスト管理です。小さく始め、ドリフト許容幅・再調整頻度・証拠金余力の3点を数値で固定化し、運用ルールとして回すところまで落とし込めば、再現性は一気に上がります。

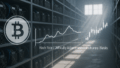

コメント