要旨:本稿は、パーペチュアル(無期限先物)と限月先物(デリバティブ取引所の期日付先物)を同時に用いる「カーブ・トレード」の実務フローを、個人投資家が再現できる水準まで具体化します。狙いは二つの歪み——ベーシス(先物と現物の価格差)と資金調達率(Funding)——を同時に取り、マーケット方向性への依存度を抑えつつ、日次で安定した損益カーブを作ることにあります。
前提知識の整理:パーペチュアルは理論上、現物価格にアンカーされ、乖離を抑えるために資金調達率の授受が発生します。一方、限月先物は期日に現物へ収斂する性質があり、キャリー(保管・金利・便益)と需給が先物カーブの形状(コンタンゴ/バックワーデーション)を決めます。暗号資産市場では、資金調達率が短期的な需給、限月ベーシスがより中期的な需給・金利を反映しやすく、二者のズレが恒常的に発生します。
戦略の骨子:同一アセット(例:BTC または ETH)について、パーペチュアルの建玉と同銘柄の最近限または次限の先物建玉を反対方向で同時構築します。代表例は、パーペチュアル・ショート+限月先物ロング(正のFundingを受け取りつつ、限月ベーシスの縮小を取りに行く)です。逆にFundingがマイナスで目立つ場合や、限月が過度なバック気味の時は、パーペチュアル・ロング+限月先物ショートのレジームが有利になります。
エッジの源泉:第一に、資金調達率は数時間単位でリセットされ、極端値は需給の行き過ぎを示しやすい。第二に、限月ベーシスは参加者の資金制約やヘッジ需要で歪みやすく、期日接近とともに収斂圧力が強まります。第三に、両市場の流動性提供主体が異なることで、ショートカバー/ロングスクイーズのタイミングが一致せず、分散的にプレミアムが回収できます。
具体例:BTC での構築手順(概念)
① 銘柄選定:出来高と板厚が十分な BTC または ETH を優先。小型アルトはカーブの歪みが大きくても清算リスクとスリッページが跳ねやすい。
② 歪みの計測:直近24〜72時間の資金調達率の加重平均とボラティリティ、さらに最近限・次限先物の年率換算ベーシス(先物価格−現物価格)/現物価格×年率を算出。目安として、Funding 年率換算 +15〜+40% が継続、かつ限月ベーシスが年率 +5〜+20% 程度の「並立」なら、Perp ショート+限月ロングが候補。
③ ロット設計:想定ボラ(例:日次年率化 60〜90%)に対し、証拠金率と清算距離を逆算。二市場合算のデルタをほぼ中立(|Δ|≦5〜10%)に保つロットで発注。必要に応じてミニサイズの現物で微調整。
④ 約定とヘッジ:成行は避け、指値で分割約定。約定後、ネット・デルタと証拠金余力(維持率)を再計算し、許容外なら即時リバランス。スプレッド拡大時のスリッページを日次の期待収益(Funding+ベーシス収斂の合計)の30〜50%以内に制限する。
⑤ モニタリング:Funding 予告値と実績、先物カーブ形状の変化(コンタンゴ→フラット→バック)を監視。急変時は機械的にクローズ、または逆レジームへスイッチ。
損益ドライバーの分解
・資金調達率 PnL:パーペチュアルで受け取る(または支払う)Funding の累積。高プラスFundingでショートしていれば受取が期待値。
・ベーシス収斂 PnL:限月先物の期日接近で現物に近づく効果。ロングならプレミアム縮小(またはディスカウント縮小)で上振れ。
・マークトゥマーケット:二市場の価格変動で生じる評価損益。デルタ中立でも一時的なベーシス拡大で含み損が出うる。
・コスト:手数料、資金調達、借入金利、ブローカー手数料、スプレッド、滑り。
リスク管理(落とし穴と回避策)
・ベーシス拡大の踏み上げ:ニュースイベントやファンディング急騰で先物プレミアムがさらに拡大し、含み損→強制ロスの危険。対策はロット縮小、分割構築、清算距離の厚取り、VAR ベースの上限設定。
・Funding レジーム転換:プラス→マイナスへ反転すると期待キャリーが消滅。対策は直近のOI(建玉)変化と板主導の短期モメンタムを併観し、予告値が閾値を跨いだら自動でクローズ。
・ベーシスの一極集中:一つの限月だけ歪むケース。ヘッジは最近限・次限で分散し、スプレッドの相関崩壊に備える。
・資金調達の決済タイミング差:取引所ごとに支払いタイミングが異なる。受け取り見込みに対し、約定・換算レート差で実入りが減る。複数取引所を使う場合はタイムテーブルを揃える。
・資本効率と手数料:両建ては手数料が二重化。VIP ティアやMM プログラムを活用し、実効コストを Funding+ベーシスの合計期待値の30%以下に抑える。
発注アルゴリズムの最小構成(擬似)
・入力:現物指数価格 I、パーペチュアル価格 P、限月先物価格 F、予告Funding f、先物残存日数 T。
・判定:年率Funding = f×年換算、年率ベーシス = (F−I)/I×(365/T)。
・シグナル:年率Funding ≧ +15% かつ 年率ベーシス ≧ +5% → Perp ショート+限月ロング。年率Funding ≦ −10% かつ 年率ベーシス ≦ −3% → Perp ロング+限月ショート。
・サイズ:目標Δ=0、|Δ|≦10% となるロット。スリッページ見込み ≦ 合成期待値×0.5。
・イグジット:年率Funding の符号反転、年率ベーシスの半減達成、またはVAR超過で全クローズ。
バックテストとライブ移行
① データ取得:指数価格、Perp 価格、各限月先物価格、Funding 実績・予告、出来高、OI。分足〜時足で十分。
② 検証設計:過剰最適化を避け、しきい値を粗く(例:Funding +10/15/20%、ベーシス +3/5/8%)。費用はテイカー想定+スリッページ固定。
③ 指標:日次シャープ、マックスDD、hit ratio、右肩下がり相場・急騰相場の頑健性。Funding の寄与とベーシスの寄与を分離表示。
④ パラの堅牢性:銘柄別・取引所別に同一パラを当て、勝ち筋が共通するかを確認。取引所特有の癖(資金調達タイミング、指数バスケット差)に敏感なモデルは縮小配分。
実運用のTips(具体)
・複数限月の分散:最近限と次限で50/50に分けると、期近イベントのギャップに強い。
・Funding の「山」を跨ぐ:支払い直前の急速な価格修正で逆行しがち。直前数分の約定は避け、イベント後の再構築も選択肢。
・指数乖離の監視:取引所指数の構成現物が薄いと異常値が出る。異所の指数とクロスチェック。
・スプレッド板の深さ:限月の板が薄いと一撃でベーシスが飛ぶ。板厚が薄い時間帯(週末・早朝)はサイズを半減。
・税務・損益管理:パーペチュアルと先物で決済タイミングがズレると損益の確定時期がズレる。日次で評価と受渡の両方を記録。
ケーススタディ(数値イメージ)
・市場条件:BTC 現物 10,000、Perp 10,050、限月(30日)10,200、予告Funding +0.01%/8h。
・年率換算:Funding ≈ +11%(0.01%×3×365)、ベーシス ≈ +73%((10,200−10,000)/10,000×365/30)。
・構築:Perp 1BTC ショート、限月 1BTC ロング。初期Δ約 −0.02BTC を現物 0.02BTC ロングで微調整。
・期待値:Funding 受取 ≈ 1.1%/月相当、ベーシス収斂が半分進めば ≈ 36%/年相当(30日換算)。費用合計がこの半分以内なら妙味。
・リスク:急騰局面の更なるプレミアム拡大で含み損。清算距離を広く、証拠金 2.0〜2.5倍余裕で対応。
運用チェックリスト
・銘柄、取引所、限月の選定根拠は明確か。
・Funding 実績と予告が一貫しているか。急変シグナルは何か。
・ベーシスの年率換算値、残存日数、OI の変化を毎日記録しているか。
・スリッページと手数料の実測が期待値の何%か。
・クローズ条件(閾値到達、VAR超過、イベント前日ルールなど)が自動化されているか。
拡張:カレンダースプレッドの重ね掛け:Perp と最近限に加え、次限ショートを重ねる三者スプレッドで、期近・期先の形状変化にベット。パラの自由度が上がる反面、板薄と手数料でエッジが溶けやすい。サイズは段階導入が無難です。
まとめ:パーペチュアルと限月先物のカーブ・トレードは、方向性相場でも「キャリー×収斂×裁定」の三層で期待値源泉を持てる、数少ない個人適用可能なストラテジーです。鍵は「歪みの同時観測」「サイズの節度」「清算距離の厚取り」「自動クローズ基準の遵守」。小さく始め、データで増やす——これが生存率を高める王道です。

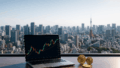

コメント