対象は主に日本株の現物投資です。信用取引やデリバティブの前に、まずは現物で勝ち筋の型を作ることを目的にします。記事内の数式は中学数学レベルで理解できますので、安心して読み進めてください。
- なぜ「配当×PBR×ROE」なのか
- 各指標の定義と直感
- 指標の関係式:PBRとROEは理屈でつながる
- 三点スクリーニングの基本ルール
- 数式とチェックポイント:指標の裏にある現実
- 具体例:仮想銘柄A・B・Cの比較
- 売買ルール案:機械的に運用する
- 運用サイズと分散の考え方
- 銘柄発掘の手順(初心者向け作業フロー)
- ミニ・ケーススタディ:投資額100万円、年4回の見直し
- よくある落とし穴と回避策
- 発展編:増配力と自己株買いをスコア化する
- 超シンプル・メンテナンス手順(3ヶ月ごと)
- リスク管理:数字で線を引く
- Q&A:よくある疑問
- まとめ:ルールで「迷い」を減らす
- 付録A:数式・指標の早見帳
- 付録B:仮想ポートフォリオ運用ログ(抜粋)
- 付録C:チェックリスト
- 付録D:初心者のための時間管理とメンタル設計
なぜ「配当×PBR×ROE」なのか
株式の魅力は二つに分かれます。一つはキャピタルゲイン(値上がり益)、もう一つはインカムゲイン(配当)です。どちらも「企業の稼ぐ力」と「市場が付ける価格」によって決まります。この二つを橋渡しするのが、PBR(株価純資産倍率)とROE(自己資本利益率)です。
PBRは「一株あたり純資産(BPS)」に対して株価が何倍かを示す指標で、安さ(バリュエーション)を測ります。ROEは自己資本をどれだけ効率よく利益に変えているかを示し、稼ぐ力(収益性)を測ります。さらに配当利回りは株主に還元される現金フローの利回りで、投資回収速度の一つの目安になります。
三点を同時に見ることで、「安く買って、稼ぐ会社を持ち、現金も受け取る」という投資の基本原則をシンプルに実装できます。
各指標の定義と直感
配当利回り(Dividend Yield)
定義:配当利回り=一株当たり年間配当金 ÷ 株価。
直感:株価1000円、年間配当40円なら利回り4%。銀行預金の利息に近い感覚ですが、株価の変動と減配リスクを伴います。
PBR(Price to Book Ratio)
定義:PBR=株価 ÷ 一株当たり純資産(BPS)。
直感:会社の「簿価純資産」に対して、いまの株価が割高か割安かを測る物差し。1倍未満は「解散価値割れ」とも呼ばれますが、資産の質と収益力を無視してはいけません。
ROE(Return on Equity)
定義:ROE=当期純利益 ÷ 自己資本。
直感:株主のお金をどれだけ効率よく増やしているか。長期的にROEが高いほど、企業価値の複利成長が期待しやすくなります。
指標の関係式:PBRとROEは理屈でつながる
企業価値は理論上、株主資本コスト(要求リターン)とROEの関係で決まります。単純化すると、PBRは「ROE ÷ 株主資本コスト」に概ね比例します。例えば資本コスト8%の市場で、ROEが8%ならPBRは1倍前後、ROEが12%ならPBRは1.5倍前後になりやすい、という直感です。
つまりPBRが低いのにROEが高い企業は、市場の見誤りか、ROEが一時的で続かないかのどちらかであることが多い。ここを見極めるのが投資の肝になります。
三点スクリーニングの基本ルール
初心者が迷わないための、シンプルで再現しやすい暫定ルールを置きます。実運用での微調整は後述します。
暫定条件:
① 配当利回り:3.0%以上(ただし極端な高利回り=減配前兆を避けるため8%以下)
② PBR:1.2倍以下(資産面の「安さ」確保)
③ ROE:8%以上(業界平均をやや上回る水準)
④ 流動性:日次出来高が50万株以上(売買執行の安定性)
⑤ 直近3年で減配なし(配当方針の安定性)
この条件は「安さ・稼ぐ力・現金還元・取引可能性・継続性」を同時に担保するための最低限の枠組みです。
数式とチェックポイント:指標の裏にある現実
1)配当性向=配当金総額 ÷ 純利益。利回りだけでなく「無理のない配当か」を必ず見るべきです。配当性向が80%を超える状態が続くと、景気後退で減配リスクが高まります。
2)自己資本比率=自己資本 ÷ 総資産。ROEが高くても負債依存が強すぎると、景気悪化で急落しやすい。適度なレバレッジと安定的なキャッシュフローがバランス良い企業像です。
3)営業CFとフリーCF:配当は現金で支払います。営業キャッシュフローが安定してプラス、設備投資を差し引いたフリーCFが配当を賄えているかは最重要です。
具体例:仮想銘柄A・B・Cの比較
銘柄A:配当利回り4.2%、PBR0.8倍、ROE9.5%。営業CF安定。配当性向40%。在庫回転良好。——合格。割安かつ稼げており、現金創出力も十分。
銘柄B:配当利回り7.5%、PBR0.5倍、ROE3.0%。配当性向120%。——不合格。利回りは高いが、利益が乏しく配当を借金と資産売却で維持する恐れ。いわゆる「高配当トラップ」。
銘柄C:配当利回り2.2%、PBR1.1倍、ROE15%。——保留。利回りが低いため本戦略の主旨から外れるが、増配余地が高い成長配当銘柄の予備軍として監視は有効。
売買ルール案:機械的に運用する
買いのトリガー
・三点条件を全て満たすと同時に、直近20日移動平均線を終値が上回るタイミングで1単位買付。
・一度に全資金を入れず、候補5〜10銘柄を分散購入します。
売りのトリガー
・PBRが目標の1.2倍を大きく超え、かつROEが悪化(8%割れ)した場合は利益確定。
・ファンダが維持されても株価が購入後に10%下落したら損切り。トレーリングストップを採用し、最高値から-12%で利確。
配当再投資
・受け取った配当は、同じ三点条件を満たす銘柄群に再配分して複利化します。
運用サイズと分散の考え方
初心者にとって最大の失敗は「一銘柄への集中」と「含み損の塩漬け」です。候補を最低5銘柄、できれば10〜20銘柄に分け、各ポジションは総資金の5〜10%を上限にします。業種分散も心がけ、景気敏感(素材・自動車)とディフェンシブ(通信・医薬)を混ぜると安定します。
銘柄発掘の手順(初心者向け作業フロー)
① スクリーニングツールで条件を入力(配当3〜8%、PBR≤1.2、ROE≥8%、出来高フィルタ)。
② 候補の財務諸表を確認:営業CF、フリーCF、配当性向、自己資本比率を一覧化。
③ 過去10年の配当履歴と方針をチェック。安定または増配傾向を優先。
④ 短期の需給確認:出来高、直近の価格トレンド。過熱感は避ける。
⑤ 5〜10銘柄に分散して小さく購入。3ヶ月に一度ルールに照らして入替。
ミニ・ケーススタディ:投資額100万円、年4回の見直し
初期資金100万円を10銘柄に10万円ずつ配分。平均配当利回り4%、配当性向50%、PBR0.9、ROE10%のポートフォリオを想定します。株価が横ばいでも、年間約4万円の配当が入り、源泉徴収後の手取りを再投資すると、単純計算で約4%の基礎リターンが見込めます。これに割安修正(PBRが0.9→1.1)によるキャピタルゲインが年2〜3%程度乗れば、年6〜7%の合成リターンは十分現実的です。
もちろん、景気後退や減益局面では逆風を受けます。その場合でも「ROEが潰れていないか」「配当性向が跳ね上がっていないか」を監視し、基準を外れた銘柄は躊躇せず入替える運用が有効です。
よくある落とし穴と回避策
高配当トラップ:一時的な特別配や減益で利回りが見かけ上高いだけの銘柄は避けます。配当性向とキャッシュフローで裏取りをします。
資産は厚いが稼げない会社:PBRは低いがROEも低い場合、値上がりには時間がかかります。明確な経営改革の兆し(不採算資産の売却、資本効率改善策)がなければ中心から外す判断も必要です。
一発の悪材料:訴訟、巨額減損、コモディティ価格急落などの事象は、スクリーニングでは拾えません。ニュースチェックを習慣化しましょう。
発展編:増配力と自己株買いをスコア化する
本戦略のコアは三点ですが、増配率と自己株買いを加点要素にすると、より「株主還元に積極的な企業」を選びやすくなります。例えば、過去5年で増配年が3回以上、自己株買い実施回数が2回以上の銘柄にはスコア+1を付与し、採点上位から組み入れるといった具合です。
超シンプル・メンテナンス手順(3ヶ月ごと)
① 現在保有の各銘柄が三点条件を満たしているかチェック。
② 外れた銘柄は原則売却し、新たに条件を満たす銘柄に入替。
③ 配当の受け取りと再投資。
④ リスク水準(最大ドローダウン見込、ポジションサイズ)を見直し。
リスク管理:数字で線を引く
・損切り:銘柄ごとの許容損失は-10%まで。全体のピークからの最大ドローダウンが-15%を超えたら現金比率を一時的に高めます。
・トレーリングストップ:最高値から-12%で自動利確。利益を守ることが複利には最重要です。
・リスク・リワード比:1取引あたり、期待利益20%、許容損失10%なら比率2。比率1未満の取引は見送り。
Q&A:よくある疑問
Q1. 配当課税で不利では?
配当再投資の複利効果は課税後でも機能します。税率を織り込んだ手取り利回りで評価します。
Q2. 金利上昇局面では?
資本コスト上昇によりPBRの上値は抑えられます。ROEの高い企業、価格決定力のあるセクターを優先します。
Q3. 景気後退が来たら?
配当性向の急騰とROEの崩れを早期に検知し、現金比率を上げる運用へ移行します。
まとめ:ルールで「迷い」を減らす
配当利回り・PBR・ROEの三点は、誰でも同じ式で計算できます。だからこそ、ルール化して守れるかが差になります。本稿の条件は完璧ではありませんが、初心者が「負けにくい」ポートフォリオを作るための骨格として十分機能します。まずは小額で、3ヶ月サイクルで回し、数字とともに自分の判断を記録することから始めましょう。
付録A:数式・指標の早見帳
・BPS=純資産 ÷ 発行済株式数。
・PBR=株価 ÷ BPS。
・EPS=当期純利益 ÷ 発行済株式数。
・PER=株価 ÷ EPS。
・ROE=当期純利益 ÷ 自己資本。
・配当利回り=一株配当 ÷ 株価。
・配当性向=一株配当 ÷ EPS。
・自己資本比率=自己資本 ÷ 総資産。
・フリーCF=営業CF − 投資CF。
【例題】BPS=1200円、株価=900円ならPBR=0.75倍。EPS=90円、配当=45円なら配当性向=50%、配当利回り=5%。ROEが10%で自己資本が増えるとBPSは年々増加します。株価が横ばいでもPBRは自然と切り上がりやすく、時間が味方になります。
付録B:仮想ポートフォリオ運用ログ(抜粋)
第1四半期:候補銘柄10社を均等購入。平均利回り4.1%。ニュースで一社に訴訟リスク、保有比率を半分へ。
第2四半期:PBR上昇で二社を利確、代わりに新規二社を組み入れ。配当4.3%に上昇。
第3四半期:景気減速で全体に軟調。自己資本比率の低い銘柄を整理。
第4四半期:決算でROE改善の兆し、自己株買いの発表を受けて一社を追加購入。
こうした定性的メモは、数値条件の外側にある「企業の物語」を補完し、判断の精度を上げます。
付録C:チェックリスト
□ 配当3〜8%か。
□ PBR≤1.2か。
□ ROE≥8%か。
□ 配当性向≤70%(平常時)か。
□ 営業CFが安定しフリーCFで配当を賄えるか。
□ 自己資本比率は健全か。
□ 日次出来高は十分か。
□ 過去3年で減配がないか。
□ 重要な訴訟・減損・規制リスクはないか。
付録D:初心者のための時間管理とメンタル設計
投資で継続するためには、時間の使い方と感情の波を淡々と整える設計が不可欠です。日々の価格変動に反応して判断を変えるのではなく、四半期ごとの決算と配当の実績という「遅い情報」に軸足を置きます。日中は板やティッカーを見ず、週末の1〜2時間で十分です。これは戦略の一貫性を守る最短ルートです。
また、ポジションの含み損益を日次で追跡しないことも効果的です。評価損は多くの場合、情報の更新ではなく価格のノイズによって生じます。判断の起点を「指標の変化」に限定すると、売買回転は自然に下がり、税コストも抑えられます。
最後に、手帳やスプレッドシートに「買付理由」「売却条件」「想定リスク」を箇条書きではなく文章で残しましょう。自分の言葉で書いたテキストは、将来の自分にとって最も説得力のあるチェック機能になります。

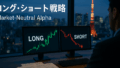
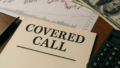
コメント