本稿では、株式投資の超基本指標であるPER(株価収益率)を、単なる「割安・割高の目安」ではなく、実際にエントリーや利益確定に使える道具として再設計します。初心者の方がすぐ実践できるよう、計算式の確認から、逆PER(=益回り)での金利比較、EPSの調整、ガイダンスの読み方、セクター別レンジ、ケーススタディ、スクリーニング手順、そして“使える”売買ルール例までを一気通貫で解説します。すべて平易な言葉で、です・ます調でお届けします。
- 1. PERの基礎 ─ 定義・式・直感
- 2. 逆PER(益回り)の活用 ─ 金利との共通言語化
- 3. トレーリングPERとフォワードPER ─ どちらを見るべきか
- 4. PERは文脈が命 ─ セクター・成長率・金利・景気
- 5. EPSの落とし穴 ─ 一過性・会計差・希薄化
- 6. 価値の二面性 ─ PER×成長率(PEG)とROE
- 7. ケーススタディ ─ 3つの銘柄タイプを数字で読む
- 8. スクリーニング手順(無料ツール+Excel前提)
- 9. 失敗を避ける8つのチェックポイント
- 10. 初心者向け“即応”ルール(テンプレ)
- 11. 逆PERと配当利回りの二刀流
- 12. マクロ環境の取り込み方
- 13. 実践ワーク:仮想スクリーニング
- 14. よくある質問(FAQ)
- 15. まとめ ─ “倍数”から“利回り”へ
1. PERの基礎 ─ 定義・式・直感
PER(Price Earnings Ratio)は「株価がその会社の年間利益の何倍か」を表す指標です。式は以下のとおりです。
PER = 株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)
たとえば株価が2,000円、EPSが100円ならPERは20倍です。直感的には「投資家が利益の20年分を先に支払っている」イメージです。PERは小さいほど一見“割安”に見えますが、企業の成長率、利益の安定性、資本効率、財務レバレッジ、金利水準、景気循環などで“適正水準”は大きく変わります。初心者の方は、まずPER単体ではなく、逆PER(益回り)という見方もセットで覚えると、判断が格段に速くなります。
2. 逆PER(益回り)の活用 ─ 金利との共通言語化
PERをひっくり返した指標が逆PER(Earnings Yield、益回り)です。
逆PER(益回り, %) = EPS ÷ 株価 × 100 = 100 ÷ PER
PER20倍なら逆PERは5%です。債券の利回りと同じ“%表記”になるので、金利や社債利回り、預金金利と比較しやすくなります。投資判断は、以下のような対話に置き換えられます。
- この銘柄の逆PERは5%。同格の社債は4%。ただし株は利益が増えれば益回りがさらに上がる(≒将来のPERが下がる)可能性がある。
- 逆に、利益が落ちれば益回りは下がる。配当利回りだけでなく、益回りと成長率のバランスで評価する。
初心者の方は「PER=倍数」「逆PER=利回り」という二軸で物事を見るだけで、ニュースや決算を数字で整理できるようになります。
3. トレーリングPERとフォワードPER ─ どちらを見るべきか
PERには大きく2種類あります。
- トレーリングPER:直近12か月の実績EPSで計算。過去の実績に基づくためブレが少ない一方、景気転換点では遅れます。
- フォワードPER:会社計画やアナリスト予想の来期EPSで計算。将来を織り込める一方、予想が外れるリスクがあります。
初心者の運用では、基本はトレーリングPER、トリガーはフォワードPERが実務的です。すなわち、実績での割高・割安レンジを把握しつつ、ガイダンスやコンセンサスの上方修正で「フォワードPERが一気に妥当化される瞬間」を捉えます。
4. PERは文脈が命 ─ セクター・成長率・金利・景気
PERには「単体の正解値」は存在しません。セクターによってレンジがまるで違うからです。安定配当型の公益・通信は低め、無形資産でスケールするソフトウェアは高め、といった具合です。さらに金利が上がる局面では将来利益の割引率が上がるため、高PER株ほど圧迫されやすい傾向があります。
| タイプ | 利益の性質 | 一般的なPERレンジ(参考) | 注目点 |
|---|---|---|---|
| 公益・通信 | 安定・低成長 | 10–18倍 | 配当と規制の継続性 |
| 製造・景気敏感 | 循環・中成長 | 8–20倍 | 在庫循環と為替、受注 |
| 消費・小売 | 安定〜中成長 | 12–25倍 | 同店売上、粗利率の持続性 |
| ソフトウェア | 高成長・高粗利 | 25–60倍 | 解約率、LTV/CAC、SaaS指標 |
上記はあくまで目安です。重要なのは、その企業固有の“正常収益力”に対していま何倍かという視点です。
5. EPSの落とし穴 ─ 一過性・会計差・希薄化
PERの分母であるEPSは“きれい”とは限りません。実務上は以下を必ず点検します。
- 一過性の利益・損失の除外:固定資産売却益、減損、訴訟関連などは調整(Normalized EPS)。
- 希薄化効果:ストックオプション、新株予約権、転換社債は希薄化後EPS(Diluted EPS)で確認。
- 会計基準差:IFRSとJGAAP/USGAAPで売上計上や減価償却のタイミングが異なる場合があります。
- 連結範囲・持分法:持分法適用会社の利益は安定性を見極めます。
初心者の方は、まずは「調整後EPS」を自分なりに作る習慣をつけると、PERの精度が一気に上がります。
6. 価値の二面性 ─ PER×成長率(PEG)とROE
PERが高いのに正当化される典型は「高成長+高還元余地」です。ここで便利なのがPEG(PER ÷ 利益成長率)です。
PEG ≒ PER ÷ EPS成長率(%)
経験則ではPEGが1倍近辺なら許容、2倍超は警戒、という使い方をします(あくまで目安)。さらにROE(自己資本利益率)が高く、利益が現金化しやすい(CFの質が高い)企業は、PERが多少高くても許容されがちです。
7. ケーススタディ ─ 3つの銘柄タイプを数字で読む
7-1. 安定成熟株(配当重視)
仮にA社の株価が2,000円、EPSが160円、配当が1株60円(配当性向38%)とします。PERは12.5倍、逆PERは8.0%です。長期社債が4%の環境なら、益回り8%は魅力的に見えます。ポイントは利益の安定性と減配リスクです。減配しにくいキャッシュフロー構造なら、PERが15倍(株価2,400円)程度までのリレーティング余地を見込みやすくなります。
| 項目 | 数値 | 示唆 |
|---|---|---|
| PER | 12.5倍 | セクター中央値よりやや割安 |
| 逆PER | 8.0% | 社債4%より相対優位 |
| 配当利回り | 3.0% | 増配余地あり |
| ROE | 12% | 資本効率は合格 |
売買の型:PER12倍以下で仕込み、配当維持の確認とともにPER15倍で一部利確、残りはトレーリングストップで追随します。
7-2. 高成長株(SaaS型)
B社は売上成長率30%、営業CF黒字化が進行中。来期EPSはまだ小さいためフォワードPERは60倍に見えます。ただしLTV/CACやNRR(解約率の逆、継続率)などのソフト指標が改善しているなら、2年後のEPS急拡大でPERが自然に低下する可能性があります。PEG視点で1.5倍程度なら継続保有を検討します。
売買の型:ガイダンス上方修正でフォワードPERが40倍台へ低下するイベントを“買いトリガー”に設定します。失速時は「売上成長率が20%を2四半期連続で割る」を撤退ラインにします。
7-3. 景気循環株(自動車・半導体等)
C社は在庫調整の最終局面で利益が落ち込み、トレーリングPERは一見30倍と割高に見えます。しかし来期は需給正常化でEPSが2倍になる見通しです。この場合、フォワードPERを主軸にします。フォワードPERが15倍なら、正常収益力のレンジ(10–18倍)に回帰するシナリオを描きます。
8. スクリーニング手順(無料ツール+Excel前提)
- 時価総額と流動性で最低基準を設定します(例:時価総額500億円以上、平均出来高基準)。
- トレーリングPERとフォワードPERを同時に取得し、逆PER(=100÷PER)も列追加します。
- セクター別中央値と比較できる列を作り、“企業の現在地”を相対値で把握します。
- EPSの一過性要因の有無、希薄化の有無をメモ列で管理します。
- 最終候補に対しては、売上成長率、粗利率、ROE、営業CFの4点を最低限チェックします。
Excelの例:=100/[@PER]で逆PERを計算し、=IF([@希薄化]="有","注意","OK")などの簡易フラグを活用します。
9. 失敗を避ける8つのチェックポイント
- 赤字企業にPERを当てない:EPSがマイナスならPERは無意味です(代わりにPSRやEV/売上を使用)。
- 一過性利益で割安錯覚:固定資産売却益でEPSが跳ねた翌期は注意します。
- 超高PERの金利感応度:金利上昇局面ではディスカウントの影響を受けやすいです。
- 為替と外需:輸出比率の高い企業は為替前提に敏感です。
- 決算期ズレ:同業他社との比較で決算期がずれていると見誤ります。
- 希薄化イベント:SO/CBの転換条件や発行余地を確認します。
- 会計方針の変更:収益認識の変更は EPS と成長率の連続性に影響します。
- PER“だけ”で買わない:最低限、成長・CF・ROE・バランスシートを併読します。
10. 初心者向け“即応”ルール(テンプレ)
完全自動ではありませんが、以下の3条件テンプレは再現性が高いです。
- 割安の入口:セクター中央値PERより15%以上低い、かつROE10%以上。
- 成長の確認:売上成長率が直近4四半期でプラス、営業CFもプラス。
- 需給の後押し:50日移動平均線が上向き、株価がその上にある。
出口:PERがセクター中央値+10%まで上昇で半分利確、残りは前日終値比-7%でトレーリングストップ。悪材料時は一括撤退。
11. 逆PERと配当利回りの二刀流
成熟株では、逆PER(益回り)と配当利回りの差が「内部留保からの将来還元余地」を示唆します。益回り8%、配当利回り3%なら、差の5%は再投資・自社株買い・将来増配の原資になりえます。ROEが高いほど、その再投資が複利で効いてきます。
12. マクロ環境の取り込み方
PERは割引率(主に長期金利)に強く影響されます。初心者でも、長期金利の方向性(上昇=逆風、低下=追い風)だけは把握しておきます。さらに、インフレが粘着的な局面では名目売上が伸びやすく、ある種の企業でEPSが予想以上に堅調になることがあります。ここでは価格転嫁力が鍵です。
13. 実践ワーク:仮想スクリーニング
次の3社(仮想)から、どれを優先するか考えます。
| 会社 | PER | 逆PER | 売上成長 | ROE | 営業CF | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A(公益) | 13倍 | 7.7% | +2% | 9% | + | 配当厚い |
| B(SaaS) | 45倍 | 2.2% | +30% | 15% | ±0 | 解約率改善 |
| C(製造) | 11倍 | 9.1% | +8% | 12% | + | 在庫正常化 |
答えは投資方針によります。収益の安定性と利回り重視ならA、堅実なリレーティングならC、高リターン狙いでボラ許容ならBです。重要なのは、自分のリスク許容度に合わせて選ぶことです。
14. よくある質問(FAQ)
Q1:PERの「適正値」は何倍ですか?
A:企業や業種、金利で異なります。必ずセクター相対と成長・ROEを併読してください。
Q2:赤字の成長株はどう見ますか?
A:PERは使えません。売上成長や粗利率、ユニットエコノミクス、キャッシュバーンの改善を見ます。
Q3:配当利回りとどちらが大事ですか?
A:両輪です。益回りが高くCFの質が良ければ、将来の増配や自社株買いの余地が広がります。
15. まとめ ─ “倍数”から“利回り”へ
PERは「割安・割高」のラベルではなく、益回りという共通言語で他の資産と比べるための窓です。逆PERで金利と比較し、EPSを正しく調整し、セクターの文脈でレンジを把握する。そこにシンプルなテクニカルを重ねれば、初心者の方でも十分に再現性のある運用を組み立てられます。今日から銘柄表のPER列を「100÷PER」という目で見直してみてください。
※本稿は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の推奨や将来の成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。


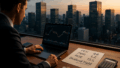
コメント