本稿は、PTS夜間の価格動向と、翌営業日の寄り付きギャップを活用して利益機会を狙うデイトレ戦略を、初心者でも実装できる手順で完全解説します。一般論を排し、銘柄選定 → 監視リスト作成 → 板読み → 注文 → リスク管理 → 検証まで一気通貫で整理します。
1. なぜ「PTS×寄り付きギャップ」なのか
PTS(私設取引システム)では、取引時間外に材料が出た銘柄が素早く価格調整されます。翌朝の東証寄り付きは、夜間の情報・需給を反映しつつも、板厚・アルゴの流入・寄り前の気配訂正などにより、新たな歪み(ギャップ)が発生しやすい時間帯です。ここに短期の機会があります。
本戦略は、次の2系統に分かれます。
- ギャップ・リバーサル型:PTSで先行しすぎた価格が寄り付き後に反転しやすい歪みを狙う。
- ギャップ・モメンタム型:強い需給(出来高・ニュース)を伴う場合、寄り付き後のトレンド継続を狙う。
どちらを選ぶかは、材料の質・PTS出来高・翌朝の板気配・寄り成り/指値の突かれ方で判断します。
2. PTSの基礎と「寄り付き」メカニズム
PTSは、取引所外の私設システムでの株式売買です。多くの個人がアクセス可能で、材料が出た夜間に先行して価格が動きます。翌朝の寄り付きは板寄せ方式で、成行と指値が交差する価格で約定します。寄り直前は気配が大きく動くため、表示板だけでなく出来高・歩み値・指値の堆積を総合判断する必要があります。
初心者ほど、寄り付き直前の「見かけの強弱」に振り回されがちです。寄り前の成行買いが分厚いのに、寄った瞬間に売り圧が出て失速—これはよくあるパターンです。
3. 戦略の全体像:ワークフロー
- 材料とPTS動向の抽出:夕方〜夜間に、決算・IR・レーティング・テーマ関連ニュースを収集。PTS価格変動と出来高を確認。
- 監視リスト化:流動性・ボラ・貸借区分・直近の信用残・規制有無をチェック。
- シナリオ分岐:翌朝の寄り前板で、リバーサル/モメンタムのどちらが適切かを判定。
- 注文設計:寄付成行 or 指値、IFD-OCO、逆指値、利確幅・損切幅、最大損失。
- 執行とモニタリング:寄り直後1〜15分の値動き特性を想定、逆指値の位置は流動性に応じてダイナミックに。
- 日次レビュー&記録:勝ち/負けの要因を定量化し、翌日以降のフィルタを更新。
4. 銘柄選定:最低限のフィルタ
初心者が実装するなら、まずは以下の守りのフィルタから始めましょう。
- 流動性:東証の平均売買代金が3億円/日以上。寄り直後にスリッページが出にくい。
- 価格帯:1株あたり500〜3,000円を目安。板の刻みが扱いやすい。
- ボラティリティ:直近20日ATRが株価の2.0〜6.0%程度。低すぎず高すぎない。
- 貸借銘柄かつ規制なし:空売りの可否はリバーサル戦略で効く。規制は避ける。
- PTS出来高:東証出来高の10〜30%に達する異常値は要注目。
- ニュースの質:単なる思惑ではなく、決算/業績修正/大型受注/ガイダンスなどの“数字”伴うものを優先。
5. 2つの基本戦略
5-1. ギャップ・リバーサル型(過剰反応の巻き戻し)
狙い:PTSで+7〜15%急騰(または-7〜-15%急落)し、翌朝の寄り付きで同方向にギャップした後、寄り直後に失速するパターンの逆張り。
前日条件:直近5日で連騰/連続陰線など片寄りがあるほど有効。PTS出来高は急増だが、歩み値は小口連発で分散していると過熱のサイン。
寄り前板:成行買い(売り)が厚く見えるが、指値板の厚さが近辺に集中。寄り成り後に一段の成行追随が入らない時は反転しやすい。
エントリー:寄り後、最初の1分足で高値(安値)を更新できないことを確認してから、逆方向に成行/指値で入る。極端なスリッページを避けるため、アグレッシブ指値が無難。
イグジット:初動の押し戻り幅(例:寄り値から±1.0〜1.8%)で利確指値。損切りは直近高値/安値の0.4〜0.8%外側。
5-2. ギャップ・モメンタム型(需給の継続)
狙い:ファンダ的に「数字の裏付け」が強く、PTSでの上げ下げが翌朝も継続しやすいケースを順張りで取る。
前日条件:直近の決算サプライズ、ガイダンス上方修正、ADR/先物の地合い追い風。PTS出来高が厚い買い(売り)の集中で構成されていると良い。
寄り前板:成行の厚みだけでなく、寄り後に食える板厚(実際に約定しやすい厚み)があるかが重要。
エントリー:寄付成行または寄り後の最初の押し/戻りで指値。半分だけ入る→押し目で追加の分割が有効。
イグジット:利確は1.0〜2.5%のレンジで分割。損切りはVWAPや5分足基準(例:VWAPを1ティック割ったら半分削る)。
6. ギャップの測り方とシグナル判定
ギャップ率=(寄り値 − 前日終値)/ 前日終値。さらに、PTS終値や寄り前気配との乖離も合わせて計算します。
- 過熱域(リバーサル向き):前日終値比で±7%超、かつPTS終値との乖離が寄りで縮小しない。
- 継続域(モメンタム向き):ギャップは±3〜7%で、寄り後に出来高急増・高値/安値更新。
初心者は、まず±3〜10%のギャップだけを対象にし、極端なギャップ(±15%以上)は回避するのが無難です。
7. 注文設計:寄付成行・指値・IFD-OCOの使い分け
寄り直後はスプレッドが広がりやすいため、成行=安全ではありません。次の原則を守ります。
- 原則:約定優先なら半分成行+半分指値。リバーサル狙いは極力指値でスリッページ抑制。
- 逆指値:約定後すぐに自動設定(OCO)。初動の振れ幅の0.6〜1.0倍を目安。
- 時間軸:想定保有は5〜30分。地合い悪化時は建てた瞬間から出口を決める。
- サイズ:1トレードあたり口座の0.5〜1.5%損失でロスカットが妥当。
8. ケーススタディ:3つの典型パターン
ケースA:過熱後の反転(リバーサル)
前日終値1,000円 → PTSで1,120円(+12%) → 寄り気配1,140円。寄り後、1分足で高値更新できず推移。1,130円割れでショート、戻り1,115円で利確、直近高値+0.6%に逆指値。
ケースB:数字を伴う継続(モメンタム)
売上・営業益の上方修正が強い。PTSで+5%、寄り+4%でスタート。最初の押し(+2.5%付近)で半分IN、VWAP維持を確認して追加、+1.2%/+2.0%で分割利確。
ケースC:気配だけ強く寄り天
寄り前は成行買いが厚いが、実際の板厚が伴わず、寄った瞬間に吸収される。1分足の高値不更新と出来高の減速をトリガーに逆張り。
9. データ取得とバックテスト(スプレッドシートでOK)
最初は無料の公開情報で十分です。前日終値・PTS終値・寄り値・寄り直後の高値/安値・出来高を日次で記録します。
- カラム設計:日付、銘柄、前日終値、PTS終値、寄り値、ギャップ率、寄り直後5分高値/安値、VWAP、出来高、戦略(R/M)、結果(%)、メモ。
- シグナル化:ギャップ率のレンジ、PTS出来高の倍率、寄り前板の厚みなどを数値化。
- 評価指標:勝率、平均損益%、プロフィットファクター、最大ドローダウン、1取引あたりの期待値。
- 最低件数:まずは100トレードを目標。次に地合い別(上昇/下落/レンジ)で分解。
初心者は、シンプルな基準(例:ギャップ±3〜7%、寄り後1分で高値/安値更新の有無)からスタートし、負けパターンを除外する形でフィルタを強化していきましょう。
10. リスク管理:よくある失敗を未然に防ぐ
- スリッページ:成行依存は避ける。分割約定+アグレッシブ指値、板の食われ方を注視。
- 誤発注:IFD-OCOのテンプレを用意し、約定直後に逆指値が入っているかを必ず確認。
- ニュースの誤読:「見出しは強いが、中身は一過性」—数字とガイダンス本文を重視。
- 規制・制度:増担保、空売り規制、信用代用ルールなどの変更に注意。
- 地合い:先物・セクターの地合いが逆風なら、サイズを半分に。
11. 実装のための環境整備
初心者でも再現性を高めるため、次を整えます。
- ブローカー:PTS対応、寄付成行・逆指値・IFD-OCO対応、手数料体系の明確さ。
- 画面設計:寄り前板、歩み値、ティックチャート、ニュース、先物、セクター強弱を同時表示。
- テンプレート:監視リスト、注文プリセット、トレード記録フォーマットを固定化。
12. 口座開設〜初回の実践フロー
- 口座開設:本人確認・マイナンバー・NISA/特定口座の選択。オンライン申込が最速。
- 取引環境のセット:PTSと東証、信用/現物、逆指値の可否を確認。デモ画面で発注練習。
- 最初の100トレード:ロットを最小にし、負け方の型を把握。週次でルールを1つだけ改善。
13. チェックリスト(印刷推奨)
- ギャップ対象は±3〜10%のみ/極端は除外
- PTS出来高は東証比10〜30%以上で注目
- ニュースは「数字」を最優先(見出しに惑わされない)
- 寄り前板:成行と近辺指値の厚みバランスを確認
- リバーサルは「1分高値/安値の不更新」を待ってから
- エントリーは半分成行+半分指値 or 指値中心
- OCOで逆指値を自動設定/想定保有5〜30分
- 日次レビューで「除外すべきパターン」を更新
14. 用語ミニ解説
- PTS
- 取引所外の私設市場。夜間に材料を織り込みやすい。
- 寄り付き
- 板寄せ方式での初回約定。成行と指値が交差する価格で成立。
- ギャップ率
- 寄り値と前日終値の乖離(%)。
- VWAP
- 出来高加重平均価格。短期の基準線として機能しやすい。
- IFD-OCO
- 新規と決済(利確・損切)を同時連携する注文方法。
15. まとめ:まずは「小さく・同じやり方で」
寄り付きは、一日の中で最も非効率が生まれやすい時間帯です。同じやり方を小さく回し、負けを減らすことが、結果的に最短距離になります。PTS×寄り付きギャップは、情報の先行と需給の再配分という構造的な要因に根ざすため、初心者にも学習効果が得やすい領域です。チェックリストに沿って、今日の寄りから一歩ずつ実装してみてください。

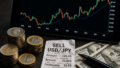

コメント