対象読者は、これからPTSを使い始める個人投資家です。専門用語はなるべく平易に言い換え、必要なものだけをピックアップして説明します。画面操作は証券会社によって異なりますが、考え方と順番がわかれば応用できます。なお、本記事では一般的な仕組みや代表的な発注設計の考え方を解説し、個別の銘柄推奨や将来収益の断定的記述は行いません。あくまで「どうすればコストと約定力のバランスを取れるのか」という実務の骨格を学ぶためのガイドです。
PTS夜間取引とは何か:東証との違いを最短で把握する
PTS(私設取引システム)は、証券会社や運営会社が提供する取引プラットフォームで、取引所(例:東証)とは別系統で注文をマッチングします。国内では、夜間に注文を出せるPTSが広く使われています。最大の違いは「取引時間」と「流動性の厚み」です。東証の立会時間は日中に集中しますが、PTSは夕方〜深夜にかけて取引します。夜間は投資家の参加者が減るため、板の厚みが薄く、スプレッド(最良買いと最良売りの差)が広がりやすくなります。これがコストの源泉です。
また、証券会社やPTS市場ごとに、成行の可否、逆指値の可否、呼値の刻み、手数料やポイント還元の取り扱いなどが異なります。さらに、SOR(スマート・オーダー・ルーティング)の挙動が、日中と夜間で違うケースもあります。まずは「自分が使う証券会社のPTS仕様」を確認し、成行不可であれば指値を基本とする、逆指値不可であれば価格監視を手動で行う、といった前提を押さえます。
口座準備:PTSに対応した証券会社を用意する
初めてPTSを使うときに高確率でつまずくのが、口座の設定です。まず、あなたが利用している証券会社がPTS夜間取引に対応しているか、ログイン後の設定画面で確認します。対応している場合でも、初回のみ利用申込が必要なことがあります。また、信用取引でPTSが利用できる範囲は証券会社によって差があるため、現物・信用いずれで発注するのかを明確にします。
口座準備の実務ステップは次のとおりです。
- ログイン後、「取引設定」または「取引口座」から、PTSの利用可否を確認します。必要に応じて「利用申込」を行い、反映タイミングを把握します。
- 手数料コースを確認します。夜間の約定でも日中と同じコースが適用されるのか、別体系なのかを把握します。ポイント還元やキャッシュバックの条件が変わる場合もあります。
- 注文画面で「市場」を選べるようにします。多くは「東証」「PTS」のように選択します。SORを有効にしていると自動で有利市場に振り分ける機能がありますが、夜間は選べる市場が限られるため、挙動を実機で確認します。
- 逆指値、成行、IOC、FOKなどの注文種類が、PTSで使えるかどうかを一覧で確認します。使えない場合の代替手順(手動監視、アラート、IFDの代替など)をあらかじめ決めておきます。
ここまで終えたら、発注練習として「数量1のダミー指値注文」を出し、注文照会画面にどう表示されるか、訂正・取消の方法、気配の更新頻度などを確認します。実弾投入前に画面の癖を知っておくと、夜間のスピード対応で迷いが減ります。
板と気配の読み方:夜間特有の「薄さ」を武器にする
PTS夜間は、板が薄くて価格が飛びやすい一方、読みやすい側面もあります。コツは「最良気配±2〜3ティックの厚み」と「サイズの変化速度」を監視することです。日中よりも参加者が少ないため、ある価格帯にまとまった注文が出ると、板の見え方がはっきり変わります。変化のスピードが遅いので、観察から仮説を立て、指値の再配置を落ち着いて実行できます。
実務では、最良買いに並ぶのではなく、「最良買い+1ティック」から順に少量で棚卸しする方法が有効です。例えば、最良買いが1,000円で数量800株、最良売りが1,004円で数量500株の場合、1,001円に100株、1,002円に100株…といった形で階段状に指値を並べ、約定した分だけ板の状況に応じて補充します。これにより、一発で価格を動かすリスクを抑えながら、平均取得単価をコントロールできます。
売却側でも同様で、最良売り−1ティックに少量ずつ出し、約定に応じて追加を出します。スプレッドが広いときは、板を自分で埋めてしまわないよう注意します。狙いは「板の厚みの谷間」に丁寧に置いて、無理に自分で最良気配を作らないことです。夜間は出来高が少ないため、一度最良気配を作ると、自分が指値を引っ張ってしまい、結果として不利な平均単価になります。
スプレッド・コストの最小化:指値設計とロット分割
夜間の最大コストはスプレッドです。成行で飛びつくと、1回の約定で日中の数回分のコストを払うことがあります。基本は「指値+ロット分割」です。具体的には、想定の最大数量を3〜5分割し、板の状態を見ながら順次執行します。約定間隔は30秒〜数分とし、板が薄くなればペースを落とします。逆にニュースで参加者が増えているときは、最良気配±1ティックに寄せ、ロットを少しだけ増やします。
また、約定力を高める目的で「見せ板」にならない最小数量を選ぶのがポイントです。夜間は100株単位でも板の印象が大きく変わる場合があるため、数量が大きいと相手の警戒を招き、約定が進みません。100→200→300と階段状に増やすより、100→100→100でテンポ良く埋めるほうが平均単価を抑えやすいことが多いです。約定したら、次の価格帯に小さく補充するか、いったん様子を見て「買い上がらない・売り崩さない」を徹底します。
スプレッドが3ティック以上開いている場合は、敢えて「スプレッドの中心寄り」に薄く置く手もあります。相手の指値が寄ってくるのを待つ形で、板を動かさずに約定を引き寄せます。ただし、ニュース直後の一方通行では逆指値が使えない環境だとリスクが高いので、価格監視と取消手順を明確にしておきます。
SOR設定と市場選択:夜間の優先ルールを理解する
SOR(スマート・オーダー・ルーティング)は、複数市場の中で最良の条件に自動で振り分ける仕組みです。夜間は選べる市場が限られるため、SORの優先度や判定基準が日中と異なることがあります。実務では、まずSORオンで発注し、注文照会の「実際に約定した市場」を確認します。そのうえで、狙いの市場で埋まらないときは、SORをオフにしてPTSを明示的に指定する、という二段構えが有効です。
また、同一価格で並ぶときにどの市場が先に約定するかは、証券会社やPTSのルールに依存します。夜間の検証は、数量1〜100の小ロットで、時間帯を変えて実施するとクセが見えます。例えば、19時台は薄いが21時台に少し厚くなる、決算集中日は20時台から一気に活発になる、といったパターンを自分の環境で掴みます。
ニュース・決算直後の流動性:過剰反応と均しの見極め
夜間の醍醐味は、決算や重要リリースの初動を観測できることです。ここでの基本戦略は「一撃で入らず、帯で拾う・帯で手放す」です。良決算で急騰しているとき、追いかけるのではなく、直近の板の谷間と価格節目(ラウンドナンバー、前日高値・安値、時間足ベースの支持抵抗)に薄く指値を並べ、約定に応じて補充します。悪材料で急落しているときも同様で、反発の厚みが出やすい価格帯に小さく置き、リバウンドでさっと手放す設計にします。
具体例として、前日終値1,000円の銘柄が決算後にPTSで950円まで売られた場合、940/945/950に各100株ずつの買いを置き、平均取得単価を945円に設定します。もし夜間の戻りが弱く、翌朝の寄付で再度売られると判断したら、翌日寄りでの手仕舞い、あるいは950/960/970での分割売りを用意します。夜間だけで完結させず、翌朝の板寄せを前提にプランを組むと、無理な買い上がり・売り崩しを避けられます。
発注テンプレート:そのまま使える設計例
買いテンプレート(逆指値なし環境)
想定最大300株。最良買いが1,000円、最良売りが1,004円の場合、1,001/1,002/1,003に各100株で指値。約定したら、1,001が埋まった時点で1,002を100→200に、1,003を100→150に変更。スプレッドが縮まったら1,004に100を追加し、平均単価を微調整。板が薄くなれば、残数量は翌朝に回す。
売りテンプレート(保有株の利益確定)
平均取得1,000円で300株保有。最良売りが1,012円、最良買いが1,008円の場合、1,011/1,012/1,013に各100株で指値。約定の勢いが強ければ、1,014に追加100株を用意し、勢いが止まったら取消。夜間で売り切る設計にせず、翌朝の板寄せで残を捌く余地を残す。
トレードメモの付け方
夜間は約定までの時間がまばらになりがちなので、「どの気配の変化を見て価格を1ティック寄せたか」「どの板の谷間に置いたら埋まったか」を短文で残します。翌朝の寄付での値動きと照合することで、次回のテンプレート改善に直結します。
よくある失敗と回避策
- 成行で飛びつく:一度でスプレッド全額を負担しがちです。基本は指値+分割。最良気配に寄せるタイミングを、サイズの増減で判断します。
- 板を自分で作ってしまう:大量の指値で最良気配を作ると、相手が警戒し、約定が途切れます。100株単位の小分割でテンポ良く埋めるのが有効です。
- 取消が遅い:逆指値が使えない環境では、手動で素早い取消が必要です。注文照会画面を常時表示し、ホットキーやワンクリック取消を練習します。
- 翌朝の計画がない:夜間だけで完結させようとすると、板が薄い局面で無理をします。翌朝の寄付での扱いまで前夜に決めておきます。
ミニ演習:自分の環境で「約定力」を見える化する
次の手順で、あなたの環境に最適化された発注テンプレートを作ります。
- 対象銘柄を、主力大型・中型・小型からそれぞれ1銘柄選ぶ(合計3銘柄)。
- 一晩で各銘柄に数量合計300株を上限に、100株×3の分割で発注する。
- 約定にかかった時間、平均取得単価と最良気配の差、取消回数を記録する。
- 翌朝の寄付〜寄り後5分の値動きと比較し、「夜間でどこまで無理せずできるか」を判定する。
- テンプレートの価格帯、ロット分割、追加・取消の条件を修正する。
この演習を2〜3回繰り返すだけで、あなたの口座・回線・証券会社の仕様に適した「勝てる型」が固まります。夜間は日中よりも再現性が高く、型化の効果が出やすいのが特徴です。
チェックリスト:発注前・発注中・発注後
発注前
- 証券口座でPTSが有効化されているか(注文画面で市場選択ができるか)。
- 手数料コースと適用範囲を確認したか。
- 逆指値や成行の可否を把握し、代替手順を用意したか。
- 対象銘柄の直近出来高と、夜間の平均的な板の厚みを把握したか。
発注中
- 最良気配±2〜3ティックの厚みと変化速度を観察しているか。
- ロットを小さく分割し、板の谷間に置いているか。
- 取消・訂正の導線を常に開いているか。
- ニュースで一方通行になったら、無理に追わず翌朝のプランへ切り替えるか。
発注後
- 約定履歴と平均単価を記録したか。
- 翌朝の寄付で残数量をどう扱うか、前夜のうちに決めているか。
- テンプレートを修正して次回に反映したか。
用語ミニ解説
- PTS(私設取引システム)
- 取引所とは別に運営される売買システム。夜間の取引が可能で、板が薄くスプレッドが広がりやすい特徴があります。
- スプレッド
- 最良買い(ベストビッド)と最良売り(ベストアスク)の価格差。夜間はここが最大コストになります。
- SOR
- 複数市場に注文を自動振分けする機能。夜間は選べる市場と優先度のルールに注意が必要です。
- 指値・成行
- 指値は価格を指定して発注、成行は価格指定なしで即時約定を優先。夜間は成行に制限がある場合があります。
- 呼値(ティック)
- 価格の最小刻み。板の谷間に薄く置くと、平均単価のコントロールがしやすくなります。
まとめ:夜間は「型化」と「分割」が効く
PTS夜間取引は、板が薄くスプレッドが広がるという難しさがある一方、観察と分割でコントロールしやすい市場でもあります。重要なのは、口座設定の確認、指値とロット分割の設計、板の谷間を意識した配置、取消と翌朝プランの二段構え、そして自分の環境に合わせたテンプレートの継続的な改善です。初心者でも、この順番を守れば無理なく再現でき、ムダなコストを抑えながら約定力を引き上げることができます。まずは小ロットで型を作り、データで裏取りしながら自分の標準手順を磨いていきましょう。

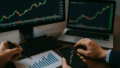
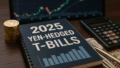
コメント