本記事では、初心者の方でも実行しやすいオプション戦略「カバードコール(Covered Call)」を、仕組みから実務の運用手順、損益の考え方、よくある失敗と回避策まで、具体例を交えながら徹底的に解説します。カバードコールは「株式を保有しながら、その株式に対応するコールオプション(買う権利)を売る」戦略で、配当とオプションプレミアムという二つの収益源を同時に取りにいきます。相場が横ばい〜緩やかに上昇する局面で特に強みを発揮し、下落時にはプレミアムがクッションとして効きます。長期インカムの強化、短期のキャッシュフロー創出、ボラティリティの収益化という観点で、個人投資家にとって実務的な価値が高い戦略です。
1. カバードコールの基本構造
カバードコールは以下の2つを同時に保有・保有/売却することで成立します。
- 対象株式の現物ロング(例:A社株を100株保有)
- 同一銘柄・同一枚数のコールオプション売り(例:A社のコール1枚売り。一般に株式100株=オプション1枚)
このとき、投資家はオプションの売り手として、プレミアム(受取額)を手にします。満期(権利行使日)時点で株価が「行使価格(ストライク)」以下であれば、オプションは無価値で消滅するため、受け取ったプレミアムは確定利益となります。株価がストライクを超えた場合は、権利行使により保有株がストライクで売却される(コールのショートが割り当てられる)可能性があり、その場合はストライクまでの株価上昇益+受取プレミアムが上限利益となります。
1.1 どんな相場で強いのか
横ばい〜緩やかな上昇局面に強みがあります。急騰局面では上値がストライクでキャップされるので機会損失が生じます。一方、急落局面ではプレミアム分だけ損失が緩和されますが、株式の下落リスクは残ります。
2. 収益の分解と損益構造
カバードコールの収益は主に以下の三つから構成されます。
- ① 配当:保有株式からのインカム。
- ② プレミアム:コール売りで受け取るオプション料。
- ③ 現物株の価格変動益(キャピタルゲイン/ロス)。
2.1 ブレークイーブン(損益分岐点)
単純化すると、開始時の株式取得単価から受取プレミアム(税・手数料控除前)を差し引いた水準が、おおまかな損益分岐点になります。配当も考慮すると、分岐点はさらに下がるため、一定の下落耐性が生まれます。
2.2 ペイオフの言語化
満期時の株価STとストライクK、受取プレミアムPとすると、最終損益は概ね以下のように表現できます(手数料・税は簡略化)。
株式損益: (ST − S0) × 株数
コール売り損益: min(0, K − ST) × 株数 + P
合計:株式損益 + コール売り損益 + 受取配当
直観的には、上側は「K(行使価格)+プレミアム」付近で頭打ち、下側は「プレミアム分だけ」損失が軽減される形になります。
3. 具体例:数値でみる月次カバードコール
次の例で、損益のイメージをつかみます(架空の銘柄、数値は例示)。
- 株価S0:1,000円
- 100株保有(投資額10万円)
- 1カ月後満期、K=1,050円のコールを1枚売り
- 受取プレミアムP:1株あたり30円(合計3,000円)
- 1カ月の想定配当:0円(配当なし月と仮定)
この場合、損益は以下の通りです。
| 満期株価ST | 株式損益 | コール売り損益 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 900円 | -10,000円 | +3,000円 | -7,000円 |
| 1,000円 | 0円 | +3,000円 | +3,000円 |
| 1,050円 | +5,000円 | +3,000円 | +8,000円 |
| 1,100円 | +10,000円 | -2,000円(割当)+3,000円=+1,000円 | +11,000円(上限付近) |
プレミアムにより横ばい時でも+3,000円の利益が確保され、上昇時はKまでの株価上昇益+プレミアムが取れます。大幅上昇では機会損失が出ますが、初心者は「プレミアムで安定を取りに行く」思想で始めると理解が進みます。
4. 年率換算(Annualized Return)の実務計算
オプションのプレミアムは満期までの短い期間に対して支払われることが多いため、収益性を比較するには年率換算が有効です。シンプルな算式は下記です(単利ベースの近似)。
年率換算利回り ≒ (受取プレミアム ÷ 現物評価額) × (365 ÷ 保有日数)
例:プレミアム3,000円、現物評価額100,000円、保有日数30日の場合、年率 ≒ 3% × 12.17 ≒ 36.5%(単利換算)。現実には満期ごとにプレミアム水準が変動し、税・手数料・価格変動・割当の影響も受けます。年率は「比較の物差し」であって、保証収益ではありません。
5. 銘柄選定のフレームワーク
初心者の方は、以下の観点で候補銘柄(またはETF)をスクリーニングすると実務に乗せやすくなります。
- 流動性:出来高・板の厚み・オプションの気配の滑らかさ。スプレッドが狭いほど約定コストが低減します。
- ボラティリティ:IV(インプライド・ボラティリティ)が適度に高いとプレミアムが厚くなりますが、急変動リスクも増します。IV Rankで相対位置を把握するのも有効です。
- ファンダメンタルズ:中長期で保有しても良いと考えられる銘柄か。決算やイベントの前後はボラが上がりやすい点にも留意します。
- 配当:配当を重視するなら、権利付き最終日の前後はプレミアムの変動や早期割当の可能性に注意します。
6. ストライクと満期の選び方(入門)
最初は「デルタ基準」か「日数基準」のどちらかに統一すると、学習が進みやすいです。
6.1 デルタ基準
コールのデルタが0.20〜0.35程度のアウト・オブ・ザ・マネー(OTM)を目安に選ぶ方法です。概ね「ほどほどの受取プレミアム」と「ほどほどの割当確率」のバランスになります。
6.2 日数基準
7〜45日程度の満期を中心に回す方法です。短すぎると繰り返しの事務負担が増え、長すぎるとガンマの効きや価格変動リスクが大きくなります。初心者はまず30日前後から始めるのが無難です。
7. 管理・ロール(実務ルール)
- 利益確定ルール:受取プレミアムの50〜75%を確保できたら買い戻しで利確し、次のコールを売る(プレミアムの再投下)。
- 損切りルール:含み損が大きくなった場合、ストライクを上げるロール(デビット、もしくは期間を伸ばす)で調整。想定損失を超える場合は現物の一部売却やヘッジを検討。
- イベント回避:決算、重要指標、公募・増資などのイベント前はポジション縮小や満期調整でギャップリスクを抑制。
- 早期割当:配当直前や深いITMでは割当リスクが高まります。デルタや時間的価値の残存量を確認して回避行動を取ります。
8. リスクとデメリットの正直な話
| 項目 | 内容 | 初心者対処法 |
|---|---|---|
| 上昇相場での機会損失 | 上値がストライクでキャップされる | 最初はOTMに余裕を持たせる、イベント前は縮小 |
| 急落リスク | 現物の下落は残る | 現金比率・分散、必要時はプロテクティブプット |
| 早期割当 | 配当直前や深ITMで発生しやすい | 時間価値の残りと配当額をチェックし回避 |
| 労力 | ロールや約定管理が必要 | 週次の定着ルーチンを確立、ルールの自動化 |
9. マーケット局面別プレイブック
9.1 レンジ相場
最も戦いやすい局面です。デルタ0.25前後・満期30日前後で回転を早め、プレミアムを積み上げます。
9.2 上昇相場
OTM幅を広げる、またはロングコールを組み合わせて上値の一部を確保する(コール比率を下げる、ダイアゴナルなど)。
9.3 下落相場
ポジションサイズを縮小、ストライクを遠ざける、必要に応じてプット買いで尾リスクを抑制します。
10. 実務ワークフロー(週次ルーチン)
- 候補銘柄のIV Rank、出来高、イベントカレンダーを確認。
- デルタまたは日数基準でストライク・満期を一次選定。
- スプレッドと板を確認し、指値で約定コストを最適化。
- ポジション台帳に約定・デルタ・受取P・想定利回りを記録。
- 目標利確水準到達で買い戻し→再度売り(回転)。
- イベント前は縮小、急変時はロール/ヘッジを実施。
11. 初心者がやりがちなNGと回避策
- ITMで厚いプレミアムに惹かれ、早期割当で上値を取り逃す → 最初はOTMから。
- イベント直前に高IVに惹かれて新規→ギャップで被弾 → イベントは避けるかサイズ縮小。
- 買い戻しの躊躇で利確機会を損失 → 50〜75%利確ルールを自動化。
- 単一銘柄集中 → ETFや分散で尾リスクを抑える。
12. 具体的計算ドリル(初心者向け)
例:現物100株@1,000円、OTMコールK=1,050円、P=30円、満期30日。
- 想定年率(単利近似):(30/1000)×(365/30)≈36.5%
- 損益分岐点:1,000−30=970円
- 上限利益:50円×100株+3,000円=8,000円(手数料等除く)
このように「小さな利益を繰り返し確定していく」思想が核です。勝ちを早めに固定し、再投下を続けるとブレが減ります。
13. よくあるQ&A
- Q. いつ始めるのが良いですか?
- A. 大型イベントが少ない週、IVが中庸で板が滑らかなときが無難です。
- Q. 満期前に強く上昇したら?
- A. ITM化が進むほど割当確率が増します。買い戻し→遠いOTMで再売り、またはロングコールを追加して上側を一部開放します。
- Q. 急落したら?
- A. プレミアムで一部緩和されますが、必要に応じてサイズ削減・プット買い・一時撤退を検討します。
14. 最後に:チェックリスト
- 銘柄の流動性・IV・イベントを確認したか
- デルタまたは日数基準で一貫性のある設計か
- 利確・損切り・ロールの数値ルールがあるか
- サイズ管理・分散・ヘッジの枠組みを持っているか
- 台帳にデータを残し、継続的に改善しているか
カバードコールは、相場の「時間価値の減衰」を味方に付けて、配当とプレミアムの二層構造でインカムを積み上げる実務的な戦略です。小さく始め、記録を取り、環境に応じた微調整を続ければ、初心者でも十分に扱えるようになります。


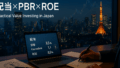
コメント