清算価格(Liquidation Price)は、レバレッジ取引において口座の有効証拠金が維持証拠金を下回った瞬間に、ポジションが強制的にクローズされる価格帯を指します。言い換えれば、清算価格は「退場ライン」です。勝率やエントリー精度よりも前に、この退場ラインをどの位置に置くかを設計できるかどうかが、長期的な生存率と資産曲線を左右します。
本記事では、初心者が最短で実務運用できるよう、清算価格の基本概念から、計算式、マーケット特有の例外(マーク価格・破産価格・ADL・保険基金)、さらにエクセルで即使える式、日々の運用手順まで、体系的に解説します。読み終えたら、ご自身のポジションで「清算価格→レバレッジ→ロット」を逆算配置できるようになります。
1. 清算価格の基礎:何が起き、なぜ起きるのか
レバレッジ取引では、初期証拠金(Initial Margin)を元手に、より大きなポジションを保有します。市場変動で評価損が拡大し、有効証拠金(初期証拠金+含み損益)が維持証拠金(Maintenance Margin)を下回ると、取引所はポジションを清算し、口座のマイナス拡大を抑えます。この維持証拠金ラインを割り込む直前の理論価格が清算価格です。
ここで重要なのがマーク価格(Mark Price)です。多くの取引所は清算判定に「成行(最後値)」ではなく、公平値として算出したマーク価格を使います。板の薄い時間帯やスパイクで「最後値」が荒れても、マーク価格は指標価格や指数に連動し、清算の過度な連鎖を抑制します。
清算後に資産がゼロを下回らないよう、保険基金(Insurance Fund)が不利約定の損失を補填し、さらに不足する場合はADL(Auto-Deleveraging)で反対側のトレーダーのポジションを一部減らしてバランスを取ります。実務では、清算=手仕舞いだけでなく、清算の余波(ADLの発動確率)にも注意が必要です。
2. アイソレーテッドとクロス:清算ロジックの違い
アイソレーテッド(Isolated)は、そのポジションに割り当てた証拠金だけで維持されます。清算リスクは限定的ですが、口座の余力があっても自動的には救済されません。
クロス(Cross、全額証拠金)は、口座全体の有効証拠金でポジションを支えます。余力のある間は清算価格が遠のく半面、複数ポジション間で損益が連動し、想定外の連鎖清算が起こりえます。初心者は原則アイソレーテッドから始め、クロスは「ヘッジ効率を最大化する中・上級者の設計」と理解してください。
3. 近似計算式:まずは“ザックリ”を掴む
取引所ごとに微細な定義差(手数料バッファ、段階的維持率、資金調達、逆指値保護など)があるため、まずは近似式で全体像を掴み、最後に取引所の公式計算を確認するのが実務的です。以下はドル建て無期限先物(USDT建て)想定の近似です(数量1を前提に単位を省略)。
3.1 ロング(買い)の近似式
清算価格_L ≒ (P - P/Lev - FeeBuf) / (1 - MMR)ここで、P=建値、Lev=レバレッジ倍率、MMR=維持証拠金率、FeeBuf=手数料・スリッページのバッファ(例:建値×0.0005など保守的に)。
3.2 ショート(売り)の近似式
清算価格_S ≒ (P + P/Lev + FeeBuf) / (1 + MMR)ロングは下落で、ショートは上昇で清算に近づく点を式が反映しています。これらはマーク価格基準の近似です。
3.3 数値例(ロング)
P=60,000、Lev=10、MMR=0.005、FeeBuf=0とすると、
清算価格_L ≒ (60000 - 6000) / (1 - 0.005) ≒ 54030 / 0.995 ≒ 54301。
建値からおよそ-9.5%で清算目安となります。
3.4 数値例(ショート)
同条件で、清算価格_S ≒ (60000 + 6000) / (1 + 0.005) ≒ 66000 / 1.005 ≒ 65672。
建値からおよそ+9.5%で清算目安です。
注意:実戦では手数料・資金調達・段階的維持率・保険基金ルールなどで数ドル〜数十ドルの差が出ます。近似で設計 → 公式で確定が安全運用の基本です。
4. 公式計算と取引所差:何がズレを生むのか
多くの取引所は、ポジション名目(Nominal=価格×数量)、初期証拠金(Nominal/Lev)、維持証拠金(Nominal×MMR)を使い、
有効証拠金=初期証拠金+含み損益が維持証拠金を下回る条件で清算を判定します。清算後に破産価格(Bankruptcy Price)での決済不足を保険基金が吸収し、足りなければADLが発動します。
ズレの主因は次の通りです。
- マーク価格の算出方法:指数、資金調達率、フェアバリューの組成差。
- 段階的維持証拠金:ポジション規模に応じてMMRが階段状に上昇。
- 手数料バッファ:清算時のコスト控除の扱い。
- 契約仕様:反値契約/USDT建て/コイン建てでPnLの通貨が変わる。
- クロス/アイソレの救済の有無:クロスは口座余力が干渉。
実務では、自分が使う取引所の「清算価格プレビュー」を必ず確認し、近似式との差を把握しておきましょう。
5. エクセル/スプレッドシートでの即戦力式
最速で導入するなら、以下の式をそのままセルに入れてください(アイソレーテッド、USDT建ての近似)。セル構成は例です。
【入力】
B2=建値P, B3=レバレッジLev, B4=維持証拠金率MMR, B5=手数料バッファ率fb
【ロング清算】
= (B2 - B2/B3 - B2*B5) / (1 - B4)
【ショート清算】
= (B2 + B2/B3 + B2*B5) / (1 + B4)より厳密にするには、段階的維持率テーブルを別シートに持ち、名目額に応じてMMRをLOOKUPで引き当てます。また、マーク価格を指数価格+資金調達によるフェアバリューで近似する列を作ると、ボラ急変時の清算想定が安定します。
6. 価格から逆算する「安全レバレッジ設計」
初心者が最初に身につけるべきは、「清算価格→レバレッジ→サイズ」の順に組み立てる癖です。手順は以下です。
- チャートとボラから「許容ドローダウン幅」を決める(例:建値から-6%までは耐える設計)。
- 許容ドローダウン幅とMMRから逆算レバレッジを出す。
- 口座残高とリスク許容(1回のトレード損失上限)からロットサイズを決める。
- 清算価格の前に逆指値(損切り)を必ず置く。清算に任せるのは「設計漏れ」。
例:建値60,000、耐える幅-6%、MMR=0.5%のロング。清算が-10%に位置しがちな10倍は危ない。ならば6〜7倍へ抑え、清算価格を-6.5%以下に遠ざけ、損切りは-3.5%に前倒し配置する、といった具合です。
7. クロス運用の落とし穴と使いどころ
クロスは口座全体がバッファになるため清算が遠のきますが、複数ポジションの同時損失で一気に資本が削られ、ADLの対象にもなりやすくなります。初心者は原則、単一戦略・単一銘柄の練習をアイソレで行い、ヘッジ運用や裁定で正味リスクが低い構造を作れるようになってからクロスへ進みましょう。
使いどころは、ペアトレードやボラ裁定で両建てに近い構造を持つとき、あるいは現物+先物のコンボ(キャッシュ&キャリー)のようにネット・エクスポージャが小さいときです。
8. 実践ケーススタディ:3つの清算設計
ケースA:初心者のロング(アイソレ、近似)
口座残高1,000、P=60,000、Lev=5、MMR=0.5%。名目は12,000で初期証拠金は2,400。近似式より清算価格は約57,286(-4.5%)。損切りは-2.5%に置き、1回の許容損失は口座の2%(20)に制限。サイズを微調整して「損切り到達時=20の損失」になるようロットを算出します。
ケースB:中級者のショート(アイソレ、段階MMR)
規模が大きくなるとMMRが0.5%→0.8%→1.2%と階段アップ。近似では65,672だった清算が、段階表ではさらに手前に寄ることがあります。「清算プレビュー」で必ず確定値を見て、余裕を持って損切りを前倒しに。
ケースC:裁定寄りのクロス(現物+先物)
現物ロングと先物ショートでベーシスを取りに行く構造。ネットの方向性は小さく、クロスでも清算は遠い。ただし先物側の清算価格は独立に存在するため、資金移動の遅延や資金調達の偏りで予想外のADLが出るリスクに注意します。
9. よくある誤解とアンチパターン
「清算に任せればいい」:清算は最悪時の安全弁であり、到達=設計ミス。逆指値は必須です。
「クロスは安全」:一見遠いが、複数ポジションの同時損が引火すると一気に吹き飛びます。
「最大レバレッジ=使うべきレバレッジ」:設計は清算価格から逆算。最大倍率は目安に過ぎません。
「手数料とスリッページは誤差」:清算境界では誤差が命取り。FeeBufを0.05〜0.1%程度でも入れて保守化を。
10. デリバティブ別の清算ニュアンス
10.1 無期限先物(Perpetual)
資金調達(Funding)がマーク価格に影響。資金調達直後の微細な価格ジャンプで清算に触れることがあります。時間帯・直近の資金調達率を確認し、直後の過レバは避けましょう。
10.2 先物(期日あり)
指数連動のフォーミュラは類似ですが、期近/期先のベーシス変動で清算距離が微妙に変化することがあります。ロール時期は特に注意。
10.3 FX/CFD(証拠金率制)
固定証拠金率mの世界では、逆行幅×ロットが口座残高の一定割合に達するかでマージンコール→強制ロスカット。近似的には、「逆行pips × 価値/1pips」が口座残高×許容損失に達したところが危険域です。
11. 日々の運用オペレーション
毎回、エントリー前に下記の順でチェックしてください。
- ボラとイベント(雇用統計など)で「許容逆行幅」を決める。
- 清算価格の近似→取引所プレビューで確定。
- 損切りを清算価格の手前に置き、サイズを逆算。
- 連続エントリーは避け、結果が出るまで待つ(過レバの主因)。
- 結果記録:損切り差・清算距離・実効レバ・資金調達・ボラ指標。
12. 付録:擬似コード
// 入力: P=建値, Lev=レバ, MMR=維持率, fb=手数料バッファ率
// 出力: L=ロング清算, S=ショート清算(近似)
L = (P - P/Lev - P*fb) / (1 - MMR)
S = (P + P/Lev + P*fb) / (1 + MMR)
// 逆算レバレッジ(許容逆行d%で清算がd以下に来ない条件)
Lev_max ≒ P / (P*(1 - d) - (1 - MMR)*(清算目標価格)) // 実装は所内仕様に合わせ補正
本稿のゴールは、「清算価格を設計変数として前段に置く」習慣を身につけることです。清算が視界に入るレバレッジは即時に縮小し、清算価格のずっと手前で、規律的に損切りする。これが生存率と再現性を大きく押し上げます。


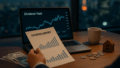
コメント