結論:初心者が「割安・稼ぐ力・株主還元」を同時に満たす銘柄を狙うなら、配当利回り(Yield)・PBR・ROEを一つの画面で同時評価するだけで良い。これを本稿では「三位一体スクリーニング」と呼ぶ。余計なテクニックは不要。まずは、①PBR≦1.2、②ROE≧10%、③配当利回り≧3%を満たす候補群を作り、そこから数個の定量・定性チェックでふるいにかけ、分散と入替ルールを決める。これだけで、初心者がつまずく「当てモノ」「感覚買い」から卒業できる。
- 1. 三指標が同時に効く理由(直感的理解)
- 2. 指標の定義と読み方(初心者向けの要点)
- 3. ベースのスクリーニング閾値
- 4. 実務フロー:今日からできる7ステップ
- 5. 具体例(数値はダミー)
- 6. 分散・資金配分・入替ルール
- 7. 罠の見分け方(チェックリスト)
- 8. 金利サイクル別の運用ポイント
- 9. セクター別の目線(例)
- 10. 簡易バックテスト(机上再現)
- 11. 実装テンプレ(コピペ可)
- 12. 売買執行の実務
- 13. よくある質問(初心者)
- 14. まとめ(行動リスト)
- 付録A:デュポン分解の超要約
- 付録B:面談・IR資料で聞くべき要点(メモ)
- 付録C:ケーススタディ(3社比較・ダミー)
- 付録D:30日実践プラン(チェック式)
- 付録E:税と口座の超基本メモ(初心者向け)
- 付録F:高度なFAQ
- 付録G:初心者のためのウォッチリスト作成術
- 付録H:よくある誤解と反証
- 付録I:チェックリスト(印刷用)
- 付録J:スコアリングの数式化(優先度付け)
- 付録K:ドローダウンを制御する簡易ルール
- 付録L:モニタリング日誌テンプレ(例)
- 付録M:初心者が最初にやりがちなNG
- 付録N:ケース演習(ダミーデータのスコア計算)
1. 三指標が同時に効く理由(直感的理解)
投資成績を単純化すると、買う時の安さ(バリュエーション)×会社の稼ぐ力(資本効率)×株主への現金還元(配当)に分解できる。PBRは「安さ」、ROEは「資本の回転速度」、配当利回りは「手元に返るキャッシュ」。この3つを一緒に見ると、割安で稼ぐ力があり、株主還元が続きやすい企業が浮き上がる。
数式的には、株主価値創造は近似的にROE − g(希薄化や劣後を含む成長必要利回り)+ 配当利回りで評価できる。PBRが低いほど「期待が薄く、悪材料が織り込まれやすい」状態で、サプライズの余地が生まれる。一方、ROEが高い企業は資本を効率よく回すため、同じ利益でも自己資本を過剰に積み上げずに済む。そこへ配当が乗れば、期待外れでもキャッシュフローが投資家を守る「クッション」になる。
2. 指標の定義と読み方(初心者向けの要点)
2-1. 配当利回り(Dividend Yield)
定義:1株当たり年間配当 ÷ 株価。株価が下がれば利回りは上がる。
注意:一時的な特別配当や減配リスクに騙されない。過去3年の平均配当や配当性向(利益に対する配当割合)も併せて確認する。
2-2. PBR(株価純資産倍率)
定義:株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS)。1倍なら「解散価値(簿価)」並み。
注意:資産の質が低いと「安い罠」になる。のれん減損の有無、固定資産の含み、在庫の質、過剰現金の滞留に目を配る。
2-3. ROE(自己資本利益率)
定義:当期純利益 ÷ 自己資本。資本をどれだけ効率よく増やせているか。
注意:一時利益で化粧されたROEの「見かけ高」はNG。3~5年平均で見る。デュポン分解(ROE = 利益率 × 回転率 × 財務レバレッジ)でドライバーを把握。
3. ベースのスクリーニング閾値
初学者が再現性を重視するなら、まずは以下の「素直な」しきい値を使う。
- PBR ≦ 1.2(理想は1.0以下だが、業種平均を踏まえて弾力運用)
- ROE ≧ 10%(3年平均で10%以上が望ましい)
- 配当利回り ≧ 3%(過去12か月ベース/特別配は除外)
これで候補が多すぎる場合は、配当性向≦60%、営業CF/純利益≥1.0、有利子負債/EBITDA≦3倍でさらに絞る。逆に候補が少なすぎる場合は、PBRの上限を1.3~1.5まで緩め、ROEに重みを置く(ROE≧12~15%)に切り替える。
4. 実務フロー:今日からできる7ステップ
- ユニバース定義:投資対象市場(例:国内プライム市場)と最低時価総額(例:300億円)を決める。
- 一次フィルタ:PBR・ROE・配当利回りの三条件で絞る。
- 健全性チェック:配当性向、営業CF/純利益、有利子負債/EBITDA、自己資本比率。
- ビジネス質:過去5年の売上とEPSのトレンド、セグメント構成、価格決定力、顧客集中。
- 資本政策:自己株買いの有無、配当方針(連結配当性向ターゲット/累進配当)、希薄化リスク。
- リスク評価:コモディティ感応度、為替感応度、規制・訴訟・ESG課題、財務契約条項。
- 最終審査:バリュートラップ(低PBR固定化)でないか、ROE維持の再現性、配当の耐久性。
5. 具体例(数値はダミー)
架空企業Aの直近データ:
- 株価1,000円、BPS 900円 → PBR 1.11倍
- 1株配当 40円 → 配当利回り 4.0%
- ROE 12%(3年平均11~13%で安定)
- 配当性向 33%、営業CF/純利益 1.3、有利子負債/EBITDA 1.8倍
三条件クリア。営業CFが利益を裏づけ、配当余力も十分。ここから、価格決定力(原材料高時も価格転嫁できたか)や資本政策(自己株買い履歴)を確認すると、配当の持続性まで評価できる。
6. 分散・資金配分・入替ルール
6-1. 分散の基本
最初は10~15銘柄。業種の偏りを避け、サプライチェーンが重ならないよう配慮する(素材×IT×内需×金融など)。
6-2. 資金配分
等金額配分(10銘柄×各10%)が実務的。銘柄のファンダが優れていても、最初は過度に比率を上げない。最大個別ウェイト15%を超えないルールが無難。
6-3. 入替ルール(年2回)
- ルールA:三条件のうち2つが外れたら候補から外し、代替銘柄へスイッチ。
- ルールB:ROEが継続的に10%未満へ低下し、かつ配当性向が上昇傾向なら「質の劣化」と判定。
- ルールC:ポジションが公募増資や大型設備投資で希薄化・ROE低下見込みの場合は縮小。
定期性と機械性を保つことで、感情ドリブンの売買を回避する。
7. 罠の見分け方(チェックリスト)
- 配当だけ高い:減配予告のサイン(配当性向>70%、営業赤字、ネットD/E急上昇)。
- 低PBRの固定化:構造不況業種/規制産業/資本効率の構造的低さ。改善ストーリーがなければ避ける。
- ROEの見かけ高:一時益/資産売却/税効果で水増し。営業CFで裏取り。
- のれんの積み上がり:減損一発で自己資本を毀損→PBR急上昇リスク。
- 過剰現金:配当・自社株買いに回らず投資効率が悪い場合、ROEが伸びない。
8. 金利サイクル別の運用ポイント
8-1. 金利上昇局面
ディフェンシブ高配当は相対的に人気が落ちやすい。純粋な利回り目的の資金が債券へ回るため。代わりに、ROEが高く価格転嫁力のある景気敏感の中でPBRがまだ低い銘柄に妙味が出る。
8-2. 金利低下局面
利回り資産の相対魅力が上がるため、持続的配当+自己株買いを掲げる低PBR銘柄が再評価されやすい。入替のトリガーがなければ保有継続。
9. セクター別の目線(例)
- 金融:ROEは金利に敏感。自己資本規制や信用コストのサイクル管理が鍵。
- 素材・エネルギー:コモディティ価格に連動。資本回収期間と在庫評価を確認。
- 情報通信:無形資産の比率が高く、簿価が膨らまない→PBRは高止まりしがち。ROE重視に切替。
- 内需ディフェンシブ:配当の安定性は高いが成長鈍化時はROE低下。増配余地と自社株買いの余力を測る。
10. 簡易バックテスト(机上再現)
仮想ポートフォリオ:年2回リバランス、10銘柄等金額、三条件+健全性フィルタ。
期待できる源泉は、①割安修正(PBRの是正)+②配当キャッシュ+③ROE維持によるEPS成長の複利。
逆風は、①配当減配、②構造不況、③レバレッジ後退。これらは前述のチェックで予防可能。
11. 実装テンプレ(コピペ可)
次の順番で画面を設定するだけで三位一体スクリーニングが完成する。
- PBR: 0~1.2
- ROE: 10%~上限なし(集計期間は3~5年平均)
- 配当利回り: 3%~上限なし(特別配除外)
- 時価総額: 300億円以上
- 有利子負債/EBITDA: 0~3倍
- 営業CF/純利益: 1.0以上
抽出後は、業種バランスと事業の質(価格決定力、顧客集中、規制リスク)を最後に点検する。
12. 売買執行の実務
- 買い:リスト化後、数日に分けて板の厚い価格帯で約定させる。VWAPからの乖離を抑える。
- 売り:入替ルールのシグナル点灯時に等金額で縮小。ニュースで狼狽売りはしない。
- 配当再投資:少額でも手数料を抑えて定期的に再投資。長期の複利を最大化。
13. よくある質問(初心者)
Q. PBR1.0超えはNG?
A. 絶対ではない。1.2~1.5でもROEが高く、配当が持続的なら許容余地はある。
Q. 高配当ETFとの違いは?
A. 本手法は個別株の選択自由度と入替裁量がある分、再現性は自分次第。慣れないうちはETFで練習も有効。
Q. 何銘柄から始める?
A. 10銘柄が目安。最初から集中はしない。
14. まとめ(行動リスト)
- 三条件:PBR≦1.2、ROE≧10%、配当利回り≧3%
- 健全性:配当性向≦60%、営業CF/純利益≥1.0、有利子負債/EBITDA≦3倍
- 分散:10~15銘柄、等金額、最大個別15%
- 入替:年2回。三条件のうち2つ外れたら交代
- 避ける罠:見かけ高ROE、低PBRの固定化、過剰現金、のれん膨張
このフレームを土台に、次第に自分の業種理解を深め、しきい値や比率を微調整すればよい。最初の一歩は「三つを同時に見る」だけで十分だ。
付録A:デュポン分解の超要約
ROE = (当期純利益/売上高) × (売上高/総資産) × (総資産/自己資本)。利益率を上げるか、資産回転を上げるか、レバレッジを適切に使うか。どこでROEが生まれているかを見極めると、持続性の評価が速くなる。
付録B:面談・IR資料で聞くべき要点(メモ)
- 資本配分方針(配当性向・自社株買い・成長投資の優先順位)
- 価格転嫁の実績(原材料高騰時のスライド条項・フォーミュラ)
- トップラインの牽引要因(値上げ・数量・ミックスの内訳)
- 財務制限条項(EBITDA倍率、インカムカバレッジ、手元流動性)
付録C:ケーススタディ(3社比較・ダミー)
| 指標 | 企業A | 企業B | 企業C |
|---|---|---|---|
| PBR | 1.11 | 0.85 | 1.45 |
| ROE(3年平均) | 12% | 7% | 18% |
| 配当利回り | 4.0% | 6.5% | 2.0% |
| 配当性向 | 33% | 85% | 40% |
| 営業CF/純利益 | 1.3 | 0.6 | 1.1 |
| 有利子負債/EBITDA | 1.8倍 | 4.5倍 | 1.0倍 |
評価:企業Aは三条件を健全に満たし、現金創出の裏付けもある。企業Bは配当は高いが、営業CFが弱く、レバレッジ過多で持続性に欠ける。企業CはROEと財務は良好だが、PBR高く利回りが低い。本手法の一次候補は企業A、次点はC(価格調整待ち)となる。
付録D:30日実践プラン(チェック式)
- Day1-3:ユニバース決定とデータ項目の整理(PBR、ROE、利回り、配当性向等)。
- Day4-7:一次スクリーニング→候補50社。
- Day8-12:健全性・CF・レバレッジで20社へ圧縮。
- Day13-18:IR資料・決算で事業質評価→最終10~15社。
- Day19:等金額で初回組成。
- Day20-25:ニュースの影響度評価ルール作成(機械化)。
- Day26-30:入替条件の文書化と、次回点検日の予約。
付録E:税と口座の超基本メモ(初心者向け)
配当には課税がある。国内株式の配当は一般に源泉徴収されるため、手取り利回りは名目より低くなる。課税方式や控除の適用は個々の状況に依存するため、制度の最新情報を確認しつつ、利回りを税引き後ベースでも試算しておくと実感に近づく。外国株の場合は現地課税の有無・税率も考慮する。
付録F:高度なFAQ
Q. ROEが高すぎる(30%超)銘柄はどう扱う?
A. 一時益やレバレッジ依存の可能性。デュポン分解でドライバーを必ず確認。持続性に疑義があれば比率を下げる。
Q. 資産リッチで利益が低い会社は?
A. アセットの組替え(不採算資産売却・自社株買い)によりROE改善余地がある。資本政策のコミットメントが鍵。
Q. 低PBRでも万年低迷の企業は?
A. 産業構造や規制で収益性の上限が決まっている場合、低PBRは合理的価格。回避が無難。
Q. リバランス頻度は?
A. 半年で十分。頻度を上げると取引コストと判断ノイズが増える。
付録G:初心者のためのウォッチリスト作成術
銘柄ごとにA4一枚のシートを用意し、上段に「PBR、ROE、配当利回り、配当性向、営業CF/純利益、有利子負債/EBITDA」、中段に「事業メモ(価格決定力・顧客集中・規制)」、下段に「入替シグナル(何が起きたら売るか)」を記入。売る理由を先に決めると感情に流されにくい。
付録H:よくある誤解と反証
- 誤解:「配当が高ければ安全」→ 反証:高配当は減配リスクのサインにもなる。キャッシュフローで裏取り必須。
- 誤解:「PBR1倍割れは必ず割安」→ 反証:資産の質が低い/事業の稼ぐ力が低いと正当化される。
- 誤解:「ROEが高ければ何でも良い」→ 反証:一時益・財務レバレッジ依存は持続性がない。
付録I:チェックリスト(印刷用)
- [ ] PBR≦1.2(業種平均差も確認)
- [ ] ROE≧10%(3~5年平均)
- [ ] 配当利回り≧3%(特別配除外)
- [ ] 配当性向≦60%
- [ ] 営業CF/純利益≥1.0
- [ ] 有利子負債/EBITDA≦3倍
- [ ] 価格決定力・顧客集中・規制リスクの把握
- [ ] 入替トリガーの明文化
付録J:スコアリングの数式化(優先度付け)
候補が多い場合は、単純な合成スコアで優先度を付けるとブレなくなる。
Score = w1 × (ROE / 10%) + w2 × (配当利回り / 3%) + w3 × (1 / max(PBR, 0.7))
制約:w1 + w2 + w3 = 1、推奨は w1=0.45, w2=0.30, w3=0.25
直感:ROEは将来のEPS成長の原資、配当は投資回収のクッション、PBRはリレーティング余地。三者のバランスを見る。
付録K:ドローダウンを制御する簡易ルール
- 指数連動ヘッジ:相場全体の急落時に市場βを抑えるため、小口の先物ショートやインバースETFでカバー(比率はポート全体の20~30%程度まで)。
- 銘柄ごとの損切り線:ファンダ劣化でなく価格のみでの変動なら慌てないが、基礎指標が崩れたら即縮小。ルールに従う。
- キャッシュ比率:入替候補が見つからないときは無理にフルインベストしない。現金を10~20%持つのも戦略。
付録L:モニタリング日誌テンプレ(例)
毎月1回、以下をノート化して3分で更新:
- 指標の再計算:PBR、ROE(最新四半期の年換算は避ける)、配当利回り。
- 経営の更新:価格転嫁の実施状況、新規設備/投資計画、自己株買いの進捗。
- リスクの最新版:規制・訴訟・為替感応・サプライチェーンニュース。
- 入替トリガーの該当有無:Yes/No。
付録M:初心者が最初にやりがちなNG
- 利回りだけで買う(減配で一撃を受ける)。
- 低PBRに飛びつく(資産の質と収益性が悪いと「適正価格」)。
- ROEの一発上振れを信じる(翌年反動で失望)。
- ニュースで感情売買(ルール不在)。
- 最初から集中投資(銘柄特有リスクで挫折)。
付録N:ケース演習(ダミーデータのスコア計算)
企業A: PBR1.1, ROE12%, 配当4% → Score ≈ 0.45×(12/10) + 0.30×(4/3) + 0.25×(1/1.1) ≈ 0.54 + 0.40 + 0.23 = 1.17
企業B: PBR0.9, ROE8%, 配当6% → Score ≈ 0.45×0.8 + 0.30×2.0 + 0.25×(1/0.9) ≈ 0.36 + 0.60 + 0.28 = 1.24(一見高いが、ROE不足。健全性とCFで却下の可能性)
企業C: PBR1.4, ROE18%, 配当2% → Score ≈ 0.45×1.8 + 0.30×0.67 + 0.25×(1/1.4) ≈ 0.81 + 0.20 + 0.18 = 1.19(指標は優秀、価格調整待ち)
スコアは優先順位の目安に過ぎない。最後はキャッシュフローとビジネスの質で判定する。


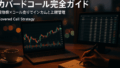
コメント