要約:本稿では「クレジットスプレッド」を軸に、投資適格債(IG)とハイイールド債(HY)、CDS、債券ETFを使った実装方法、金利とクレジットの分離、ヘッジ設計、リスク管理までを初歩から丁寧に解説します。株や暗号資産中心の投資家にとっても、クレジット市場の理解は景気循環や流動性の変調をいち早く掴むための強力なコンパスになります。
- クレジットスプレッドとは何か
- 金利とクレジットの分解(スプレッド・デュレーションの基礎)
- 投資適格(IG)とハイイールド(HY)の違い
- スプレッドの主なドライバー
- 商品選択:個別債、ETF、CDS
- スプレッドだけを取りにいく:金利中立の発想
- IGとHYの戦略テンプレート(初心者向け)
- 数値で理解する:スプレッド×金利の同時変化
- CDSで学ぶ「純スプレッド」の考え方
- HYのキャリーを現実的に評価する
- エントリーとエグジット:しきい値と手順
- ポートフォリオ設計:例
- 実務ディテール:約定・流動性・コスト
- よくある失敗と対策
- ケーススタディ:スプレッド縮小トレード
- デフォルトと回収率の基礎
- 情報インプットの優先順位
- 実装チェックリスト
- まとめ
クレジットスプレッドとは何か
クレジットスプレッドとは、同じ満期・通貨の無リスク金利(一般に国債利回り)に対して、企業債などの信用リスクを負う債券が上乗せされる利回り差のことです。直感的には「この企業にお金を貸す追加リスクに対して、市場が要求する余分な利回り」です。実務ではG-spread(国債スプレッド)、I-spread(インターバンクスワップに対するスプレッド)、Z-spread(割引曲線に対する均等スプレッド)、OAS(オプション調整スプレッド)など複数の定義が用いられますが、初学者は「国債に対する上乗せ利回り」と理解すれば十分です。
金利とクレジットの分解(スプレッド・デュレーションの基礎)
債券の利回りは概ね「国債利回り+クレジットスプレッド」で表現できます。価格感応度は金利要因(デュレーション)とクレジット要因(スプレッド・デュレーション)に分けて考えると理解が進みます。単純化すれば、価格変化(%)≒ −デュレーション×金利変化(bp)/100 − スプレッド・デュレーション×スプレッド変化(bp)/100 です。これに凸性(コンベクシティ)を加えれば、より精緻になります。
投資適格(IG)とハイイールド(HY)の違い
IGは格付けが高くデフォルト確率が低い一方で、スプレッドは相対的に小さくなります。HYは格付けが低く、景気悪化局面ではスプレッドが大きく拡大しやすく、価格ボラティリティが高くなります。利回り水準だけでなく、流動性・コベナンツ(債務契約の保護条項)・産業分散・発行体集中度に注意します。
スプレッドの主なドライバー
- マクロ要因:景気循環、雇用・物価・金融政策の変化、金融ストレス(例:流動性逼迫)がスプレッドを動かします。
- 発行体ファンダメンタルズ:レバレッジ(ネット有利子負債/EBITDA)、利子負担能力(インタレスト・カバレッジ)、フリーキャッシュフロー、産業サイクル。
- 需給・流動性:ETFおよびCLOのフロー、プライマリー(新発)/セカンダリー需給、四半期末のバランスシート制約等。
- テクニカル:国債金利の大振れ、イールドカーブの形状変化、社債指数リバランス。
商品選択:個別債、ETF、CDS
初心者はまず流動性・分散の観点からETFの活用が無難です。投資適格では代表的にIG系ETF、ハイイールドではHY系ETFが挙げられます。個別債は銘柄選択の妙味がある一方、情報・約定・税務の手間が増えます。CDSやクレジット指数先物はスプレッド変動を直接取引でき、ヘッジや裁定(アービトラージ)で使われますが、初心者はまず価格連動性が分かりやすいETFから入るのが安全です。
スプレッドだけを取りにいく:金利中立の発想
「国債金利は読めないが、スプレッドの方向は読める」という場面は多くあります。そこで、デュレーションを国債(もしくは金利先物)でヘッジして、クレジット要因だけを取りにいく手法が有効です。考え方はシンプルで、長期社債ETFをロングし、同じデュレーション(DV01)になるよう国債ETFや先物をショートします。これにより金利変動要因を相殺し、スプレッド縮小による価格上昇(または拡大時の下落)にクリーンにエクスポージャーを取れます。
ヘッジ比率の計算例
例として、社債ETFのデュレーションが8.5、国債ETFのデュレーションが7.5、投資金額は各100万円とします。DV01は概ね「デュレーション×価格×0.0001」で近似できます。価格をパー(100)と仮定すると、社債ETFのDV01は約85、国債ETFは約75です。金利要因を中立化するには、国債ショートの金額を85/75≒1.13倍に調整します。すなわち、社債100に対して国債113をショートすれば、金利変動に対してほぼデルタニュートラルになります。
IGとHYの戦略テンプレート(初心者向け)
1. IG:景気減速~安定局面の「ゆっくり積み上げ」
景気が鈍化し、政策金利がピークアウトまたは高止まりする局面では、IGのスプレッドは緩やかに縮小する傾向があります。この環境ではドルコスト平均法(DCA)でIG ETFを積み上げ、急なリスクオフでスプレッドが一時的に拡大したときに追加投資します。指値で待ち伏せし、急落を拾う設計が有効です。
2. HY:景気転換点を狙う「厚いクッション+薄い攻め」
HYはキャリー(分配金)魅力がある一方、景気悪化ではスプレッドが急拡大しやすく、下落耐性が必要です。初心者はポートフォリオの核をIGや現金等で守りつつ、HYエクスポージャーは小さく始め、トレンドが明確になってから段階的に増やすのが安全です。移動平均の上抜け/下抜けなどシンプルなルールと、最大ドローダウンの許容幅を事前に決めます。
数値で理解する:スプレッド×金利の同時変化
社債ETF(デュレーション8.5、スプレッド・デュレーション7.5、価格100)があるとします。ケースA:景気回復で国債金利+0.50%、スプレッド−0.80%。価格変化は概ね −8.5×0.50% − 7.5×(−0.80%)= −4.25%+6.00%=+1.75%(凸性を無視した単純化)。ケースB:景気悪化で国債金利−0.60%、スプレッド+1.20%。変化は −8.5×(−0.60%) − 7.5×1.20%= +5.10% −9.00%=−3.90%。このように、金利低下でもスプレッド拡大が大きいと価格は下落し得ます。ヘッジを入れて金利要因を中立化すれば、ケースBの下落幅を抑制できます。
CDSで学ぶ「純スプレッド」の考え方
CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)は、発行体のデフォルト保険料です。CDSスプレッドは、社債のOASと強く連動しやすく、よりダイレクトに信用リスクの価格を示します。CDSを直接取引しない投資家でも、CDSスプレッドの動きを情報指標として参照すると、ETFの売買判断に深みが出ます。
HYのキャリーを現実的に評価する
HYの分配金利回りが高く見えても、長期ではデフォルト損失と回収率(リカバリー)を差し引いた「純キャリー」で評価する必要があります。たとえば、名目利回り8%、デフォルト損失(デフォルト率×損失率)が年2%と見積もれば、期待キャリーは6%程度に下がる可能性があります。景気悪化でデフォルト率が上がると、キャリーの優位は急速に薄れます。
エントリーとエグジット:しきい値と手順
- IG積立のしきい値:スプレッドが平常時より明確に拡大した局面(例:±標準偏差のバンド上限)で追加投資。平常水準ではDCAのみ。
- HYの慎重な増減:価格が中期移動平均線を回復し、出来高が伴う上昇で段階的に増やす。下抜けでいったんリセット。
- ヘッジの実装:IGやHYロングに対して、期間の近い国債ETFや先物でDV01マッチング。ヘッジ比率は月次で点検。
ポートフォリオ設計:例
総額100万円のうち、IG 50%、HY 20%、国債(ヘッジ目的のショートと相殺して実質0~10%)、現金20~30%。景気の先行指標や企業利益のモメンタムが改善すればHYを段階的に増やし、悪化すればIG比率を高めます。
実務ディテール:約定・流動性・コスト
- 約定:流動性が高い時間帯に、基本は指値。板気配の薄い時間帯の成行はスプレッド損が拡大しがちです。
- コスト:信託報酬(年0.1~0.5%程度)に加え、実質的な「組入債券の売買コスト」がETFで内部的に発生します。
- プレミアム/ディスカウント:ETFの市場価格とNAVの乖離は、ボラティリティ拡大時に一時的に広がることがあります。
よくある失敗と対策
- 利回りだけで判断:名目利回りの高いHYに偏重し、景気悪化で大きく損失。分散とヘッジで緩和します。
- 金利サプライズ無視:金利低下=債券上昇と短絡。スプレッド拡大が打ち消す局面を忘れがちです。
- ヘッジ比率の放置:デュレーションや価格の変化でDV01がズレます。月次点検で再調整します。
ケーススタディ:スプレッド縮小トレード
社債ETF(価格100、デュレーション8.0、スプレッド・デュレーション7.0)を100万円分ロング、国債ETF(デュレーション7.5)を113万円分ショートし金利中立化。1か月後、国債金利+0.30%、スプレッド−0.50%とします。金利影響はロング側(−2.4%)とショート側(+2.26%)でほぼ相殺、スプレッド効果は+3.5%前後。手数料と税金を除けば、ほぼ純粋なスプレッド縮小益が残ります。
デフォルトと回収率の基礎
HYの損失は「デフォルト率×(1−回収率)」で近似されます。回収率は景気・担保の質・優先順位で変化します。景気悪化時はデフォルト率が上がり、回収率は下がりやすいため、損失の相乗効果が起こります。セクター分散と銘柄集中リスクの管理が重要です。
情報インプットの優先順位
- マクロ:雇用、物価、金融政策の先行き。
- 市場ストレス:ボラティリティ指標、資金フロー、流動性指標。
- ファンダメンタルズ:レバレッジ、カバレッジ、FCF、コベナンツ。
- テクニカル:価格帯・出来高、移動平均、リバーサルシグナル。
実装チェックリスト
- 目的:キャリー重視か、スプレッド縮小益狙いか。
- 商品:IG/HYの比率、個別債かETFか。
- ヘッジ:DV01中立の有無、ヘッジ先の選定(国債ETF/先物)。
- サイズ:最大損失許容額、段階的な増減計画。
- ルール:エントリー/エグジット、ドローダウン制限、点検頻度。
まとめ
クレジットスプレッド投資は、景気循環と企業の信用力を一本の指標に凝縮して扱える魅力的な手法です。初心者はまずIGで分散とルール運用を身につけ、HYは小さく慎重に。金利要因はヘッジで極力切り分ける。数式やデュレーションの概念を恐れず、シンプルな指値・段階発注・月次点検の3点を守るだけでも、ポートフォリオの安定性は大きく向上します。
※本記事は情報提供のみを目的とし、特定の投資行為を推奨するものではありません。投資に関する最終判断はご自身の責任でお願いいたします。


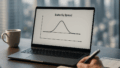
コメント