本稿では、ドル連動型ステーブルコイン(USDTやUSDC等)を用いて、中央集権型サービス(CeFi)の貸借レートと分散型金融(DeFi)の貸借レートの乖離を収益化する「金利アービトラージ」の考え方と実装手順を解説します。相場観に依存せず、原則として価格方向のリスクを取らずに利ざや(ネットスプレッド)を積み上げる手法です。初回は少額・短期で試行し、プロセス全体を安全に回すことを最優先にしてください。
1. 戦略の全体像
狙いはシンプルです。「金利が低い市場で借りて、金利が高い市場で貸す」。具体的には、CeFiで年率が低いときにステーブルを借り、同時にDeFiのレンディングプールで年率の高い利息を受け取る、あるいはその逆を行います。ポイントは、ネットスプレッド(受取APY − 支払APR − コスト)が正であり続ける時間をできるだけ長く確保することです。
本戦略は為替や仮想通貨の価格変動に賭けません。ただし、金利の変動・ブロックチェーン手数料・清算/信用・デペッグ・ブリッジといった固有リスクは存在します。後述のチェックリストで最小化します。
2. 用語の整理(APRとAPY)
APRは単利の年率、APYは複利効果を含む実効年率です。日次複利での目安は、APY ≒ (1 + APR/365)365 − 1。短期案件の比較では、都度APY換算して「ネットで何%残るか」を見る癖をつけます。
3. 代表的な建付け(3パターン)
3-1. CeFiで借りてDeFiで貸す
例:CeFiのUSDT借入APRが8%、DeFiのUSDT貸出APYが14%。差は概ね6%ですが、入出金手数料・ブリッジ・ガス代・担保維持費を年換算で差し引いてネットを算出します。KYC済みアカウントを用い、出庫・入庫の手順を事前にドライランしておくのが安全です。
3-2. DeFiで借りてCeFiで貸す
例:DeFiでUSDCをガバナンストークン担保で借り(可変APR)、CeFiの定期/フレキシブルで貸出(固定〜変動APY)。担保価格変動リスクがあるため、LTVに余裕(例:最大許容の50〜60%程度)を取り、清算バッファを確保します。
3-3. DeFi間/チェーン間スプレッド
同一チェーン内でもプロトコル間でレート差が生まれます。さらにチェーンが異なると、ガス単価・TVL・インセンティブ設計の違いで差が拡大します。ブリッジ往復のコストと遅延、ファイナリティを必ずコスト化して比較します。
4. 数値シミュレーション(現実的なサイズ感)
初期元本10万USDT、借入APR 8%、貸出APY 14%、ネット差6%と仮定します。入出金・ブリッジ・ガス等の固定費を合計で80ドル、運用期間を30日とします。
30日間の受取利息は概算で 100,000 × (0.14/365) × 30 ≒ 1,150 USDT、支払利息は 100,000 × (0.08/365) × 30 ≒ 657 USDT、固定費80ドルを差し引くと、約413 USDTがネット利益です。年率換算の感覚を掴むには、ネット利回り ≒ (413 / 100,000) × (365/30) ≒ 5.0%。この値が十分に高い期間だけ資金を回すべきで、ネット2%を下回るようなら撤退を検討します。
利回りは常に変動するため、差が1%縮小するごとに利益がどれだけ減るかを事前に感応度で把握しておきます。例えば差が6%→4%に縮むと、上記条件では利益が約1/3減少します。
5. 実行フロー(チェックリスト付き)
アカウントと資金動線の準備
(1)CeFi口座のKYC完了、(2)セルフカストディのホット/コールド切分け、(3)複数チェーンのウォレット(EVM系、必要なら他系)、(4)安全なブリッジ経路の確保、(5)少額での試験送金。この5点を必ず事前に整備します。
銘柄と担保設計
担保は価格変動が小さいアセットを優先し、LTVは控えめに設定します(目安50〜60%)。清算閾値・清算ペナルティ・オラクル仕様(TWAPか、複数供給元か)を読み込み、清算バッファ=清算閾値 − 自己LTVを常時把握します。
レート監視
少なくとも1日2回、借入APRと貸出APYの両方をチェックし、ネットスプレッドをシートで自動集計します。手数料は「入出金・ブリッジ・承認(approve)・供給(supply)・引出(redeem)」をそれぞれ見積もり、年換算コストとしてネットから差し引きます。
執行と記録
取引実行は「同日内・短時間で往復」を徹底します。Txハッシュ、時刻、金額、レート、手数料、残高を台帳化。後日検証できる形で残すことが勝率を高めます。
6. リスクと抑え方
スマートコントラクト/監査
監査の有無は安全性の十分条件ではありませんが、無いよりは良い指標です。タイムロック、マルチシグ、アップグレード権限の所在、監査報告の既知の問題の残存などを確認します。
デペッグ
ステーブルコインは常にパリティを維持できるとは限りません。万一の逸脱に備え、単一銘柄に過度集中しない、複数銘柄を跨ぐ(USDT/USDC分散など)、ペッグ回復の履歴とメカニズムを調べておきます。
清算/信用
担保価値の急落やスプレッド縮小でネットがマイナス化した場合は、想定外の価格リスクやカストディ/信用リスクが顕在化します。LTVを下げる、担保をより安定的なものにする、資金を部分撤退するなどのルールを事前に決めます。
ブリッジとファイナリティ
ブリッジは遅延と手数料に加え、まれに一時停止や上限制限が発生します。片道で詰まらないよう、代替経路と同一チェーン内での一時退避先を用意します。承認済みトランザクションのキャンセル手順(ノンス置換)も練習しておきます。
7. 実務KPI(毎回チェック)
- ネットスプレッド(受取APY − 支払APR − 年換算コスト)が何%か
- 清算バッファ(%)と担保のボラティリティ
- 想定撤退コスト(往復ガス・ブリッジ・スリッページ)
- カウンターパーティ分散(CeFi/DeFi/チェーン/銘柄)
- 期間(持ち続ける根拠があるか。反転シグナルは何か)
8. 進化版:資金効率を高める工夫
(A)レバレッジ層の追加:安全マージンを保ちながら担保をループ供給すると、ネットスプレッドが厚い時期は年率を押し上げられます。ただし清算リスクが急増するため、初心者は避け、経験を積んでから限定的に用います。
(B)ヘッジの導入:担保がボラティリティの高いトークンの場合、先物ショートでデルタを中立化できます。資金調達率(ファンディング)が支払い超に傾くとネット低下要因になるため、組合せ時は慎重に計測します。
(C)自動監視:レートAPIやオンチェーンのイベントを定期取得し、閾値を下回ればSlack等に通知。手動反応から半自動化へ段階を踏むと安定します。
9. 典型的な失敗パターン
「レートが良いから」と一極集中し、引出し不可やレート急変で身動きが取れなくなる例が頻発します。常に出口の速さと撤退コストを先に確認し、複数の逃げ道を確保してから資金を入れます。もう一つは、清算閾値の誤解です。表示のLTVと清算LTVの定義がプロトコルごとに違うため、ドキュメントで算式を確認します。
10. ステップバイステップ実行例
- 資金計画:元本5,000〜10,000USDTで開始。最大損失と撤退条件を明文化。
- 口座準備:CeFiのKYCと出庫上限設定、ウォレットのバックアップ(シード厳重管理)。
- 試験送金:10〜50USDTで入出金とブリッジの往復を実施し、手数料と所要時間を記録。
- 本実行:同時刻に借入と貸出を行い、ネットスプレッドを表計算で記録。
- 監視:日次でレートとLTV、清算バッファ、ネット利回り、撤退コストを更新。
- 撤退:ネットが事前閾値(例:3%)を下回るか、清算バッファが縮小したら部分/全撤退。
11. まとめ
ステーブルコイン金利アービトラージは、価格予想に頼らずに収益を積み上げられる一方、金利・コスト・清算・デペッグ・カストディ等の複合リスク管理が生命線です。ネットスプレッドの可視化・清算バッファの常時監視・出口設計の3点を徹底し、小さく始めて学習曲線を登っていきましょう。
※本稿は一般的な情報提供であり、特定の取引や商品を推奨するものではありません。最終判断はご自身の責任で行ってください。

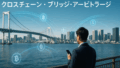

コメント