1. オンチェーン分析の射程と誤解
オンチェーン分析は、ブロックチェーン上のトランザクション、Utxo/アカウント残高、手数料、マイナー/バリデータの行動など“公開データ”を材料に、市場参加者の行動を推定する手法です。価格は板と建玉の結果ですが、その背後で資金がどこから来て、どこへ向かうかはチェーン上の痕跡に現れます。欠点は、①匿名性(主体の特定が難しい)、②遅延(確定ブロックまでラグ)、③オフチェーン行動の不可視性(OTC/取引所内部のネッティング)です。長所は、①改ざん困難、②24/7で更新、③取引所APIが止まってもチェーンは動く点です。
2. 投資で使う“6つの柱”
- アドレス行動:新規・休眠・クジラ・スマートマネーの動き。
- 取引所フロー:入金(売り圧)/出金(保管・長期化)バランス。
- マイナー/バリデータ動向:売却圧・手数料レジーム・難易度や活性度。
- 手数料・混雑度:L1/L2の混雑は投機サイクルと連動しやすい。
- ステーブルコイン供給:購買力の“弾薬残量”。発行/償還の方向性。
- デリバティブ指標:建玉・清算・資金調達率(ファンディング)で過熱を測る。
この6本を単独で見るのではなく、同時に2〜3本以上が同じ方向を指す時だけ行動するルールにするとダマシが減ります。
3. データのとり方:無料〜低コストの現実解
初心者は、まず無料または低コストのAPI/ダッシュボードを組み合わせます。例:ブロックエクスプローラ(mempool/etherscan 等)で手数料とブロック混雑、取引所のプル/プッシュフローは取引所公表値やアグリゲータ、先物建玉/清算/資金調達率は先物所の公開API、ステーブル供給は発行体のチェーンデータなど。表計算(Googleスプレッドシート)とPythonの両方で取得できる形に整え、日次で更新すれば十分戦えます。
4. 指標設計:シンプルさが武器
4.1 新規アドレス・休眠アドレスの活性
新規アドレス数が7日移動平均を上回りつつ、90日移動平均も上向く局面は、個人投資家の参加再開を示します。逆に、長期休眠のクジラアドレスが目覚め、大量の入金が取引所に流入する時は売り圧リスクが上がります。
4.2 取引所入出金フロー
ネットフロー(入金−出金)がプラスに偏ると短期の売り圧が増えがち。連続してマイナス(出金超過)が続く時は、セルフカストディ化や長期保有志向の強まりを示唆します。
4.3 手数料レジーム
平均手数料が急騰する“混雑レジーム”入りは、投機熱の上昇期に起きやすい反面、手数料ピークアウトは短期天井の手掛かりにもなります。L2の手数料低下が続く局面では、新規ユーザーのオンボーディングが進み循環が滑らかになります。
4.4 ステーブルコイン供給
USDT/USDC等の循環供給と時価総額の変化率を採り、年率換算の増減で“弾薬”の増減を測ります。供給増が価格上昇に先行することは多く、供給増の鈍化や償還超過は天井圏で出やすいシグナルです。
4.5 デリバティブ:建玉・清算・ファンディング
未決済建玉(OI)の増加はトレンドの燃料ですが、資金調達率(Funding)が過度にプラスへ傾いたままOIが拡大する局面は、ロング過熱→清算ドミノの下落リスク。逆に、FundingがマイナスでOIが増える時は、ショートパンプの危険が潜みます。
5. 合成シグナル:3点一致ルール
売買の実装では、複数の独立シグナルが同方向に一致した時だけ仕掛ける“合成シグナル”が有効です。例として以下のロング・セットアップ:
- ステーブル供給の3週間年率が+20%超に再加速。
- 取引所ネットフローが出金超過へ転じ、7日合計が過去90日パーセンタイル70%超。
- Fundingが+0.03%/8h以下で中立、OIは増勢だが清算は落ち着いている。
逆にショート/利確・セットアップ:
- 平均手数料がピークアウト、トランザクション数が減速。
- 取引所ネット流入が急増(入金超過)。
- Fundingが+0.08%/8h超で過熱、OIが高止まり、直近24hでロング清算が極小。
6. 戦略テンプレート:現実的な売買手順
6.1 スイング(週次判断)
週次で上記“3点一致ルール”を判定。エントリー後は、資金調達率が指定閾値を連続3回超える/ネットフローが反転/手数料がレジーム変化、のいずれかで部分利確。残りはトレーリング。
6.2 ベーシストレード併用
ロング現物+ショート先物(または無期限)のキャッシュ・アンド・キャリーでFundingやベーシスを回収。オンチェーン側の強弱に応じ、現物比率を段階調整します。
6.3 リスク管理
1回のトレード損失上限は口座の1〜2%。清算リスクのあるレバは控えめ(最大3倍程度)。イベント日はポジション圧縮。取引所/ブローカー分散、自己保管の徹底。
7. シグナルの数式化と簡易コード断片
例:ステーブル供給の年率成長(直近21日)= ((S_t / S_{t-21}) - 1) * (365/21)。Fundingは8h単位を年率換算し、年率 ≒ (1 + f)^(3*24) - 1で概算。パーセンタイル閾値でレジーム判定し、3点一致でフラグを立てます。
Pythonを用いる場合、日次CSVを読み込み、各指標を標準化(z-score)した上で、同方向の合計スコアが一定以上でシグナル=1、といった実装が簡便です。
8. ケーススタディ
過去の強気局面では、ステーブル供給の増勢→取引所出金超過→Fundingの中立〜微プラスという順で整列しやすく、押し目でのロング優位が続きました。逆に天井圏では、手数料ピークアウトと入金急増が早期に点灯し、Funding過熱と組み合わさると急落の導火線となりました。
9. 実務運用チェックリスト
- 毎日:主要指標の更新とレジーム判定ログ。
- 毎週:パフォーマンス要因分解(どの柱が寄与/阻害)。
- 毎月:パラメータ見直し(移動平均長、パーセンタイル閾値)。
- 常時:カストディ分散、API障害時のバックアップ手順。
10. まとめ
オンチェーン分析は単体で万能ではありませんが、ステーブル供給・取引所フロー・デリバティブ過熱・手数料レジームを束ね、同時一致で意思決定するだけで、裁量のムラが大きく減ります。再現可能なルールへ落とし込み、資金管理と併走させることが収益の安定化に直結します。


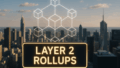
コメント