本稿は「半減期(ハルビング)」を価格の“単発イベント”として眺めるのではなく、継続的に収益機会を創出するための構造的テーマとして扱います。供給ショックの定量、マイナー経済の連鎖、先物・パーペチュアルのベーシスと資金調達率の挙動、オプション市場のボラティリティ構造まで接続し、初心者でも実装できる手順を具体化します。
- 半減期の本質:新規供給が半分に落ちる“キャッシュフローショック”
- マイナー経済と売り圧の地政学
- 先物・パーペチュアルの癖:ベーシスと資金調達率の“傾き”
- 価格は「噂で買い、事実で一服」になりやすいのか
- 実装戦略①:現物コア+保険としての長期PUT
- 実装戦略②:期先コンタンゴ捕捉(キャリー)
- 実装戦略③:イベントIVの時間差を狙うカレンダー
- 実装戦略④:ガンマ・スキャル(上級者向け簡易版)
- 実装戦略⑤:Funding偏りの両建て回収
- 実装戦略⑥:コール・スプレッド+テール保険
- データと指標:何を見て判断するか
- 実行手順テンプレート
- リスク管理の実務
- よくあるミスと回避策
- ミニケース:数値で見る設計例
- まとめ:テーマは“継続運用”で刈り取る
半減期の本質:新規供給が半分に落ちる“キャッシュフローショック”
半減期は約4年ごとに訪れ、ブロック報酬が半減します。例えば2024年の半減期では報酬が6.25 BTC → 3.125 BTCに減少しました。これは「マイナーに流れる新規BTCキャッシュフローが半減」することを意味し、売り圧の構造低下として現れます。新規発行量が半分になるため、理論的にはマイナーの売却起因の恒常的なネット供給が縮小し、需給バランスは中期的にタイト化します。
マイナー経済と売り圧の地政学
マイナーは電力・設備・資金調達コストを抱え、掘った瞬間から在庫リスクに晒されます。半減期直後は収益性(USD/BTC換算のハッシュプライス)が悪化し、効率の低い事業者が撤退する一方、効率の高い事業者はヘッジを厚めに掛け、キャッシュマネジメントを強化します。結果として次の現象が観測されやすくなります。
- 短期:ハッシュレートの一時減速や難易度の調整ラグ、マイナー在庫売りの変動。
- 中期:生存者バイアスにより設備の高効率化が進み、再びハッシュレートは上昇基調へ。
- 価格波及:撤退段階では一時的な売りが強まり得るが、構造供給減が効いてくるにつれてドローダウン耐性が高まることがある。
先物・パーペチュアルの癖:ベーシスと資金調達率の“傾き”
半減期周辺では次の傾向がしばしば観測されます(確定ではなく傾向)。
- 期先ベーシスの張り出し:コンタンゴ(順ザヤ)が拡大しやすい局面では、期先の年率換算ベーシスが上振れやすい。
- 資金調達率(Funding)の振幅拡大:短期センチメントの偏りが強まり、プラス・マイナス双方の極端値が出やすい。
- イベント前後のIV段差:オプションのインプライド・ボラティリティ(IV)がイベント前に上昇、通過後に低下(IVクラッシュ)する典型的パターン。
これらは裁定・ヘッジの設計図になります。例えば、現物買い+期先売り(キャリー)、IV高止まり局面でのボラ売り(ただしガンマとテールを管理)、Fundingの偏りを利用したクロス取引所・両建て戦略などです。
価格は「噂で買い、事実で一服」になりやすいのか
歴史的には「事前上昇・直後一服」のパターンが語られますが、毎回同じではありません。本稿では「パターンの再現性に依存しない設計」を重視します。具体的には、シナリオ木(上昇・横ばい・下落の3分岐)に対し、各分岐で損失制限が効く戦略を配列します。これにより、方向性の読み外しでも致命傷を避け、繰り返しの試行で期待値を押し上げます。
実装戦略①:現物コア+保険としての長期PUT
構造供給減のテーマをコアに据えつつ、プロテクティブPUTでテールを抑えます。例:現物(またはETF)を段階的に積み増し、6〜12か月先のOTM PUTを購入。コストはかかりますが、資金曲線の最大ドローダウンを限定できるため、心理的な握力を確保しやすいメリットがあります。
実装戦略②:期先コンタンゴ捕捉(キャリー)
現物買い+期先先物売り(またはパーペチュアルのショート)で年率換算ベーシスを刈り取る手法です。想定外の上昇でショート側の清算が起きないよう、レバレッジは低く、保険的に遠いOTMコールを少量買っておく選択もあります(コール・キャップ)。
実装戦略③:イベントIVの時間差を狙うカレンダー
半減期周辺では近月IVが盛り上がりやすい一方、期先は相対的に落ち着くことがあります。近月ショート・期先ロングのカレンダースプレッドは、イベント通過後のIV低下を利益源泉にしつつ、遠い将来の上振れには期先ロングがデルタの“保険”として働く設計です。ただし近月ショートはガンマがきついため、価格が大きく走るシナリオではガンマ・スクイーズに注意。
実装戦略④:ガンマ・スキャル(上級者向け簡易版)
IVが高い局面で安易な裸売りは厳禁です。代わりに、少量の近月両側買い(ストラドル/ストラングルのミニサイズ)を起点に、価格変動に合わせて現物/先物でデルタを中立に保つガンマ・スキャルでプレミアムを回収する手法があります。執行・スプレッド・手数料・滑りを厳密に管理できる環境でのみ検討してください。
実装戦略⑤:Funding偏りの両建て回収
パーペチュアルの資金調達率が極端にプラス/マイナスに偏る局面で、クロス取引所両建てでFundingを取りにいく方法です。カウンターパーティ・リスク、システム・リスク、乖離解消時の強制決済連鎖には最大限の注意が必要です。証拠金は独立管理し、相互担保にならないように構成します。
実装戦略⑥:コール・スプレッド+テール保険
上方向の凸性(コンベクシティ)を確保したいが、プレミアムを抑えたい場合、OTMコール買い+さらに上のOTMコール売りのコール・スプレッドは有効です。下振れのテールは別途OTM PUTや資金管理ルールで抑え込みます。
データと指標:何を見て判断するか
- 新規供給量・インフレ率:半減期前後の発行ペース。
- ハッシュレート・難易度:マイナーの稼働状況と調整ラグ。
- マイナー在庫推定:売り圧の代理指標。
- 先物ベーシス(年率):現物と期先の価格差。
- 資金調達率(Funding):センチメントの偏り。
- IV term structure:イベント月と期先の段差。
- 清算ヒートマップ:強制決済密集帯。
実行手順テンプレート
- シナリオ木を作成(上・横・下)。各分岐の損失上限を数値で定義。
- コア配分を決定(現物/ETF、またはキャリー戦略の有無)。
- ヘッジ手段(PUT、コール・キャップ、期先売り)の水準と枚数を決める。
- 受益源泉(ベーシス、Funding、IV差)を一つに絞らず、相関の低い2つを組み合わせる。
- 執行条件(スプレッド上限、板厚、滑り許容)をルール化し、自動化できる部分は自動化。
- 日次でKPIを記録:有効レバ、VaR、マージン比率、未実現P/L、ベーシス年率、IV、Funding。
リスク管理の実務
- 最大損失の先出し:戦略開始時点で最悪ケースの損失額を固定。
- 清算価格からの距離:レバは低く。清算域に近づく設計は不合格。
- 取引所分散:単一障害点を作らない。資金も分散。
- 先物限月ロール:ロール時の滑り・手数料・課税影響を見込む。
- ボラ・レジーム転換:IV低位→高位、高位→低位で戦略の有利不利が反転。
よくあるミスと回避策
- イベント一本勝負の裸オプション売り:テールで壊滅。スプレッド化か保険で抑制。
- Funding狩りの過剰レバ:瞬間の逆回転で同時清算。証拠金独立・低レバ・上限金利で統制。
- キャリーの逆ザヤ転換:期先の逆転で損失拡大。ルールに基づく即時縮小。
- 板薄時間帯の大口発注:スリッページの温床。時間帯と数量分割を徹底。
ミニケース:数値で見る設計例
例:現物300万円相当を毎月積立、期先(3か月)を同額ショートしベーシス年率8%を狙う。同時に6か月先OTM PUT(デルタ10)を保険として2%相当購入。価格が急騰しベーシスが縮小・逆ザヤ化したら現物バイアスを残しつつ期先ショートを段階的に縮小。価格が急落しIV上昇時には保険PUTが効き、損失は許容域に収まる設計。
まとめ:テーマは“継続運用”で刈り取る
半減期は一夜限りの花火ではありません。供給ショック → マイナー行動 → デリバティブの歪みという連鎖が生み出す構造的な収益源を、低レバ・厳格な損失上限制御・複線化した受益パスで着実に刈り取る。これが個人投資家が長く市場に残るための現実解です。


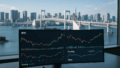
コメント