「レバレッジは何倍が正解ですか?」と聞かれたら、私の答えは常に同じです。倍数より先に、口座設計と清算幅(破綻までの距離)、そして分割エントリーとヘッジを決めてください。これらは相場観より再現性があります。この記事は、暗号資産の先物・パーペチュアルで破綻確率を最小化しつつ期待値を積むための「設計図」を、初歩から丁寧に示します。
1. まず用語整理:クロスマージンとアイソレーテッド
クロスマージンは口座全体の残高(実現損益・未実現損益を含む)を証拠金として共有する方式です。ポジション間で余力を融通でき、単発の急変に強い一方、悪化が連鎖しやすい欠点があります。
アイソレーテッドはポジションごとに証拠金を独立させ、清算も個別管理します。損失切り離しが利点ですが、余力の融通がききません。結論から言うと、方向性の同一バスケットはクロス、逆相関・別戦略はアイソレで分けると、口座全体の破綻リスクを抑えやすくなります。
2. 清算価格の考え方:安全域を“距離”で決める
清算価格は取引所・銘柄・レバレッジで異なりますが、実務では「清算までの距離=想定最大逆行幅 × 安全倍率」で逆算するのが有効です。例えば、BTCの1日最大逆行幅(99%タイル)が5%と観測できたなら、安全倍率2~3倍をかけ、10~15%の余裕を最低限確保します。
清算距離をD、現在値をP、口座残高(USDT等)をE、ポジション名目(ドル建て)をNとすると、単純化した必要証拠金Mは概念的にM ≈ N × Dで近似できます(資金調達や手数料、メンテナンス証拠金は別途上乗せ)。
このとき許容レバレッジLはL = N / Mですが、先にDを決めてからLが決まるのがポイントです。
3. 口座設計テンプレート(実数例)
口座残高E = 10,000 USDT。BTC-PERPでトレンドフォローを想定。過去検証で想定最大逆行幅は7%、安全倍率2倍⇒D = 14%に設定します。
- 最大名目Nmax:M = N × D なので、E全体を危険に晒さないため、口座の40%を証拠金上限にする設計とすると、Mmax = 4,000。よって Nmax = Mmax / D ≈ 4,000 / 0.14 ≈ 28,571 USDT。
- 分割エントリー:Nmaxを5分割(初回30%、残り4回は等分)。初回8,571、以降各5,000の増し玉。
- クロス vs アイソレ:同一方向のピラミッドはクロスで運用し、逆方向ヘッジはアイソレで別枠管理。
- 強制ロスカットの前段:清算価格の手前(例えば清算距離の60%地点)に自分の強制損切りを置きます。清算到達は「設計ミス」。
4. 分割エントリーの“距離”設計
裁量の「なんとなく追撃」は破綻の源です。価格距離に基づく機械的追撃を定義します。例:初回からの逆行がそれぞれ1.5%、3%、5%、7%で追加(名目は前述)。同時に、ストップも段階で前進。平均建値と清算距離を常に再計算し、清算までの余白がDを割らないよう監視します。
5. Funding(資金調達率)と先物ベーシスを“コスト化”する
パーペチュアルのロングは正のFunding、ショートは負のFundingでコスト/収益が発生します。設計では、想定保有期間 × 予想Fundingを前もってコストに織り込み、期待値を歪ませないようにします。
例:年率換算で+12%のFundingが続く環境でロングを数週間保有する設計は不利です。逆に過熱局面のショート+現物ヘッジ(キャッシュ&キャリー)は収益が立ちやすい。
6. ヘッジの実装:現物・オプション・別銘柄
現物ヘッジ:ロング先物に対し同額の現物ショートは難しいため、実務では「先物ショート+現物ロング」が基本です。トレンドロング派なら、急落時のドローダウンを緩和するため短期の先物ショートをアイソレで別建てします。
オプション:保険料はかかりますが、下限を固定できます。特にイベント週は、OTMプットの部分買いでテールを切るのが有効です。
別銘柄ヘッジ:BTCロングに対しETHショート、もしくはアルトの高βショートを少量。当日の相関係数を監視し、逆相関が崩れたら即撤収が鉄則です。
7. 清算を避けるための5つのルール
- (1)清算は設計ミス:清算到達の前に自己強制損切りが作動するよう距離設計。
- (2)分割は最大5回:回数が増えるほど平均建値の改善効率は逓減し、損切りの心理抵抗だけが増します。
- (3)一日損失上限(DDL):Eの2%など固定値。DDL到達でその日は必ず停止。
- (4)イベント前は名目半減:CPI、FOMC、主要ETF関連ニュースなどはボラ噴出。Nを半分に落とすテンプレを事前に準備。
- (5)同方向バスケットはクロス、逆方向はアイソレ:連鎖損失を遮断。
8. 実装チェックリスト(口座を開く前に)
- 想定最大逆行幅:銘柄別に過去データから99%タイルの1日リターンを推定。
- 安全倍率:2~3倍。清算距離Dを決める。
- 証拠金上限:口座Eの40%(裁量可)。
- 分割距離・比率:逆行1.5/3/5/7%など距離で固定。名目の配分比も先に定義。
- ヘッジ手段:先物ショート、オプション、別銘柄。条件と解除ルールを明文化。
- 損切り距離:清算手前60%地点など、価格トリガで固定。
- イベント時の縮小:名目半減ルールを事前宣言。
9. 具体例ワークフロー(BTC-PERP、ロング想定)
(A)初期条件:E=10,000、D=14%、Mmax=4,000、Nmax=28,571。手数料・Fundingは別途2%/月相当と仮定。
(B)建付け:価格P=60,000と仮定。名目28,571は約0.476BTC相当。これを5回で追撃:初回0.143BTC、以降0.083BTC×4。ストップは清算手前60%で置き、平均建値上昇に合わせて等距離で前進。
(C)ヘッジ:日足RSIが過熱、Fundingが年率+15%超なら、アイソレで短期ショートを名目の20~30%付与。急落時はショートで緩衝、上昇継続ならコストとして許容。
(D)イベント対応:CPI前日は総名目半減(各サイズを半分に)。終値基準で元に戻す。
(E)日次判定:損益がEの±2%を超えたら新規は停止。勝ち日は増やさない、負け日は取り返さないが原則。
10. よくある失敗と対策
- 平均建値の錯覚:ナンピンで平均建値が改善しても、清算距離Dが縮んでいないかをチェック。Dが縮むなら追撃禁止。
- 相関の崩壊:別銘柄ヘッジは相関が動的に変化。相関が0.3を割る/超えるなどルールで測定。
- Fundingの転化:過熱から冷却へ相場が転ぶと、Funding優位が一夜で消える。保有根拠がFundingだけなら、転化で即時クローズ。
- クロスの連鎖清算:同方向ポジションをクロスに寄せすぎると、想定外の総崩れで一網打尽。異戦略は必ずアイソレ。
11. 最小構成の自動化(手動でも使える)
表計算で十分です。列は「建値」「ポジションサイズ」「名目合計」「清算距離D」「想定Funding」「ストップ位置」。
新規・増し玉のたびに自動再計算し、Dがしきい値未満なら発注不可にするだけで破綻確率は激減します。
12. まとめ:レバレッジは“距離”で管理する
勝者は「何倍で入るか」ではなく、どれだけの距離を常に残すかでレバレッジを設計します。クロスとアイソレの役割分担、分割の距離設計、ヘッジの条件、イベント時の縮小、そして日次の停止ライン。この5点を事前に文章化し、その通りにしか動かない——それがレバレッジ運用で資産を守りながら増やす最短ルートです。


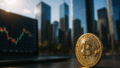
コメント