本稿では、これまであまり体系化されてこなかったDAOトレジャリー運用を、個人投資にも応用できる形で実務レベルまで落とし込みます。焦点は利益最大化ではなく、確率的に破綻しない最適化。資金配分、売却・買い増しルール、イベント駆動のヘッジ、会計と監査、権限分散(MPC/マルチシグ)まで、具体的に示します。
1. トレジャリーの目的関数を数式化する
トレジャリーの失敗は「目的が曖昧」から始まります。以下の3指標を最小化/最大化の対象として明示化します。
- ランウェイ確保:運営費(月次バーン)×12〜24ヶ月の現金/ステーブルを確保。
- ドローダウン制御:最大ドローダウン(MDD)上限を-30%などに設定し、超えないよう再配分・ヘッジ。
- 希薄化/売り圧の最適化:ネイティブ売却は出来高のX%/日以下、イベント(大型アンロック等)前後でルール化。
目的関数(例):maximize E[Nav_{t+12}] - λ1·Prob(Runway<12m) - λ2·Expected(MDD)。λは理事会/コミュニティが合意。
2. 資金配分モデル:3バケット方式
基本は運営(OPEX)/コア(Core)/戦略(Alpha)の3バケットです。
2.1 運営バケット(OPEX)
用途:給与・開発費・法務・監査。
構成:ステーブル80〜100%。
目安:月次バーン×12〜24ヶ月。金利獲得は信用・流動性リスクの低い先へ限定。
2.2 コアバケット(Core)
用途:プロトコル価値と連動するネイティブトークン保有、主要アセット(BTC/ETH)での土台づくり。
構成:ネイティブ40〜60%、BTC/ETH40〜60%。
ルール:ネイティブは価格影響を抑えるVWAP分割売却、BTC/ETHは下落局面での段階買い。
2.3 戦略バケット(Alpha)
用途:低相関の超過リターン源。例:キャッシュ&キャリー(先物ベーシス)、資金調達アービトラージ、完全ヘッジ型イールド。
上限:総資産の10〜25%。ドローダウン限度とVaRを明記。
3. 売却・買い増しルール(実務)
3.1 ネイティブ売却のVWAP運用
取引高の薄い時間帯を避け、1日当たりの売却量を「直近30日平均出来高の1〜2%」に限定。
実務:売却数量/日 = min(保有目標超過分, 0.02 × ADV30)。
板が薄いCEXではTWAP、DEXではスリッページ上限(例:0.3%)を必ず設定。
3.2 ファンディングレート連動ヘッジ
ネイティブ下落局面でのショートは、資金調達率がプラス(受取)の取引所を優先。ヘッジ比率はβで管理:Hedge Notional = β × ネイティブ時価。βは回帰で推定(週次更新)。
3.3 先物ベーシスのキャッシュ&キャリー
手順:スポット買い+同額の先物売り。年率化ベーシスAPR = (先物-現物)/現物 × (365/残存日数)がリスク調整後に正なら実行。
注意:ロール時のスプレッド、金利、資金調達率の変動を織り込む。
4. リスク限度とアラート
- MDD限度:ポート全体で-30%(例)。超過時はOPEX以外を縮小し現金化。
- 単一カウンターパーティ限度:預け入れは総資産の15%以下/社。CEX・レンディング双方に適用。
- 流動性リスク:90% VaRが日次出来高のX倍を超えたら分散。
- スマコン/ブリッジリスク:監査済み・バグバウンティ実施先のみ。ブリッジは多段経路を避ける。
5. カストディ設計:MPC/マルチシグ/コールド
支出系(OPEX)はMPCウォレットで2/3や3/5、戦略系は3/5〜4/7、コア保管はコールド+エアギャップ。
ロール(ガス代高騰時の誤送金)対策として送金前シミュレーションと少額テスト送金を標準化。
6. 会計・監査とオンチェーン開示
オンチェーン台帳(メイン/サブ口座)を分け、エクスポート→会計台帳→月次レポートのフローを固定。
DCF/ランウェイ、MDD、ベーシス収益、ヘッジ損益を月次で開示。
Dune等のダッシュボードにリアルタイム残高・配分・ルール逸脱アラートを表示。
7. ガバナンス整合:提案→執行→検証
運用ポリシーはガバナンス提案として可視化。
提案書テンプレ:
- 目的関数・KPI(Runway、MDD、配分)
- 3バケット配分と上限
- 売却・ヘッジ・ベーシス戦略の条件式
- 権限(MPC閾値、緊急時フリーズ、監査人)
- 報告(週次Ops、月次レポ、四半期監査)
8. 実務ワークフロー(週次)
- データ取得(残高、出来高、ADV30、資金調達率、先物曲線)
- KPI更新(Runway月数、MDD、VaR、配分乖離)
- ルール判定(売却/TWAP、βヘッジ、ベーシス仕掛け/クローズ)
- 執行(スリッページ上限、ティア別CEX/DEX配分)
- 記録(Txハッシュ、約定明細、スクリーンショット添付)
- 開示(ダッシュボード更新、コミュニティ報告)
9. 個人投資への応用
DAO規模でなくとも、家計/個人ポートフォリオに3バケットを適用できます。OPEX=生活防衛費、Core=長期保有(BTC/ETH/インデックス)、Alpha=小規模裁定やヘッジ。
売却はVWAP/TWAPで感情を排除。
ファンディング受取ショートやベーシスは必ずポジション中立で。
10. ケーススタディ(簡易数値例)
総資産10億円、月次バーン2,000万円のDAO。
- OPEX:2,400〜4,800万円(12〜24ヶ月)をステーブルで確保(分散保管)。
- Core:6〜7億円をネイティブ/ETH/BTCで配分。ネイティブ売却はADV30の1.5%/日。
- Alpha:1〜2.5億円。年率ベーシスが6%超で仕掛け、ヘッジはβ=0.6で動的。
MDDが-30%接近でAlpha停止、Coreの一部をETH→ステーブルへ再配分。Runwayが12ヶ月割れでネイティブ売却比率を引き上げ。
11. 禁則事項とレッドライン
- 未監査スマコン・単一ブリッジへの集中。
- 資金需要の予見なくロック期間の長い運用へ過度にコミット。
- 出来高の薄い板での成行大量売却(価格影響)。
- 内部者取引・非公開情報を用いた取引。
12. まとめ
DAOトレジャリー運用の肝は、明確な目的関数、3バケット配分、ルールベース執行、権限と監査の分離、そして継続的な開示です。これらを固定化すれば、相場のボラティリティに翻弄されず、コミュニティ合意の下で“減らさず増やす”運用が可能になります。


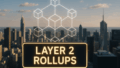
コメント